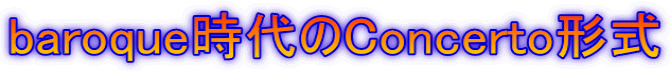
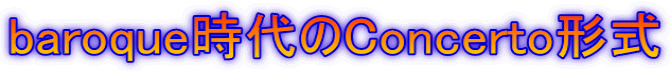
![]()
baroque音楽を理解するには、basso continuo、所謂、通奏低音という音楽の演奏形式を理解する事が大切です。
baroque時代のConcertoの形式を理解する時にも、この通奏低音という演奏形態を理解しておく事が、結構、当時の音楽を理解する上で、必要です。(後述します。)
Facebookより
baroque時代のConcertは、形式学的には、ritornello形式と言われる、所謂、循環形式で作曲されている。
ritornello形式と言っても、一般的にはどういった形式か、分かりませんよね??
分かりやすく言えば、orchestraの合奏部分(tuttiの部分)と、soloの部分が繰り返される形式の事を言います。
orchestraの合奏の部分をAとして、繰り返されて、soloの部分は、その都度、新しい形で演奏されます。
A+solo1+A+solo2+A+solo3+A、という風に演奏されます。
tutti(合奏)のAの部分に対して、soloの1+2+3+の部分はその都度、新しいpassageで出来ています。繰り返しの回数は、決まっていませんが、A+solo1+Aでは、Symmetryの構造になってしまいますので、若し、この構造式を持ったConcertoがあったとしても、それはritornello形式とは言いません。ですから、最低でも、A+solo1+A+solo2+Aはなければなりません。
循環形式という事なので、形式だけを見ると、同じ循環形式であるrondo形式と勘違いをしている輩も極々、稀にはいるのだが、rondo形式は、舞曲の中の一分野なのだから、Rondoと呼ぶには、tempoやRhythmの色んな制約があって、Themaが自由に設定出来る形式であるritornello形式とは基本的に、比べるべくもないのだ。
rondo形式の場合
themaA+B+A+C+A+D+A・・という風に、展開していくのだが、最後はAに回帰する場合が多いのです。
A+B+A+C+A+Dの場合には、最後のDがCodaや展開部である場合が多く、複合2部形式ともなる場合がある。また、rondo‐Sonate形式となる場合もある。
いずれにせよ、演奏形態では、BやCがsoloの部分では無いので、根本的にritornelloには成り得無いのだよ。
ritornello形式の意味と、その例外となるVivaldiの場合・・・
(一般的には、ritornelloはそのthemaAが繰り返される時には、全く同じようにthemaが反復される事が多いのだが、Vivaldiの場合には、繰り返えされる毎に、形を変えて繰り返される。)
baroque時代の作曲家がritornello形式に拠って作曲をしたその意味
ritornello形式の作曲法は作曲の促成法であり、速記法であり、演奏家達に取っては、簡易演奏譜になるのだ。
ritornello形式やbasso continuoの手法は作曲家には取っての速記法であり、演奏家達への手軽な演奏法になるのだよ。
こんにちのように、BGMがSwitch一つで流れる現代社会と違って、baroque時代にはBGMは生の演奏で演奏された。
「凄い❢❢」「贅沢❢❢」と思われるかも知れないが、当時は、生の音楽しか有り得なかったのだよ。
だから、貴族達は、partyの度に、音楽家(演奏家)を雇わなければならなかったし、貴族達も、常設で音楽家を雇う程には裕福ではなかった。・・という事で、作曲家は、毎週の日曜日のpartyに演奏する曲を作曲する仕事と、演奏家を雇って、楽譜を書いて、曲を練習させる・・と言う仕事に、毎週、追われなければならなかった。
まあ、近現代のproオケの練習1回、rehearsal 、本番の形は、baroque時代から、続いていたのだよな??
それでも、partyを成功させるためには、曲を最低の練習で演奏出来るように作曲をしなければならなかったのだよ。
また作曲家自身も曲を作るのが、partyの為の曲目の準備や構成企画から、演奏家の手配、part譜の作成と、演奏家への練習の下見等々、日頃から非常に大変忙しかったので、相当頑張らなければ、仕事を落としてしまい兼ねない忙しさであったのだよ???
そう言った大変な忙しさを助ける為に、編み出された手法が、このritornello形式なのである。
練習1回、rehearsal 本番の日雇いの音楽家達が演奏するのは、ritornelloのtuttiのthemaだけである。演奏時間に対してのnormaは極めて低いのだよ。
その宮廷で必要な音楽家は、soloのviolin、(或いはsoloのCello)とCembalistと、通奏低音を演奏するcontinuoのviola
da gamba奏者だけであり、そのいずれかは作曲家が演奏が出来たので、常任で宮廷が雇うのはその場に必要な2名だけである。(つまり、3名を雇えば、常設で毎週の演奏会が可能だったのだよ。)
日雇いで来た音楽家達はorchestraのtuttiだけを演奏すれば良いので、曲数が5曲であろうと、10曲であろうと、演奏する曲は、その1曲に対して、短い1Pageにも満たないpart譜である。
それ以外は、作曲家本人がsoloを演奏する場合には、伴奏者に対しては覚書程度の楽譜を提供すれば良いだけなので、当日、自由に弾きまくれば良いのだ。
まあ、サラリーマンとしての作曲家ならばそれでも良いのだろうが、上昇志向の強い作曲家に取っては、自分の作曲をちゃんと残して行く、・・且又、出版する事が自分の名を上げる事でもあったのですよ。
だから、真面目な作曲家達は、このConcertoの速記法であるritornello形式の曲を、真面目に楽譜に起こして、後世に残しているのです。
Vivaldiの場合
しかし、Vivaldiは、Pietà音楽院で、捨てられた女の子達の音楽の指導を任されていました。
ですから、Vivaldiの周りには、常に、Europaで一番優秀な演奏家達が、愛弟子として居たのですよ。
という事で、Vivaldiだけは、自分のorchestraがいつも傍にあって演奏をしてくれると言う、ある意味恵まれた環境にあるので、ritornelloが全く同じ形で、繰り返す必要は無かったのだよ。
それ以上に、ritornelloの形式を繰り返す毎に、微妙に変化して繰り返す事は、より暗譜を確実なものにして、演奏の技術や、音楽的な表現の能力を上げる効果があります。
参考までに:
Vivaldi Violin Concerto a moll Op.3 Nr.6
この世界中に有名なVivaldiのConcertoなのですが、何処かの音楽教室の独特の演奏styleで、世界中の演奏家がVivaldiのViolin Concertoに対して、拒否感を抱かせるようになった曰く付きの曲です。
私もこの曲のおかげで、多くのviolinist達に、I Musiciとかの演奏を聴いて貰える事すら・・・大変な思いをしました。
それ程迄に、音楽を学ぶ人達や音楽家達をして、Vivaldi嫌いにした、名曲であります。
下に掲載した写真で、演奏をしているのは、ViolinからCello迄は、小学生達です。CembaloとKontrabassだけが、中学生です。
演奏表現はperiod奏法で演奏しています。
当然、弓の持ち方も1点支持の持ち方です。
残念ながらViolinとbowはmodern楽器で、pitchも443cycleです。
通常では、最低必要人数は9名なのですが、Cembaloの七星ひかりちゃんがⅡ楽章でCembaloからViolaに持ち替えているので、最初人数の8名での演奏になります。
この演奏人数が、必要最低の人数になります。
写真をclickするとYou Tubeにlinkします。

You Tubeより
comment
『Knaben-kammerについて』
教室開設当時には、教室の児童orchestraは、Ashizuka-Knaben-kammer-Streich‐Orchestraという大変長い名称を持っていました。
ドイツ語の『Knaben』という単語は日本語では「児童」と訳すようなので、日本語では『芦塚児童室内弦楽オーケストラ』と訳すようです。
私が千葉で教室を開設した当時は、生徒達は皆、小学生だったので、orchestraが『Knabenkammer』でも良かったのですが、やがて、時間が経過して、子供達が中・高校生となると、この『Knabenkammer(児童室内)』の名称は使えなくなってしまいました。
英語のjuniorという単語は、ドイツ語ではJugendとなるので、本来ならば、Ashizuka-Jugend-Kammer-Streich-Orchestraとすべきなのですが、第二次大戦の時にHitlerがHitler-JugendとしてJugendを連発していたので、私にとっては、Jugendという呼称に余り良い印象がないのですよ。
しかし、今回はお久し振りの小学生中心のKnaben-kammer-Streich‐Orchestraが再開出来ました。
中学生の助っ人として、CembaloとViolaを弾いてくれた七星ひかりちゃんと、Kontrabassの川島綾乃ちゃん(中1)の二人だけが助っ人参加しています。
『出演者と持ち替え楽器について』
『出演者』
solisteは、楽章毎に、
1楽章のsoloは美音(小3)
2楽章のsoloは紗來(小5)
3楽章のsoloは瑞希(小5)としました。
その理由はCapacityではなくて、なるべく多くの生徒達にsoloを演奏させたいからです。
公開演奏を出来る子供達なので、どの生徒も全楽章を弾き通す実力はあります。
basso continuoのcontinuo-celloは真雅(小5)
continuo-Cembaloはひかり(中2)です。
Kontrabassは綾乃(中1)です。
Ⅱ楽章は、紗來ちゃんがsoloを演奏し、Cembaloのひかりちゃんがviolin(Viola)Ⅲに持ち替えています。
Ⅲ楽章では、violaの瑞希ちゃんがviolinのsoloに移動したので、紗來ちゃんがviolaに持ち替えて弾いています。
(violinの生徒達は全員violaの譜面は読めるので、楽器の持ち替えは問題はありません。)
『楽器編成について』
Vivaldiは、violinとviolaとcello(Kontrabass)の編成の曲を数多く作っています。
つまり、この曲も2ndviolinを欠いた編成になっています。
演奏は本来の必要最低人数の9名ではなく、Ⅱ楽章を、Cembaloの七星ひかりちゃんが第三violinに持ち帰る事によって、更に、1名少ない8名編成になっていますが、これはVivaldiの意図にも叶っているbaroqueの編成です。
『vibratoについて』
「baroque特有の奏法であるsenza vibrato奏法について」
また、純正の和音の響きを活かすために2楽章はvibratoをしないで演奏しています。
このlevelの生徒達に取っては、逆にvibratoを入れないで演奏する・・という事はかなり難しい事なのです。
vibratoを入れる事が癖になっている・・という事以上に、vibratoをしないと、音のちょっとした狂い(pitchの差)でも際立ってしまうので、逆に音を合わせる事が非常に難しくなってしまうのです。(実はタップリとvibratoを入れて演奏すた方が演奏としては楽なのですよ。
しかし、vibratoを入れると純性の美しい響きが失われてしまいます。
period奏者達がbaroque音楽を演奏する時に、non-vibratoで演奏するのは、そう言った純正の和音の響きを活かす・・という理由によるのです。)

「ornamentの奏法について」
Ⅱ楽章のornament(装飾音)は、教室のcurriculumとしては、高校生からは自分で作る事になっていますが、今回は小学5年生の演奏なので、芦塚先生が代わりにornamentを作っています。

勿論、Cembaloのcontinuoのpart( bezifferten Baß 所謂、右手のpart)も芦塚陽二先生の作曲です。Cembaloのpartは、soloの生徒のlevelに合わせて、初初級のlevelから、上級迄、数種類の伴奏があります。
参考までに: 初初級versionのCembalo‐continuo譜
左手の動きは、basso continuoの動きなので、これを変える事は出来ません。
Vivaldiのa mollのCembaloのpartを弾く条件は、この「左手が弾ける事」という前提になります。
但し、Cembaloの鍵盤の幅は、少し短いので、Pianoで演奏するよりは楽です。
「Vivaldi独特の絡め合わせによる作曲法」
Ⅰ楽章のrhythmicalなup-tempoの演奏なのですが、そのrhythmは、violaとcelloの『絡め合わせ』の技法によるもので、violaに対しての、celloの食い付きが非常に難しいのです。
Violaの瑞希ちゃんがcelloの桃迦ちゃんの方を向いて演奏していますが、食い付きのtimingを合図(einsatz)を出しながら演奏しているのです。

絡め合わせのeinsatzのtimingをViolaの瑞希ちゃんがCelloとKontrabassのpartに送っています。

「空中bowing」
次にviolinのsoloの部分で見受けられるviolinとviolaのunisonの伴奏は、4分音符と4分休符が繰り返されるので、通常は弾き止めを使用して、4分音符を弓を半分だけ使用して、4分休符は弓の動きを止める事で演奏しますが、今回の演奏では、休符のpassageも弓を弦からホンの少し持ち上げる事で、音を出さないように空滑りをさせる・・所謂、『空中bowing』を使用して、恰も、全弓で演奏しているかの様に演奏しています。
この空中bowingの演奏技法はbaroque奏法における色々な奏法の基本になるので、この空中bowingの奏法が出来るようになると、色々なbaroque時代の演奏表現が出来るようになりますが、日本では未だ知られていないperiod独特の奏法となっています。
この奏法による色々なperiodの奏法の中で、最も大切な奏法としては、余韻の演奏法です。
余韻の奏法としてのこのconcertantを演奏する場合には、ViolinとViolaの全ての音がdownのbowになるのですが、この八千代の演奏では、空中bowは使っていなくて、通常のup
downを繰り返しています。

score上では、soloに対して、ViolinとViolaと、continuoのCelloがsolo(soli)で伴奏していますが、これをconcertantと言います。
これがsoloではなくて、ViolinのpartとViolaのpartで伴奏する場合には、ripienoと言う言い方をします。
但し、八千代のこのVivaldiのa mollの演奏では、、ViolinとViolaの伴奏はconcertantではなくて、ripienoとして伴奏しています。
「technical-acousticのお話」
今回の演奏でのperiod奏法で、一番際立っている奏法が、technical acoustic奏法である余韻の奏法です。
例えば、今回の八千代のような多目的ホールの場合には、講演者の言葉が聞き取り易いように残響を抑えてあります。
言葉が聴き取りやすい・・という事は、弦楽器やsoloの管楽器に取っては、致命的になってしまいます。
楽器の演奏で一番大切なのはacoustic(残響)だからです。
しかし、period奏法には、残響の無いHallでも、恰も残響があるように弾く奏法があります。口伝の奏法なので、名前は付いていないようなので、便宜上私はtechnical
acousticと呼んでいます。
そういった残響の全く無い多目的ホールでも、残響のあるコンサート・ホールで演奏しているように、聴こえるのは、baroque時代の、この特殊な奏法によるものです。
つまり、ホールの残響の余韻の音を、楽器で演奏しているのです。
そういった奏法の事を私はtechnical-acousticと呼んでいますが、この奏法は、とても大切なbaroque時代の演奏法なのですが、日本では未だ知られていないperiod時代の独特の奏法になります。
「体を揺らして演奏する事について」
私達の演奏で、一番よく批判を受けるのが、体を「揺らし」て演奏する事です。
しかし、私達の教室では、意図して体を「揺らし」ています。・・・と言うか、「揺らし」を学んでいます。「揺らし」は、bowの体幹を感じて、音に豊かさを表現するための方法なので、正しく体を揺らす事は、非常に難しい事なのです。日本にはその体幹を学ぶ・・という事が伝わっていないようで、力で音を出す方法が一般的なのですが、1点支持では、楽器に負担のある力で弓を押すという奏法はTabooなのです。
また、体を揺らす意味は、音に対しての体幹の意味意外にも、音のtimingを合わせる・・と言う意味もあります。
日本では体を揺らして演奏する事は、情緒的感情的な演奏として忌み嫌われていますが(※)、実際には、指揮者無しの演奏では、このような超狭い演奏者と演奏者の間が10㍍にも満たない舞台の距離・・だとしても、耳で相手の音を聴いて合わせると、100分の1秒ぐらいのズレが生じて、後弾き(所謂、音のズレ)が起こってしまいます。
日本のClassicの演奏者の多くの人達が持っている悪い癖である・・独特のtempo感の無さ・・所謂、乗りの悪さは、常日頃、popularの奏者達がClassicの演奏家に対して文句を言っている「rhythmの後引きの演奏」は、耳で音合わせをする事によるrhythmの遅れが生じる事から起こるrhythmのズレなのです。
popularの演奏家達の場合には、音楽をbeatで体感して演奏をするので、そういったClassicの演奏家達特有のrhythmのズレは起きません。
一般の人達や他の音楽教室の先生達からよく言われている、芦塚音楽教室の子供達の演奏の独特の『乗り』と『rhythm感』ですが、それは、一般的には耳で合わせるbeatを、目と、体の動きで合わせるので、体感としての合わせになって、lagが発生しないからなのです。
また、室内orchestraの場合には、指揮者が立たないので、concertmasterの演奏を聴いて音を合わせる場合が一般的なのですが、今回の子供達の演奏も、指揮無しなので、体の「揺らし」でrhythmを合わせる事が非常に重要なのです。
つまり、子供達が体を揺らして演奏しているのは、日本で普通に考えられているような情緒的・感情的な揺らしや、performanceではなく、計算されたchoreography的な揺らしになるのです。
この曲のⅠ楽章のripienoのviolaとripieno-celloが、お互いが速い交唱になっていて、絡み合わせのtimingを、耳で合わせるとズレてしまうので、violaの瑞希ちゃんが、初心者のオケcelloの桃迦ちゃんに目でeinsatzを送って、そのrhythmの出遅れがないようにしています。
「eye-contact」・・、目と目の合図ならば、絶対にtempoの遅れは出ないので、顔を見合わせて演奏する事は、交唱を演奏する場合の基本的な演奏法になります。
(※)体の「揺らし」を演奏法という言葉で表現すると、日本人の音楽家達の中には奇異に思われる人達も多いと思います。
勿論、「情緒的に、或いは感情的に『体が揺れる』のは、演奏法ではなくて、単なる無駄な動きに過ぎません。」
体を揺らす事は、単に『rhythmを取る』と言う意味だけではなく、bowの自然な動きや、体の重心を取る意味もあって、演奏そのものにも多大の影響を与えます。
・・と言う事で『体の揺らし』は、performanceとしての、『情緒的感情的な動き』ではなく、音楽技術的な理論的なtimingによって、正確に振り付けられた『体の揺らし』だと言う事を理解しておいてください。
「continuoのmelodieの変更」
Ⅲ楽章の最後で、旋律がよく知られているこれまで出版されている一般的な楽譜の動きと違う動き(ミ♭)が出てきますが、これはSequenz進行によるⅤ度圏の進行を活かすための音の変更です。

Cembalo譜は初級versionなので、上級versionでは次のようになります。

一般的な音符の進行の場合には、baroque時代には禁忌とされた(Celloの通奏低音の動きにとても不自然な)増4度の進行が起こってしまいますので、それを防いで、しかもSequenzを忠実に守るための音の変更です。
Baßの動きを自然に正しく演奏するか、melodieを一般的な演奏にするか・・の二択なのですが、
今回は普段は、一般的には聞かれる事のない・・Baßの動きを正しく演奏した場合として演奏しました。
「1点支持の奏法」
おそらく日本の音楽界では、violinを学んでいる人達・・というかproのviolin奏者も含めて、多分、98%ぐらいの人達が3点支持による弓の持ち方をしていると思います。
しかし、baroque時代の弓の持ち方は、当時のbaroque絵画を見ても、1点支持の弓の持ち方が基本でした。
その持ち方が3点支持に変わったのは、19世紀に入ってからTourteとSpohr達の手に寄って、強い音量を出すために、新しいbowに改良してからのお話なのです。
弓が現代のbowに改良されて、楽器もbaroque仕様から、modern仕様に変更されて、それから弓の持ち方が3点支持に代わりました。
だから、baroque時代や古典派の時代までの古い弓の時代の音楽と、現代の音楽の演奏表現では、全く音の出し方から違っていたのですよ。
Europaの神様classの演奏家達は、音楽を歴史的に学んでいるので、そういった弓の持ち方を音楽の表現や時代表現に合わせて使い分けています。
しかし、日本の音楽のlevelでは、なかなかそこまでは行かないようです。
「膨らまし奏法」
baroque奏法で、日本で勘違いされている奏法があります。
それがこの「膨らまし奏法」です。
教室では、その「膨らまし奏法」の事を、後押し奏法と呼んでいます。
明治時代の音楽事始めの時に日本に入って来た弦楽器の奏法なのですが、この「膨らまし奏法」は、弾き方が日本の小節の歌い方によく似ているので、日本人の民族性から・・日本の民謡や演歌に見受けられる「後押し奏法」と、勘違いされてしまいました。(・・・というか、現在でも勘違いされているままで、そのように弾く人達が多いのです。)
間違えた後押し奏法は、弓で音を押さえて強く出す奏法で、日本の演歌によく見受けられる『アンコ~椿の~」の「~」の部分なのですよ。力んで声に力を入れる歌い方を小節(こぶし)の歌い方と言いますが、弦楽器(特にViolinでも・・)では、特に、そう言った奏法で生徒を指導した某国立音楽大学の教授の門下生だけではなくて、一門の生徒達だけではなく、一般の弦楽器奏者達でも、そういう風に弾く人達が非常に多いのです。
しかし、この「後押し奏法」は、viola da gambaの奏法によく似ているのですが、Europaに人達に取っては根本的に違った奏法になって、結構、忌み嫌います。
私は、この「膨らまし奏法」を、生徒達には、非常に厳しく注意しているのですが、上級生達でも、チョッと油断しておくと、この「後押し奏法」が、随所に見受けられるようになってしまいます。
厳しく、注意しているのに、チョッと、任せて置くと、コロナのように、またぞろ、出て来るのです。非常に困った事なのですが、これは民族性なのでしょうかね??
正しい「膨らまし奏法」は、Renaissance時代からのviola da gambaの曲でも、よく聴く事が出来ますが、最初、音を出してkonsonanzに当てると、konsonanzの音が徐々に膨らんで大きくなっていきます。それが、日本人に取っては、恰も、後押し奏法のように、聴こえて来るのですよ。
viola da gambaのような大型の低音楽器では、そのkonsonanzが当然の如く、聴こえて来るのですが、楽器が小さくなると、そのkonsonanzの幅も小さくなるので、ensembleで低音楽器と合わせる時には、Violin等では、少し人為的に、そのkonsonanzを演奏しなければなりません。
それが日本人には小節(こぶし)の奏法のように勘違いされてしまったのです。
VivaldiのscoreでもsoloとViolinは、レの音なので、konsonanzを持っています。しかし、Violaのpartはソ#なので、konsonanzは持っていません。それで、弓で或る程度の後押しをして、恰も、konsonanz奏法であるような風に演奏しました。
(上記のYou Tubeの演奏では、0:25秒の所になります。)
しかし、それが日本人のViolinの後押し奏法の原因にもなってしまいました。
「settingmistake」
今回のsettingの失敗は、この小さな舞台にKontrabassだけが舞台の下で演奏をしたのですが、実際にはKontrabassも舞台上に乗るゆとりはあったのですが、setting担当の人の「絶対に、乗れない」・・という思い込みがあって、私が「Kontrabassも舞台上に・・」と、頼んだのに、setting担当の人が、Kontrabassを舞台下にsettingをしてしまいました。
rehearsal の時に私がcheckをすれば良かったのだけど、忙しくて、check出来ませんでした。
そうしたら全員舞台で演奏出来たのに・・・ね??
今回の最大の反省で、悔やまれます。ハイ!(以上、You Tubeのcommentより)
![]()
音楽形式はそれぐらいにして、次にはbaroque時代のConcertoの演奏形態のお話をしましょうかね??
tuttiの部分は(Vivaldiの極めて珍しい例外を除いては)simpleに単純に作るのが常識でした。
作曲家が自分の名人芸を見せるのは、勿論、soloの部分です。
このお話をする前に、baroque時代の作曲法は、通奏低音(basso continuo)の作曲法の時代である・・というお話をしなければなりません。
通奏低音は音楽用語では、basso continuoと言います。
bassoとは低音、所謂、Baßを指します。
continuoは、dramaの最後に出て来るContinueと同じ意味で、「続く」と言う単語なのです。
ですから、それを纏めて、basso continuoは通奏低音という約になります。
baroque時代の演奏形態では、soloに対しての伴奏で、「何の楽器で伴奏するのか??」という事は、実に曖昧でした。
・・というか、その場にある楽器、若しくはその場に居る人が伴奏する・・という事で、楽器が正確に、その楽器でなければならない・・という事は無かったのです。
極端に言えば、soloの楽器ですら、Violin、or、fluteと書かれていたりする事の方がorthodoxだったのです。
という事で、伴奏もviola da gambaが通奏低音を弾いて、Cembaloの代わりに、Lauteが和音を提供したり、guitarのおばけであるtiorbaが伴奏をした場合もあります。

tiorbaだけの伴奏によるCacciniのAmarilli, mia bellaです。
なんと、美しい❢❢
いや、女の人が、じゃあなくて、baroque時代の発声法が・・です。
(画像をclickすると、You Tubeへlinkします。)
当時のConcertoは、繰り返されるsoloの部分をより効果的にする為に、通奏低音のpartをviolinやviolaに振り分ける事もあったのだが、その場合には、orchestraのpartとしての伴奏の場合と、partからのsoloだけで伴奏する場合があった。
なんだかんだ・・と、説明すると、ややこしくなってしまうので、掻い摘んで言うと、soloの伴奏を色々な伴奏の形態で伴奏した・・という事なのですよ。
soloに対して、Violinのpartが伴奏をしたり、Violinのpartのconcertmasterやpart‐masterがsoli(一人づつ)で、伴奏したり・・です。
時には、continuo‐Celloの代わりに、Violaのsoloでcontinuoを演奏する場合もあり、soloに対しての伴奏・・と言っても、結構、多様的に伴奏したのですよ。
また、solo自体も一人だけで演奏する、所謂、こんにちでは普通の、solo楽器によるConcertoと、当時の普通の室内楽の形式であったtrio‐Sonate(※)を組み込んだsoli群、所謂、2台の楽器のsoloとcontinuoの楽器による形式、所謂、Concerto Grossoの形式としてのConcertoとしてのも作曲されていた。
まあ、いずれにせよ、作曲技法的にはcontinuoに拠る作曲法に準拠する。
(※)trio‐Sonateというgenreは通常は同族の楽器2本の交唱と和音を司る楽器に寄って構成されるので、trioなのだ。しかし、この和音を司るというのが、難物で、2本のmelodie楽器に対しての、Baßの楽器は和音を司る楽器(所謂、basso continuoの楽器であって、Baßのpartの符の上に数字で和音を表しているだけなので、格別楽器を指定している分けではない。
だから、上の写真のtiorbaのように、一人で低音の動きから和音迄を演奏出来る場合には、通奏低音を受け持つviola da gambaのような低音楽器は必要はない。
Händelの名曲であるrecorderSonateのような曲を、 Hans-Martin Lindeは、古式豊かに、viola da gambaとCembaloに因る典雅な演奏styleに拠る伴奏のCDと、Lauteに拠る所のSessionとも言える、悪ノリ直前迄の演奏の二枚のCDの演奏の違いは非常に面白く、且又、優れた演奏である。
baroque時代では、独奏と呼ばれる演奏形態はこんにちの私達が呼ぶように、伴奏を伴う場合ではなくて、Ohne Begleitung(無伴奏)というgenreがあった。
音楽と言うか、一つのmelodieの中に、Baßを司る部分と和音を司る部分、それにmelodieを司る三つの部分に分けて演奏されたのである。
それに対して、一般的なsoloの曲の場合には、こんにち知られているようなviola da gambaとCembaloが、basso continuoを演奏する事は、実際上は稀であって、(CembaloやOrgan等の楽器は非常に高価な楽器であって、王宮や教会等にしか、所有される事は無く、庶民的、一般的では無かったので、)低音を司るviola
da gamba(若しくは、Cello)とLauteやguitarが和音を弾いて伴奏をする事が寧ろ、一般的であった。
また、低音で和音を指示するviola da gambaは低音を司るguitar族であるthéorbe(キタローネ)に代用される事もあったのだ。
(つまり、baroque時代では、その場所に準備出来る楽器で演奏の代用していたのだよ。)それは、驚く事に、solo楽器ですら、他の楽器で演奏される事もあったのである。
(violin2台をfluteが演奏するとか?あるいは1台がfluteで、2台目はViolinとかで、しかも、伴奏の楽器に至っては、何の楽器が伴奏するか・・という事は、その都度の対応だったのだよ。だから、作曲者も、楽器に対しての、必然性は、然程厳密ではなかったのだよ。)
orchestraの場合には、ritornelloのtuttiに対してのsoloの部分で構成されるのだが、通常は、soloの部分は、basso continuoと呼ばれるgroupで伴奏される。
和音を司るので、Baßの通奏低音を演奏するviola da gambaとその音の上に、和音を司るCembalo(若しくはLaute)で構成されるのが一般的なのだが、soloが繰り返される場合には、その演奏形態だけでは、飽きが来るので、それ以外のpartを使用して、orchestraのpartであるviolinのpart等が伴奏をする事も通常であり、一般的である。
しかも、その伴奏は、orchestraのpartとして、複数の奏者のunisonで演奏されるripienoの場合と、part-Leaderが一人でsoloの伴奏をするconcertinoの伴奏の場合がある。
また、楽器的特性に応じて、continuoのviola da gambaのpartをviolaが担当する事もよく見受けられる。(音量的な配慮に拠る。)
continuoは日本では単調に(simpleに)演奏される場合が殆どなのだが、和音を司るcontinuoとしての場合と、soloに対する対旋律(Kontrapunkt)としてのmelodieを司って演奏する場合があるので、その弾き分けが大切なのである。
(Bachの場合には、invention(※)から、その奏き分けの説明をしている。themaに対しての対主題としての旋律と、themaの和音を付けるためのcontinuoとしての旋律の違いである。その違いはbaroque時代の全ての作曲家に共通するbaroque時代の様式としての奏法である。その違いを分からずして、continuo
Celloを弾く事は出来ない。)
・・・と言う事で、continuoを演奏する場合には、その演奏のstyleを変えて演奏しなければならない。
所謂、continue-soloでの、ワキの奏法と、シテの奏法の違いの弾き分けを明確に出す事である。
(※)「芦塚先生のお部屋」⇒inventionとsinfonia
http://ashizuka-s-oheya.ashizuka-ongaku-kenkyujo.com/bc...