
ご父兄からの質問メール
こんばんは。
夜分に申し訳ありませんが、どうしても気になってお尋ねしたいと思い、メールさせていただきました。
アイロンがけやら繕い物やらしながらCDをかけていたのですが、先ほどまでヴァイオリンを聴いていてピアノ曲に変えたところ、ヘルツのためかと思われますが、音が低くノスタルジックなかんじで音の高さに違和感を感じます。前々からなぜだろう?と思いつつ棚上げにしていたのですが、どうしてヴァイオリンとピアノの調律は異なるヘルツで行うのですか?たとえばピアノ協奏曲のときはオケはピアノのヘルツにまでみんなが下げているのですか?また管楽器はどうなのでしょうか?
芦塚先生、どうか疑問を解消してください!
たぶん、ピッチの事はホームページの論文に詳しく書いていたと思うのですが、どのPageに書いたのか思い出せませんので、簡単にご説明させていただきます。
参考までに、教室のホームページ[芦塚音楽研究所]から、「芦塚先生の部屋」⇒「楽典のお話」⇒「baroque時代のpitch」で、少しpitchに関して触れていますので、ご参考になさってください。
まず、余談で・・・:
ご質問にお答えする前に、言葉の定義をします。
[ヘルツとサイクル]
まず、ヘルツという言葉とピッチという言葉ですが、ピッチとは音楽用語では音の高さの事を言うようです。
ヘルツというのはもっと厳密な振動数の事です。
Aの音は何ヘルツであるか、というように使用します。
1Hzとは1秒間に一回振動した、という意味です。
ヘルツもサイクルも同じ振動数の意味です。(勿論、1?の音は低周波と言って人には聞こえない音ですがね。)
ご質問の意図は、Pianoとorchestraのpitchが違うという事は、Pianoを単独に聞いて、他の曲を聞いた時に・・・別のタイミングでorchestraの演奏を聞いた時に・・・、というと意味が変わってしまうので、orchestraのconcerto等でPianoのpitchが・・・という意味の二つに解釈が出来るので、チョッと回答が変わってしまうので、どちらの意味かな??と考えてしまったのですが、最初の意味だとすると、それは、Pianoもorchestraも、結構好みでpitchが変わったりするので、論外になってしまいます。
orchestraとの共演等でpitchが変わってくるとなると、それは結構、大問題なのですが、それはそれで理由はあります。
orchestraの基本では、pitchは一番pitchの調整が難しい楽器を基準にして、チューニングします。通常はオーボエが一番音が合わせにくいので、オーボエを基準にして全体の楽器をチューニングします。
Pianoを使用するorchestraの場合には、会場では、当然、Pianoに合わせてチューニングをする分けですが、orchestraの楽器は自由にチューニング出来るわけではありませんので、基本的には、Pianoはorchestraの楽器のチューニングの範囲内のpitchを越してチューニングする事はありません。
一見すると矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、次のbaroquepitchのお話と読み比べて貰うとわかりやすいかもしれません。
baroqueのpitchは後述しますが、基本的には435サイクルから430サイクルです。世界で最初に統一の国際高度を決めた時の国際標準pitchは435サイクルだったのです。
だから、本来的なbaroqueのpitchは435サイクルでなければなりません。
しかし、Cembaloのような古楽器でも、現代の440サイクルで演奏しなければならない機会が多いのです。特にアンサンブルをする時に、baroqueの音楽の演奏をbaroqueのpitchで演奏するには演奏者がbaroquepitchの楽器を持っていなければならないからです。
しかし、baroquepitchの楽器を持っている人はproと言えども非常に限られています。
という事で、仕方なく、Cembaloを現代の標準pitchの440サイクルで調弦した場合に、鍵盤を下にスライドさせて、半音下の音を弾くようにして、便宜上それをbaroquepitchと定めました。
つまり、半音下のAsの音をbaroquepitchのAの音にしたのです。これで、baroque楽器を持たない人達もbaroqueのpitchで演奏する事が出来るようになりました。
参考までに:Pachelbel chaconne f 芦塚陽二version(A=418)で、ホ短調で演奏していますが、実はf moll へ短調です。
baroquepitchでは、f mollの曲ですが、ホ短調にする事で、baroque楽器を持たない子供達でも、baroquepitchで演奏する事が出来る分けですよね。
concerto等の場合には、pitchは基本的にはsolisteではなく、指揮者が決めます。
演奏会では、コンサートが始まる前に、予めPianoの調律を調律師がチューニングします。そのPianoのpitchに合わせて、orchestraの楽器がチューニングをするのですが、それはPianoのAに合わせて正確にチューニングをします。
但し、コンサートホールでは、空調の性やお客さまが入る事によって温度や湿度が急激に変化するので、弦楽器や管楽器は可能な限り演奏しながら微調整をしながら演奏します。
それでも、orchestraのpitchがPianoよりも高くなってしまう事はママあります。
ご質問の内容はそういったことでしょうか??
[基準のpitch]
古の昔は、基準になるpitchというものはありませんでした。
 私達は「Fiori musicali baroque ensemble」と言う、とてつもなく長い名前で古楽器の演奏団体として演奏をしています。
私達は「Fiori musicali baroque ensemble」と言う、とてつもなく長い名前で古楽器の演奏団体として演奏をしています。
その古楽器の時代のヴァイオリンやチェロなどの弦楽器は、現在のような張りの強い切れにくい色々と加工された弦ではなく、それこそ自然なままのガット(羊やブタの腸から作られた弦)で演奏しますので、その日の気温や湿度のコンディションに左右されて、切れたり、演奏中に緩んでしまったりしました。
そのために、その日の演奏会の基準のpitchは、その日の気候の状態で、一番良く鳴って切れにくい弦の張り具合のpitch(音の高さ)で演奏していました。
それがヴァイオリンなどを基準に考える場合には、通常は(一般的には)、435から438の間である事が多かったのです。
ヴァイオリンという事は、チェロやバス・ガンバ等の低音をつかさどる楽器はもっと低いpitchでもよかったはずです。
あくまでヴァイオリンやソプラノ・ガンバを中心に考えた時のお話ですよ
管楽器は逆で、むしろ現代よりも高いpitchの楽器も多く見受けられたのですよ。
弦楽器を中心として、考えた場合に、ガット弦のpitchの限界として、438辺りのpitchがbaroquepitchと呼ばれるようになったのです。
ですから、教室の生徒達の場合には、普段443サイクルでチューニングしているので、もしガット弦を使用して演奏した場合には、弦が張りすぎて、演奏する前に、すぐに切れてしまうでしょうね。
そう言う風にガット弦は、現代の弦と比べて張りが弱く、pitchを高くする事は苦手だったので、それが理由で「baroque時代はpitchが低かった。」という通説が流れてしまいました。
通説(風説)というのは、先程も言ったように、pitchが低かったのは弦楽器のガット弦のためであって、管楽器では逆にpitchは高かったからです。
つまり、baroque時代にはpitchが低かったというのは、それは弦楽器を中心にして考えた時のお話であって、風説に過ぎなかったのですよ。
[管楽器の場合]
弦楽器が切れやすい弦の張力のせいで、pitchが低めになることのほうが多かったのに対して、管楽器は逆にpitchが高い方が演奏が楽である事は今も昔も変わりありません。
ヨーロッパの村のブラスバンドの基準のpitchは町の教会のオルガンのpitchに合わせて、作られることが多かったのです。
その主な理由は、勿論、利用頻度です。
教会では毎週の日曜日の午前中に、定期的におこなわれるGottesdienst(日曜礼拝)のために、色々な音楽(楽器)が演奏されました。教会での演奏の方が、お祭りやイベントなどの演奏よりも遥かに演奏回数は多かったのです。(楽器の使用回数が多かったと言うことです。)
そのために、村の管楽器のpitchはその村の教会のパイプオルガンのpitchにあわせて制作されることが多かったのです。ヨーロッパの村は、教会との結びつきとても強く、また映画も音楽会もない、単調な村の生活にとっては、唯一の娯楽であり、息抜きでもあったのです。
参考:小さなKochel村の教会

私が初めてドイツの地に足を踏み入れて、アルプスのふもとの小さな村に語学研修のために2ヶ月程暮らした。この小さな村の小さな教会の礼拝堂にも、立派な(小型のポジティーフ・オルガンではなく)本格的なパイプオルガンがあって、Pianoがなくて練習が出来ない私のためにパイプオルガンを、ミサが行われている時以外は、いつでも快く貸してくれた。その頃の日本ではパイプオルガンはNHKと武蔵野音楽大学と・・・という風に、「まだ日本で2,3台しかない・・」という時代であったのだが、さすがにオルガンの国であるドイツでは、どんな小さな村にでも、素晴らしい本格的なパイプオルガンがあった。
今の人達には、もう理解できない事かもしれませんが、昔の(昭和20年代頃までの)日本もお寺がそう言った民衆の心を支える役目を持っていたのです。
また、蛇足ですが、パイプオルガンを調律するのは、まるで大工さんの作業のように、かなづちを持って、1本、1本のパイプをトンカチ、トンカチと調性します。大変な作業で何日もかかってやるので、本当に容易な事ではなかったからです。現代のパイプオルガンともなると、6千本、7千本というパイプのtuningをしなければなりません。それこそ、調律が終わるまで、1ヶ月、2ヶ月という、天文学的な作業です。だから、村のブラスの管楽器を教会のパイプオルガンのpitchに合わせる方が、数倍も楽だったわけです。というわけで、「Baroque時代のpitchや、古典派の時代のpitchをどういう風に調べるのか?」という事は、その時代のCD等の録音がなくとも、当時の保存されている楽器を調べる事で、正確に分かります。
それで、改めて、ヨーロッパの各地の村々に残っている楽器や教会のpitchを調べて見ると、前述の「baroque時代や古典派の時代のpitchは低い。」という通説は裏切られる事が多く、その村のpitchの中にはかなり高いpitchもあって、その中には現代の標準のpitchよりも遥かに高い448サイクルの村もあったそうです。
もっと困った事には、一つの村のpitchであったとしても、時代によって高くなったり低くなったりを繰り返した、痕跡があることです。曰く、それ程、pitchは情緒的で不安定なのです。
ですから、baroque時代や、古典派の時代は現代よりもpitchが低いと一般的に言われているのは、俗説であると言う事は、すでに証明されています。(とは言っても、今でも専門的な音楽大学ですら、そういう風に教えているのですがね!)
弦楽器はガット弦の強さの問題があってそう簡単にpitchを上げる事が出来ませんが、逆に大量のブレスを必要とする管楽器は低いpitchは音が出にくくなってしまい、当然音の張りもなくなってしまいます。高いpitchの方が息継ぎも楽だし、音に張りがあって、神々しく華やかに響きます。だから、管楽器が中心の村ではどうしても、pitchが高くなる傾向がありました。
管楽器が村民を中心に発達して言ったのに対して、弦楽器は楽器が高価なことも、習得が大変難しいという事もあって、宮廷の中で職業として発達していきました。地方の豪族達の知性と豊かさのステータスとして、イタリアから音楽家を呼び寄せたりしたのです。
というわけで、極端な場合には一つの村に、宮廷のpitchと教会のpitch等々、複数のpitchが同時に存在する事もまれではありませんでした。
(閉鎖性の強い村では、同じ村に住んでいたとしても、職種が違っただけでも、交流が行われない事は、そんなに珍しいことではありませんでした。マイスターというかギルド制がそう言った閉鎖性を増長していたからです。)
しかし、そういった事は、時代が進んで、色々な村々との交易が頻繁におこなわれるようになり、文化的な交流もよく行われるようになると、色々な村と合同で音楽会を企画し演奏する機会も増えてきて、楽器のpitchの不統一は、そういったイベントなどにはなはだ不都合になってしまいました。(当時の楽器は現代の楽器のようにpitchを微調整するための機能もついていませんでしたからね。)
そこで、かなり古い時代から、基準の音を決める必要が出来て、何度も話し合いがもたれてきました。それがだんだん国際的になっていって、19世紀からは世界のベースで、何度も基準音を決める会議がありました。そして、最終的には1939年ロンドンの国際会議でAを440Hz決めて、それが世界の標準pitchという事になって今日に至っています。
話は前後しますが、ここでもう一つお尋ねの、「それからなぜ教育関係は440なんでしょう?443にしてしまえばいいのにと素人としては思うのですが、理由があるのでしょうか?」 というご質問にお答えしようかと思ったのですが、それは諸説紛々で、どれが正しい答えなのかはわかりません。
「教会で神父達がグレゴリオ聖歌を歌うときにちょうどよい中間音域の切の良いpitchである。」とか、先日は「お産の時に産声を上げる赤ちゃんの最初の泣き声がAのpitchである。」という事を、まことしやかに述べている人もいます。(私は男性なので、その事実は分かりかねますが・・・。)
私がその事について、あまり深く追求しないのはその国際標準pitch自体が、最初から音楽家達にとって守られる事はあまりなかったからなのです。
つまり、通常のコンサート・ホールやorchestraは演奏会高度(pitch)というのを使用していて、通常は442から444Hzが普通です。私達の教室も普段から443Hzの演奏会用pitchを使用してlessonしています。教室の発表会や対外出演などはコンサート・ホールでやることが多く、殆どの会場のピアノのpitchが443サイクルになっているので、子供達が混乱しないようにするために443サイクルのpitchを採用しているのです。
日本では、国際標準pitchの440Hzを意固地に守っている所は学校でのみ(当然、学校と言っても音楽大学は除きますが)です。ですから演奏会のホールでも教育会館のピアノは意固地ついでに基本的な440で調律されています。
ここでも、先程のmailの後半のご質問、「443にしてしまえばよいのに・・。」 というお尋ねの答えは、その443サイクルと言う数字自体が、単に慣習的なものであって、その根拠とするに足るだけの必然的な理由が特別にはないということなのです。
演奏会高度は指揮者や演奏家の好みで決められます。そこに根拠はないのです。
ベルリン・フィルは演奏会高度がとても高いので有名です。
しかし、orchestraのpitchは原則として指揮者が指定します。その権限は指揮者にあるのです。ですから、当然、指揮者が変わればオーケストラのpitchも変わります。指揮者が特にオーダーを出さないタイプの指揮者の時には、オーケストラのpitchを指定するのはコンサートマスターの役割です。勿論、ソリストが自分のpitchをorchestraに要求する事もよくあります。Orchestraの奏者はその都度色々な注文によるpitchを、好むと好まざるとにかかわらず、弾き分けなければならないのです。
また、日本で一般的に市販されている日本製のorchestra用の演奏会用の楽器は、その殆どが442サイクルです。
それに対して、大概のホールのピアノは443サイクルで調律されていることが多いようです。
しかし、不思議な事に録音スタジオのピアノのpitchは442の場合が多いようです。
それも単なる慣習的なもので、何か根拠があってそうなっているのではありません。
というように、「基準になるべきpitchを何サイクルにするのか?」という事は、好みの問題であり、原則としてpitchに関しての決まりはないのです。
「440サイクルの2octave下の音は?」といわれた時に、瞬間的に「110!」と答える事ができますが、
「443サイクルの2octave下の音は・・?」と聞かれても、「110.75!」って、瞬間的に答えられる人は少ないでしょうからね。それでも、Octaveならまだいざ知らず、5度上の音や3度上の音も計算で出す事も実際の現場ではよくある事なのですよ。
学校教育においては、演奏会pitchのような、441から446に至るような、そういった確実性のないpitchの中からいずれかのpitchを標準pitchとして定めるよりも、国際会議で国同士で決めた区切りの良い国際標準pitchの方が、何かと便利であるという事で、440サイクルのpitchを採用した、というところでしょうかね。
また、学校は本来アカデミズムの権化ですから、一旦定めた教義は何があっても死守しようとします。そこが、学校の学校たる所以です。
そう言った日本の小学校の教育上の依怙地さ、頑迷さの、その顕著な例は、「世界中で日本しか使用されていない、ドイツ式リコーダー」のお話をすると、その体質がよく分かるのではないでしょうかね??
ドイツ式リコーダーはヒットラーの少年少女親衛隊であるヒットラー・ユーゲントのためにナチの委託によってドルメッチにより開発されました。当然、音楽的な価値は全くなく、負の遺産としての歴史的な価値しかありません。
また、そのドイツ式のリコーダーについては、それを開発した張本人のドルメッチですら、後年、自分の誤りを自分の伝記で自ら公表しています。
当のドイツですら誰一人その存在すら知らないドイツ式リコーダーを、世界中でただ一国、戦後60有余年の歳月を経た今でも、いまだに日本の学校だけが使用し続けていのですからね。
不思議な話です。
現在は、中学校ではもうイギリス(baroque)式recorderを使用するところがだいぶ多くなったようですが、小学校でドイツ式の運指を習ってきた生徒達は、中学校に入学した途端に、baroque式の指使いを新しく覚えなおさなければ、ならないのですがね。
それなら、最初からイギリス式のリコーダーで勉強すれば良いと思いますよね。
まだ、日本が大変貧しくって、富国強兵として、国のお金の大半が軍隊に行ってしまって、教育にお金を使う事ができなかった時代には、子供達に本物の楽器のイミテーションである簡易楽器や、実際には現実の社会では全く使用される事のない摩訶不思議な教育用楽器と言うものがあって、幼稚園や小学校で、そう言った楽器を使用して音楽を教えてきました。
その結果は、子供達は「学校の音楽は貧弱でつまらないものだ」としか受け取ることが出来なくなってしまいました。経済的にはもうすっかり豊かな時代になっていたはずの、お母様達の子供時代も、しかし、簡易楽器や摩訶不思議な教育用の楽器に悩まされてきたのではないでしょうか?
世界に冠たる経済大国になった今現在、日本では教育にお金をふんだんに使う事も出来ます。
私も(というか、教室としても)幾つかの小学校、中学校にorchestraを作るためのお手伝いをしてきました。
しかし、それなのに、やはり相変わらず、学校では子供達のrecorderはドイツ式なのです。どんなに間違えた教育であろうとも、それを変える事は出来ないのです。
学校とはそういう所なのです。それこそ学校がアカデミズムたる所以なのです。
こんな事を言うと、オーボエ奏者に怒られてしまいそうですが、orchestraの楽器の中で一番音合わせがしにくい楽器がオーボエであるといわれています。
というわけでorchestraは慣習的にオーボエが基準のAの音を取り、それに弦楽器や管楽器などのほかの楽器があわせていきます。
余談ですが:
私の弟子が、今年の某音楽大学の受験生のための冬期講習を受けた時に、ヴァイオリンの先生から「ヴァイオリンの音を合わせるのにAの音を耳で聞いて調弦するのは、幼稚園生までだよ!大人になったら、チューナーは音を出さずに(ヴァイオリンの音も聞かないで)、チューナーの目盛りを目で見て合わせるんだよ!」と言われて、呆れて帰ってきました。
勿論、tuningの話だけではなく、その後のlessonの内容も同じように五十歩百歩で・・・ですが、それには、ここでは触れないことにします。
あまりにもばかばかしいので、言わずもがな・・ですかね。
彼女の話を聞いて、教室の先生達には信じられない話ばかりで、「うっそ〜!お義理でも音大の先生でしょう??」 と、カルチャーショックだったようです!!!ハッ、ハッ、ハッ!
余談の余談ですが:
某国立orchestraのコントラバス奏者の先生が、某名門学生オーケストラを指導に来ている時の話です。
そのコントラバスの先生が学生達に「長年のオケの経験でわかったことは、オーケストラでは音でチューニングすると喧嘩になるのでチューナーの目盛りで合わせたほうがよい。」と言う話をされていたそうです。
音楽大学の先生なら兎も角も、卑しくもプロオケの奏者の話としては、ちょっと笑えない話ですね。
余談の解説です:
どうして、こんな馬鹿げたお話がまかり通るのでしょうか?
つまり、プロのオケマンであっても、完全5度を正確に合わせると言う事が出来ないと言う悲しい現実があるからです。
では、どうして、プロともあろう人達が完全にpureな5度を作れないのでしょうか?
はっきり言って「pureな完全5度を作るのは難しいからなのですよ。」 ・・・アッ、ハッ!それを言っちゃ、元も子もないか??
私達の教室の生徒達が、プロにとっても難しいpureな完全5度を、なんなく作れるという事は、これは芦塚メトードの独特な指導法にその理由があります。
それは芦塚メトードにおける「間違いの練習法」というメトードによるのです。
「間違いの練習法」というのはtuningのメトードではありません。「間違いの練習法」という大項目であり、その大項目の中には無数の中項目があり、更に小項目もあります。
例えば、子供がどうしてもある箇所をmisstouchをしてしまって、幾ら練習しても直らないとします。
私のメトードでは、その間違う音を意識的に間違えて練習させます。
Lisztのラ・カンパネラでは2octaveの速い跳躍があります。誰もがFisの音を弾かなければならないのに、間違えてF?の音を弾いたり、Eの音を弾いたりしてしまいます。ですから、逆に2octave飛んでいる時に、先生が「F?!」とか「G!」とか叫んで、生徒はわざと間違えて先生の指定した音を弾きます。それによって跳躍のintervalの感覚を身につけるのです。 こういった方法論で練習をすると、生徒達は殆どmisstouchをしなくなります。安定性が出来てきます。
今の「間違いの練習」の例は生徒を指導する場合の例でしたが、先生の場合にも、そう言った練習が必要になるケースがよくあります。その中の一例をあげると、私達の教室の先生は、当然、生徒の曲を模範演奏出来るまで、弾けるようにしなければなりません。ここまでは、どこの音楽教室でも同じでしょう。しかし、模範演奏が出来るだけでは、私達の教室の先生としては充分ではありません。
先生に与えられた、もう一つのしかも「最も重要な課題」は生徒の「間違い」をちゃんと真似して弾けるという事が出来なければならないという事です。
それも、「同じように真似をする」・・・・だけではなく、デフォルメしてオーバーに真似る事が出来なければなりません。先生が幾ら生徒の真似を上手にしても、生徒の方は自分が正しいと思い込んで弾いていたとすると、先生が子供の真似をして演奏しても、子供に分かってもらえない・・というケースがよくありえるからなのです。ですから、子供にも分かりやすいように、もっとオーバーに表現することが必要な場合がよくあるのです。
こういったことが出来るようになる事は、先生の技術の向上にとっても、とても良い勉強になります。
ちょっと長い、お話でしたが、今、お話をしてきた事と同じように、Pureな正しい5度を生徒達に指導する秘訣は、間違えた正しくない5度の響きを教えればよいだけなのです。
しかし、不思議な事に、そう言う指導が日本人の指導者には出来ないのだな?・・・・・つまり、「間違える事を子供に指導する事は、教育ではやるべきことではない。」と思っている。(勿論、間違えて指導するのは、教育ではないのだが・・!!)
だから、痛みを知らない無慈悲な子供が育ってしまうのだよ!
音を合わせると言うのは二つの振動が完全に同調(同期)する事を言います。
二つの近いサイクルの音はほんの少しでもサイクルがあっていないと、余分な微細な振動を出します。この余分な振動を全くなくすのが、pureな完全5度の響きを指導すると言うことです。
ピアノやCembaloの調律は弦楽器のチューニングと違って、平均律のチューニングをします。ですから、弦楽器のようなpureな完全5度ではないので、最もっと高度で難しい知識と技術を要します。ピアノやCembaloのチューニングに必要な事は5度をどの範囲までに狂わせるかと言う技術です。
そのもっとも一般的なピアノやチェンバロの平均律のチューニングには5度で音を合わせていく(狂わせて行く)、5度調律と3度で合わせていく(狂わせて行く)3度調律というものがあります。
5度や3度を狂わせていく、と言っても、あてずっぽうに狂わせるとそれこそ大変な事になります。
どの和音もめちゃめちゃの響きがするようになってしまうのです。ですから、それぞれの音を正確に狂わせなければなりません。また平均律は半音の音程の幅が全てが同じであるように思っている人が多いようですが、実はそれぞれの半音の幅は同じ幅ではないのです。ドとレ♭なら何セクト、レとミ♭なら・・と言う風に正確に決まっているのです。
というわけで、よく調律師が3度の和音を鳴らしながら、腕時計を耳に当てて調律しているという光景を見にしたことが・・・・・・、今時、あるわけないよね!!
今は電子チューナーのメモリ(針)だもんね!
ハッ、ハッ、ハッ!(笑)
私もCembaloを調律する関係上、5度調律、3度調律の両方で調律が出来るようには・・・、しています。ですから仮にチューナーがなかったとしても5度調律か、腕時計で(私は時計は持ち歩かないのですが・・) 3度調律かで調律をする事は出来ます。腕時計の秒針の音と3度の和音が引き起こす「うなり」の音をシンクロさせることで、微妙な音を正確に狂わせる事が出来るのです。
ですから、私にとってはpureな完全5度を作ると言う事は、いとも簡単な事です。
私がこれまでpureな完全5度ということばを使用してきた事を不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。「Pureな5度とは、完全5度のことではないか?」と思われたかもしれません。
その言葉の理由を次に説明します。
5度を完全5度に合わせる。しかし、生徒達に指導する場合には、困った事に、この完全5度の振動の幅が意外と広いのです。
その前に、少し長くなりますが、Aのpitchの事を説明しておきます。Pureな完全5度のお話の前に基礎知識として必要だからです。
教室の子供達は、正確に440、441、442,443、の違いを言い当てる事ができます。これは別に絶対音感がまだ育っていない生徒でも、Aの音だけは言い当てる事ができるのです。
しかし、弦楽器を正しくチューニングする場合には、その100分の1のサイクルまで聞き分けなければなりません。
極普通の一般の人には440.00サイクルと、440.03サイクルの違いを聞き分ける事は出来ないでしょう。
何故出来ないのか?
答えは簡単です。

![]() 一般に市販されているメトロノーム式のチューナー(メトロノームとチューナーが一緒になっている機械)は非常に高性能なメトロノームでも、チューナーとしては440〜445サイクルまでの1サイクルずつの刻みです。例外的にbaroquepitchの音を出すものもあり、438(435)とスライド鍵盤用の415サイクルが設定されています。しかし、小数点以下のpitchの微調整を持っているチューナーは、特別なチューナーで通常、一般の店舗では販売されてはいません。
一般に市販されているメトロノーム式のチューナー(メトロノームとチューナーが一緒になっている機械)は非常に高性能なメトロノームでも、チューナーとしては440〜445サイクルまでの1サイクルずつの刻みです。例外的にbaroquepitchの音を出すものもあり、438(435)とスライド鍵盤用の415サイクルが設定されています。しかし、小数点以下のpitchの微調整を持っているチューナーは、特別なチューナーで通常、一般の店舗では販売されてはいません。
右の写真はセイコーの電子メトロノームで、私のお気に入りのメトロノームの内の一台です。 Pitchはbaroquepitchの415と、438から446までを1刻みで設定する事ができます。(baroquepitchを持っているメトロノームは珍しいのです。)
そう言った事よりも、このメトロノームで特に気に入っているところが、メトロノームのtempoを2つ同時に設定する事が出来て、第一tempoから第二tempoへと、正面のボタンで瞬時にチェンジする事が出来るという、このメトロノームの機能です。
しかしながら、幾ら高性能のメトロノームであったとしても、100分の1のサイクルのpitchを出すわけではありません。
殆どの音楽家は、100分の1サイクルのpitchを確かめながら、音楽の勉強をする事は通常は有り得ないという事なのです。
しかし、私達の教室では、子供達に純正調を指導していますから、当然100分の1のサイクルの単位が必要になってくるのです。
100分の1の音程の訓練と言っても、それを感覚的に指導しているわけではありません。
教室には100分の1の音程を作るためのキーボードが数台あります。(数台と言うのは教室別に1台ずつ・・と言う意味です。)
![]() この写真の製品はヤマハ製です。
この写真の製品はヤマハ製です。
 教室で使用している古い方の楽器は「ハーモニー・トレーナー」と言っていたようですが、この楽器は「ハーモニー・ディレクター」と名前を変えています。一見すると1,2万の安物のキー・ボードのようにも見えますが、本体価格は16万ぐらいする超高性能の代物です。(それに別売の脚台等の付属品が必要です。)
教室で使用している古い方の楽器は「ハーモニー・トレーナー」と言っていたようですが、この楽器は「ハーモニー・ディレクター」と名前を変えています。一見すると1,2万の安物のキー・ボードのようにも見えますが、本体価格は16万ぐらいする超高性能の代物です。(それに別売の脚台等の付属品が必要です。)
「純正調を子供達に指導している。」といっても、勿論、平均律を指導しないまま、いきなり純正調でorchestraの指導、教育をしているわけではありませんよ!純正調を勉強している子供達にとっては、まず、平均律は出来て当たり前の事なのですから!
私達の教室ではオケのグループを年少グループから、年中、年長グループの3段階に分けています。3段階といっても子供達のキャパシティーでの分類ですから(実際の年齢は関係ないので、本当は初級、中級、上級という呼び名の方が正しいのでしょうが、いたずらに子供の競争心を煽るようなので、そう言った呼び方は避けているのです。) 当然、年中の生徒は年少のグループのお手伝いが出来て、年長のグループは年中と、年少のグループのお手伝いが出来るわけです。
私達は子供達のオケを指導する時には、その生徒達が既にその曲をマスターしたとしても、それでその曲は「卒業」という考え方はしません。何回も年下のグループのお手伝いをする事によって、自分達が勉強した曲のフィード・バックをさせていくのです。これはオケ練習のカリキュラムのお話ですが、当然、年中オケや年長オケのグループに入る前に
(中年オケやおじいさんオケではありませんよ!)、年少オケや室内楽などで、・・・或いは普段のlessonの指導の中で、絶対音感を勉強しているのですから。
当然、「年中や、年長のオーケストラ・グループの生徒達にとっては、平均律の音は当たり前の事として、ちゃんとpitchを取れる。」と言う前提のお話です。
私が今ここでお話しているのは、もう一つ上のグレードの音感訓練のお話です。
ヤマハで売っているハーモニー・ディレクターですが、これは主に学校のブラスの指導用として売られています。ですから、キーボードとして一般の販売店に陳列されている事は非常に少なく、音楽学校を目指している学生達ですら目にする機会は殆どありません。キーボードとして使用するだけのためには非常に高価な楽器ですから、その使い方を知らない限り、一般の音楽家が、このキーボードをこの値段で買い求める事は無意味です。
ですから、この楽器はブラス・バンドの訓練用にとしてしか販売されていないのです。
一般の人達が絶対音感を育成するために、高いお金を出して、このハーモニー・ディレクターを買ったとしても、絶対音感を育てるためのカリキュラムがなければ、実際には絶対音感が身に付く事はありません。よく一般の人達が間違う事ですが、その道具を買えば、それなりに何らかの効果があると期待します。しかし、残念ながら、道具は道具に過ぎないのです。それを、どう使用するかでその道具の本当の価値が決まってくるのです。
私達の教室でも、「音符カード」のように、市販の物で、代用が出来るものは、なるべく市販の物で間に合わせるようにして、先生達が音符カードなどを製作しなくてもよいように、無駄な努力をしないですむようにしています。
しかし、私達の教室のlessonを見学した外部の先生方が勘違いして、「市販の音符カードを買い込んできて大体同じようにlessonすれば私達の教室の子供達と同じように、音符がすらすら読めるようになると思い込んでしまう。」という事は、はなはだその理解が短絡的で残念な気がします。
このお話には、さらに尾ひれが付いて、「芦塚メトードとはオリジナルのものだと思ったのだけど、市販のカードを使って指導していると言う事は、オリジナルではないのでは?」という、もっととんでもない事を外部の先生に質問されたこともあります。
市販の音符カードを使用して、譜読みの訓練をしている、芦塚メトードの「メトード(譜読みのメトード)」というのは、ソフトの事であって、使用するカードは別にどのカードでもよいのです。
ハーモニー・ディレクターも全く同じ事が言えます。つまり、ハーモニー・ディレクターを買ったからと言って、生徒達に絶対音感が付くとするのなら、そこらの小、中学校のブラスの部活の生徒達にも全員絶対音がついていなければなりませんよね。 ところが、それが、そうはいかないのよね!!
ここでやっと本題に話を元に戻して、・・・・・・・
音楽を専門に勉強する人さえ、通常では100分の1のpitchの世界は体験した事がないので、どうしても、正確なpitchを身につけると言う所は曖昧になってしまうのです。
ですから、どうしてもオケマンには、低めにチューニングする人と高めにチューニングする人が出てきてしまいます。つまり、完全5度の幅は思ったよりも広いのです。
それがAの音の話だけならば、そんなに問題はなく、そう言った「pitchは針で合わせなさい。」とかいう誤った事を言い出す先生もいなくなるはずです。
しかし、ヴァイオリンやチェロ、コントラバスなどは基本的には4本の弦を持っていますから(コントラバスは五弦もあるので)、曖昧な音から、更に曖昧な完全5度で、次の音、次の音と受け渡されて行くと、最終的には、それぞれの音の微妙なずれが増幅されて行って、例えばヴァイオリンを例に取ると最低音のGの音が全く誰とも合わないという事になってしまいます。
ましてや、フルオケではAのpitchの管楽器(通常はA管と言います。)やB♭の楽器(当然、B管です。)、Es管の楽器にホルンなどのF管の楽器なども、一つのオーケストラの中に渾然として存在します。ですから、オーケストラで「ド」の音を一つに聞こえるように合わせると言うのは至難の技なのですよ。だから、先程の話「チューニングは針でするほうがよい。」という話になるのです。そりゃ、単なる勉強不足だよね!
アッ、ハッ、ハッ、ハッ!
某国立オーケストラで、オーケストラの奏者が全員で、自分のチューナーの針を見ながら調弦をしているのを見るのは、きっと壮観だろうね!?
私達の教室は弦楽オーケストラなので、Aをピュアーなサイクルの中で(振動の中で)高めに合わせて、各自がそれぞれの弦を高めに5度のチューニングをします。(勿論、コントラバスは4度調弦ですがね。)チューニングが終わったら、たまに確認のために全員でGの音を出すことがあります。
それで全員の音が完全に合っていて、混じりけのないピュアーなGの音が出たら、完全に音が合っていると言うことです。(「4本の弦を1本、1本、弦が合っているかどうかを確かめる必要は無い」と言う話です。)
音を耳で聞こうとしないで、機械の針でtuningをする人が、正しい音感を持てる事はない、という事は当たり前ですよね。
耳で音を聞くことをしないで、チューナーの針で音合わせをすると言う事は、絶対音感どころか、正しいAの音さえ「聞き分ける事が出来ない」と言う前提に立っているわけでしょう??
先程の某国立orchestraの先生は、潜在的に「私はAの音が分かりません。」と言っている事になってしまうのですよ。
耳で正しいpureなAを取る事が出来ない人が、A♭やCの音、色々なpitchの音を聞き分ける事が出来ないのは当たり前でしょう??
基準の音さえ聞くことが出来ないのに、どうして、octaveの残りの11個の音が聞き分けられるのでしょうかね。ましてや、「Aの4分の1高い!」 なんて聞き分けるのは、そりゃ「至難の業!」じゃなくって、「不可能!」でやんしょうよ!!
それで、わが国を支える、某国立音楽大学の先生??某国立orchestraの奏者??
それじゃぁ、お先真っ暗じゃん!!
でも、本当に、お先は真っ暗なのかもしれません。
私がコンクールの審査員に呼ばれて、受験生達を審査をした時の話ですが、小学生ならまだいざ知らず、中学生、高校生になっても、tuningがすばやく正しく出来る生徒はいませんでした。コンクールの地方予選なら、いざ知らず、本選、全国大会でですよ!
あまりの酷さに、伴奏者がヴァイオリンを取り上げてチューニングした事もあります。(プロのヴァイオリンの伴奏者はヴァイオリンも演奏出来ます。)
私もコンクールの時に、受験生がtuningが出来ないままに弾き始めようとしたので、生徒を止めて「D線からのtuningをやり直しなさい。」と叱った事があります。
その時に審査に見えられていた他の先生が「芦塚先生は自分の生徒でもない生徒にtuningをやり直しさせた。」と自分の生徒と他人の生徒に対しての分け隔てない態度に甚く感激されてしまいました。私としては、そんなに深く考えたわけではなく、たんに狂ったpitchで曲を聞かされるのがたまらなかっただけなのですがね。
余談の余談の余談ですが:
私達の教室の生徒達は、ピュアーな5度の取り方や純正調の音の取り方等を学びます。
まず、最初はpureな完全5度の中で、高めのpureな完全5度、真ん中のpureな完全5度、低めのpureな完全5度の3段階が識別出来るように訓練をします。
その訓練を積んでいる内に生徒達は、半音の半分や半音の4分の1の違いも分かるようになってきます。
ですから弦楽器を勉強する生徒達も、ピアノを勉強する生徒達も殆どの生徒が絶対音感を持っています。(ピアノではtuningをする事はないので、ピアノの生徒の音感をつける指導はまた別のやり方なのですが、今回はお話が長くなりますので、それには触れません。)
例えば、つい先日のお話ですが、小学校の1年生の女の子のお父さんが子供のヴァイオリンのチューニングのためにi-podを買ってきました。さっそく、Aの音を鳴らしてみると、その女の子が「pitchが低い!」と文句を言いました。お父さんは「i-pod
だからAが狂っているわけはない。」と言って子供と喧嘩になってしまいました。そこでお父さんが教室に質問に来ました。
それで、担当の先生が「標準Aと演奏会pitchのお話」を説明して、「子供の主張も正しい」という事を説明しました。お父さんは「子供に負けた!」と悔しがって、喜んでいましたがね。
まぁ、負けたか勝ったかは親子のcommunicationの話で、どうでもよいことですが、つまり、お父さんが買ってきたi-podは標準の国際高度である440サイクルで、子供の絶対音は演奏会用高度の443サイクルだったわけです。勿論、その事が分かっていれば、i-podでも、443サイクルに基準音を直すことができます。今のキーボードはおもちゃでなければ、殆どの楽器がpitchの切り替えが出来るようになっています。
さて、よく私達の教室の子供達は「殆どの生徒達が絶対音感を身に付けている」というお話をよくしますが、まずは「Aの音を正確に覚える」と言う事がなければ、絶対音感が身に付くという事はありえません。当たり前のお話ですがね。
「絶対音感を習得する」と言えば、今年の秋口に、江古田の事務所を椎名町に引越ししましたが、その町には絶対音を習得させる事を売り文句にして、それだけで長野や名古屋などの関東各都県から、椎名町に生徒達を集めている(この私でさえその存在を知っているという)超有名音楽教室があります。
そこの教室の生徒達は、絶対音感を習得するために、小学生の低学年の時から、何年も何年もかけて、日夜、絶対音感が身に付くように努力しているわけですがね・・・・??
そこの教室との一番大きな違いは、私達の教室の生徒達は取り立てて絶対音を身に付けるための特別な訓練はしていないのに、いつの間にか絶対音感が子供達の身に付いてしまうという事なのです。
補足:
「なんとなく絶対音が身に付く。」 なんておいしい話は、まぁ、絶対にありませんよね。
「いつの間にか絶対音が身に付く。」 と言うのは、あくまで生徒の側からの感想であり、指導者が「絶対音が自然に身に付くような特別な訓練をしなければ、子供達に絶対音が身に付く。」という事はありえないのは、当たり前の話ですよね。
椎名町のその教室との大きな違いは、「努力するのが先生か生徒か・・」の違いでしょうかね??
次のお話は今までの話とは、間逆のお話です。
「某国立音楽大学に行きたいから・・・!」と言って、中学校を卒業すると同時に教室をやめて、某国立音楽大学の先生のところに替わって行った生徒がいます。当然、某音大ではscaleの試験があるので、その某音大の先生の指導の元にscaleの勉強を、ピアノで一音、一音取って、ヴァイオリンでそのpitchを一音一音合わせて弾いていくと言う日本型の勉強を高校生の間の3年間、みっちりやらされてしまいました。
3年間の涙ぐましい受験勉強の期間を経て希望の某国立音楽大学に入学した頃には、もうすっかり子供の頃に私達の教室でしっかりと身に付いていた、「半音の半分や4分の1半音を聞き分ける絶対音感の能力」は失われてしまっていましたよ。
その結果、彼女の愛用の楽器もすっかり音が出なくなってしまっていましたよ。
当然、某音大では楽器の「konsonanzを使用しての作音」というのはやらないのでしょうからね。
(蛇足:konsonanzという単語は普通の今の辞書ではなかなか出てきません。日本の辞書では木村・相良のドイツ語の辞書ならちゃんと出てきます。)
日本の音楽大学では、音を取るのに「ピアノに合わせて音を取る」なんて、とんでもない教育がいまだにまかり通っているのですね。(勿論、Aの音だけを取るのであれば、何の問題もありませんがね。)
生徒だけでなく、先生ですら、平均律と言う意味や、調律の事、或いはピュアーな純正調の事が全く分かっていないという事なのですね。
困ったものです。
余談の蛇足で、チューニングとは直接は関係がないのですが、弦楽器の奏者や大学の先生達がチューニングの時によくやってしまう、ヴァイオリンの製作者やディーラーにとってはとても考えられない、ヴァイオリンや弓を壊しかねない恐ろしいやり方があり、私達は驚かされてしまいます。
*よく音大の先生達がやっている、松脂を多めに塗った後、弓をピッ、ピッと振って余分な松脂を落とすやり方は、弓のコンディションにとって最悪だと言うだけでなく、もっと最悪の場合には弓が折れて、修理不能になってしまいます。
*チューニングの時に、ペグを何回もウィーンウィーンとかコキコキとか回すやり方は、“当たり”を取り除く方法なので、やればやるほどペグが止まらなくなり、pitchが合わなくなってしまいます。
*最悪のチューニングはチューニングが下手な音大生がチューニング中に音が低めになったら、peg-boxの内側に指を入れて弦を押してpitchを上げるやり方です。この方法は、演奏中に楽器のpitchが下がった時に非常手段として使用する場合がありますが、通常のチューニングでそれをやってはいけません。そのチューニングでは演奏中にすぐにpitchが下がってしまいますし、ヴァイオリンにチューニングの当たりは出来ません。まして、そう言ったチューニングでは正確なチューニングをする事は出来ないのです。
*ちょっとしたコツですが、木製のpegは穴との当たりのために、完全にpitchを合わせてしまうと、pegから指を放した瞬間に、ほんの少しpegが引っ張られて、pitchが下がってしまうのです。チューニングの上手な人はそのラグを計算して少し高めの時に指を放します。また、新しいヴァイオリンを買った時など、教育用pitchの440サイクルで当たりが出来ているヴァイオリンの場合があります。その場合にはその当たりを取ってしまって、443サイクルの演奏会用のpitchに当たりを付けないといけないので、当たりを取ってしまうために、前述の間違えたやり方(pegをコキコキ回すやり方)で当たりを取ってからチューニングをしなおして、新しい当たりを作ります。
*弦楽器をケースにしまう時に、楽器を拭くときには、必ず松脂の付いている所を拭く布と、それ以外のところを拭く布は分けなければなりません。松脂が付いた布で胴体などを拭くと、松脂でコーティング・ニスを削ってしまうからです。・・・・えっっ??「拭かないでケースにしまうからいい!」って・・・??
[baroquepitchについて]
最初のお話は、先程のお話とダブってしまいますが、さて、その他には所謂、baroquepitchというのがあります。
リコーダー(Recorder)も、本来はbaroque時代の楽器ですから、プロ仕様の楽器は435〜438Hzが一般です。
勿論、日本の学校用のrecorderは国際標準pitchの440サイクルの調律です。
というわけで、私が所有している木製のrecorderはbaroquepitchなので、私達の教室の生徒達の発表会でも使用する事ができません。
教室の発表会のpitchは演奏会pitchの443?だからです。
ですから教室の子供達のための発表会用には、木製のbaroquerecorderではなく、日本製のプラスチックのrecorderを使用します。
参考:芦塚先生所有のbaroquepitchのrecorderのセット

蛇足:
しかし、日本製のrecorderはモダンpitchであったとしても、440サイクルですよね。では教室の443サイクルのpitchとは合わないのではないか?と思われる方も多いと思います。
それはそうなのです。
しかし、recorderはブレッシングでpitchを調整することができます。息を歌口に強く吹き込むと、pitchは高く上がります。息の速度を強く早くするために吹き込む息を糸のように細く鋭くする事によって、透徹力のある美しい音を作る事ができます。
そうすると、440サイクルのrecorderでも、443サイクルまでpitchを上げて演奏する事ができるのです。
一見するとpitchが全く変えられないように思われがちのCembaloですが、現代のbaroqueCembaloには、baroque時代には無かったスライド鍵盤という機能を持っているCembaloがあります。
教室で演奏会用に使用している2段のグジョン・モデルのconcertoCembaloと1段のルーカス・モデルbaroqueCembaloもスライド鍵盤の機能を持っています。
私の個人所有のグジョン・モデルのconcertoCembaloです。

色々なpitchに対応するためにCembaloのpitchを、頻繁に調律によって変える事は、Cembaloのpitchが不安定になるだけではなく、Cembalo本体の構造にも負担を与えてしまう結果になります。
ですから、楽器への負担を省くために、鍵盤をスライドさせて、半音下の弦を弾くようにして半音低い音が出るようにします。
つまり、鍵盤を移動する事で、AでなくってGis(As)の弦を弾くのです。現代のキーボードのトランスポーズという機能でCをBに設定する(移調する)のと同じ事になります。
ですから、Aの音はbaroquepitchよりも遥かに低いGisの音、つまり415Hzになります。
ちなみに、私達の教室で使用しているCembaloのスライド鍵盤は、教室の基準のAのpitchが443サイクルなので、スライドさせたAの音は418サイクルになります。
当たり前の話ですがね。
しかし、その415サイクルのpitchではbaroqueviolinのガット弦にとっては、 ちょっと低すぎてしまって、violinの音があまり鳴らなくなってしまいます。
やはり、ガット弦も435から438ぐらいの方がきれいな音がします。
recorderに至っては、同じbaroqueのrecorderであっても、415サイクルのrecorderはめったに製作されてなく、415サイクルのrecorderを買い求める事は非常に難しい事かもしれません。
幾らbaroque時代であったとしても、当時415サイクルまでpitchを下げる事はそんなになかったからです。
ですが、モダンの440のpitchと、普段切り替えなければならない可哀そうなCembaloの場合には、スライド鍵盤のpitchは楽器の保護のためには仕方がない必要悪でしょうかね。
でも、その必要のないいつもbaroque音楽だけを演奏している団体が、どういうわけか、Cembaloのpitchを415サイクルで堅持しているのは、ちょっとlacherlich(お笑い)です。
Baroquepitchが便宜上のbaroquepitchである415サイクルと勘違いした事によるものです。
(意味を知る事も無く慣習に従っている結果です。)
私達の教室の場合、教室にある2台のスピネットの内の1台をbaroque専用にすれば、435〜438ぐらいのpitchで調律できるので、baroqueviolinやrecorder等の楽器的には良いのですが、今現在は2台のスピネットとも教室で普段に子供達が使用しているのでそれが出来なくって困っています。「じゃぁ、もう一台、baroque専用に買えばよいのでは・・・?」
アハッ!!そんな、バブリィーな!!
ちなみに、今日では、スピネット・タイプのCembaloでも、スライド鍵盤を持っているものが売られています。
90万前後で買えるのかな?
それこそ、よもやま話になってしまいますが、後は、ソロpitchと呼ばれるものがあります。
実際に、solopitchというtuning法があるわけではありません。
ですから、このお話はpitchの話とは直接的には関係がありませんが、orchestraの中で、ソロの楽器の音が浮き上がって聞こえるようにソリストがorchestraよりも、ほんの少しpitchを上げ気味にして演奏する事を言います。
「上げ気味に演奏する」と言っても、1ヘルツも上がるわけではありません。0.1とか0.05Hzとかの素人目には分からない程度にpitchを高めに取るのです。
このお話はプロの演奏家の場合のお話ですが、その先は応用編です。
[教室のtuningの隠し味]
教室では伴奏のピアノとヴァイオリンをほんの少し変えてチューニングします。
ピアノが演奏会高度で443ヘルツならば、ヴァイオリンは443.3Hzぐらいまで上げるのです。
そうすると、伴奏に対してしっかりと浮き上がって聞こえてくるのです。
しかし、この違いは一般の人達が聞き分けられるほどの差では困ります。本当にお客様達に悟られない範囲で、ごくわづかの差を付けるのです。
一般の発表会の場合には、先生達はピアノと子供達のヴァイオリンを全く同じpitchにするので、ピアノの音量に負けてしまって、ヴァイオリンの音が聞こえなくなったりします。
しかし、私がやっているtuningのお話は、これは裏技なので、一般にばれてしまう程、大きくpitchの差を付けてしまうと、逆にみっともなくなってしまいます。
[演奏会の会場でのpitchの変化]
演奏会場では、人の体温で客席の温度が急激に変化するために、楽器は最初に調律したときから、演奏の終わりまでにかなりpitchが上がってしまいます。
極端な場合には、C Durの曲がCis Durぐらいまで上がる事も珍しくはありません。
管楽器は温まると、pitchが上がっていくからです。
管楽器のpitchが上がっていく中で、orchestraが常に正しいpitchに調整しなおしながら演奏すると、かなり興ざめなしらけた感じになるので、弦楽器も管楽器も自然な温度の変化に合わせてpitchを徐々に上げていくのです。
そこで、やっとご質問のお話になります。
先程のピアノ・コンチェルトの場合の「ピアノのpitchが低く聞こえる」というお話ですが、一応は、ピアノも会場の温度が高くなるにつれて、pitchが上がる事は上がります。
しかし、弦長が短い弦楽器や、人の息で楽器が温まってしまう管楽器の温度差には、ピアノという楽器はとてもかなわないのです。
よく、冬場の演奏会の前に、管の人達が必死になって「ひゅうひゅうと」管楽器に息を吹き込んでいる光景を目にしますが、それは急激なpitchの変化を防ぐために、予め管楽器を自分の息で暖めているのです。
会場に人が入ってきて、会場の温度が急激に上がると、とんでもなく管楽器の温度が急激に上がってしまい、pitchが演奏中に急激に異常に高くなるのを防ぐために、あらかじめ、演奏する前に楽器をある程度暖めているのです。昔、私が乗っていた車も、冬場は車を走らせる前に暖気運転と言って、エンジンをかけるとしばらくの間、アイドリングをさせてエンジンを温めておかなければなりませんでした。しかもエンジンが冷えている間は、手でチョークという混合気を作るノブを引いて音と排ガスの色を見ながら少しずつ微調整したものです。
ご質問の「ヴァイオリンのCDを聞いた後に、ピアノの演奏を聞くと低く聞こえる。」と言うお話ですが、まずは実際にpitchが違う場合のお話だけをしてきましたが、もし、お母様が聞いているCDについての質問ですが、どのCDもそう言う風に聞こえてしまうとしたら、原因は実際のpitchのお話でなく、次の二つのお話がその理由になります。
そのまず一つ目は、私のホームページにも、掲載していますので、軽く触れるに留めておきますが、オケ練習などで、湿度が高かったり、生徒の元気がなかったりで、どんよりとした雰囲気で練習が上手く行かないときがあります。そういったときには非常手段として、「今日は、乗りが悪いから444で行こう。」とかいって、生徒達の楽器のpitchを上げて、練習をしなおすことがあります。そうすると、見違えるように、活き活きと音楽が蘇ってきます。でも、普段の子供達が元気なときには、444のpitchは高すぎて、逆に子供達にストレスを与えてしまうのですよ。不思議な話ですが、これは私しか、やっていないような子供達のコントロールの仕方のようです。
二つ目は、よくプロの音楽家でもだまされてしまう音の特性に、音の遠音のお話があります。(遠音についても私のホームページにもその幾つかの例を掲載しています。)
楽器の音色や音の質で、その音のpitchが高く聞こえたり、或いは音自体が(本当は強い音なのに)弱く聞こえたりする事があるのです。
私がこの音の遠音のお話の説明をする時に、いつも引き合いに出すのはハープです。
ハープの音はとても柔らかい優しい音なので、ハープ奏者が優しく弱く弾いているように思われますが、実はハープは大変音量のある楽器なのです。
ですから一見すると、柔らかい優しい音で弾いているように思われますが、実は大フルオーケストラをたった1本のハープの優しい音で支えてしまう事が出来るのです。
「支える」と言う言葉はまたまた、業界用語ですから、説明しますと、つまり、オーケストラがfortissimoで演奏をしていたとしても、優しいハープの音がちゃんとオケの大音量の中から浮かび上がって聞こえてくると言う意味です。
1本のハープのarpeggioの伴奏で大オーケストラがmelodieを弾いていくというpassageすらよくあるのです。
そう言ったような音のマジックは、ハープ以外の楽器にも色々見受けられます。
私は不思議な事に音大在学中も、留学中もよくlessonのピアノの下見を頼まれる事がよくありました。私がOKを出すと、不思議に教授もその曲を合格させるからです。
という事で、私がまだMuchenの音楽大学に在学していた頃、MozartのPianoconcertoをオーケストラ・バックで演奏会で弾くピアノの生徒の練習の下見をしていたことがあります。
そのMozartのPianoconcertoなのですが、ある箇所でオーボエ2本がoctaveのユニゾンでmelodieを演奏する箇所がありました。ピアノで(この場合pは「弱く」と言う意味の「ピアノ」ですがね。)Melodieを2本のオーボエでoctaveのunisonで演奏しているときに、ピアノのsolopartの指定も当然pで弱く演奏しなければならないという箇所がありました。
そこの箇所を、私は「ここはオーボエは楽器的な特性上pで演奏する事は無理なので、Pianoのpartも同じようにforteで演奏しなければならないのですよ。」と説明しました。
その後で、その生徒が担当のHindemith教授(大作曲家のPaul Hindemith教授の従妹かな?)のlessonを受けた時に、そのpassageの演奏をHindemith教授は烈火のごとく怒って、「そこはMozartが楽譜にpと書いているでしょう?」と、言って「もっとPianoで!」「もっと、もっと、pianissimoで!」とエスカレートしてしまいました。
その後、彼女が私のlessonを受けると、私が「そこはもっとforteで弾かないと、オーボエに音量が負けてしまって、ピアノの音が聞こえなくなるよ!」と言うので、可哀そうに、そのピアニストはパニックになっていました。
ホールでのオケリハの当日、orchestraがそこの箇所に差し掛かると、案の定、2本のオーボエは一生懸命にpで演奏してはいるのですが、音域的にpで弾く事は無理なので、当然、オーボエの音が強すぎて、ピアノの音がかき消されてしまい全く聞こえなくなってしまいました。
それを客席で聞いていたHindemith教授は、顔を真っ赤にしながら、「もっとforteで!」「もっと、もっとforteで!」と叫んでいました。
アッ、ハッ、ハッ、ハッ!
ところがそのpassageをCDに録音してしまうと、そのオーボエのpartがpで演奏しているように聞こえるのだから不思議なものです。
勿論、作曲家はそういった楽器的な特性も考えてオーケストレーションをしているのですがね。
ちょっと話が細かくなってしまいましたし、音色のお話はpitchの話とは直接には関係がないように思われるかもしれませんが、纏めてみると、実は「鋭い音は高めに聞こえ、それに対して柔らかな音は、例え音量が強い音でも、弱く低めに聞こえる」と言う特性があるのです。
Pianoの場合、音色は楽器が決めるように思われがちですが、実はそうではありません。
やはり、touchの良し悪しで、同じPianoでも「これが同じPiano!?」というほどに、弾き手のtouchによって、Pianoの音色が全く変わってしまいます。
私がドイツ留学から帰国して、再び東京に住むようになった頃の、今からもう既に40年近くも以前のお話です。
私はそれまでは積極的に生徒をとって指導していた音楽大学の学生時代も含めて、子供を指導した事はありませんでした。
ですから、私が初めて指導した子供達の中の一人である小学校に入ったばかりの女の子は、私の個人的な音楽の指導の研究という意味もあって、最初から(Beyerの段階から)leggierotouchのMozart奏法で指導しました。その生徒が小学3年生頃になって、Czernyの30番やインベンションなども終了した頃になると、とても柔らかな優しい美しい音でMozartやBachなどの演奏が出来るようなっていました。
その生徒がコンクールに参加したときには、審査員から「もっと力強い音で弾きましょう。」との評価を貰いました。つまり、あまり良い印象は与えなかったようです。
しかし、実はその日は、私はミキシング・ルームで、NHKの録音技師の人や楽器製作者の人達と一緒に聞いていたのですが、コンクールの審査員が模範演奏として弾いていたピアノの音は録音機器のメーターが半分も上がらず、ホールの関係の人が「ホールの真ん中までも音が届いていない。」とぼやいていました。
私の弟子の小学生の生徒が演奏した時には、会場では耳には、とても音が優しく、弱く聞こえたのですが、実はミキシングルームのメーターはMaxを振り切っていたのです。
音楽大学を卒業して、オーディションに通ったピアニストでもメーターを振り切れる事はめったにないのです。
ですから、会場の録音技師の人も「会場の隅々までしっかり音が届いています。」とその子のtouchと音を絶賛していました。
(それは先日の大崎の教室のオーケストラや室内楽の演奏でも、同様の評価をPAの人や、会場のプロデューサーからもいただきました。)
日本人初のforte-pianoのtouchが出来るMozart奏者になれたかもしれないと周りの人達から期待され、絶賛されていた生徒ですが、家庭の事情でピアノを中学生になるときにやめてしまいました。「どういう、家庭の事情??」 つまり、家庭の事情ですよ!
その後は、Mozart-touchの生徒は一人も育てていません。
Mozart奏法のforte-pianoのtouchはあまりにも専門的過ぎて、録音技師や古典専門の研究者や楽器製作者達等の専門家の人達から以外には、正当に評価されることがないからです。
つまり、音楽の専門家であっても、遠音の聞く音と唯単に弱い音を聞き分けられる人達はいないのです。自分でそう言う音を出せない限りね!!
さて、「ピアノ・コンチェルトの場合には・・・」 というご質問には、まだお答えしていませんでしたね。
さてさて、困りました。きっと、指揮者の人達も頭を抱え込むでしょうね。
実はオーケストラの演奏会場では、先程も言ったように、本当はピアノも演奏中は、少しづつpitchが上がっているのです。
ですが、管楽器や弦楽器ほどに、極端に上がるわけではありません。
ですから、そこはプロ、実際に管楽器や弦楽器が本来上がるはずのpitchよりも少し低めにpitchを戻してピアノに合わせて、ばれない程度にpitchを調整しているのですよ。
勿論、最初の弾き始めのpitchよりは高くなってはいるのですがね。
(しかし、先程も言ったように、orchestraでは自然に上がっていくはずのpitchをあえてそのままのpitchにする事は、(お客様が興ざめになるので)通常はする事はありません。
そう言った上げる幅の微調整が必要なのはピアノ・コンチェルトの場合だけなのですよ。これはお客様には内緒の話です。)
とりあえずは、ここらまでにします。
参考までに:
http://ashizuka-onken.jp/chouseitoonnkainituite.html
調性と基準音の話です。
2009/12/06 (日) 12:10
昨夜はありがとうございました。
昨夜は遅い時間にメールしたにもかかわらず、早速にお返事を下さってありがとうございました。ピッチというんですね。こんなに広い幅がピッチにはあるんですね。添付されていたリンクのお話などは難しくてわからないことだらけでしたが、管楽器が温まるとピッチが上がって弦楽器がそれに合わせて上げていくなどおもしろいオケ内の事情をきけておもしろいなぁと思うと同時に、そんなことをしているなんてすごいなぁと思いました。それからなぜ教育関係は440なんでしょう?443にしてしまえばいいのにと素人としては思うのですが、理由があるのでしょうか?昔々はいろんなピッチがあったのは仕方ないとわかりますが。ピアノ協奏曲では先生のお話ですと、上がっていく管楽器に合わせて弦楽器も上げていき、主役のピアノはほとんど最初のピッチのまま他からおいてきぼりになるということですよね。曲が進むにつれ他に比べ沈んでいくということですか・・・?ピッチのお話は不思議なことが多いですね。
(このメールを書いている間に、ご父兄からお返事をいただきました。そのお返事に対しての回答です。)
先程、頂いたmailのお返事の最後のお話には、少し誤解があるようですから、もう一度確認のために説明をしておきます。
管楽器や弦楽器は自分達の楽器のpitchが上がっていくのを、少ししかpitchが上がらないピアノに合わせて、上げ幅を少なめにして演奏すると言うことなのです。
ピアノが「曲が進んで行くにつれて沈んでいく」という事は「ピアノのpitchを無視して、それぞれの楽器がpitchを上げていく」と言う事をおっしゃっているのだと思いますが、オーケストラは学校ではないのですから、そういった置いてけ堀にするという事は絶対にありません!
プロのオーケストラの演奏は、全員で一つの音楽なのです。
一人でも落ちこぼれていては、全体の演奏が「下手だ!」といわれてしまいます。
ですから、「置いてけ堀!」は、絶対にないのです。
その代わりに、プロの世界では出来なきゃ「首」なだけです!
あるのは、「出来るのか?」「出来ないのか?」 と言う話だけで、陰湿な虐めなんか、ないんですよ!
すっきりしたものですよ。「出来なきゃ、 首よ!!」、 「首!!」、 「首!!」
ましてやPianoconcertoでは、Pianoがsoloなのですからね。
ソロというのは、オーケストラにとっては、お客様という意味ですよ!
お客様を立てるのが、営業ですからね。
しかし、人生、色々あるもので、極稀に、ピアノが沈んでしまっているCDがないわけではありません。しかし、それは、唯、下手なだけの、「ヘボ・オケ」です。
そう言ったCDは買わないこと!
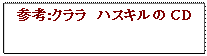 ・・・という事で、今回、クララ ハスキルのMozartの23番のPianoconcertoをネットで見つけて、購入しました。
・・・という事で、今回、クララ ハスキルのMozartの23番のPianoconcertoをネットで見つけて、購入しました。
 もう、販売されていないCDなので、プレミヤが付いて、なんと1枚6千円もしました。
もう、販売されていないCDなので、プレミヤが付いて、なんと1枚6千円もしました。
さすがに、クララ ハスキルのMozartのPianoの演奏は見事なのですが、オーケストラの下手な事!
いやぁ〜、ヘボ・オーケストラの下手な事!・・・・下手な事!
クララ ハスキルのPianoの音がヘボ・オケの音に潰されて、もごもごしてしまっているのです。
勿論、録音も最悪だしね!
「こんな、名演奏家もこんなCDを出すんだ!」という見本にしては、ちょっと高いなぁ〜!
2010年 1月 某日
江 古 田
一静庵の寓居にて
芦 塚 陽 二