
baroque時代の絵画のような持ち方は、modernbowを使用する現代のviolin奏者達にとっては、異種文明のculture・shockの持ち方であり、そういった持ち方に変更出来る人は殆どいない。
そのためにbaroqueviolin等の奏法そのものが、fremd(未知との遭遇)の分野になってしまう。
(右側の写真は、baroqueの絵画ではなくルネサンス期の絵画であります。指の状態がよく見えるので掲載しましたが、未だviolinではなく、violinが出来る前のルネサンスの古楽器になります。)
私達の教室では、子供達はviolinを学び始まる一番最初から、baroqueviolinと同様の、1点支持の弓の持ち方をしているので、baroqueviolinのbaroquebowに持ち替えても、違和感は全くないのだ。
私の教育方針である、「奏法の原点は、そのrootsにある」という事による。
拠って、violin奏法の1点支持であり、Pianoの生徒達がBeyer教則本の時から勉強をする(forte-piano奏法でもある)single actionの「leggieroのtouch」でもある。
baroqueの弓の持ち方と現代の弓の持ち方を、一つの曲の中で変えて演奏した例を、生徒達の実際の演奏で見る事が出来る。八千代の連続演奏会である。
Corelli=Geminianiのla foliaは、baroqueの音楽ではなく、擬古典の曲であるので、当然、普通の演奏styleを採用して演奏している。
しかし、その中にbaroqueのperiod奏法を、もちいて演奏している部分がある。これは必見である。
Corelli=Geminiani la folia
一般によく誤解されている事なのだが、そもそも「無伴奏というgenreの曲は、無伴奏のmelodieで演奏される」という意味ではない。単にohne Begleitung (伴奏のない)という意味で、そこに「一声部」という意味はないのだ。
Telemannの12のfantasiaでも、書いているように、melodieに、伴奏のpartとmelodieのpartが書かれていて、それを表現するための、細かいarticulationを表すbowslurなのだ。
Bachのfacsimile版では、それらのarticulationが非常に細かく、また、実に緻密に、しかも、正確に書き表されている。
私がこのphraseを演奏させる時には、Motivの切れ目であり、調を決定させる重要な音を表すための短い音の停止(それは殆ど和声の主なる音を表すのだが・・)と、phrase(melodieの切れ目《Stollen》)を表す中程度の長さの終止と、大きなphraseの区切りを表す長い終止を区別して演奏させる。
この事は、無伴奏というgenreの音楽を演奏する上では、極めて重要なpointとなる。
蛇足ではあるが、基本的には、Bachの無伴奏の曲の場合には、エンドレスで書かれている。(しかし、endlessとは言っても、終わりの音が、次のphraseの最初の音になるからであって、 Wagnerのトリスタンの無限旋律とは根本的に発想が違う。)
では、実際に、最初のphraseである冒頭から、6小節目までのarticulationを書き表して見よう。
(6小節目まで・・、というのは、それが文節の区切りであり、以下同文になって、延々と同じ説明を繰り返して続ける事は無意味であるからだ。)
小学生や中学生の生徒達に注意している事は、「一時が万事」であり、パソコンの作業と同様に、themaのarticulationを変更すると、以下の同じthemaのみならず、同じthemaから派生した全てのMotivまでも同様に変更される・・という事なのだ。
全ての音楽のlessonは、同様であり、その曲の持つmaterial(要素)をlecture指導すれば、後は、「以下同文」で済ませる事が出来る。
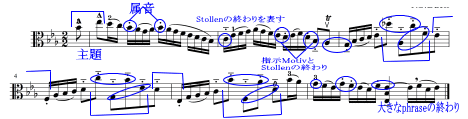
予め注意しておくが、次の(右に掲載した)楽譜に書かれているarticulationであるstaccatosostenutoやstaccato等は、音を鋭くとか強くとかいう意味は持たせていない。
本当ならば、数字か記号でも良かったのだが、finaleの入力の都合で既成のarticulationを使用したに過ぎない。
1小節目のB、Esの音は呼びかけを表すようなthemaである。
だから、次のD,Cはmelodieのauftaktである。
しかも、次のBは属音を表すので、際立たせのstaccatoであり、音を切るという意味はない。
2小節目の冒頭のsostenutostaccatoは、phraseの切れ目を表し、またSdominanteを表すための重要な音なので、強調して演奏し、次のauftaktの16分音符に入る間は、この場合には、二番目の切れ目を表す「カンニング・ブレス」になる。(記号で書く場合には、カッコの付いたブレス記号(V)になる。
2小節目の4拍目の裏のtrillと次の16分音符は、bass-melodieを表す重要な音であり、1拍目の後の16分音符は、auftaktになる。
つまり、主題の提示部とも言える最初の6小節は、前半部を2小節目と3小節目を跨ぐ音符で分割されて、6小節目の3拍目が allemandeの主題の提示の終わりとなり、4拍目が次の展開部のauftaktとなる。
という事で、このコンマは完全なブレス(記号はVである。)でなければならない。
また、3小節目からは、Sequenzによる進行であり、そのSequenzはしっかりと表現されなければならない。
ちなみに、3小節目の8分音符のMotivは上のククリ(括り)がmelodieを表し、下のククリはbaseの音を表す。・・・多声部書法の所以である。
次の8分音符は上のpassageがmelodieであり、下の8分音符はBassの音になる。
その奏き分けは大切な要素である。
実に、ミニマムな演奏を要求されているように見えるが、Bachはそうしたミニマムなapproachが、音楽をチマチマとした演奏にならないように、大きな指示動機(Leitmotiv)を作っている。
このmelodieを大きく捉えて行くとthemaのBとEsの8分音符だが、8分音符だけを追って見ると、B,Esと演奏された音が、3小節目ではDes,C、4小節目で更に、C,B、次の5小節目でもB,Asと来て、6小節目のstaccatoでG,GF,FEsと大きなmelodieを構成している。
音楽を大きく捉えて演奏表現する事は、baroqueから近現代に至る迄の、重要な表現であり、その殆どがBassfuhrungによって書かれている。
このBachの無伴奏での、melodieでのfuhrungtonは、極めて珍しく、Bachならでは・・と、言わざるを得ない。
縦の和声的な構成と、横の大きなmelodieの構成が、点描されているのだ。
これがBach時代の無伴奏の特徴である。
その原理を知る事無しに、無伴奏を弾く事は出来ない。
「無伴奏を勉強した」とは言えないのである。
しかし、今日の作曲技法から見ると、甚だ、楽理的であり、理屈っぽい!それはどうしてなのか?
ルネッサンスからbaroqueに掛けては、神に近づくには、完璧である事が求められた。
三位一体を表す3拍子 Brevisの原理同様に円が完全な物・・数学こそは神の意思(教義)となった。そこから対位法の発展が生み出されて行く。
fugaやpassacaglia等の数学的な動きは、baroque時代の神聖な作曲の理念でもあったのだ。
無伴奏というgenreの音楽も、そういった教会的な教義に影響を受けている事を忘れてはいけない。
音楽がそういった教会や神の概念から離れて、人間の感情を表現するようになるには、ロマン派の時代までは待たなければならないのだ。
しかし、こんにちの演奏家達は、そういった現代の人間を中心とした、情緒的、感情的な音楽のapproachの感覚でルネサンスやbaroqueの音楽を、全く同様に捉え、解釈しようとする。
そこには重大な時代錯誤(戦国時代に機関銃を持った少女が登場するような・・・)が存在する事を理解しようともしないで・・・・。
参考までに、Maurice Gendron校訂の版を掲載しておく。日本の全音楽譜出版社から出版されている版である。

あ〜あ、またまた愚痴になってしまった・・・!!