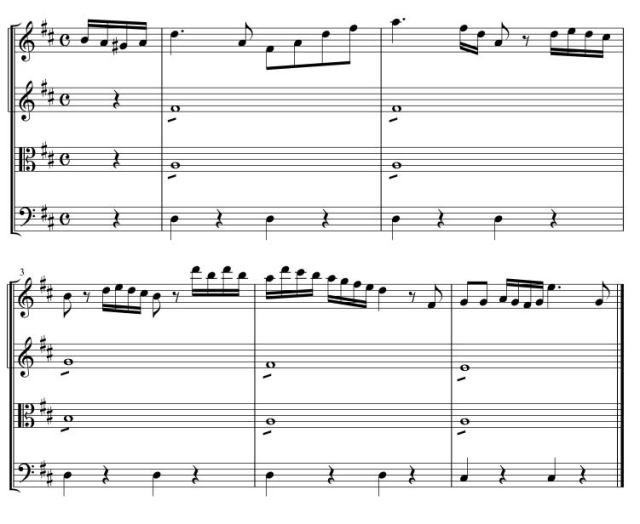
上は弦楽Quartettのarrangeでしたが、下は弦楽trioのarrangeです。

弦楽器の場合には、こういった同音連打は、左手のpositionはそのままで、動かないので、右手のfingerbowだけでleggieroで演奏するので、非常に簡単で軽やかな感じに演奏出来ます。
それをそのままPianoにtransposeすると、左手の手首が硬直してしまい、ぎこちない動きになってしまいます。
だから、左手のbeatを活かして、しかもBasのcelloのpartも活かして、Alberti-Basで演奏します。
Basのpartは、celloのimageで少し長めにsostenutoで演奏します。
たった、それだけを気をつけるだけで、恰もorchestraのように聴こえるようになります。
古典派の奏法はそういったkleinigkeitの積み重ねで演奏するのです。
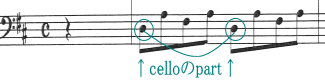
古典派の奏法に関して、その曲から、一つ一つの奏法を解説lectureする事は、思いの外大変です。
つまり、当時の慣習なので、説明に限がないからです。
唯、何度もお話をするように、その奏法は、当時の弦楽器の演奏方に過ぎません。
ですから、無制限にあるように見える古典派の奏法も、弦楽器の人達にとっては、結構当たり前の奏法である場合が多いのです。
ヨーロッパでは現在でも、pianistはviolinの奏者も兼ねる場合が多いのです。
歴代の作曲家達も、色々な楽器を演奏出来ました。
Mozartは当代随一のpianistであったと同時に、violinistでもありましたし、Haydnは室内楽の1stviolinを受け持っていましたし、Beethovenも、幼年時代には、呑んだくれの父親の代わりに、orchestraでviolinを演奏していました。
それはSchubertも同様です。
まあ、そうでなければ、あれだけの曲は書けないよね。
例外中の例外であるChopinとSchumannが、Pianoしか演奏出来なかったので、一般的には、それが当たり前のように、(日本では)思われるようになりました。
でも、Chopin、Schumann以後の作曲家達も、色々な楽器が演奏出来るのが普通なのですよ。
ヨーロッパではそれが当たり前なのです。
100年の歴史しかない日本と、500年以上の歴史のあるヨーロッパとの文化の違いなのでしょうね。