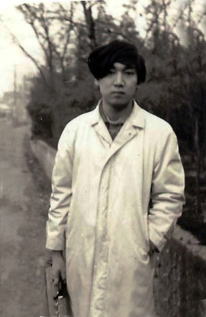
これは単なる蛇足ですが、勿論、私は高校2年生の時から,生まれて初めて、Pianoを習い始めたので、音楽大学に入学して、比較的直ぐに、ヨーロッパ製のMy violaを買うには買ったのだけど、困った事には、そのviolaの弾き方を私に指導してくれる弦楽器専攻の友人や先生はいませんでした。
つまり、弦楽器専門の友達は、沢山いたのだけれど、「弦楽器を学ぶには、早期教育が必要な楽器であって、大人になってから、弦楽器を習うものではない」、という風潮が音楽大学や一般社会の中には、あったからです。
というわけで、このviolaの楽器は、私が余り練習をする事も無しに、オケや室内楽を担当する友人に貸したのですが、その楽器を「又貸し」されて、結局誰の元に貸し出されたのかさえ分からなくなってしまって(つまり、弦楽器専攻の学生達の間に勝手に貸されてしまって・・・・)、1年程経って、やっと私の元に返って来た時には、もう私のviolaは、楽器が少し壊れていました。
烈火の如く怒り狂った私は、その楽器を弦楽器の先輩に高く売りつけてしまいました。
買った時の、倍以上の値段でね?!!
その当時の私は結構喧嘩っ早くって、結構怖い存在だったのですよ。
それで、弦楽器を勉強するというタイミングと意識をなくしてしまった私は、violinとはMunchenに留学して、古道具屋で、Munchen時代の私のviolinの愛器である「Ganaritatelius」と巡り合うまでの4年間は、弦楽器とは疎遠になって、決別していました。
しかし、そういった弦楽器とは無関係の学生生活の中でも、青春真っ只中の音楽大学時代に、既に、音楽大学の勉強とは全く関係なく、弦楽器特有の古典派の奏法の研究を始めていたのですよ。
日本にそういった勉強がないのに、音楽大学にそういった奏法の研究をする人や書物があるわけはないでしょう??
誰もやっていないから、興味を持って、その研究が出来るのですよ。
人のやっている事を、勉強するだけならば、それは学習すると言って、研究する・・とは言わないのですよ。
そこのところが日本人には分からないのだよな??
forte-pianoに関しては、未だにそういったPianoの前身の楽器がある・・・ということすら知られていなかった頃で、それ以前に、Cembaloという楽器も、未だ日本には数台しかなく、baroqueとは言っても、とてもとても、やっとVivaldiの四季が世界で知られるようになってきた頃のお話です。
未だ、BachのG線上のAriaやVivaldiの四季等の、こんにち有名な作品がやっと一般大衆に少し知れられようになって来た頃のお話です。
勿論、baroqueや古典派の研究書等というものは全く出版されていなかったし、古典派の独自の奏法があるということすら、誰も知らなかった時代です。
そういった話が一般の人達の耳に届くようになるには、1980年代の後半から、90年代に入ってからのお話になるのですからね。
しかし、私達の教室では先生達に、1987年にはFiori musicali baroque ensembleというbaroque楽器による、baroque奏法のensembleを立ち上げて公開演奏会を始めていたので、世界最先端よりも少し早めですよね。
Ku?ken4重奏団の創設は86年なので、殆ど同時期にoriginalbaroqueの公開演奏を始めていたことになる。
つまり、世界の最先端ですら、86年なので、当然それ以前のbaroqueというのは、現代の奏法でbaroqueの音楽を演奏しているに過ぎない、時代考証も何もない一昔前のチャンバラ映画を見ているようなもんで、お笑いにはなったかもしれないが、それをbaroqueというのは・・・幾ら何でも無理があるのだよね。
私の音楽大学時代はそれこそ、60年代の前半の時代だったので、baroque音楽そのものの、黎明期であって、古典派の奏法等と言うお話は世界中でも口にされることは無かった時代なのですよ。しかし、それでも、私は個人的にBachのcantataや、Mozartの古典派の奏法を自分なりに研究を始めていました。
古典派のviolinの奏法の研究も、violinの練習を始めるよりも前に、既に始めていたのです。
violinを弾く、弾けないに関わらず、violinの奏法の研究は始めていました。
研究書も資料も無くって、どうやって研究したのか??って・・・???
それこそ、日本流のコピペの、猿真似の考え方ですよ。
研究というのは、誰もやっていないことを調べて、考察していくから研究であって、世界の研究書を翻訳して丸写しするのは、研究とは言わないのだよ。
そこが日本人には分からない・・・・!!
誰も、研究していないから、面白いのだよ。
斉藤先生にbiberのviolinの研究をさせているのも、世界でbiberが弾ける人が少ないからさせているのよね。
でも、日本人は皆がやるから、自分もやる・・・、それってi dentityの無さ過ぎじゃない??
皆がChopinを弾くから、自分もChopinを弾いても、誰も評価はしてくれないのよね。
baroqueのviolinの奏法を研究するには、現代のviolinの奏法を知っておかなければならないのは、勿論なのだが、それ以上に、間違えたviolinの奏法やmethodeも、ちゃんと知っておかないと、研究とは言えないのだよ。
だから、一般的な鈴木のmethodeや、ロシア派のmethodeも、それこそベルギー派のmethodeも研究はするのだよ。
だから、ある大学のviolinの先生が生徒に何を注意したのかを聞けば、その先生の求めているものも、その先生の水準も分かる。
だから、その先生の求めているものに合わせてlessonをする事も可能だ。・・・というか、簡単なのだよ。
容子が高校の全国大会のコンクールを受ける時に、1週間前に、未だ64箇所の注意点が残っていて、出来ていなかったのだが、その64箇所の注意点を全部、クリヤー出来たら、全国大会で入賞出来る・・と言っていたのだが、容子は当日の朝までに、19箇所までに絞り込んできた。私は「この19箇所が全部クリヤー出来たらねぇ〜・・??」と残念がっていたのだが、何と、それでも全国でベスト3には入賞していたよ。
だから、音楽大学時代から、弦楽器の友人達から「芦塚さんはviolinが弾けないのに、どうして、violinの弾き方に詳しいんだい?violinの弾き方が分かるんだい?」と皮肉としてではなく、素朴な驚きとして、よく尋ねられました。
「皮肉ではなく・・・」という意味は、音楽大学に入学したばかりの頃の時代にも、弦楽器専科の連中が、学校の試験や、演奏会の本番の前に、自分達の弾けない、難しいpassageの、演奏のコツをよく尋ねて来たからです。
「このpassage難しいのだけど、どうすれば弾けるの??」「それはねぇ〜・・・・」
violin専科の学生が、violinを全く弾けない私に、質問をする・・という、不思議な光景は、結構日常的であって、それを疑問に感じている学生は、いなかったのですよ。
やっぱり、作曲科の学生なので、分かって当たり前・・・という風潮でもあったのかな??
そのpassageが弾けるようになった友人達は、「violinの先生は「こう弾くんだ!」と、弾いて、見せるだけだけで、どうしてそうなるかは、分からないのだけど、芦塚さんは、理屈で説明してくれるから、とても、分かりやすいわ!?」とよく言っていました。
そりゃ、そうだよね、音大生が弾く、Tziganeなんて難しい曲を、私が弾ける分け、ないもんね・・・??
理屈でしか説明出来ないわさ!!
でも、「弾けないのにどうして、その弾き方が分かるの??」
というのは、一般人の疑問なのでしょうが、violinの弾き方は、理屈では分かっているのだけど、指や体がついていかないだけなのよね。violinの学生の場合には、弾けるけれど、どうしてそう弾けるのかの理屈は分かっていないのよ!理屈が分かっていなければ、微妙な間違いすら分からない。そこを指摘されても、どう直して良いのかは全く分からないのだよ。
そこの所を説明して、弾き方を指導する分けなのだな!?
