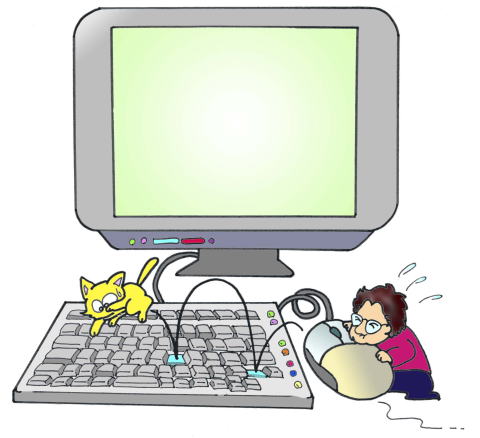
[定型作業]
routine作業について
究極の時短、外注と部下に任せる
蛇足ですがⅡ
[feedbackについて]
[脱線して…雑談]
[本題に戻って・・・]
[並行作業の勧め]
![]()
[あとがき]

私の幼年時代は、戦後の復興期で日本も大変貧しい時代でした。
だから、当然、今日とは物の考え方が全く違います。
私達が子供の頃は、食事を残してはいけないとか、好き嫌いは絶対にダメだと習ってきました。
今では、想像もつかないでしょうが、お米が無くなってしまって、お椀にカボチャが「4分の1欠け」だけが、その日の食事だ・・という時もありました。
カボチャとは言っても、昔のかぼちゃは、今のように美味しい「栗かぼちゃ」ではなく、皮は緑色でしたが、ヒダが深い甘くもないし、パサパサして、それにとても硬い、とても不味いかぼちゃでした。 それでも、その時代には、その日に食べるものがあるだけ、未だ、良かったのですよ。
それでも、その時代には、その日に食べるものがあるだけ、未だ、良かったのですよ。
祖母には、4人の息子と、1人の娘がいたのですが、4人の息子全員が戦争で死んでしまいました。4人の息子の奥さんも、全員が戦争未亡人になってしまったのですよ。
当時は、そういった家庭は珍しくなかったのですが、それでも、戦争に行っていた夫や息子が、復員兵として、家に帰って来た家庭は早々と経済的にも持ち直して来ました。
そういった働き手のいる家庭と、戦争で働き手を失った家庭では、子供の来ている服ですら、歴然とした違いがあった時代なのです。
進駐軍が小学校にやって来て、ノミやシラミの防止に全員の子供達にDDTを噴霧したり、不味い肝油を飲まされたり、噛んでも噛み切れない鯨のワラジみたいな、ステーキを食べさせられたり、極めつけは、脱脂粉乳で作られたミルクで、これを飲まされて、よく吐いてしまっていたな??
ビンの牛乳も不味くて、とても飲めなかったのですが、ドイツに行って、その日に牛さんから絞り出した成分無調整の牛乳を飲んで、「え~っ??牛乳って、こんなに美味しかったの??」と驚いてしまいました。他の日本人の留学生達は、「ナマ乳は、強すぎて、下痢をするから・・」と言って、皆さん飲めなかったのですがね。
(このお話の続きは、芦塚先生の子供のための料理教室を、参照して下さい。)
今は、子供の肥満防止のために、食べ物を残す方が美徳とされる事が多いようです。
それに、古くなったモノはどんどん捨てて、常に新しい最新の物を傍に置いておくのがステータスになっています。
携帯もパソコンも車でさえ使い捨ての時代です。
だから、私のように、車でもパソコンでも、故障したら直して使う人間は、逆に、周りの人達に、何かと苦情を言われてしまいます。「吝い(しわい)!!」ってね!!
もう、そういった「物を大切に!」といったような、古い考え方は流行らないようです。
今は、物を捨てることの方が美徳となる考え方が一般的です。
でも、音楽の場合には、新しいものが良いという考え方は、amateur的です。
車のように、性能の良いものは新しい車で、古い車は安い中古・・という考え方は、音楽の場合にはamateurの領域です。
(もっとも、車でもヴィンテージ・カー(vintagecar)というのがありますが、それは新車よりもピカピカなので、少し意味が違うかな??)
現代では、音楽のLibhaberでも、Classicの愛好家は、段々少なくなっています。
広く一般大衆を、clientにしているヤマハのグランドは、当然の事ですがや、steinwayのような高価なPianoでも、基本的に、新しいgrandpianoは、現代のpopularやjazzの影響で、音が硬くキラキラとした音になっているし、高音域のpedalの掛かりも、ClassicのPianoとはかなり違います。
19世紀から20世紀に掛けての純然たるClassicのPianoは、touchが重く、音も重い響きがします。
日本のヤマハのPianoでも、昔のヤマハのピアノは、カナダの山から切り出される材木から、楽器に相応しい木材だけを選別して購入していました。
それが、昭和40年代(60年代)に入って、世界中で森林保護が叫ばれるようになりましたが、ヤマハ等の大手のメーカーは、前もってカナダの山を購入して、楽器用の材木を確保しました。
但し、それ以前の木材は楽器用に、とても良い材木を選別して購入していたのですが、森林保護が叫ばれるようになって以降は、その山で切り出される木材は、基本的にピアノの材料にするようになりました。
だから、それ以降のPianoでは、響板用の板に節目があったとしても、その木材を補修して使うようにしたり、それまでは木材の端材を加工して作っていたパーツや、金属で作っていたパーツを、安いプラスチックに切り替えるようになりました。ペダルのような、金属で出来ていたパーツも安い楽器ではプラスチックで作られている楽器さえ作られるようになってしまいました。
メーカーの主張では、「こういった変更は音には影響しない」と言っていますが、実際には、やはり微妙に音に影響が出て、結局、安っぽい音になってしまいます。
という事で、教室では、昔のヤマハのグランドでconditionの良いものを、renewalして使用しています。
作られた年代が古ければ、音や性能が良くなる・・という安直な分けではありません。勿論、幾ら中古でも、ちゃんと、renewalした結果、良い楽器になる物を探さなければなりません。
それには、それなりの「目利き力」が必要となります。
それで、運良く良い素材の楽器を見つける事が出来て、優れた技術を持っているPiano製作者の手を経て始めて、ヨーロッパの優れた楽器に遜色を取らない、素晴らしい昔の音のヤマハの楽器が出来あがります。
現代のヤマハの薄っぺらな軽い音よりも、よっぽど良い音がするし、アクションや鍵盤や弦は、いつでも新品のパーツに交換する事が出来るから、性能が劣って来るという事は有り得ないからです。
私達の教室は、当然、Classic専門の教室ですから、同じヤマハでも、昔の職人の手による楽器の方が良いに限るからです。
勿論、今の音大生達にとっては、音も鍵盤もtouchも重くって、弾けないでしょうけれどね。
ここまでは、古いものは、必ずしも、粗悪品の安かろう悪かろうという意味ではない・・というお話です。
パソコンでも、xpやwindows7までは、良いのですが、8や8.1になってしまうと、仕事には使えません。
スマホが幾ら大型になって、その性能が上がったとしても、パソコンではないし、パソコンの代用にはなりませんよね。
新しいものが必ずしも、使いでが良いとは限らないのですよ。
業者の人達は、新しい製品を売りたいのでしょうが、使う側から言わせてもらえば、そうばかりとも言えないのですよ。
物を捨てるという「断捨離」とかいうタイトルの整理術の本が、ベストセラーになる時代のお話です。
物が豊かになって、狭い部屋に溢れる時代には、・・・確かに都心の狭い部屋に住んでいれば、・・・狭い自室のスペースを有効に活用するには、必要のない物は捨てるに越したことはありません。
それが現代の豊潤の時代にふさわしい、合理的な考え方だと言えるかもしれません。
確かに、今当面使用しない物を狭い事務所に置いて置く・・と、いう事は、それ自体場所を取っているので、場所代に換算する事が出来ます。
置き場所は、都会ではお金に換算されますからね。
しかし、狭い部屋に、当面の不要な物が溢れて、物を捨てることが、已むに已まれぬ状況の場合とは事なって、その人の性格として、すぐに物を捨ててしまう人がいるのです。
一つの作業の為に物を買うけれど、終わってしまったら、直ぐにポイと捨ててしまうという事なのかな??
幾ら、飽食の時代とはいえ、もったいない話です。
よく観察をしていると、その人達は、合理的な理由から物を捨てている分けではなく、単に物を整理整頓する事が面倒くさいから、物を捨てているという事が殆どで、決して生活上の効率や時短を図る為の手段として、物を捨てている・・という事ではないようです。
でも、私の「もったいない」という感覚で、お話をすると、「たった一回こっきりしか使用しない」・・・「その次には、必要でなくなってしまう」・・というものならば、最初から買わない・・と、思います。
たった一回のためだけならば、それは、私達の目から見れば、単なる贅沢にしか見えませんがね。
本当に必要なものならば、何かで代用してしまいます。
しかし、一般家庭のようなcaseとは違って、会社のように、「仕事の効率化のために道具を購入する」という理由ならば、「物」は仕事上の必要に迫られて買うわけなので、それが終わって、必要でなくなったから(場所代が掛かるから)という理由で、せっかく購入した物を捨てていては、次のprojectで、再びまた必要になった時に、改めて、「また買う」という事は、現実的には出来ないし、それこそ、会社としては、経済的に・・だけではなく、会社として、最も大切にしなければならない時間を失ってしまいます。
つまり、道具を購入するのは、会社としては、企画購入から始めなければならないから、時間をいたずらに失ってしまう・・という事で、そういった前提は成り立たないのです。
また、重要な資料等では、一度無くしてしまうと二度と手に入らないものも多いのですが、会社としては道具でも、捨ててしまうと、二度と購入出来ない物すら数多くあるのです。
私達の教室の場合にも、以前、会社が、経理担当の丼ぶり勘定の乱脈経営で、左前になった時に、会社の立て直しの為に、それこそ、地代家賃の節約の為にと言って、私が教室の為に長年にわたって買い揃えていた仕事道具類を「場所を取るから」という理由だけで、殆ど捨てられてしまって、その後、会社経営が立ち直って来て、また改めて、時短のために、そういった道具が必要になっ来た時に、経済的にも、時間的にも、以前、持っていた道具類は、なかなか買い揃える事はもう出来なくなってしまいました。
「捨てる」という事も、個人の場合には、なければ無いで済ませられますが、仕事上の物では、「ある」と「ない」では、時間的にも、効率的に雲泥の差になってしまうのです。
そういった意味では、会社経営上は、「捨てる」という事が、経済的な、或いは、仕事率としても、効率を生み出す事は、あまりありません。
但し、道具は(パソコンでも、Pianoでも)使えるようになってこそのナンボの世界です。
道具の使い方に不慣れなら、それこそ時短にはならないで、逆に膨大な時間の損失を生みます。
常日頃から、使い方に慣れる事が、時短の秘訣になるのです。
それが必要になる時には、それを使い熟すための時間は、決して無いのです。・・その事が、幾ら説明しても理解して貰えません。
困った事です。
これは、実際の説明が必要かと思いますので、幾つかの実例を上げて、補足説明をしておきます。
最初のお話は、「教室に取って」と言うよりも、会社としては、実に一般論なのですが、音楽の場合には、技術職になります。音楽教室を経営すると、教室で使用する色々な作業が、実に専門的な作業になります。
直接は、音楽とは関係の無いように見える音楽教室の事務作業が、音大生が考えるような、バイト的な作業ではないのです。
という事で、「江古田詣」の生徒達には、そういった作業の方法論を、細かくミスがないようにlecture、指導しなければなりません。
ミスをすると、それはミスをした人のプライドの問題ではなく、実際に会社としての損失で、具体的に金額の損失につながるのです。
たった一枚のコピーをミスしたとしても、それはコピー代の単価全体が損失になってしまいます。
勿論、それに時間的な損失も出てしまいます。
でも、学生達はミスを、ミスとしてしか、感じていません。
平気で100枚ぐらいのミスプリをしてしまいます。
業務用のコピー機では、確認を怠って、コピーを始めて、スイッチを押した瞬間にミスを気が付いて、停止ボタンを押したとしても、その一瞬の2,3秒の間に100枚ぐらい印刷してしまいます。
1枚のランニング・コストが10円だとしても、100枚なら千円の損失になってしまうのですよ。
税務処理や経理では、ミスは、数字一つも認められません。税務署の前に税理士の人達の専門家によるcheckが入って来て、ミスをすると、書類がやり直しで、戻って来てしまうのですよ。
そういった、人材を育てようとすると、大変なエネルギーが必要になります。
また、そういった人材を育てている間は、教室としては、収入が無くなってしまうのです。
だって、その人材を指導している時には、その先生は働けないし、お金も稼げないからなのです。
double teachers(ダブル・ティーチャーズ)とは、先生の経験の浅い先生を、ベテランの先生が補佐指導しながら、実際の生徒指導にあたる・・という意味なのですが、その場合には、生徒が二人分の月謝を払ってくれる分けではないですからね。
生徒の月謝は、その経験不足の先生に対してのペイだけなのです。
つまり、ベテランの先生はただ働きになってしまうのですよ。
もう一つの例は、ベテランでも、初心者でも関係のないお話です。
寧ろ、その人の性格的な事かもしれません。
非常に優れた道具でも、使い方が分からないと、その道具は意味がなくなります。
その一つの例として、音声認識ソフトがあります。
一般的に売られている音声認識ソフトは、教室で使用する専門用語や、専門的な作曲家の名前には対応出来ません。
しかし、私が愛用している音声認識ソフトは、ドラゴンスピーチというソフトは、単語を登録する事が出来るし、逆に、使用しない変換候補に出てきてしまう迷惑な単語を、一瞬で削除する事が出来ます。
という事で、私達のように、専門的な仕事で使用する場合の文章を入力するのに適しているソフトです。
近頃の音声認識ソフトは、殆ど、お喋りをする速度で、入力する事が出来ます。
でも、どうして音声認識ソフトは、一般化しないのか?・・・というと、やはり、パソコンの悲しさ・・で、パソコンに教える・・・自分がソフトに慣れて、コマンドを使いこなせるようになる・・・には、どうしても、1週間から、一月ぐらいの、Erziehung(ヤチーユング・教育 育てる)期間が必要になるのです。
だから、その教育(自分が慣れる期間でもあるのですが・・)の時間が「もったいない」と感じる人には、どうしてもこういったソフトを使いこなす事が出来ません。
という事で、仕事が忙しくなって、一人でこなせなくなった時に、上記の二つのいずれか??或いはその両方をしなければならないのですが、忙しいの時間に追われてそれが出来ないで、アップアップしてしまう・・というドツボにハマってしまうのですよ。
道具は、なんでもない時、その道具が必要でない時に、その道具を使用して使いこなせるようにしておかなければなりません。
地震の対策のようなものです。いざ、地震が来た時に、説明書を読みながら、「これはどう使用するんだっけ??」なんて言っていたら、なんの意味もないのですよね。
ここまでのお話は、時短をするには、物を使いこなせるようになる事が重要だ・・というお話でしたが、それはあくまで、会社としてのお話、つまり仕事としての物の価値観のお話でした。
だから、そこの所は、個人で「趣味で物を買う」という一般家庭の場合の話と、音楽教室や、音楽家達の・・・仕事として使用する場合では、「物」そのものに対するお話では、「物」に対する考え方や意味合い、或いは価値観等々が全く違います。
時短をするための道具がなければ、何かで代用すればよいという一般の家庭の考え方と、「時間は金である・・(time is money)」という一瞬一秒の遅れも、許されない・・、即、金銭の損失に繋がる、研究室や会社等の立場での考え方では、基本的にその価値が違うのです。
会社の場合には、物を保管する場所代や、倉庫等の保管場所から仕事場へ持って行くという手間暇を差し引いて考えても、「捨てる」という事を優先に考えると、結果としては、仕事の効率上、金銭的にも、膨大な損失を招いてしまいます。
会社の仕事道具に関しては、「捨てる」という事は、持ち合わせている道具よりも、より効率の良い代替え品が手に入った時だけなのです。
何故、この話をここでするのか?というと、生徒達が趣味で音楽を勉強しているのなら、整理術は必要ないのかもしれません。
しかし、一旦、音楽を将来の職業とするために、今の勉強をしているのなら、例え今が小学生であったとしても、「今、現在、具体的に何を勉強したか」・・という事を、しっかりと保存して、自分の音楽歴として、即、提示出来なければならないからなのです。
仕事(職業)としての勉強ならば、それは会社の仕事と変わるものはないからなのです。
今、勉強している事が、学生としての勉強であって、そのまま将来に活かせない(繋がって行かない)のなら、その生徒が将来プロになる事は絶対にないからです。
そこの所を、よく理解した上で、以下の話を聞いてください。
個人に限らず、会社でも、情報のfile類や、file関連の小物に関しては、一般家庭と同じように、整理整頓が仕事上の重要な要素になって来ます。
