 陶器の歴史は大変古いものなのですが、茶の湯が盛んになったのは室町時代からで、高価な国宝級の茶器が沢山作り出されました。
陶器の歴史は大変古いものなのですが、茶の湯が盛んになったのは室町時代からで、高価な国宝級の茶器が沢山作り出されました。それから、江戸時代に入って有田で陶石が見つかり伊万里で制作が始まりました。
陶磁器は当時はとても高価なもので、大切に補修しながら、使われました。
焼き継ぎとは、白玉(しらたま)と呼ばれる鉛ガラスの粉末とフノリを水で溶いて混ぜ合わせた釉薬を磁器の継ぎ目に塗り付けて接着してから、炉の中に入れて低温度(約800℃)で焼いて接合する方法です。
白玉とは、珪石と鉛をいっぺん熔解して鉛ガラス(フリット)を作り、それを粉砕して粉状にしたものです。
金継ぎの話
「金継ぎ」とは、破損した陶磁器を漆で継ぎ金や銀で上化粧して直す・・という日本独自の伝統技術で、日本で茶の湯が盛んになった室町時代に茶道の世界に始まったといわれています。
注目すべき点は、金継ぎの意味は、ただ単に、割れて無価値になってしまった高価な茶器を、単に修復するだけでなく、その補修の後を、美的価値に捉えた事です。
 金継ぎをする事で、元の陶磁器よりもその価値を高めるという特徴をもっています。
金継ぎをする事で、元の陶磁器よりもその価値を高めるという特徴をもっています。その修復した傷跡を「景色」といって、割れる前の陶磁器よりも、美的価値が上がるという日本独自の伝統芸術です。
壊れた物が価値が上がるというのは、世界でも理解出来ない理屈でしょうね。
実際の金継ぎの話
昔々は、練馬の田中屋本店でも、立派な清水焼や伊万里の陶器を使っていて、蕎麦猪口には、金継ぎがしてあって、驚いた事があります。
清水等の高価な蕎麦猪口だとしても、普通は欠けたら捨ててしまうこんにち、手間暇を掛けて、大切にしている姿が好感を持てました。
田中屋本店は二人のお爺さん達とともに今はもうありません。
練馬の豊玉の田中屋本店でも、お爺さんがいる時には、本当に味に締りがあって良かったし、私が蕎麦を啜りながら、唇を拭いていたら、直ぐに、替えのタオルをお爺さんが手ずから持って来たり、心配りが職人なのよね。
そこが違うんだよな!!
池袋のデパートの田中屋も、銀座の田中屋も、心意気が、お爺さん達とは、チョッと違うんだよな??
蕎麦を打つ技術の違いだけではなく、金継ぎの技術も、残念ながら、技術を伝承する後継者がいなくなって、困っているそうです。
割れてしまったら・・・、否、縁がほんの少しだけでも、欠けてしまったら・・・、惜しげもなく、捨ててしまう・・という事は、世界で評価されている日本人の持つ美徳である「勿体無い」の心も育ちません。
ましてや、音楽を学ぶ芸術家であるべきproのpianistにとっては、楽器は、自分の恋人よりも勝る存在であり、自分の命すら預ける事の出来る戦友のような存在であるべきなのです。その二つとない大切な楽器を、愛する事もなく、grandPianoの査定が下がるというだけの理由で、買い換える事が美徳とされるような感性では,それではとても、音楽家、芸術家とは呼べないでしょうね。
 トトロのマグカップ
トトロのマグカップ右側の写真は、私のお気に入りのトトロのマグカップです。
トトロのマグカップは結構私のお気に入りなので、自分専用に、各、教室に置いていたのですが、不思議な事に、全部のカップが同じ縁の所に、瑕が付いてしまいました。
練習やlessonの合間に、子供達はお茶菓子timeをしますが、子供達はシンクの中に、飲んだお湯呑み等々置きます。それを洗って、水切りのカゴに入れるのですが、その時に、上に、上にと、ドンドン重ねて置いていったりするので、どうしても下の陶器の脆い部分に皺寄せが来るようで、このトトロも、5客、6客と買いなおしても、次々に同じ場所を瑕がされてしまいます。
重いものは、乗っけないように、注意しているのですが、忙しくなると、湯呑の上に、フライパン等の重量級の物さえ乗っかっていたりして、結局、傷が付いてしまうのです。
それを、いつも注意するのですが、忙しさにかまけて、やっぱりうず高く積み上げられてしまいます。
欠けた湯飲み茶碗は、そのまま、捨てるにも忍びないので、その内の一つは、底にドリルで穴を開けて、植木鉢にしました。でも、トトロの植木鉢は1個でいいし、段階の世代としては、捨てる・・という事が中々出来ないのです。
意を決して捨てて、同じトトロの新しいマグに買い換えようと、デパートやnetでも調べてみたのですが、今は、新しいマグカップは、もう売られていないようです。
・・・という事で、やむなく、欠けて鋭くなって唇を切りそうな所に、電ドリで、陶器専用のヤスリを掛けて、怪我をしないように、滑らかに成型して使っています。
割れた茶碗や欠けた茶碗等ですが、まづ食器として無害である事が条件で一番です。
陶器の花瓶のようなものならば、ボンドで補修するという手もありますが、食器や湯飲みの類いならば、それよりも前に無害であるという絶対条件があります。
食品として安全という事になると、そうすると金継ぎしか方法はないようです。
金継ぎで補修が出来ば良いのですが、なかなかそれをするだけの時間がありません。
金継ぎのsetは、東急ハンズで買って準備はしてあるのですがね。

後日談です。
右側の写真は漆固めの作業ですが、下側のマグは透漆がたれてしまっています。
でもこれは拭き取ればよいだけなので、問題はありません。
実際に、自分でやって見ると、金継ぎの作業自体は、一般に言われているようには、難しくないようなのですが、一つ一つの工程が終わる毎に、2週間、3週間と間を置かなければならなくって、完全に乾燥するのを待って、次の工程に入らないといけないので、それが大変面倒くさく、金継ぎを利便性のあるものではなくしているようです。
ほんのチョッと作業したら、放置して、また少し作業して、・・と、その工程を幾つもしなければならない・・というのは、一般家庭ではなくても、これはたまらん!!
湿度を加えながら、乾燥させる乾燥の室(むろ)のような物もあるようですが、そこまではprofessionalではないので、出来ません。
そうすると、部屋の中で一番湿度があって、生活の邪魔にならない場所・・・・、そんな所あったかしら??
あった!!あった!!
 物を置いていると、総てがカビてしまう洗面所です。
物を置いていると、総てがカビてしまう洗面所です。じゃあ、そこに置いておこう!!
もう一つの問題点は、作業工程で使用するそれぞれのpartsの作り方、材料が無数にあって、それぞれの工房で呼び名まで違う事です。
欠けた部分を補修する材料ですら、色々なもので補修するので、やり方が多すぎて困ってしまいます。
趣味なら趣味に徹すれば、先ず、一つの工房のやり方を完璧に覚えた後に、他のやり方を応用として覚えて行けば良いのでしょうが、それには、大変な時間が必要となってしまって、「タダ補修すれば良い!」という本来の目的に外れてしまいます。
困ったものです。
ハイツの陶器
基本的には、私は自分で使うお茶碗や自分で着る物等々を、自分で買いに行く事はありません。
だから、湯飲み茶碗は、トトロのマグカップを除いたら、この写真の両方の湯飲みも長崎から貰ったものです。
しかし、私は必要な物しか買いませんし、気に入っている物しか買わないのです。
だから、私の身の回りにある陶器類は、私が欲しがっている陶器類ではなく、寧ろ、必要の無い邪魔な陶器が多いのです。
つまり、私の自宅にある無数の長崎からの陶器類は、自分が気に入っている物は非常に少ないのです。
それに、お袋の場合には、陶器を買うのは単なる日常のストレスの発散のためです。
ですから、買って来たけれど、家に持ち帰ってみると、気に食わなかったり、直ぐに飽きてしまったりすると、捨てるのは忍びないので、私の元に送って来ます。
もう少し気に入ったもので、手元に置いておきたりしたいものは、兄貴の元に送ります。必要のない物が私の元に送られて来ます。
だから、私も当然、気に食わなくて、しかも置き場所が無いので、親と喧嘩をする事になります。
だから、先生達が「陶器が多すぎるから、部屋が狭いのよ!」と言われると、私は、腹が立ってしまいます。
「好きで置いている分けではないだろう!!」ってね!!
これもある意味、親孝行なのですからね。
それを前提にして・・・。
下の左側の写真は、赤絵の清水焼のお湯呑みです。
お袋から貰った陶器の中でも、珍しく気に入ったお湯呑みなのですが、とても脆いのが欠点です。
教室でお客様用にしていたのですが、いつの間にか、僅か2客になってしまっていて、慌ててハイツに回収して来ました。
次に、右側の湯飲み茶碗は、長崎から来た時は、12客と数も多かったので、これも教室で使用していたのですが、結構、脆くて、落とした瞬間にパリンと割れてしまうし、直ぐに欠けてしまうので、3客割れた時点で、ハイツに回収してしまいました。
「9客もあってどうするの?」と、思われるかもしれませんが、体調が悪い時には、食べ終わった食器類は全部洗わないで、シンクの中にそのまま放置します。
体調の良い時に、纏めてシンクの溜まりに溜まった洗い物を洗います。
この湯飲み茶碗は、お茶を飲むだけではなく、小さなご飯茶碗の代用、味噌汁のお椀、スープカップの代用としても使います。
抹茶用の茶碗を雑炊用のお茶碗にするのと同じです。
だから、9客ある湯飲みの全部が、シンクに溜まってしまう事もあるのですよ。
でも、いつの間にか縁の部分が欠けていたので、今回の金継ぎの練習に使用する事にしました。
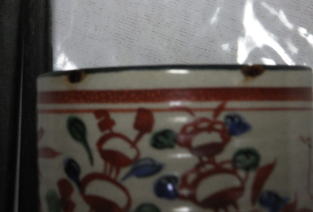

 右側の湯飲み茶碗は、生徒用のお気に入りの湯飲みです。
右側の湯飲み茶碗は、生徒用のお気に入りの湯飲みです。気に入りなので、「ハイツにも2,3個ちょうだい!」と言ったら、断られてしまいました。
数が少ないからです。
でもお金を出して、かっぱ橋で、40客、50客と大量に買ったのは、俺なのに・・ね??
・・という事で、「縁が欠けていて、子供が口を切ったら困るので・・・」という事で、捨てる事になっていたニャンコの「お湯呑み茶碗」をハイツ用に貰って来ました。
金継ぎをして、ハイツで使うつもりです。

お気に入りの土鍋の中に小鉢を入れて仕舞っていたら、取れなくなってしまった。