メトロノームについて
前書き
[index]
第1章 メトロノームの歴史
Metronomはメルェルがつくったのではない
蛇足ですが、メトロノームの歴史に対しての疑問
MälzelのMetronom
BeethovenとMälzelの不思議な関係
作曲家の書いたメトロノームテンポの信頼性
第2章 メトロノームの選び方 音色と音量
メトロノームの嫌いな子供達
メトロノームは正確にrhythmを刻んでいるのかな?
電子式メトロノーム
第3章 メトロノームの使い方
基礎編
不遇なメトロノームが指導者達からその価値を認めてもらえない理由
レスナーへのアドバイス
前書き
初心者へのメトロノームの導入
メトロノームの早期教育
指導のための段階(step)の設定
メトロノームのテンポが見つけられない潜在的な理由
蛇足:指導者が生徒を(自分のレッスンを)客観的に見れるようにするための訓練法
初歩の段階では拍子の音を入れてはいけない
メトロノームのbeatの設定は拍子を設定するものではない
音の粒を出すためのメトロノーム練習(ビッコの矯正のメトロノーム)
拍の読み替えの練習
弾けてはいるのだが完成度のバランスが悪い
初心者に良く見受けられる、弾く事に一生懸命で、メトロノームの音が聞こえない場合の指導法
メトロノーム練習は極端に遅くして練習をしても必ずしも易しくなるわけではない
弾けないからと言って、闇雲に遅く練習しても意味はない
メトロノームは抜き出し練習の場所だけを練習する事
応用編
テンポの設定
その曲がその曲であるためのテンポ
一つの曲のなかでの複数のメトロノームテンポの設定
臨界テンポのお話
練習テンポのみつけ方
1小節を1拍として捉える曲
最後の小節に付け足された空白の小節の意味
拍子の弾き分け
メトロノームを使用した練習法の例
奇数のbeat
等分割されないrhythm
phraseによる、等分割されない拍取り
変化する拍の例
rubatoの例
Hemiola(ヘミオラ)
Verschobene Takt(推移節奏)
あとがき
前書き
ピアノやヴァイオリンの先生等の音楽を教える先生でメトロノームを使用したことがない、持っていてもほこりをかぶったままで、一度も使ったことがない、それどころか持っていない先生が意外と多いようですが、それは「メトロノームをどうやって使ってよいのか分からない」或いは「メトロノームを子供に使ってみたが、実際にメトロノームに合わせることが出来なくって、子供が嫌がった。指導していて挫折してしまった。」 という理由があるようです。
メトロノームに音楽を合わせて弾く事は意外と難しい。にもかかわらず、現実的には「メトロノームの使い方」、或いは「利用の仕方」という本はまだ一冊も出版されていません。
音楽大学などの先生は、「メトロノームを使用するのは初心者の間だけで、メトロノームは音楽性をだめにしてしまうから、使用してはいけない。」などと真顔で言う先生がいるから困ったものです。日本の音楽大学のlevelは、本当に困ったものです。テレビを見ていたら、某国立音楽大学のヴァイオリンの先生が、「ヴァイオリンは腰をねじって構えるから、腰痛になるのよね!!」なんて、真顔でおっしゃるので、ついつい 「それはあなたの構え方が悪いからでしょう??」といいたくなります。
ヴァイオリンを練習していて腰痛になるようなら、それはプロの厳しい練習には耐えられないと思いますよ。録音の時などは、丸1日缶詰になって、演奏しなければならないことなど、ざらなのですからね。(だって、オペラや、ミサ曲を本番でたった1曲、演奏会で弾くだけで、4時間は弾きっぱなしなのですからね。それで腰痛になるようなら、大学の先生は出来ても演奏家は無理!!
まず、そこのところから、考え方、意識を直していかなければね。
メトロノームの話でも、音楽のプロの世界では、打ち合わせは全てメトロノームを使用します。「早く!」とか「ゆっくりと!」なんて感情表現や情緒表現はプロの世界にはないのだよね。
そんなことをやっていたら、時間が足りなくなるでしょう??
合わせてから、テンポやタイミングを取るのではなく、あらかじめメトロノームでお互いに揺らしのtempoを確認して、練習を済ませてから、合わせるのですよ。
私の友人のオルガニスト(女性だから、本当はオルガニスティンですけれどね)が、目白のカテドラルでパイプ・オルガンの伴奏で日本人の女性歌手の人が歌う事になって、その練習の時です。曲のクライマックスの部分で、カデンツのように自由に歌うpassageが出てくるのですが、そのpassageを彼女は「私の歌を聞いてちゃんと合わせてください。」とオルガニストに噛み付いてきました。彼女は「オルガンは、私がキーを押して、0.5秒後に音が出るので、あなたが、こういう風に歌いたい!と言って聞かせてくれると、私がそれに合うように伴奏をしますから。」 と、とても親切に丁寧に説明をしたのですが、「だってカデンツはそのときの気分だから、そう歌えって言われても・・・!」と頑として、納得しませんでした。さて、どんなコンサートになったことやら??
オルガニストの彼女は 「日本ではこういう演奏家が多いのよね。」と諦め顔で笑っていました。
つまり、音楽を正確に揺らすためには、崩す前の基本のtempoが無ければ、正確には揺らせないのです。
あてずっぽうに感情的に揺らす事はプロの技ではないのです。感情的に揺らすのであれば、毎回の演奏会でも違った演奏になってしまうのであろうし、毎回揺らしが違うという事はそれこそ演奏の水準が毎回違ってしまうという事です。
以前、マルタ・アルゲリッチという女流演奏家の演奏がそうでした。
気分が乗ると、素晴らしい演奏をするのですが、気分が乗らないと、2流の演奏どころではない、それどころか、演奏会そのものすらすっぽかすのです。それをフアンは「芸術家だから・・!」と許容してしまう。
そういったアルゲリッチの演奏スタイルが許せない私は、せっかく人から貰った彼女の演奏会のチケットを人にあげてしまいましたがね。
もっとも、歳を取ってからは、マルタ・アルゲリッチも室内楽を専門に勉強しなおすようになりました。室内楽ではそういった感情的な演奏で演奏するのは不可能ですからね。
音楽教室や音楽大学の先生に子供を学ばせている親御さんには、先生がメトロノームを使用すると、「非音楽的だ!」と言って、怒り出す親御さんがいます。それは、そういった先生達の話を真に受けてしまっているからなのです。
メトロノームを使用すると、まずそういった父兄に対して、メトロノームに対する誤解を解く事から始めなければなりません。しかし、誤解を解くためには、結構専門的な話をしなければなりません。
それも先生達にとっては、結構な負担となります。ついつい、めんどくさくなって、メトロノームを使用しないままに、子供達にレッスンを始めてしまう。普通の先生達にとっては、教えている子供達がrhythm音痴になろうと知った事ではないからね。
周りの先生達もそうだから、正確に弾いてくる生徒はいないから、どうせ分かりはしない。
メトロノームの話に戻って、一般の人達にとっては、メトロノームはただ単にテンポが揺れる時にそのゆれを矯正するという意味でしか考えられていないようで、それがメトロノームを誤解される元になっています。
勿論、プロ的なMetronomの使用法は、曲の中の微妙なtempoの設定や、揺らし、変則的なrhythmを確実にする事、等々の確定に用います。
メトロノーム自体は単なる動具にしかすぎないので、そのメトロノームの多様な役割と本当の価値を引き出すには、それを使いこなすためのハウツー、所謂、「相当な技術」が必要なのです。
どういう風にメトロノームを使ったら上手に曲を仕上げる事が出来るようになるのか、そして、メトロノームを最大限に使いこなしていけるのか、そういったthemaで、私の経験に基づいてメトロノームの使用する時の方法論を説明していきたいと思います
ちなみに心理学の教科書等を紐解くと、「絶対音は、幼少期にしか身につかない。拍子感、rhythm感は原則として、先天的なものであって、絶対音よりも身につける事は難しい。」と書いてありました。
しかし、それは世間一般の音楽教育においては、メトロノームを軽視しするあまり、「絶対テンポ」(今のtempoがメトロノーム幾つであるか?)という概念を、生徒達に指導することがないからなのです。ちなみに、私は脈を2,3秒計るだけで、脈が分かります。脈拍とMetronomのテンポは同じものだからです。(つまり、1分間に幾つ拍動するか、ということなのだからです。)
私のメトードでは、小学生の時迄に教室に入会した生徒は、殆どの生徒が絶対音を身につける事が出来るようですし、拍子感、rhythm感はもっと遅く、中高生になっても充分に身につけることが出来ます。
勿論、rhythmの訓練は私の特別なメトードを使用しますし、その基準として、生徒達は今演奏しているMetronomのテンポを言い当てることが出来るようになります。
メトロノームは道具に過ぎません。道具は使用する人の力量でその価値が決まります。
闇雲な努力だけでは、目標を達成する事は困難です。
私の書いた箴言集があります。
「ヨージーの法則」というタイトルの箴言集です。
その本のプロフェッショナルについての項では、
「普通のことをやっていたら、普通にしかならない。」
「プロになるには、1%の努力と、99%のプロの考え方をすること」
と私は書いています。
プロになるためには、プロになるためのカリキュラムで、プロになるための練習をしなければならないのです。決して、普通に音楽大学に進学するような勉強をしても、その中でプロになれる人はいません。仮にその人が音楽大学に在籍していたとしても、普通にレッスンを受けていたわけではありません。やはり、プロになるための特別な練習をしていたわけです。
但し、プロというのは「何を持ってプロというのか?」という定義の問題があります。
演奏会を立派なホールで開いたからと言って、そういった人の事をプロというわけではありません。殆どの自称演奏家の人達が自腹を切って演奏会を開いているからなのです。
私がプロという人は音楽で飯を食っている人達のことです。
しかも、クラシックで・・・!
クラシックで・・というのは、popularやジャズはまたジャンルが違うからです。
そこはそこで、またプロという人種がいます。しかし、どこまでがプロで、どこからがアマチュアかは、私の領域ではありませんので、このお話の中ではパスします。
ジャンルが違えば考え方も、勉強法も全て違います。私の所に間違えてやって来たそちらのジャンルに進みたい学生は全てそちらの先生達にまわしてしまいます。
面倒見切れないからね。
第1章 メトロノームの歴史
写真:MälzelのMetronom

[Metronomはメルツェルが作ったのではない。]
音楽を演奏する上で、テンポをより客観的に表すための試みは、メトロノームの発明よりも随分前からなされていました。
(随分前・・というのは、音楽が人に伝達されるようになった頃からという意味で、有史以前からという意味です。)
メトロノームが発明される以前の古い時代には、一般的にはメトロノームの代わりとしては、人の心臓の拍動,つまり脈拍を基準にして決めていたと考えられています。
健康な成人の安静時の脈拍は1分間に約60~80回で、各個人によって安定しているので、基準となったわけです。しかし、人間の脈拍はその時の感情や体調によっても左右されるし、ましてや男女、或いは個人によっても変わります。甚だ、不確定な方法であったといえます。当然、より正確なtempoの指示が求められたわけです。
正確なtempoという事は、言い換えると時間を正しく測定するという事に繋がっていきます。
そのもっと正確な物理的な「正確な時間の測定」という事を研究した人が16世紀末に現れます。かの有名なガリレオ・ガリレイです。ガリレイは「振り子の等時性と振り子の周期の2乗がひもの長さに比例する」という有名な法則を発見しました。これは音楽の分野とは別の物理学の世界の発見でしたが、「振り子の等時性の発見」は、やがてメトロノームの登場に繋がって行く基となる画期的な発見でした。
音楽のテンポを指示するものとして振り子の原理の可能性をはっきりと認識した最初の人はトマス・メイスというイギリス人で、彼は鉛玉状のものを糸につるすことで一定の等時性を保てるということを1676年にロンドンで発表しています。またフランス人のエティエンヌ・ルーリエは、これを改良し、糸を長くしたり短くしたりすることで振り子の異なった運動速度を得ることができるということを1696年に発表しています。
しかし、こうした試みはあまり人々の注目をひくことはできなかったようです。
多くの人によって種々の改良がなされたのですが、いずれも実用性に欠けていたようです。
そのネックになっていたのが、振り子の糸の長さでありました。
たとえば1秒を示すのに1メートル以上の紐を使わなければならなかった、それが日常生活の中での実用性を阻んでいたからです。
というのが、一般的(教科書的)な通説です。
ハッ、ハッ、ハッ!
[蛇足ですが、メトロノームの歴史に対しての疑問]
しかし、よくよく調べて見ると、この説には、はなはだ疑問があります。
先程も述べたように、メトロノームの原理は時計の原理であり、やはり、必然的に時計の歴史とかぶってきます。
という事で、時計の歴史を調べて見ると、その歴史はとんでもない昔まで遡ります。メトロノームのぜんまい式の前に、メトロノームの原理の一つになっている脱進機の発明ですが、脱進機を持つ時計でまだぜんまいがなかった頃の時計は、ぜんまいの代わりに錘で動いていました。そのタイプの時計は8世紀の中国まで遡る事が出来ます。
それにぜんまい式の懐中時計も16世紀までに遡る事が出来ます。
時計の歴史を紐解くと、一般的な学者先生達の通説である振り子の原理の発見の歴史と、職人の世界の時計の歴史は全く咬み合わないのです。
つまり学問としての振り子の歴史と、産業の発達の歴史とは年代に大幅なずれが生じます。
蛇足ですが、私がMunchenに留学していた頃、お店でとても古い昔の時計を復刻した柱時計が売ってありました。歯車も木作りで5,6枚しかなく、分針が無く、時針の一本だけというのがなんともおしゃれで、錘がそこらへんのごつごつした石を紐で縛った超原始的な時計で、欲しくてたまらなかったのですが、当時、1万円か2万円しかしないその柱時計が、当時は買えなかったのよね。貧しくて・・・・。 今でも、時々、思い出しては、貧困時代が懐かしくなって、その時計をネットで売っていないか調べていますが、そういった原始的な時計は売っていないのよね。(木造のからくり時計の性能の優れた時計は、今でもドイツ製やスイス製で売っているのだけどね。) あの時、お金があったら買って日本にもって帰ってきたのになぁ・・・・!!
こういった学者先生達の誤りを調べていく事はとても楽しい事なのですが、(人の不幸は蜜の味・・・・!) 此処ではあくまで、メトロノームの歴史のお話ですから、こういった矛盾点には立ち入らない事にします。それだけで、一大論文になってしまいますからね。興味がある人は「時計の歴史」というthemaでいろいろな文献を調べて見てください。とても、面白いですよ。
[MälzelのMetronom]
という事で、話を元に戻して、現在の振子型のメトロノームの原型は、19世紀の初頭になって初めて現れます。
Metronomは一般的にはJohann Nepomuk Mälzel(ヨハン・ネボムック・メルツェル)(1772年レーゲンスブルグでオルガン製作者の息子として産まれる~1838年)によって制作されたとされています。しかし、それは正しくはありません。
Mälzel(メルツェル)はMetronomの特許を取っただけで、正しくはアムステルダムで活躍したドイツ人のディートリッヒ・ウィンケルが、1812年に、ほぼ現在のメトロノームと同形の機械を発明しました。今使用されているメトロノームと殆ど変わりはありません。
「メトロノーム」という名前は「メトロン」(拍の意)とノモス(規則の意)という2つのギリシャ語から、メルツェルが考案した造語です。
それ以前のテンポを計る機械は、クロノメーターと呼ばれていて、メトロノームとは構造が違っていました。それは、歯車式のテコの仕掛けで木炭をたたくといったものでした。
「メトロノーム」は1816年にMälzelが特許登録をしたときに付けた名前です。
速度表示のM.M.」=60などいう場合のM.M.は、メルツェルのメトロノームという意味です。
1815年にアムステルダムのウインケルの元を訪れたヨハン・ネポムック・メルツェル(1772~1838)がこれを模倣し、目盛りを加えるなどのいくらかの手を加え、1816年にいち早くパリで特許をとって、あたかも自分が開発したかのようにして、量産を開始したのです。ですから、特許をとったのはメルツェルですが、実際に機械を作った人はウィンケルであったと言えます。
[BeethovenとMälzelの不思議な関係]
メルツェルは、ベートーベンの伝記には省くことのできないエピソードをもっている人です。
彼は、耳の聞こえなくなったベートーベンに補聴器などを発明しています。
そのエビソートの一つは、ベートーベンが一時ウィーンを去るということで、送別の宴が開かれました。
例:An Mälzel
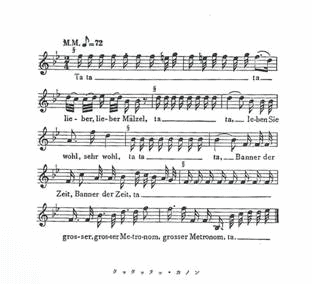
ベートーベンはこのとき、ふざけてメルツェルとメトロノームをうたったカノンを作曲しました。それがすなわち「クックックッ・カノン」で、後になってそのまま第8シンフォニーの第二楽章、アレグレット・スケルツアンドの主題として用いられました。しかし、これについては、セーヤーも、ノッテボームも、1812年にはまだメトロノームの語を使っていなかった事実を指摘して、これはベートーベンが1817年、一時仲違いをしていたメルツェルと和解したときに、この歌詞をつけて歌ったものだろうという見解をとっています。
この仲違いの原因も、メルツェルの発明が始まりでした。
メルツェルは、パンハルモニコンという機会じかけの楽器を発明しました。これは、トランペット、フルート、オーボエ、太鼓、トライアングルなど、軍隊用の楽器を全部取り入れて、機会によって自動的に演奏される極めて精巧なものでありました。
ベートーベンは、このパンハルモニコンの為に、戦争シンフォニーという曲を作曲しました。
お互いの金銭の貸し借りから、この曲の所有権について争いが起こり、ベートーベンが訴訟を起こす迄に至ってしまったのです。
[作曲家の書いたメトロノームテンポの信頼性]
ベートーベンはメトロノームのことを大変高く評価していました。ベートーベンが耳が聞こえなくなり、「いかに楽譜を正確に書くか」と努力していたときには、楽譜にメトロノーム表示を書いていました。
ところがこれは逆にメトロノーム自身の評価を下げるための一つの主張にもなってしまったのです。
それはBeethovenが楽譜に書いたMetronomのtempoは演奏不能のtempoであったからです。
一般的には「その当時のBeethovenは全く耳が聞こえなくなっていて、そのためにMetronomのtempoも、頑の中でだけで考えられたtempoであって、実際に音として体で聞き取った音楽ではないから」 とされています。
でも、私達も楽譜読んで調べる時や、checkする時には、実際の音には頼らず目と頭の中だけで音楽を聞いていきます。
しかし、だからと言って音楽が実際の演奏よりも早くなる事は絶対にありません。
もしそうだったら、指揮なんか出来ない事になってしまいますからね。
ですから、BeethovenのMetronomのtempoの指定が早かったのは、耳が聞こえなくなった性であるとは思えません。
近現代の作曲家であり、耳はちゃんと聞こえていたはずのバルトークのつけたMetronom tempoも、早すぎる場合が多いのですが、それはそんな昔の話ではないので、資料も充分に残っていて、その原因ははっきりと分かっています。
それはBartókが使用していたMetronomの精度が正しくなかったからなのです。
(なんと!!ハッ、ハッ、ハッ!)
ましてやBartókよりも100年も150年も前のBeethovenの時代のMetronomの黎明期の機械的な精度はおして知るべしでしょう。
では、どうして、そういった疑問がこれまで出なかったのでしょうか?
それは、繰り返し述べているようにMetronomは振り子の振幅の速度で測るので、物理的に極めて正確であるという風に、科学的なものは絶対に正しいと思い込んでいる人が多いからなのです。
ですから、単なる機械にしか過ぎなかったBeethovenの所有しているMetronomをcheckして、もう一度正確なtempoを調べなおしてみようという人がいなかったのです。
しかし繰り返し言うように、実はMetronomというものは単なる機械に過ぎないので、一般の人達が思っているほど正確なものではないのです。
(そのことについては、次章に詳しく述べる事にします。)
第2章メトロノームの選び方
音色と音量
[メトロノームの嫌いな子供達]
レッスンでPianoを習い始めた子供達にメトロノームを使用させようとすると、メトロノームの使用を嫌がる生徒が結構多くいます。
私もまだ中、高生であった頃には、メトロノーム練習はとても嫌いでした。一応やってはいましたがね。
しかし、ドイツに留学してからは、メトロノーム練習は、不思議な事に、ちっとも嫌でもなかったし、苦にもなりませんでした。
ですから、私が日本に帰ってから、いろいろな先生達の教室の生徒のレッスンのcheckを頼まれるようになった頃、私がメトロノーム練習を宿題にしても、ちっともメトロノーム練習をやってこない、メトロノーム練習が嫌いな生徒に質問して見ました。
「君はどうしてメトロノームの練習が嫌いなの?」
「メトロノームの音が嫌いだから!」
「そうなの?じゃぁ、君んちのメトロノームを持ってきてみてよ!」
そのメトロノームは日本製の大手のメーカー品でした。
鳴らしてみると、確かに、音が頭にキンキン来る!
国産(当時)のプラスチック製のメトロノームは、カ・チ・コ・チ・カ・チ・コ・チ・と鳴らすと、その鋭いノイズの音が頭にギンギン響いて、ヒステリックな感じさえしてきます。
ためしに、同じメーカーの一番高価な大型の木製のメトロノームでも、試して見ました。
木製であるにもかかわらず、やはり、カ・チ・コ・チ・と嫌なキンキンした音やノイズが頭にギンギン響いてきます。
私はその生徒に「これじゃぁ、メトロノーム練習をしたくなるのも、うなづけるよね!」と言って、私が使用しているメーカーの(西ドイツ製のWittner社製の)メトロノームを親に買ってもらうように言いました。(というか、親に直接ですが・・。) 当然、その生徒は、それからはメトロノーム練習を嫌がらなくなりましたよ。
つまり、子供たちがメトロノーム練習を嫌がる最大の理由は、「日本製のメトロノームの音のノイズが感にさわって、聞くに堪えなかった。」という事だけの話だったのです。
[メトロノームは正確にrhythmを刻んでいるのかな?]
写真(音は少し小さいが、携帯に便利なメトロノーム:Wittner社製)