
メトロノームを専門に売る店の人達でも、(日本にはメトロノームの専門店はないようですが)ぜんまい式のメトロノームは時計のふりこ式と同じ機能なのだから、非常に正確だと思っている人達が以外に多いようです。
でも実際にはメトロノームを買うときには、そのメトロノームの精度はあまり信用してはいけないのです。
ぜんまいの力を利用して動いているわけなのだから、どうしても往きと帰りの振幅の幅がずれるのは当たり前だからなのです。
もしも、メトロノームに精度だけを求めるのでしたら、現在発売されている電子式のMetronomはぜんまい式のメトロノームに比べて、比較の対象にはならないほど正確です。つまり機械式の(ぜんまい式の)Metronomに、精度はそれほど期待してはいけないのです。
勿論、私がドイツに留学していた時代には、まだそういった精巧な電子メトロノームはまだ作られていなかったし、この「メトロノームについて」のお話が書き始められた頃も、まだクオーツ発振のMetronomは作られていませんでした。
[蛇足]
というわけで、このお話の中に出てくるクオーツ式のMetronomのお話は、今から20年、30年前に書いたワープロで立ち上げた文章を、この1,2年の間にOCRして、(パソコンに読み込んで)pc用に変換させた文章に、そのOCRの作業の過程で、新たに書き加えたものであって、ワープロ時代の文章には入っていません。
当時は電子メトロノームはまだ発売されていなかったからです。
当時、ぜんまい式のメトロノームを専門に扱っているWittnerの代理店のような楽器店ですら、ぜんまい式のメトロノームの不正確さを理解している人はいませんでした。
私がドイツに留学していた頃、メトロノームを買うために、私がすんでいる村の近くのメトロノームの代理店を訪れました。私が欲しかった型版のメトロノームをそこのお店にあるだけを全て(20台以上ですが)出させてcheckをしました。
お店の人は、最初の間は「メトロノームは物理的な動きなので、どのMetronomも正確で同じですよ。」と文句を言っていたのですが、まず、そのメトロノームのメモリにある一番遅いMetronom tempoで往きと帰りのbeatのずれを量りました。(本来は、ずれのcheckには腕時計の音の回数を利用します。これは昔の調律師がPianoの音を完全に音を合わせた後に、音を平均律にずらして調律するために、うなりの数を正確に合わせるための方法です。)
勿論、その前に、水準器を使って、Metronomを置く台の水平を取っておかなければなりません。台が斜めになっていると、正確な振幅は測れないからです。
という事に注意を払って、正確に往きの数と、帰りの振幅の数を数えると、これが違うんだな!困った事に!!
実際に私がお店でcheckした時には、わざわざ腕時計のかすかな音でcheckをするまでもなく、見ているだけでもそのお店のメトロノームの半数以上がボツ(却下)になったのだよ。
Wittnerの店員のおじさんは真っ青になりました。「エ~ッ、そんなに不正確なのか!?」
水準器を手に取って、台が斜めになっていないか、確認をしながら、「20年以上この店で働いているけれど、一台一台が、こんなにずれているなんて、初めて知ったよ!」と驚いていました。
しかし、私の厳しいcheckはまだまだ続きます。
次には、Metronomのtempoを60にセットして、正確に時計の秒針に合わせてMetronomをスタートさせました。
本当は1分間(60回)メトロノームの動かして、そのズレをcheckしようと思ったのですが、殆どのMetronomが20秒から30秒経たない内に、秒針とのズレが生じてきました。
殆どの機種がそれでボツになったのですよ。
私のテストの中で、30秒以上経っても、メトロノームの振れが狂わなかった、(ずれなかった)唯一生き残った貴重な一台のMetronomが、それ以降の私のドイツ留学中のピアノ練習の伴侶になった最愛のMetronomです。(写真参照)
プラスチック製なのですが、音はとてもきれいな音がして、鳴らしながらPianoを演奏しても、その音が感にさわる事はありません。
写真:Wittner社製のMetronom(私がドイツ留学時代に愛用していた携帯用のMetronom)

殆どの人達が「メトロノームは時計と同じで非常に正確なtempoを測っている。」と思い込んでいて、実際には、殆どのメトロノームが往きと帰りではタイミングが微妙にずれている、と言う事を知っている人は(売る側も買う側も)皆無だと言えます。
しかも、「同じメーカーの、同じ種類の製品」であったとしても、機会的に微妙に違っていて、当たり外れがあるのですが、それは機械の特性上致し方のないことだと思います。
しかし、こういったメトロノームの選び方(買い方)が出来たのは、私が西ドイツに留学していたからで、日本では同じWittner社の製品を20台、30台も置いてある店は何処にもないと思います。
[電子式メトロノーム]
勿論、メトロノームの精度を求めるのであれば、現在は日本製の電気のメトロノームが沢山つくられていて、正確さでは機械式とは比べ物にならない程、それは正確です。
しかし、メトロノームを制作する人達がそのメトロノームの音を、どうしてぜんまいじかけのカチコチのいやな音に似せてしまうのかが私には理解出来ません。
もっと柔らかい音で聞き取りやすい音ででも良いのではないでしょうかと思いますがね。
もう一つは、電気式メトロノームの音量はぜんまい式に比べて小さいので、アンサンブルなどで使用するには聞き取りにくいのです。
ヴォリューム調整で音量を幾らでも大きくする事が出来るのだから、音量の幅をぜんまい式のメトロノームより、小さな音から大きな音まで出せるようにすれば、アンサンブルや学校のブラスアンサンブルなどにも使用出来て良いと思いますが、未だにそのようなメトロノームは発売されていないようです。(学校のブラスバンド専用の旧型のハーモニートレーナーは音量が非常に大きな音量まで出せたのですが、新しいハーモニートレーナーは音量が小さすぎて使い物になりません。20万近くする楽器なのだから、わざわざアンプに接続して音量を上げるのではなく、楽器本体の能力で、そういった音量的な許容範囲も欲しいところです。)
写真:日本製の電気のMetronom
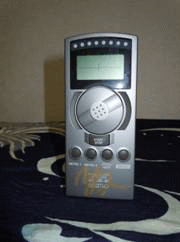
このハンディータイプのMetronomは、弦楽器のチューニングのAの音が出せることと、簡単な3;2などのrhythmのトレーニングが出来る事や、何よりも、Metronomのtempoが二つ同時にセット出来て瞬時に切り替えが出来るので、一つの曲の中で第一tempoと第二tempoを非常に多く指定する私のレッスンでは、とても便利なのでいつも愛用していて、生徒達にも進めていたのですが、残念な事に日本製の他の製品同様に、あまり長い期間は販売されないで、すぐに次の製品にモデルチェンジしてしまいました。次に販売された同型の機種では、そういったこの機種のメリットはもう搭載されていませんでした。(もう一つの、メリットはメトロノームのメモリが1コマずつ上がっていくという事です。)
教室のオケ練習等では生徒達が色々なタイプのメトロノームを持っているので、テンポの設定を一般のテンポに合わせて、80,84,88,92,96,100、という刻みになっています。でも、子供の場合には82では弾けるけれど、83では弾けないと言う事が起こってきます。その82のテンポの事を私は臨界テンポと名付けました。(臨界テンポは後で詳しく説明します。)ところが一般のメトロノームでは82の次は84なので、臨界テンポを一メモリ上げるという、臨界テンポの練習が上手くいかないときがあります。道具が高性能なのにはそれなりの価値があるのですよ。
[不遇なメトロノームが指導者達からその価値を認めてもらえない理由]
私の長い人生の経験では、音楽大学で教鞭をとっている超有名な先生ですら、実際にはメトロノームに合わせて演奏する事が出来ない先生達が多くいました。その先生達が私に弁解した時の定番の言葉は 「メトロノームで練習をすると、演奏が非音楽的になるから・・」という言葉なのですが、その先生達の演奏がMetronomを使って練習していないのにかかわらず、杓子定規で、画一的で、とても非音楽的であるから、メトロノームで直すように、指導をしたのですがね。
「メトロノームで練習をすると非音楽的になるから・・」という事よりも、ただ単にメトロノームの使い方を知らなかったから、メトロノームで練習しなかっただけだと思いますがね。
先生が使い方を知らなければ、生徒がメトロノームを使えるようになるわけはありません。
音楽大学の先生がメトロノームを使えないわけですから、その生徒達が音楽大学を卒業して、それから就職して指導している殆どの音楽教室には、最初からメトロノームが置いてないし、当然、その教室の生徒達はメトロノームに合わせる事ができないのですよ。
そこでその教室のオーナーに「何で教室にメトロノームを置いていないのか?」 と訊ねると、「この教室では、音楽的に音楽を指導しますので、情操教育上害になるような、非音楽的になるようなそういった道具は置いてないのですよ!」と自慢げに語ってきます。
しかも、リトミックやrhythm教育をしている音楽教室ですら、同じような答え方をして、メトロノームを置いていないのですから、どういうrhythm訓練をしているのか、疑問を抱いてしまいます。基準になるtempoが最初から無いので、曲のtempoが途中でふらふらと変わるのは当たり前の事で、弾き始めのtempoも一回ごとに違います。それではプロとしては使えない。勿論、人と合わせるアンサンブル等で正しいtempoは取れません。日本のアンサンブルでは、力関係でtempoが決まります。力関係が無いプロの世界では誰かの感情的なtempoに、皆が合わせるというような、情緒的な合わせは絶対にしません。
ですから、皆、打ち合わせにはMetronomを使用して細かい小節ごとのMetronomのtempoの打ち合わせをします。
第3章メトロノームの使い方
基礎編
レスナーへのアドバイス
前書き
譜例: