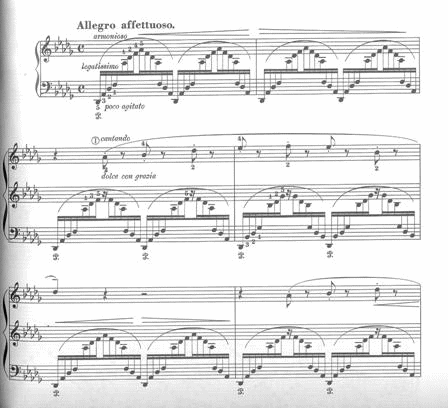
この曲の冒頭の前奏は指定はないのだが、8分音符の点描されるmelodieはportatoで蛍の光が点滅するように、浮かび上がるimageで美しく柔らかく伴奏のfigurationから浮かび上がってこなければならない。だから、伴奏部のpassageはPかpianissimoから膨らまして、せいぜいmezzo P辺りまでの膨らましであろう。と言うわけで、最初の8小節は延々と7連音のpassageが美しく演奏されなければならないのだが、7連音の粒粒を綺麗に出すことが出来ないので、力任せにすごい速度でfortissimoで弾き捲くる無神経なピアニストが多くて困る。
7連音はゆっくりと美しく「きれいな音で、ピアノを弾こう。」と、お話ししながら、言葉に合わせて演奏すれば、自然に美しく粒粒を出す事ができるようになる。
7連符 9連符、5拍子、などの奇数のリズムの練習は、言葉を当てはめて練習すると良い。
[phraseによる、等分割されない拍取り]
言葉を当てはめると、良い結果を生み出すのはrhythmに関する訓練だけではない。
Beyer教則本の実に早い段階でも、phraseを指導している。
譜例:Beyer教則本18番 不定形のphrase
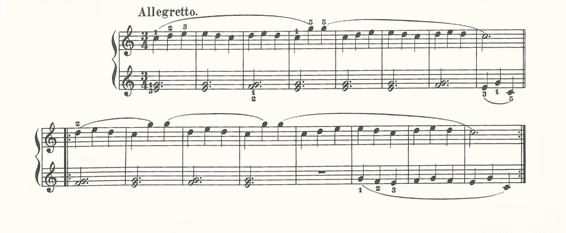
Beyerのこの課題曲をBeyerの意図通りにphraseを子供に指導している先生を見た事はない。もし、この段階で、子供に指導するのが無理だと思うのなら、phraseに合わせて子供が喜びそうな歌詞を作って見ると良い。無理なら親に作らせても良い。phraseとphraseの間がちゃんとブレスになるように歌詞を作るのが基本である。
よい言葉の選び方
拍頭を表す言葉は、力行、夕行などの発音がはっきりしている言葉を選ぶとよい。
逆にサ行とかナ行のように、言葉にアクセントがない単語は、リズムがとりにくくなります。
より高度なrhythmの例は幾らでも探す事は出来る。それはその都度練習していけばよい。
[変化する拍の例]
①ritardandoやaccelerandoなどの拍を揺らす記号の例
メトロノームではritardandoやaccelerandoが出来なません。
今の技術ではそういったメトロノームを作る事は簡単に出来るはずなのに、まだそういったメトロノームが発売されていないので、大手のメーカーに、私が「揺らしの数式」を持ってMetronomを作ってくれるように頼みに言った事があります。
その時のMetronomの大手メーカーの人の返事は、「クラシックの世界ではMetronom自体があまり売れないし、ポピュラーの世界では、シンセサイザー等の自動演奏を使用するので、揺らしはしない」のだそうです。ですから、私が自分lessonで生徒に推奨していた、rhythm trainerすら、売り上げ不振で販売中止になったのだそうです。
だから、世界初のritardandoやaccelerandoの出来るMetronomの製作は諦めざるを得ませんでしたが、それは使い方次第で幾らでもカバーすることが出来ます。
私が生徒に指導する場合には、rit.の始まる前のphraseから正確なメトロノームテンポで練習して置き、次にその到着点(accelerandoやritardandoが終わった所)から、その目標のテンポでメトロノーム練習しておきます。
そして、そのつなぎの部分をちゃんと目標のテンポに収まるように練習しておけば正確にrit.やaccelerandoをかける事が出来るようになります。
この練習は、もしアンサンブルに興味がある人や、管楽器、弦楽器の人達にはきわめて重要です。ピアノを勉強している人も、アンサンブル(ピアノトリオ、ピアノカルテット等)が好きだから、とか言う理由ではなく、本当に正確な演奏を勉強する上ではとても大切な事なのです。
弦楽器や管楽器の人達は、常にアンサンブルをしているので、テンポに対してとても敏感です。他の人達との、兼ね合いがあるからです。だからritardandoやaccelerandoの勾配や目的のテンポに対してもとても正確に、演奏する事が出来ます。ところが、一人天下のピアノの人達は、その日、その時の気分で弾くたびに、揺らしの加減が違うことが多いのです。
揺らしの加減が違うという事は、当然、テンポの勾配が違う分だから、目的(揺らした後の結果)のテンポも変わってきます。そのために演奏会などでは思いもかけない破綻をきたすことも、間々あります。
ましてや管楽器や弦楽器との伴奏合わせや、Pianotrioなどの室内楽をする時には、気分でrit.やaccelerandoをしていると、練習にならなくなって、喧嘩になってしまいます。
音楽大学等では、よく見受けられる光景ですがね。
[rubatoの例]
②rubatoのメトロノームの合わせ方
勿論、メトロノームではrubatoはできません。ですが、rubatoには、ゆっくりすれば、その分どこかが速くなるという原則があります。例えば、accelerandoが大きくなればなるほど、後のソステヌートが大きくなる。逆に前に大きくソステヌートをかければ、あとのaccelerandoも大きくしなければならない。だから、テンポの揺らしがあっても全体の曲(あるいはフレーズ)の良さは変わらないのです。つまり、テンポを思いっきりゆっくりしたいと思ったら、その前か後に思いっきり速い部分をっくればよいのです。人間の呼吸と同じで緊張と弛緩が1つの流れなのです。小節の無い、或いは、2、3小節間のrubatoの場合には、ふくらませたり、あせったり、ちぢませたり、ゆっくりしたりしながらも、小節の頑などのポイントの拍だけをメトロノームに合わせるように練習すると良いでしょう。それがうまくなると2~4小節ぐらいのrubatoでもメトロノームに合わせられるようになります。
③rubatoとritardando,accelerandoの違い
rubatoは楽譜には書かれません。定説としてrubatoで演奏することが多いのです。
Rubato(ルバート)
曲の情緒表現としてのnuanceなどによってテンポを揺らすのがrubatoです。
それとは別にウィンナ・ワルツとか、ポロネーズとか、民族音楽としての独特のrhythmで演奏されるものもあります。ChopinのMazurka(マズルカ)のように、2,3Pageに過ぎないのに、幾つものrhythmを多様に表現しなければならないものもあります。(Chopinの一番短いMazurkaで、解説をしようかと思ったのですが、口伝と演奏では簡単にimageを伝達する事は出来ますが、文章に書くとなるとちょっと・・・という事で、諦めました。
Rubatoの原則は、必ず、大きなphraseではテンポのつじつまを合わせるという事です。
Melodieは必ず質問と答えの二つのMotivで成り立っています。まれには質問が2回繰り返されたり、答えが2回繰り返されたりする事がありますが、必ず、phraseはそう出来ているのです。ですから、質問がゆっくりとrubatoされたら、答えが速くなります。質問を速く畳み掛けてすると、答えはゆっくりと安心して返してきます。それがrubatoの原則なのです。
それともう一つ、rubatoは必ず、1、2小節ぐらいの短い単位で動きます。
曲のつなぎ等のpassageで、短い単位にriten.と書かれていても、それはつなぎのpassageなので、rubatoとは呼びません。
Hemiola(ヘミオラ)
数多くの曲の中で使われる技法で、初心者から上級者まで、いつも演奏しているのにもかかわらず、正しく演奏されない拍取りにHemiolaというものがあります。それこそ、歴史は古くからあって、baroque時代、Bach、Händelなどの大作曲家達からChopinやSchumannなどのロマン派の作曲家達、近現代のBartók等の大作曲家達に至るまで、非常によく使用されてきた技法です。Hemiolaは曲の途中で2拍子と3拍子が交替します。
つまり、2拍子の曲の一部が3拍子になるのです。それを殆どの人達が2拍子のままでsyncopationで演奏しています。
Verschobene Takt(推移節奏)
この聞いた事の無いような言葉は、実はこの言葉を聞いた事がなくても、演奏では、しょっちゅうお目にかかるphraseです。
拍がずれて演奏される事を言います。
verschobene TaktはAgogikと間違いやすいのですが、Agogikは拍子の中で、別の拍節法を取る事を言います。
いずれにしても、syncopationと間違われて演奏されることが非常に多いようです。
あとがき
Beyerについてやメトロノームについても、過小評価ではなく、その真価が分からない人がけなしているのを聞くたびにBeyerやMetronomの身になって、心を痛めています。おお、可哀想なMetronom!
芦塚メトードでは音符の譜読みの導入に「市販の音符カード」を使用します。
ある時に、それを見た音楽の先生が「譜読みのメトードは芦塚先生のオリジナルのメトードだと思ったら、市販のメトードだったのですね。」と言っていました。
その人は、メトードが音符カードそのものだと思ったのですね。Beyerは優れた教則本です。でも、Beyerを使用したからと言って、子供が上達するわけではありません。音大の先生達が「Metronomを使用すると、非音楽的になるから、Metronomを使用してはいけない。」と言っているのを聞いて、「音楽のプロと呼ばれる人でMetronomを使用しない人はいないのだけど・・・」と、ついつい可哀想になってしまいます。
つまり、Beyerは教則本に過ぎないし、Metronomはただの器械にすぎません。どのように優れた曲であっても、その演奏に創意工夫がなければそれはただのつまらない曲に過ぎないのです。
教室に見えられた先生が子供の伴奏でDiabelliの連弾をつまらなく弾いていたので、私が「Diabelliは、こういう風に奏くのですよ。」と、説明したら、その先生が「この曲は奥が深いのですね~ぇ!」と驚いていました。子供の曲だからつまらない曲だと思うのは、大変な間違いなのですよ。Beyerだって、Beethovenと同じ時代から、本当に多くの人に支持されてきたのです。それだけ時代を生き抜いてきた曲がつまらない分けが無い。それを理会出来ない音楽家がいたら、その人の演奏はつまらないものでしょうね。
Metronomを馬鹿にする人は、アンサンブルも、いや正確な揺らし(rubato)も出来ないでしょうね。ましてや、ChopinのPolonaiseやMazurkaを正確に演奏していく事は不可能でしょうね。正しく揺らすには、基準が必要なのです。強弱(forte、Piano)でも、tempoでも、基準が会って初めて、自由に使いこなす事が出来るのです。その基準となるMetronomを馬鹿にする人は、きっとMetronomに笑われて、馬鹿にされていることでしょうね。
あとがき
(第二稿に寄せて)
このメトロノームについての論文は、実は今から30年以上前のワープロ時代に書かれたものです。
ですから、昔々、一度、完成した論文は、発表会の時に、生徒父兄の希望者の方達に配られたのですが、その後、ワープロからパソコンへの移動や事務所や私の自宅の引越し等々で、他の論文同様に、フロッピーディスクや完成した原稿、配った冊子が全て失われてしまいました。
というわけで、完成前の反古の紙切れや、やっと見つかったかなり初期の段階で入力されたフロッピーディスクから、OCR(文字認識)ソフトで、ワープロ文章をパソコンに取り込んで、その過程で、譜例や若干の新しい文章を付け加えました。20Pageほどの音楽夜話のお話でしたが、譜例などを加えたために倍近いPage数になってしまいました。
というわけで、前半部のよもやま話と指導マニュアルに近い後半の専門的なお話を分けて冊子にすることにしました。
という事で、全くリニューアルされ改定された文章になってしまいましたが、少しは以前の文章よりはましになったかなと思っております。

2010年6月20日
江古田の寓居一静庵にて
一 静 庵 庵 主
芦 塚 陽 二 拝