
①のrhythmの練習法には、6連音のrhythmの練習があります。この練習は上級になってもよく練習しなければならない大切な練習法です。
譜例:6連音のrhythmの分割練習(Czerny30番教則本より、)通常のskip練習とは別にrhythmの分割練習をします。
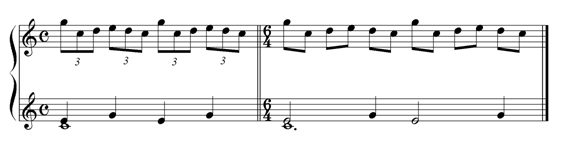
先程も述べたように、BrahmsやSchumann、Chopinなどのロマン派の大作曲家達の両手や音の粒をクリヤーに出す一般的な方法として、単純なrhythmをわざわざ複雑に演奏させる事によって、声部を独立して浮き立たせるような作曲法を使用しました。そういったロマン派の演奏技法に慣れておくためにも、初期の段階からそういったpolyrhythmを練習しておくと、高度な音楽を演奏する上でとても重要です。
譜例:ChopinのÉtudeOp.10Nr.10複雑な拍取りの例
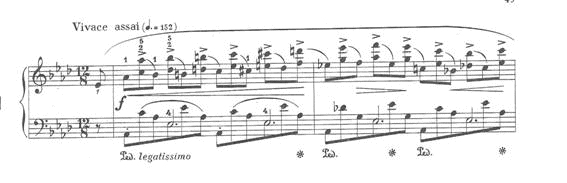
Czerny 30番ぐらいの、levelから色々なrhythmの訓練やarticulation練習をしていると、こういった曲の演奏はさほど難しくはありませんが、いきなりChopinのÉtudeから複雑なrhythm(拍取り)を練習しようとすると、超絶技巧的に難しくなってしまいます。
[奇数のbeat]
奇数の拍子
近頃のメトロノームは拍子の設定も1拍子から9拍子まで、1刻みで拍子の設定が出来るようです。しかし、5拍子や7拍子等は、裏拍の拍取りは、5拍子の場合には、3+2、若しくは2+3と取る、両方の場合があるのです。同様に7拍子も4+3拍の場合と3+4拍の場合があります。
譜例:5拍子の例:チャイコフスキー シンフォニー第6番2楽章
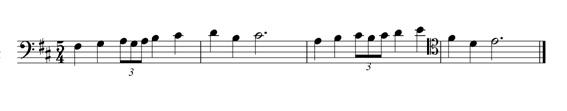
この曲は2+3の例である。
[等分割されないrhythm]
音楽が始まって以来、等分割されないrhythmはごくごく、普通に見受けられる。
しかし、ゆっくりと丁寧に分割されない音符の粒粒を出す事は意外と難しい。
私はよく、子供達に言葉を当てはめて、声に出させながら演奏させる。
6連音ならば「新幹線」とか、3連音が2個の6連音ならば、「白いうさぎ」とかである。
次の譜例はLisztの三つの演奏会用練習曲より第3番「ため息」の冒頭のpassageである。
譜例:Lisztの三つの演奏会用練習曲より第3番「ため息」