![]()
 昔々、(とは言っても、いつの頃か分からないので、もう少し詳しく)音楽大学在学中の頃の話なのだが、東京のうどん屋に置いてあった七味唐辛子に虫が湧いていたという事で、大騒ぎになった事があった。
昔々、(とは言っても、いつの頃か分からないので、もう少し詳しく)音楽大学在学中の頃の話なのだが、東京のうどん屋に置いてあった七味唐辛子に虫が湧いていたという事で、大騒ぎになった事があった。
当時は、七味は辛いので、殺菌作用があると、勘違いをしている人が多かったのだよ。
私も、古い七味は、その粉を白い紙に薄く広げて、ルーペで、粒粒を観察する事がある。
でも、わざわざルーペを出さなくても、粉が動くので、気を付けてさえいれば、直ぐに分かるのだよ。
七味は単なる香辛料なので、そんなに殺菌作用がある分けではないのだよ。
寧ろ、香辛料の薬味に虫が湧く物も多いのだからね。
教室を作って、間もない頃、先生達と成田さんにお参りに行った。
参道に七味屋さんがあって、その場で好みの香辛料をブレンドしてくれていた。
勿論、私達も、教室用に、自分流の七味を作って貰った。
私は温かい蕎麦には七味を入れるのだが、うどんは一味を入れる事の方が多い。
教室を作ったばかりの若い頃、音大の近くの(音大の先生達や生徒達の溜まりになっている)寿司屋があって、そこに私達もよく行って打ち上げをしていた。
先生達と喧嘩をして、未だ逃げ場を持っていなかったので、その寿司屋で酒を飲んでいたら、先生が迎えに来た。
originalのレシピで、当時は未だゲソを塩と辛子で焼いて出す寿司屋は珍しかったので、私が自分のmenuと言う事で「ゲソを塩で焼いて、一味をふりかけて・・」と、オーダーしたら、「七味はあるけれど、一味なんてないよ!」と寿司屋のマスターが言った。次にお店に行く時に、一味を買って行ったら、「こんなのがあるんだ!!??」と驚いていた。
要するに、一味とは、トンガラシだけの香辛料で、本当は、薬味の種類によっては、五味もあるし、三味もあるのだけどね。
だから、七味と言っても、必ずしも、七種類入っているとは、限らないのですよ。
だって、六味とか五味では、なかなか売れないでしょう??
江戸時代の七味唐辛子に使われている七種類の薬味は「赤唐辛子」、「生姜」、「陳皮」、「山椒」、「黒胡麻」、「青紫蘇」、「麻の実」です。
また、別の老舗のレシピでは「赤唐辛子」、「山椒」、「白胡麻」、「黒胡麻」、「青紫蘇」、「青海苔」、「麻の実」の七種類です。
関西と関東では、当然、レシピが異なります。
今、教室で使っている七味は長野の七味です。
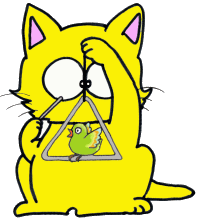
ニャンコをクリックすると、前のindexのPageに戻ります。