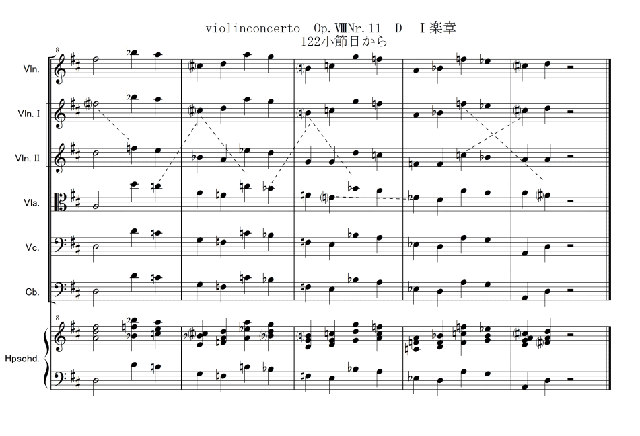前ページ
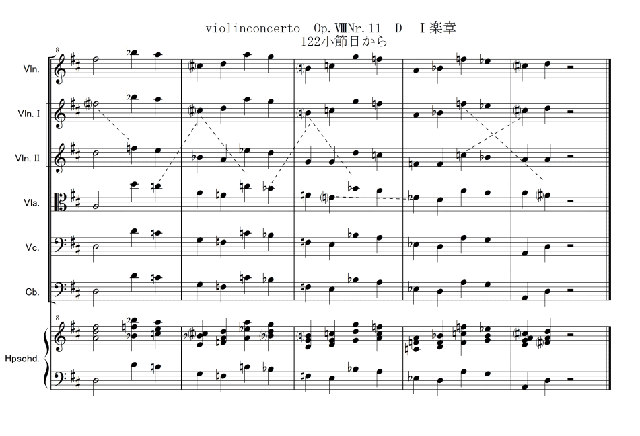


音楽を勉強する時に、「難しい!!」「弾けない!!」と思った時に、一生懸命にひたむきに練習する事を、日本の音楽教育では推奨します。。
日本の教育界では(或いは、社会では)努力そのものを評価する傾向にあります。
非効率的に、いたずらに時間が掛かって、無駄な努力を続けたとしても、その努力や時間に対して評価をする・・という傾向が日本の教育社会には・・あります。
しかし、実社会では、そういう分けには行きません。
私が生徒に教える、「物事を考える上での考え方」の方法論に、4択マスがあります。
これに実社会で、仕事を注文された場合を想定して4択マスを書いて見ます。
一つは、仕事が早いか、遅いかのマスです。
もう一つは、仕事がミスがあるのか、丁寧か?のマスです。
それを4択マスに書き込むと以下のような表になります。
丁寧雑 / ①② 早い ③④ 遅い
①この場合には、1番のマスは、問題は全くありません。しかし、そこ迄出来る人達は決して多くはありません。
④遅くて雑な仕事をする人は、仕事には向いていないのです。他の職業を選ぶべきなのです。社会の迷惑にしかなりません。
③の「丁寧だけど、遅い」というのは、作業にtimelimitがない作業や、endless作業の場合には、仕事として成り立ちます。
②の「早いけれど、雑」という作業も、下準備の作業としては、例外的に成り立つ場合があります。作業の殆どは、外注したとしても、必ず、checkは自分でし直さなければならないのです。①の作業をする人で、長年の信頼関係が成り立っている場合には、例外的に、checkも任せられる場合がありますが、それは例外中の例外なのです。
ただ、パソコンに入力だけをお願いして、後で、間違いを手直ししながらの作業でも、「時短」になる作業がある場合には、この②番の人に仕事を発注する事はあります。でも、信頼されている分けでは無いので、ちゃんと仕事が出来る人が現れた場合には、首になってしまいます。
社会は、そう言った意味では、非情なのですよ。慣れ合いのような人間関係は有り得ないのですよ。
音楽を指導していて、保護者の自分の子供への人生の選択が信じられない事がよくあります。
音楽を好きで、proに成りたいという願望のある教室の生徒達は、日本中の同じ楽器を演奏する子供達の間で、頂点の四指に入る技術と音楽表現力を持っているのですが、親は、その子供達が、大した成績を上げている分けでもない、極、普通の学校の勉強を、メインに勉強させて、塾に行かせて、好きでもない大学進学を目指して、頑張らせる・・という事なのです。
せめて、音楽と同じlevelで、東大を目指して勉強する・・というのなら、何とか納得も出来るのですが、何処の大学か分からない大学を目標にして、日本の一級のlevelを捨ててしまうのです。
私達にとっては、自分の子供のproとしての道を捨てさせて、どうして、どうでもよい一般大衆の中に埋没させるのか、その理由が分かりません。
「苦労をさせたくない」というのかも知れませんが、自分に合ってない事に対して、努力を費やす程、苦労をする事は無いし、その苦労が自分に帰って来る事はありません。
それに、「好きな事を努力する事」は、苦労にはならないのですよ。
一般の世の音大生が音楽に進むのは、寧ろ親の夢です。
本人は、好きでもない音楽を、ひたむきに練習させられるから、その努力を苦労と感じて、苦痛に思いながら練習をするから、その努力が報われないのですよ。
「音楽を好きでもない」・・という事は、教室の生徒達には、絶対に理解出来ないでしょうがね??
そこが、教室の生徒達と一般の音楽を勉強している生徒達の根本的な違いです。
話を本題に戻して、練習の無駄を省くコツは、何故、それが出来ないのか??を理解する事です。
それが、理解出来れば、その対処法も理解出来るし、効率的な練習法も作り上げる事が出来るようになります。
つまり、この曲の場合には、先ずは、verschobene Taktを理解し、その前の、本来のtaktがどういう風に移動したのか??を理解する事です。先ず、本来のtaktで練習をして、次にMetronomを使って、verschobene
Taktを練習します。
次の音程の難しさですが、別の楽器が弾いているQuerstand(対斜)の音符を、自分でも弾いて見て、その音程が別の楽器とちゃんと同じ音になっているのかを確認する事です。それで、音がどのように微妙にズレてしまうのかを理解出来れば、音程を正確に取れるようになります。
神経戦の練習にはなりますが、しかし、時間を無駄に使う事は全く無くなるはずです。
でも、この練習はscoreが読めないと、出来ない練習ですよね。日本人の自分のpartしか、勉強しようとしない人達には、出来ない練習法ではありますよね。
日本人は、無駄な練習をしないように、他の人のpartは見ようとしません。ひたすら、自分のpartのみを必死に練習して、責任を果たそうとします。
そこの所が、日本人特有の無駄に対する考え方です。
violinの生徒がPianoを勉強したり、他の楽器を練習する事を極端に毛嫌いする所も、基本は儒教の考え方から来ています。
一兵卒は、なまじ色々な事をやらないで、言われた一つの事をやればよいのだ!!という考え方です。
色々と勉強すると、知恵が付いて、言う事を聞かなくなってしまうからね!!
この考え方が、これまでの企業を支えて来たのです。
でも、それは終身雇用制度であったから成り立った考え方なのです。
現代のglobalstandardな企業社会では、もう成り立たない・・という事は企業サイドはよく知っています。
大体、日本を代表する大手の企業が片っ端から潰れて台湾等の企業の傘下になっている現状です。Panasonicを始めとして、三菱自動車や、シャープも同様で、日本の大手企業に一昔前の勢いは無いのですよ。
しかし、一般の社会では、そういった現状に対する恐怖心は無い。ましてや、企業に人材を送り込む学校教育の世界では、今までの教育制度をそのまま継承しているのです。
教育界は、江戸時代、明治時代から、閉ざされた世界のままであり、教育界にglobalstandard(世界を見つめる視野)は、未だに無い・・・からです。・・というか、その前提すら無いのですよ。
沈没船の上で、明日のディナーの料理を夢見ている・・そんな具合なのですよ。
今から40年前に、年金の問題と原発の危険性を提唱したのですが、一笑に付されてしまいました。
年金は、日本の人口が際限なく増え続ける・・という前提で成り立つので、1970年に1億人を突破して、私がその話を役所でした時には、日本の人口は1億1千万人で、日本の人口のキャパシティは1億2千万までですよね。それからは、人口は減少するはずなのだけど・・と、言うと、すっかり馬鹿にされてしまいました。
原発の場合は、私と同じ質問を記者の方がされていて、「もし、原発が故障した場合にはどうするのですか?」という問いかけに、「原発は絶対に壊れないという条件で設計がなされているので、ありもしない前提には答えられない。」というのが、学者の方の答えでした。「でも、もし、壊れた時には、100年、千年単位で失われてしまうのですよ。リスクが大きいのでは??」という質問に対して、ありもしない・・云々という答えを繰り返すだけでした。
そのありもしないことが、二つとも起こってしまったのだよね。
分かり切った事なのにね。
これも、驕り・・なのだよね。
教室の生徒達が全く練習をしないのに、pro並に演奏が出来るのは、ある意味凄い事なのですが、保護者の人達も、それどころか、本人達も、普段、全く練習をしていない分けなので、自分が上手い・・と言う事に価値を見い出せなくって、しかも上手いとすら、思っていなくって、練習量だけが凄くて、大した技術も持っていない人達に対して、「これだけ練習するのだから、きっと上手いに違いない」って、コンプレックスを抱いています。
冷静に演奏を聴いて、その評価が出来たとしても、「今回は、偶然下手なだけだ!」「本当は、キッと上手いはずだ!!」と、思い込んでしまいます。
馬鹿げた事なのですが、掛けた時間の量が、その人の技術である、と思うのが、一般社会の評価なので、先生に指導されて、上手なだけなので、信念を持って上手い分けでは無いのです。
でも、「練習量が凄い」という事は、それ自体は、社会的には、何の意味もない事なのですが、学校教育上の評価で、「凄い」って思ってしまうのですよ。
子供達の24時間は学校教育の中にどっぷりと浸かっているからね。
先程も言ったように、仕事は「出来てなんぼ」のものなのに、時間を掛けるという事は、社会では、マイナス要因とされるのに、学校教育上では、良い事とされるからなのです。
学校で一番困った事は、「宿題」です。
昔は、生徒達に、「学校で出された宿題は、学校で済ませて、家に帰ると、家では音楽の練習に専念出来るよ!」と言ったら、学校の先生が、「宿題は家での勉強の躾のために出すものです。学校で宿題を済ませるのならば、宿題を追加で出す事にします。」と言われて、呆れてしまいました。その先生達は学校の宿題以外は、勉強ではない・・と思い込んでいるのですよね。
学校が対象にしている子供達は、家で全く勉強をしない「ノビ太君」のような生徒の話なのですよ。
アスリートの真央ちゃんや、泣き虫愛ちゃんや、Balletを勉強している人や、pro野球を目指す人、絵かきに成りたい人達のように、自分の人生に目標がある人達は、学校の勉強を家でやるような、時間は無いのですよ。人生が忙しいのは、学校の先生達よりも、数倍忙しいのです。
それが一般人の学校の先生達には理解出来ない。
困ったものです。
そのために、多くの一芸に秀でようとする子供達が何度もの転校を余儀なくされています。
世の中は、そういった一芸を求める人達に支えられているのですがね。
一般人は、消耗をする人達に過ぎないのです。
世に何かを提供する人達は、総ての人達が、一芸を求める人達からの恩恵なのですがね???


お話が水掛け論になる原因の多くは、その課題の定義が整合していない事が多いのです。
昔(とは言っても、2,3年前のお話ですが・・)何時ものように、テレビをつけっぱなしにしたまま、パソコンの仕事をしていました。
NHKの討論会で、学生、社会人、経営者、男性と女性と年齢に分けて討論をしていました。
女性の起業家の人が、「同じ仕事をしても女性では評価されない!」と苦言を呈していたのに対して、同じ経営者の熟年の世代の男性が、「もし、トラブルが起こった場合には、深夜であっても、駆け付けてくれるのか?」とその女性起業家に質問をしました。
その起業家の女性は、「ちゃんと、仕事は責任を持ってやっている!」と答えるだけで、その「深夜にトラブルが起こった場合には・・」の質問には、答えようとはしませんでした。
小学校の女の先生で、子育て中の女性であったとしても、学校の生徒が、家出をしたら(別に遊びに出掛けて帰って来なかった場合でも同じなのですが)、例え、深夜であったとしても、子供を探しに出て、その生徒が、見つかるまで、徹夜で・・でも、子供達を探さなければなりません。これは自分の教室の生徒では無くても、その責任は変わらないのですよ。
女性起業家は、深夜に工場のラインが止まるとその会社にとっては死活問題である・・という事は理解出来ません。
女性起業家の人は、自分が会社で働く時間内は、一生懸命に働いて、家に帰ると、妻という立場と母親という立場が待っているので、その立場に責任を持って一生懸命に頑張らなければなりません。
本当に、24時間頑張らなければなりません。
女性起業家は、そこの所を、しっかりと認めて欲しかったのです。
でも、熟年の会社経営者は、もし深夜ラインが止まって、納期に間に合わなくなったら、従業員の生活の問題になってしまい、最悪の場合には、その会社が倒産する事にもなりかねません。そうなると、一家の心中ものです。
それなら、男性の従業員の居る、深夜でも責任を持って、駆け付けてくれる会社と契約するのが当たり前ではないでしょうかね??
私達は、それを、「女性差別」とは言わないと思いますよ。
音楽のお話に戻って
ヨーロッパの音楽大学と日本の音楽大学には、大きな違いがあります。
ヨーロッパの音楽大学では、女性の音大生は殆どいません。大学生の殆どが男性なのです。
それにはいくつかの理由がありますが、一番大きな理由は音楽を職業として捉えているからであると言えます。
これは、一般大学のお話なのですが、お隣韓国の留学生が日本人の学生が就職の事で親に電話で、相談をしているのを見て、呆れていました。大学生になって、親に決断を委ねるの??ッテ・・、それに対して、日本人の学生は、だって親は社会的経験があるのだから、相談するのは当たり前でしょう??ってね。
私の知っているアメリカの大学生は、皆、バイトをして大学に行っています。
ドイツで知り合ったアメリカの女の子・・大学生も、語学研修でドイツに来る費用は、電話の交換の仕事を貯めたものだそうです。
ヨーロッパでも、アメリカでも、大学は、専門課程なので、普通の人達は行きません。
お金をバイトして、学費を稼いでまで、勉強したい人だけが行くのです。
そこは、日本の、猫も杓子も大学に行くという・・女子大生亡国論の国とは、大学の意味が少し違います。
大学は勉強する所であって、遊ぶ所ではないのですよ。
この私も、音楽大学の入学金だけは、超高額だったので、伯母に借金をしましたが、生活費や、勉強のためのお金は、4年間、全部自分で稼ぎました。
自分で汗水垂らしてお金を稼いでいる分けなので、遊ぶお金等には、勿体無くって使えないのだよ。
だから、この歳になっても、ディズニーランドで、無駄なお金を使う暇があったら、CDを買うね!!いや、楽譜かな??
だから、大学生にもなって、学費を親が出すという日本の習慣はあまり分かりません。
という事なので、人生を親が決めるという事は、理解不能なのですよ。
それが、団塊の世代の意識です。
。
日本の音楽大学の場合は、音楽大学の女性の割合は95%近くにもなります。
つまり、女子大生の音楽大学なのです。
だから、音楽を職業として捉えようという意識や、姿勢はありません。
某有名音楽大学の院生に、卒業したら、どうするのですか?と質問して、音楽で生活をするのか?という事を暗に尋ねたら、「音楽が職業である・・という事は、初めて知りました。」と言っていたので、「音楽大学は職業学校ではないのですか?」と聞き直したら、「そういう考え方は、初耳です。」という答えが返って来ました。
では、何で、音楽学校で勉強しているのだろう・・と思ったのですが、その質問をするlevelではないよな・・と、質問する事自体を諦めてしまいました。
院生ですら、その程度なのだから、音大生は押して知るべし・・・なのですよ。
単に、結婚に至る迄のstatusに過ぎないと言っても過言ではありません。
小学生の時から死に物狂いで、脇目も振らずにlessonに通って、concoursや発表会に専念して、一流の音楽大学に入学して、海外に留学して、帰国して、2,3回もコンサートを自分でやったら夢は達成されて、後は、お見合いをして、結婚をして子育てに専念します。
その人生の何処に、proがあると思いますか?? 否、職業としての音楽があると思いますか??
せいぜい、片手間に自宅かヤマハ等で音楽教室で生徒を教えるだけが、人生でしょうね。
お見合いをして、結婚して子育てに専念をするのなら、もっと別に勉強しなければならない事が無数にあるはずだと思うのですがね。
音楽は楽しみのための趣味で良いのではないのですか??
だって、音大生の人生の結果は、それしかないのだからね。
結果がそれなら、貴重な子供時代の人生を、厳しいproの勉強で費やす事は、人生の無駄ではないでしょうかね??
音楽はブランドのバッグではない・・と思うのですがね。
音大生にこういう質問を投げかけました。
趣味のPianoを弾く人と、proの演奏家の違いは何ですか?
返って来た答えは「音楽の表現力や技術力です。」だって??
趣味の子でも、音大生より上手な子はザラなんだけどね。
ザラよ!!ザラ、ザラ!!
・・で、私が更に返して、「一般の人達が演奏を聞くとして、趣味の上手な人の演奏と、proでも下手な人だとどちらの演奏を聞くと思いますか?」と質問すると、流石に、答えに窮していたよね!!
つまり、音大生にとっては、この設定は有り得ないのだから・・ですよ。
趣味の上手い演奏を聴いた事が無いのよね。
趣味の人達は、皆演奏が、下手だと思い込んでいるのですよ。
自惚れも甚だしい!!
謙虚さの欠片もないという事だよね!!
音楽大学の95%が女性である音楽大学に勉強して来た男性陣は、女性達よりも、もっと女性化しています。
男性であるにも、関わらず、音楽で生活出来ると思っていないのです。
「芦塚先生、音楽で生活して行くのは無理ですよね。」
40年以上、音楽で・・しかも、Classicだけで、生活をして来た私に聞く事ですかネ??
私は、一体何をして、生きて来たと思っているのかね??
Pianoの教室やviolinの教室のように、自宅で出来て、設備投資も何も要らない音楽教室は、一般の音大生にとっては、何の苦労もなく、稼げる場所です。
演奏活動で、生きて行けなかったとしても、子供達を教えたり、色々なイベントに参加したりして、生活をたてる事は可能なはずです。
私の場合には、チョッと特殊で、別口の方がもっとお金を稼げるので、子供達を教えたり、イベントに参加しない方が、お金になります。
私の場合には、私の本職の方が、当然、お金が稼げるのです。
本職は、子供達の教育とは無関係で、proとしか接しません。
だから、音楽教室は、私の場合には、私の音楽教育のメトードの在り方、・・というか、教育そのものの在り方を示すための、公開の場に過ぎないのです。
芦塚音楽教室の「生い立ち」は、大学に努めていた私が大学の論文である、紀要に掲載した私の教育論文が、切っ掛けになるのです。
その論文を読んだ、当時文部省の関係の仕事をしていた知人が、大阪から東京まで、わざわざ出向いて、私に、「論文を読んだのだが、本当にその通りだとは、思うのだが、一般の人達は、その論文を読んでも、それが理想論であって、机上の空論だとしか思わないよ。」「だから、芦塚さんが実践したとしても、それは芦塚さんという教育の出来るとしか思われない。それが芦塚さんの生徒達が同じ指導が出来るのなら、それはsystemであり、curriculumと言えて、普遍性が出るので、それを実践して見せて欲しい」という説得を、実に熱っぽくされました。
教育に携わる人達は、その分野の現場に立つだけの力量が無いので、子供達の教育でお茶を濁しているのが現状なのだが、本当は、一級のtopの人達が教育の現場に立つ事が、millennium以降の日本を支えるのだよ!
と、大風呂敷を広げられて、その大ぼら吹きについつい、乗ってしまったのが、鬱の始まりであり、私の悲劇の始まりだったのです。
事で、その年に花園教室を立ち上げました。
教室を立ち上げるには、私の理論を勉強する人が必要で、それを募集したのですが、昔の私の弟子が、それをやってくれる・・ということになって、その人の専攻が音楽だったので、音楽教室になったに過ぎません。私としては、学習塾でも料理教室でも良かったのですがね。
文部省の仕事をしていた知人、本人は、とうの昔に、そういった教育問題からは逃げ出してしまったのですが、一度立ち上げた教育を途中で止める分けにも行かず、生徒達を見捨てる分けにも行かないし、その子供達が大人になった時に、「自分達が育った、この教室でそのまま働きたい」という申し出があったので、教室を会社にしてしまい、逃げるに逃げられない状況を作り出してしまいました。
発起人達は、ソソクサと逃げてしまったのに、逃げ遅れた私達が相変わらず、私財と人生を投じて、世界に類の無い、教育をやっています。
音楽教室を個人で経営する場合には、Pianoは学生の時に使って来たもので充分だし、楽譜も生徒に買わせる分けだし、何も必要な設備投資は要りません。
お店を開くには、何百万、下手すると何千万の単位の準備金が必要なのですが、音楽の場合には必要がないし、消耗品も無いので、ボロ儲けです。
しかし、私達の教室のように、個人でorchestraや室内楽をやるとなると、一般的にはそれは、不可能なのです。
だから、orchestraや室内楽は、基本は、市や県が主催して、(或いは、大手企業が、社会還元のためにやる事もあります。)それに一般の音楽の先生達が指導に行く事が通常です。
でも、それは、普通のorchestraの場合です。
そこに、教育目的や、curriculumや、研究という意味は含まれません。
あくまで、イベント達成のためのorchestraに過ぎないのです。
芦塚音楽研究所のorchestraや室内楽というgenreは、そういった、一般的な市主催のorchestraや企業主催のorchestraとは、一線を画しています。
先ず、膨大な楽譜や書籍類、古楽器類、パソコン等の機材とオディオ機器、そこらの日本の音楽大学の資料とくらべても見劣りはしません。
一般の音楽大学の図書館のように膨大なgenreの資料は持ち合わせてはいませんが、狭いbaroqueや古典派、近現代の分野に限っては、大学の資料に負けないのです。
私個人の研究なので、分野を広く広げる必要はないからです。
狭い時代に限っての研究であったとしても、それでも、資料的には膨大なものになります。
普通の家なら、2,3軒は立つかも知れません。
でも、そう言った資料や楽器類、機器類は、音楽教室の所有物ではありません。
音楽教室の稼ぎのお金で買い揃えたものではありません。
音楽教室で、そういった物を揃えるためにお金を出資する事は、法務局の認可が降りないからです。
ですから、そう言った資料や楽器類その他は、全部、私の稼ぎから出た、個人財産になります。
つまり、芦塚音楽教室は、私の個人的な趣味で運営されている教室に過ぎないのです。.
でも、私が音楽教室から莫大な金額を搾取している分けではありません。
逆に、自分のお金を注ぎ込んでいるのですよ。
音楽教室は、私に取っては、私財をはたいて経営している趣味の教室なのですよ。
教室の実入りをよくするには、勿論、生徒を増やす事なのですが、先生に負担を掛けないようにするには、先生を先ず増やす事が大切です。
しかし、多くの教室から芦塚音楽研究所を求めて来る生徒達は、教室の芦塚メトードを求めて来るのです。
芦塚音楽研究所の先生が良い先生である・・という事は、そのメトードが優れているからなので、そういった芦塚メトードを勉強しようという先生を育てる事が、教室の大きな目標なのです。
しかし、努力もしないで、音楽を楽しみながら、基礎が学習出来て、上手に成れるというような夢のような生徒を育てられる先生は、大変な努力が必要になるのです。
生徒を芸大に入れるよりも、留学させるよりも、演奏家に育てるよりも、教室の先生を育成する事の方が指導する方も、学ぶ方も難しいのです。
という事で、今現在も、牧野先生と斉藤先生以外の先生で、芦塚メトードで指導出来る先生が全く一人もいないので、教室を拡大して行く事が出来ないのが、悩みです。
教室を拡大して行く方法は、もう一つは、教室を学校法人にすれば良いのです。
この世界にも稀な、音楽教室を学校にするためには、学校法人の認可を取る必要があるのです。
私の考え方に同調する出資者が6名必要で、指導をする先生達もそれなりの人数を雇わなければなりません。
芦塚メトードで指導して、concoursに合格させたり、音楽大学に進学させたり、海外に留学させたりする事は、いとも簡単な事なのです。
しかし、芦塚メトードで指導出来る先生を育てる事は不可能です。
しかも、学校法人の条項で必要とされる人材は、芦塚メトードの教育でもっとも忌むべき存在としての人材になります。
教育制度では、そういった人材が必要なのですが、その人材が教育をダメにしている役職なのです。
それは、当然、・・言える分けはないでしょう???
よく、日本人は言います。「一緒に暮らしていれば、自然に愛情なんて湧くものよ!!」
あ〜っ、それを愛情とは言わないのよね。
日本の離婚率は二組に一組、をとうの昔に越してしまった・・という話は知っていますよね。
愛情を持って結婚しても、離婚をするのだから、愛もなく慣れ合いで結婚すればもっと悲惨な将来が待っているのは分かり切った事です。
一昨日、テレビで主婦の人が、面白い事を言っていました。
好きで結婚したのなら、チョッとした事でも許せないのだけど、どうでもよい相手と結婚した場合には、所詮、この程度の人だから、と許せるのよね〜ぇ!だそうです。
それは、余りにも可哀想な人生だとは、思わないのかね??
最初からその程度という想定の人生なら、人生は無駄だよね。
私なら、miserable!!と思ってしまうけれどね・・・???
誰でも、主婦になる事は出来ます。
でも、芦塚メトードで指導出来る先生になる事は、駱駝が針の穴を通るよりも難しいのですよ。
コンビニでバイトをする事は誰でも出来ます。
しかし、職人になる事は難しいのですよ。
私は、音楽は職業と思っています。音楽家は職人だと捉えています。
Genzmer先生もそうですが、HaydnもBachだって、自分の事を職人と思っていたのですからね。
芸術家は生活は必要ないのですよ。職人である必要もない。
しかし、その人が芸術家であるか否かを判断するのは、その本人では無く、100年後の人達なのですからね。
音楽大学では生徒も先生も、音楽を職業としては、捉えていないのですよ。
それで、音楽が職業になる分けはないのは当たり前でしょう??
だから、音楽で食べて行けませんよネ。・・なんて、妄想が起こるのです。
そんな、馬鹿げた事を言ったり、思ったりする人が居る分けが・・・
だって、音楽大学の先生も学生も、皆、そんなに馬鹿げているのですよ。
だって、教えている先生がお嬢様で一度も社会で働いた経験がない。それで、仕事としての音楽・・と言われても分かる分けはないのですよ。
でも、うちの音大は子供の教育に力を入れていて、先生が学生達に子供達の指導のlectureをしてくれるのですよ。
音楽大学の音楽教室に来る生徒は、ある程度、夢が叶うのなら、その音楽大学に入学したいと思っている父兄、音楽の勉強に対する意識が、一般の音楽を学んでいる生徒達とは全く違うのですよ。
だから、小さな子供達でも、音大の先生に厳しいlessonにも対応出来るのですよ。親と子供が泣きながらlessonに通っているのをよく目にします。
私の自宅は音大の直ぐ傍なのでね。
一般の音楽教室で同じようなlessonをしたら、一瞬で生徒達はヤメてしまいますよ。
教室の保護者の中にも、子供の頃、泣きながらPianoのlessonに通った思い出があるので、自分の子供達にはそんな、辛い思いをさせたくない・・と言っている親は多いのですよ。アハッ!
私達の教室の生徒達は、音大生のPianoの音やviolinの音が「耳に来る!!」と言って、大嫌いです。
だから、日本流の音である部活のorchestraのviolinの音も耐えられない。
公文の練習の仕方の話等の、高等な話とは別で、本能的に、神経(感性)が耐えられないのです。
しかし、人間の順応性は素晴らしいもので、音楽大学に入学して、1年も他の生徒達と一緒に音楽の勉強をしていると、耐えられなかったはずの音が、何も感じなくなって、普通になってしまいます。
でも、その時には、教室で学んできた一番大切な「美しい音を追求する」・・「音楽は美しい音から成り立つ」というconceptがいつの間にか、消えてしまって、逆に、今まで許せなかった音であったはずの、「押さえつけられた歪んだ割れた音」が良い音である・・という風に感性が代わって来るのです。
遠音の利く音が、小さな細い音に聞こえて来てしまって、傍鳴りの音が、力強い音になるのです。
そうなったら、音楽は、終わり・・・???
いやいや、日本人の普通の勝れたそこらの音楽家になるのですよ。
めでたし、めでたし・・!!!