
その一つは、verschobene Takt(推移節奏)と言われる聞き慣れない音楽用語なのですが、要するに拍が半拍前にズレているからrhythmが取れないのです。(1,2,3,4と声を出しながらこのpassageを聴いて見ればその難しさが分かります。)
下の譜面に訂正して書き直したrhythm・・・、これが本来のrhythmで、このように3拍目にphraseの頭が来れば、極めて簡単に演奏する事は出来るのですがネ。
そこがVivaldiのお洒落ですよ。
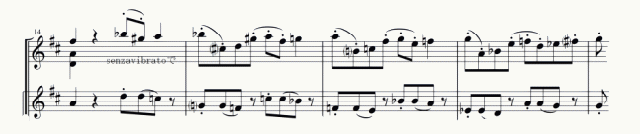
もう一つの難しさは、和声学でQuerstand(対斜)と呼ばれる禁則を、ワザと使用して音を取れなくしているからなのです。
こういった曲集は、Vivaldiの可愛い生徒達の中でも、上級のclassの生徒達が演奏するための曲です。
より、音感を正確にするためには、その逆、音感を如何に狂わせるかというthemaで曲を作れば良いのです。
チョッとした悪戯です。
きらきら星を対斜だけで作って見ました。

パソコンにはplug-inという機能があって、そのソフトが入っていないと、音声や映像が再生されないようです。
この「対斜によるきらきら星」は、netから直接開くと音声が聴けるのですが、Facebookのlinkから開くと、「対応出来るplug-inが入っていません。」というmessageが表示されて、音声が再生されません。これは、「開いているパソコンによって」、なので、私の設定ではどうにもなりません。もし、音声が表示されない場合には、netからダイレクトに開いて見てください。再生出来る場合には、この文章は無視してください。
melodieはハ長調のままで、何の変更もしていないのですが、歌うのが超難しいとは思いませんか??
伴奏の和音が変わるだけで、melodieはこんなにも変化してしまうのです。
その対斜を、使ってVivaldiがこの曲で書いたpassageです。(勿論、他のpassageには、二度と対斜は出て来ません。)
点線で繋いである音符が対斜になる音符です。
和声学の原則では、同音が#や♭で変更される場合には、必ず同じ声部の音で変更されなければなりません。
こういう風に異声部間で音符を変更する事を対斜と言い、和声学の禁則とされます。(原語ではQuerstandと言います。)
このように、声部を違えて音を変化させると、音程が不正確になって、必要以上に難しくなってしまうからです。
もっとも、これを演奏が簡単になるように手直しする事は、作曲法としては、とても簡単です。
Vivaldiが簡単になるように作曲しなかったのは、Vivaldiが、可愛い生徒達のためにワザと難しく書いたのであって、「いじめ」ではなく、音感のトレーニングの方法の一つなのです。
私の場合の子供のためのPianotrioの作曲法は、曲の入りが難しく書かれているのですが、それと同じ理由です。