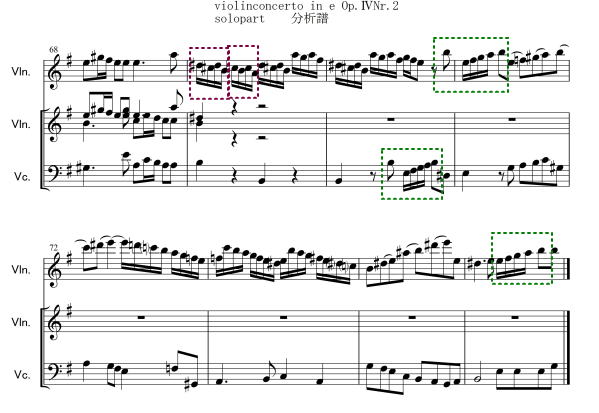

参考までに:
https://www.youtube.com/watch?v=3rxTs7kR__A
You Tubeで模範になるような演奏を探してみたのですが、残念ながらこれという演奏はありませんでした。
もう一つの演奏なんかは、早いだけで、演奏も乱暴で、Vivaldi先生が聞いたら、多分怒り出すのではないか??という演奏でしたが、そういった早いだけの乱暴な演奏が、今は主流のような気がします。
Vivaldiのbaroqueversionの演奏と思わなければ良いのでしょうがね。
次の演奏は、tempo感は、早すぎないで、演奏もまあまあ、良いのですが、solisteがfigurationを演奏していると、後半になると、どんどんtempoが早くなって、basso continuoを置いてけぼりにしていたりします。
早く演奏したければ、figurationのfigur(音型)を変えて演奏すれば良いのですよ。
tempoは変えてはいけません。
もし変えるのなら、ripienosoloに変わった所で、はっきりと変えなければなりません。
だんだん、tempo-upして、早くして行くのは当時の慣習としては、邪道であり、非常に良くないのですよ。
参考までに:
https://www.youtube.com/watch?v=Tqbv9cPyBfs&index=2&list=RD3rxTs7kR__A
eccentric(エキセントリック=奇妙な)演奏ということなのか??
でも、近頃の、baroqueversionとされる演奏では、こういった演奏の方が主流になっているようです。
ブルース、ウィルスおじさん(Stefano Montanari)の演奏の影響でしょうかね??
eccentricと言えば、日本人のproの演奏家達が抱くVivaldiに対しての嫌悪感のimageは、日本の世界を席巻した大手のviolin教室のVivaldiの演奏のstyle、ギシ、ギシと弓を擦らせてeccentricに演奏する・・・というVivaldiへのトラウマ的な汚い音のimageなのです。
そのために「violinを習わせるのは、考えてしまう。」という、ご相談をよく受けた事もあります。
またそういったVivaldの音楽に対する偏見があって、私が音楽教室を開設した当時、私のmethodeの中のensembleーprogramの一つである、orchestraーcurriculumで、Vivaldiのprogramを導入しようとしたのですが、当時、私の音楽教室を開設するために手伝って貰っていたproの先生達から、Vivaldiーprogramに対して、猛反対と猛スカンを食ってしまいました。
「Vivaldiは嫌だ!」という先生に、半ば強引に、当時のbaroque音楽演奏の定番であったI Musiciのa mollを、聞いて貰ったのですが、こんにちでは、普通の演奏なのですが、先生達にとっては、カルチャー・ショックだったそうで、「こう言う曲だったの?」と、驚いていました。
しかし、長年の身に付いた演奏のstyleは、変わらなくって、指導の時には、やはり、子供の頃、習ったそのままの日本流のギシギシとした音のimageが抜けなくて、私の弓の使い方の指導法には、とても苦労していたようですがね。
ギシギシというimageは、子供は弾き止めが出来ないので、弓にプレッシャーを掛けて(弓で弦を押して)弓を止めて、弾き始める時にも、力を入れたままに弾き始めるから、ギシギシとしてしまうのです。
detacheと引き止めの、間違えた解釈と方法論から引き出された誤りです。
日本の超有名な大手の音楽教室では、楽譜の「譜読み」の仕方は基本的に指導しません。
それは、「子供達は楽譜を読めない」という前提があるからです。
という事で、譜読みは必要のないものとして、口移しの音楽教育で指導されます。
勿論、色々な音楽教室では、五線紙上やPianoを指導する時に、その楽譜上で楽譜の音符(ドレミ)の読み方を指導するのですが、困った事には、一生懸命、楽譜を見ながら生徒に指導しても、それで、楽譜が読めるようになる事は、殆どありません。しかし、教室では、初見の練習があるように、殆どintempo(その曲の本来の演奏の速度)で初見の合わせをしたりします。
そのために、教室に入会した初心者の生徒達には、音符カードを使用して、音符の読み方のトレーニングをします。
教室独自のmethodeで、芦塚メトードと言いますが、ある先生が、私達の教室では、「楽譜の読み方を生徒達に、指導するのに、市販の音符カードを使うから、芦塚メトードではない。」と言っていました。
しかし、それは、その先生が、curriculumとは何か??とか、methodeとは何か?・・・という事を、全くご存知ないからです。
音符カードも教室で作れば、教室独自のmethodeという事になって、それはそれで良いのでしょうが、私の方針では、極力、無駄は省く・・・「市販のもので、間に合うものは、市販のもので間に合わせる」・・・という事が、芦塚メトードの「時短の法則」なのですよ。
私達の教室で、「市販の音符カードを使用して、生徒達が譜読みが出来るようになった」・・・からと言っても、だから「同じ音符カードで指導しても、譜面が読めるようには決してならない」・・・のですよ。
つまり、譜読みに、methodeを持って指導しない限り、生徒達が譜読みに強くなる訳はないのですよ。
音符カードはmethodeではないのです。そこで使用するmethodeがソフトであり、そのソフトの使用法がmanualなのですよ。
教室の子供達が、音楽を楽しみながら勉強しているのを見て、「子供は子供達同士で一緒に何かをやれば、好きになるのよ!」と、言っていた先生もいましたが、その先生が練習を嫌がって余りしない生徒達に、生徒同士でensembleをさせたら、生徒達は、友達と練習するのを嫌がって、教室をやめてしまったそうです。アハッ!
ensembleの指導は結構難しいのですよ。「やらせりゃいい」 、というcurriculumは、原則ないのですよ。
同様なお話は、講師希望者の見学(聴講)にもあります。
講師の希望者は、教室で採用される前に、教室の事を良く知って貰うために、先生達の見学をさせます。
その時に見学者が一応に言う事は、「普通にlessonしているだけですよね。」という感想です。
これは、ひょっとしたら、教室の生徒達に見学させても、同じ事を言うのかな??
試して見たいものですよね。
余談はさて於いて、「普通にlessonをしている」・・という事なら、同じようにlessonが出来るはずなので、lessonをさせて見ると、これが全く出来ないのだよね。
最初の最初から、一つも上手く行かないのですよ。
で、自分は同じようにlessonしているつもりなのに、何が違うかが分からない!!
・・・どうして、上手く行かないのか分からないのですよ。
それは、何も分かっていない、という事なのですがね。
それでも、その先生が自宅で教えていたり、他の音楽教室で教えていると、上手く行くのですよ。
どうして???
答えは簡単です。
その先生の指導力があるのか、ないのか??・・・その、比較する対象がないからなのです。
それと、「近場の先生で間に合わせる」という意識と、「音楽で少しでも、何かを得て欲しい。」という親では、教室に対する望み(価値観)が全く違うからです。
教室では、最初から親の「先生に対する価値付け」が違うからなのです。
私達の教室を訪れて来る親の方達には、教室に対して、子供を 「〜にして、欲しい」という願望があります。
「周りの生徒(お友達)がお稽古事をやっているから、自分の子供も、人並みに・・何かを学ばせなければ・・・」という親達の場合には、そのお稽古事が、音楽である必要もないのですよ。
それは単なる子育ての、statusに過ぎないのですからね。
「音楽を学ばせたい。」という親と「お稽古事なら、別に何でも良い。特に音楽である必要もない。」という親では、教室の先生に対して求めるものが全く違うのは、明らかですよね。
ですから、自分の子供に、「音楽を学ばせたい。」と思っている親が、先生が自分の子供に対して、指導する内容が、その希望に達していなかったら、その先生に対して、子供も親も批判的になるのは、当たり前の事です。
他所の教室の優れた先生よりも、教室の先生の方が、良い・・という親が求めるものは、当然決まってきます。
普通に指導出来る・・というのは、Pianoの指導、violinの指導だけではなく、子供の自宅での練習の相談に乗れるか?という事であったり、譜読みをどうやってするのか?という相談もあります。
「将来、音楽家になりたい」・・という相談かもしれません。
そういった質問や相談にも応えられるのか??
それも含めての指導者の力量です。
譜読み一つをとっても、普通に音符カードで指導して、音符カードが読めるようになったとしても、それで楽譜が読めるようになった分けではありません。
Sait-Saёnsは、「普通に本を読むようにscoreを読めるようにならなければならない。」と言っていました。
そのSait-Saёnsの書いた本を読んだのは、ちょうど音楽を始めた頃の高校生の頃です。
音楽を始めたばかりの頃の私にとっては、絶対音感もないし、譜面を読む事は、まあまあ、周りの人よりも強かったけれど、Sait-Saёnsのその言葉は、「そんな事、可能なの??」という信じられないぐらいに、とてもハードルの高い要求でした。
しかし、大作曲家が嘘を自分の本に書く分けはありません。
ましてや、オーバーに自己の能力を過大に評価する事も有り得ないのです。
だから、当時の友達にPianoで、ランダムに音を弾いて貰って、「音当て」をしたり、和音を弾いて貰って、その和音を当てたり、と、自分なりにsolfegeの訓練をしました。
その時の努力がそのまま、その頃指導していた受験生に、当時一番難しかった芸大の聴音の課題を、全く一度も聴音をやった事のない生徒達に半年、一年で、完璧に取れるようにするmethodeを作って、指導して、成果を上げて行きました。
私自身も、音楽大学に入学した頃には、下宿ではレコードを譜面を見ながら何度も聞いて、orchestra等の楽器の音色を覚えて、学校の授業と授業の間の時間には、楽譜を見ながら音を思い出しながら、楽譜を覚える(音符を映像として覚える)という努力を大学時代の4年間続けました。
本当ならば、イヤフォンで音楽を聞きながら、楽譜を見て行けば良いのでしょうが、当時は、未だ、ウォークマンのような、スマホのような、外に外出している時も、音楽を聞ける媒体は全くなかったからね。
未だ、カセットレコーダーも無くて、オープン・リールの時代だったからですよ。
でもその努力は確実に報われて、30歳になった頃には、楽譜屋で新しい曲を探す時に、VivaldiからBrahmsぐらいまでのorchestraの曲ならば、レコード(CD)を聴くように、scoreを見るだけで、音が聞こえて来るようには、なりました。
流石に、未だ、Stravinskyのような、大orchestraでは、技術が足りないのですが、新曲でもscoreを見ているだけで、音が聴こえて来るのですよ。
ただ、迷惑なのは、ヤマハのような大手の楽譜屋さんの楽譜売り場で、BGMが流れている事です。
素晴らしい曲に巡りあった時には、BGMもそれ程邪魔にならないのですが、気の乗らない曲を探している時には、集中しないと、音が聞こえなくなってしまうのですよ。疲れるのよね!!
周りの人達は気にならないようなので、音は聴こえていないのかな??
Sait-Saёns先生のadviceは、私に、「楽譜を読む」という以外にも、メリットをもたらしてくれました。
この20年ぐらいは、作曲をする時にも、編曲をする時にも、Pianoを弾く事は全くなくなりました。
おかげで、自宅で五線紙がいらなくなってしまいました。
直接、finaleにパソコンで入力するからです。
教室のlessonでも、何時も先生達に、「生徒をlessonする時の、楽譜は必ず事前に楽譜を私に渡してくれるように・・!」と言っているのですが、時々は、準備が遅れてlessonの場所で楽譜を見せられる事がよくあります。
幾ら私でも、violinの教則本の曲や、小品の曲迄は知らない曲も多いのでね。
それでも、その場で、楽譜を渡されて、ホンの2,3分、眺めていると、その曲のpointが見えて来るのですよ。
これが、餅屋の技術なのかな??
全く、一度も聴音をやった事のない学生は、当然、絶対音感等はありません。
でも、1年間ぐらいで、目的の音楽大学に入学させなければ、なりません。
「出来ない!」ままでは、音楽大学に入学する事は出来ないからです。
そこに、芦塚メトードのcurriculumが必要になってくるのです。
それは、音楽大学を受験する生徒だけではなく、一般の教室の生徒に対してでも、同じなのです。
私は、Pianoのlessonを普通に生徒にlessonをします。
或る生徒を、始めてlessonした時に、抜き出しのlessonの所で、「ここから弾いて・・!」とPianoを弾いてsuggestしたら、「この生徒はそれは出来ない!」と、担当の先生に言われてしまったので、その時間のlessonはその方法論だけでlessonしました。
勿論、不可能と思われた、その抜き出しの方法も、最後には、普通に出来るようになったのですよ。
「難しいから出来ない」「子供だから出来る分けがない!」という思い込みだったのですよ。
その後も、そのやり方で他の生徒達も指導していますが、はやり、どうしてもその先生は、「その生徒は、そのやり方は指導していないので出来ない!」が始まります。
という事よりも、その先生自身がそのやり方が苦手なのだと思いますがね。
抜き出しの練習の箇所のお話ですが、それは、同時に暗譜のlessonにもなるし、同様のpassageが調が違って色々な小節にあるので、絶対音感の訓練にもなっているし、勿論、当然、譜読みの訓練にもなっているのですよ。
見学している人達がどこまで、私の時短methodeの絡め合わせのtechnicを見れるのかな??
という事で、殆どの一般の音楽教室の指導者の人達は、幾ら音符の読み方を熱心に指導しても、生徒達は音符を読めるようにはならないのですよ。
しかし、音楽大学に進学したり、proの音楽家になるのでなければ、(popularで趣味でやるのなら)譜読みの難しいmethodeは必要ない。・・・というか、指導出来る先生を雇う事が出来ないし、必要もない。
という事で、大手の音楽教室では、最初から譜読みは必要ない・・という前提で生徒達を指導しています。
そのために、大手の音楽教室で勉強した人達が、音楽に興味を持って、音楽大学に進学しようとしても、一人では「譜面が読めない」、「楽典も勉強した事はない」、それ所か、Pianoのtouchの仕方も習っていない。
姿勢も、・・・も、なんの基本も出来ていない・・というのでは、音楽大学に進学する事も、指導者になる事も、無理難題になってしまいます。
「Pianoがある程度、弾ければ、音楽教室の指導者には、なれるのではないの??」
確かに、戦後のある時代には、そういった時代もありました。
戦後のドサクサでは、教員免状を持っていなくても、小学校の先生になれた時代があったのですよ。
そういった基礎の教育を受けた事のない先生達が、子供を指導して、校長先生になって・・・、でも、教育委員会では、そういった先生を首を切る権限がなかったのですよ。
当時、教育長の言葉です。
「もう少し時間が経つと、そういった時代の先生達が定年を迎えるから、そうしたら教育改革が出来るので、もう少し待っていてください。」
そんなに待てるかよ??!!
学校教育でも、推して知るべし、で、その程度なのだから、音楽の社会は、もっと悲劇的です。
日本では、不思議な事に、教育音楽(所謂、音楽教室の音楽)と学校教育の音楽と、音楽大学の音楽と、proの音楽では、全く属している社会が違います。
学校教育用の合唱の発声法というのがあります。
しかし、そこで、幾ら、発声法を学んだとしても、それは音楽大学の発声法とは全く別物です。
学校教育用の発声法とは、そこだけの社会で成り立っている発声法なのです。
・・・という事を、小学校の先生達を集めて講演している時に、若い芸美卒業の先生から、「先生、学校の絵の世界も全く同じなのですよ。」と言われました。
学校とは、どうやらそういった、独立、完結型の世界らしいですね。
音楽教室の場合は、もっと、悲惨です。クライアントは、一般の子供達であり、親なのです。
雪の女王の曲が弾ければ良くて、Lisztの愛の夢が弾きたい分けではありません。
しかし、指導者の先生は音楽大学で厳しいlessonに堪えて来ている。
厳しいlessonに堪えて、生き残って行く事が、その先生のstatusなのですよ。
でも、クライアントの子供達や、親は流行の曲が弾けるようになればそれで良いのです。
そこには、致命的とも言える程の意識の落差があります。
クライアントが一般家庭である音楽教室と、音楽大学の世界は、全く違う世界なのでね。
proの音楽家と言っても、それこそ、千差万別です。
popularの音楽に対するproの演奏家もいます。
お金を稼ぐのが目的なら、20代で家が建つぐらいに稼げるpopularの演奏家の方が良いでしょう。
人が寝静まった時間に働くスタジオ・ミュージシャンの仕事もあります。
夜型の人にはお薦めの仕事です。勿論、お金にもなるしね。
昼間は遊べるしね。
クラシックの音楽でも、結構、演奏する場所には困りません。
それは、その人の企画力と、営業力に関する事なので、その人の音楽の力量とは無関係のお話なのですよ。
violinの初心者が出すギシギシした音は、指導者が、子供達にviolinを指導する時に、violinの美しい音を教えないという、そこに尽きます。
美しい音に対してのsuggestionを、violinを持ったその日に子供に与えると、子供達は、二度とそういったギシギシした音を出す事はありません。
芦塚メトードでは、初歩の初歩の段階から、弓の弾き始めと、弾いている部分の所と、弾き終わりの部分を、三つに分けて指導しています。
それぞれの部分で、奏き分けが出来るように指導します。
教室に初めて来られたproの人が、「violinは嫌いじゃないのだけど、初歩のviolinだけは聞くに堪えないので、どうしよう??・・と思っていたのだけど、この教室の子供達はそんな嫌な音は出さないのだけど、それは、どうしてかしら?」と質問してきました。
「力を込めて弓で弦を擦ると、こんな嫌なギシギシとした音が出るのだけど、力を抜いてそうと弾くとこんなに綺麗な音が出るんだよ!?」と最初に教えると、二度と変な音は出さないのだよ。・・と、説明したら、妙に納得していました。
分かったのかな???
本当はそんなに簡単に説明が出来るものではないのですがね。

trillの奏法は、常日頃、私が口を酸っぱくして言っているのですが、日本人には、どうも受け入れられないようですね。
装飾音には全て音楽表現の意味があります。
trillには「強拍を表すtrill」と、「弱拍を表すtrill」があります。
その奏法はしっかりと奏き分けなければなりません。