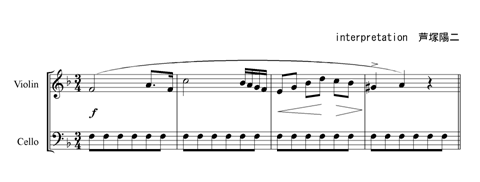
実際に、この楽譜をピアノで弾いてみると、左手の動きが何ともたどたどしい。つまり、ピアノにとっては同音連打とはそんなに簡単な技術ではないのである。それを如何にも簡単に演奏出来るように、ピアニスティックに編曲したのがAlberti氏である。そして、あっという間にその方法は世界の作曲家達に使われるようになった。
もし先程のBeyerの103番の原曲が弦楽四重奏だったとしたら、たぶん次のように書かれる。
譜例:
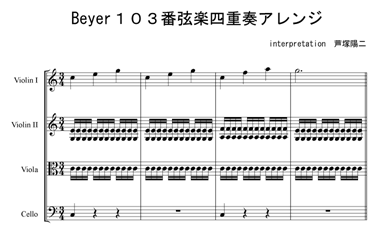
violinⅡとviolaはleggieroで軽いstaccato(もしくはflying staccato)のような独特の弾き方で奏する。とても、軽やかな感じになる。
この場合、violinⅠのslurは、Beyerに書かれているslurは(phraseのslurなので、)violin用には使用されない。violinの場合はあくまで、bowslurが優先するからである。violinⅠのbowslurは1小節単位か、2小節をone phraseで奏するのが普通であろう。
と言うことで、103番の場合にも、右手のmelodieがtempoを決める。dolceでゆっくりと歌ったとしても4小節が一単位(one phrase)なので、それが一息(non breath)で歌えるtempoでなければならない。
[Alberti-bassの奏法]
また、ピアノでこの曲を演奏する場合、左手もAlberti-bassであるので、弦楽器のtremoloか刻みのように、非常に軽やかにleggieroで弾かなければならない。
その場合のAlberti-bassのleggieroの奏法は、まず軸になる指を決めなければならない。
この音型の場合には、親指が軸の指になる。
軸指は力を完全に抜いた状態で、動かさない。
指の重みで少し鍵盤が沈む程度でよい。そして、5の指と3の指はleggieroのstaccatotouchで力を抜いたまま、指先だけで弾き上げるように、軽く弾く。
練習の初めでは親指を弾かないで、鍵盤上に置いておくようにするとよい。
軽く弾いている間に、軸の反動で音が出始める。あえて、音を出そうと思わなくとも、自然に音が出てくる事がアルベルティ・バスのコツである。
そういう風にして出てきた音は、右手のmelodieを邪魔しない軽やかな響きがするはずである。もしビッコを惹いたり、ガタガタと乱暴な音になったりするときには、どこかに不自然な力が残っていると言うことである。
譜例:
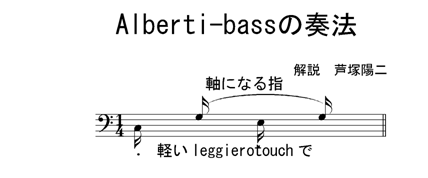
[Beyerのgrade]
これはBeyermanualを読めば理解できるはずであるので、ここであえて書く必要はないのだが、Beyerの指導に行き詰まる原因は、Beyerがそれぞれをそのgradeの中のグループとして作曲されているので、その段階の技術やtempo感や拍子感、を確実にマスターしていかなければ次のstepには移ることができないはずなのである。[7]
日本では、色々な出版社から沢山のBeyer教則本が出版されている。可愛い絵がふんだんに盛り込まれていて、絵本としてもとても楽しい。と言う事で、私達の教室でも小さな生徒に対しては、そういったBeyerの楽譜を使用している。しかし、Beyerの原典版で指定されている課題曲の配列をBeyerの指導上の意図とは無関係に単なる譜面の易しさで並べ替えると、指導上のgradeと曲の互換性がないままになってしまう。それは校訂者がBeyerの指導上のmethodeを知らないための無知ゆえのミスである。それは、音楽の指導者、教育者として許せない無知である。
[Beyerのグルーピング]
Vorschuleの片手練習は教室ではめったに子供にはやらせない。
(私自身は長い人生の中で、いまだに、実際に生徒に練習させた事はない!)
それこそ、私の「キリンさんの教則本」の方が、音楽的で楽しいし、拍子感を育てたり、音感やtouchの注意などにも使用できて良いからである。
同じ「ドの音」であったとしても、「楽しいド」、「悲しいド」、「うれしいド」、「優しいド」等、色々な音色があるはずである。
「ドの音」一つの音の出し方でも、子供に音楽性を身に付けさせる事が出来る。
そういった意味で、「キリンさんの教則本」を使用していただけるとありがたい。
同様にBeyer教則本も1番から11番までは連弾になっていて、先生の持って行き様では、結構音楽的に指導する事が出来る。また、その一曲一曲に個性を持たせたMetronomのtempoを設定する事が可能であり、指導上とても効果的である。
また、Beyer教則本ではピアノのフレーズ感を育成するのに、歌わせて指導をする事を基本としている。しかし、Beyerの基本のフレーズは4小節単位である。小学生低学年の子供達にとっては、Beyerの4小節のフレーズはとても長く、息が持たない。小学校の中学年生でも、まだ4小節を一息に歌う事は困難なケースが多い。だから、私の場合にはカンニングブレストと、本当の息継ぎのブレスを最初から指導する。(カンニング・ブレスは(∨)と、カッコつきで表わす。)
また全てのBeyerの曲が歌いながら弾けるわけではなく、特に左手のパートはBeyerの後半の課題になると、(アルベルティ・バスになるので)歌えなくなってしまう。
だから50番台迄によく左手を歌う練習をしておかなければ、左手を楽に歌えるようにするための教材がなくなってしまう。
1番から2番までが第一グループであり、3番から11番迄で第一段階の連弾を終了する。
12番からが本格的Beyermethodeの開始になる。
それまでの教材は、私達はvorschuleと呼んでいる。
12番から、31番まではドからソの鍵盤に対してのshiftである。基本の型である。Shift上の指の独立の勉強である。16番は反進行と斜進行の切り替えの練習である。複音楽的な要素で両手の対等な進行がとても大切な要素となる。17番はlegatoのトレモロである。滑らかに右手のmelodieを邪魔しないように、さわやかに弾かれなければならない。決して、力いっぱい元気にガタガタと弾かせてはならない。18番は左手の3度の和音が小学生以下の子供にとっては困難である。(事前にそれを理解しておかなければならない。)この段階では手は動かないので、打鍵の位置や手の型、姿勢等をこの段階でマスターしておく事はとても有意義である。特に掌の中に卵が入るようにと言う意識付けBeyerの64番までに終わらせておかないと、次のstepに入るとshiftの位置が移動するし、その次のstepでは指のくぐり(scale)が入ってくるので手の型(掌)が潰れやすくなってしまう。(この段階では、逆に一度付いた手の型が、scaleの指のくぐりのために、潰れてしまって、壊れていくのを防ぐので必死になる方が多いのだ。)
32番からは手の基本の型は、鍵盤上の何処の位置に移動しても型は変わらないと言う事を理解させるための課題である。
その課題も、44番、45番でBeyerの第一gradeは終了する。
46番からは6度の型である。6度の型は基本の型の延長線上になければならない。
1の指をshiftして、残りの指を移動したものと、5から2までの指をshiftして1の指だけを移動するパターンで練習する。
48番では初めての付点4分音符が出てくる。
51番53番54番では、octaveではない、position移動による(手の形を崩さないままの)octave移動が出てくる。(一般に言われている手を広げてとるoctaveはBeyerには出てこない。7度の型が出来ない子供が正しいoctaveを弾けるわけがないからだ。乙女の祈りのように手を広げてとるoctaveは型ではないので、初歩の段階の教則本には出てこないのだ。)
だから、指を伸ばしてoctaveを取らさせては、絶対にいけない!!!
52番は初めての6拍子である。59番の3拍子との弾き分け、或いは52番を3拍子で弾いて、59番を6拍子で弾くとかそういった弾き分けの違いを指導する事。(まず先生が弾いて聞かせる事)私の場合には、3拍子の時に、むしろ1小節毎にワン、ツウ、ワン、ツウと弾く。6拍子の場合には、2小節でワン、ツウと弾く。人は自分が弾いているよりも、小さく取ってしまうからだ。その説明はBeethovenの第9シンフォニーやピアノ・ソナタの悲愴の1楽章の時にも、歴史に名を残す大作曲家はよくそう演奏している。(何故、そのように演奏したと言う事が分るのかというと、楽譜にそのように書かれているからだ。)
58には初めての膨らまし、crescendo、decrescendoが出てくる。
59番では、中間部で複雑な(この段階では)フレーズを表現させる。
それが課題である。
60番からは、速いvorbereitの練習である。
61番は高い音の譜読みの予備練習とスキップの予備練習
62番は両手のすばやいvorbereitと、左手のleggiero(指の独立の課題)この曲が弾けなければブルグミュラーのアラベスクが弾ける事はありえない。
vorbereitの練習を一人でやるにはMetronomが必要なので、この段階までに一人でMetronomが使用出来るようになっている事の方が望ましい。
65番からは、次のstepである。
scaleが入ってくる。打鍵の位置や手の型が再び確認される箇所でもある。
例: 打鍵の位置 白鍵のみの打鍵の位置 と 黒鍵を含んだ打鍵の位置


[3度の練習について]
68番、69番、70番、71番、72番
正しく、力を抜いて速度でtouchをしている子供にとっては、68番以降の3度(特に左手の3度)を滑らかに自然に弾く事は至難の業である。それは、子供の基準となる手の重さや、力を抜いて脱力した状態の指先の力(重さ)がピアノを弾くのには充分ではないからなのである。ピアノはヴァイオリンと違って、子供用の分数のサイズがない。また、ヴァイオリンはサイズが縮小すると力も比例するので問題はないが、ピアノの場合にはサイズが縮小したからと言って、touchに必要な力が減るわけではない。[8]
73番(vorbereit、7度の型、半音階、同音連打、臨時記号)これだけの課題が一曲の中に!!
74番指回しの練習曲です。Moderatoの美しいmelodieは右手で左手はかなり速い速度で弾かなければならない。(同音連打)トリオーレンのスキップ練習基本の3パターンの練習、melodieが右手、左手に変わる。同じmelodieがフォルテとピアノで弾き分けられる。等!
75番左手の231の指使い
76番3-5を広げる。
78番軽快な6拍子と左手の5の指のshift(延ばし)の練習、2小節単位のフォルテとdolceのコントラスト(弾き分け)同音連打
[80番から83番へ]
80番、81番はかなり難しい。
ワルツではなく、もっと素朴なlandler(レントラー)です。左手はleggieroの3拍子(ワルツはBeyer以降の時代です。)80番は前打音と膨らましながらの半音階2octaveの飛ばし。
81番の課題は同音連打と半音階、auftaktによるverschobene Takt(推移節奏)と中間部の1拍目からのrhythmの、すばやいリズムの切り替え。
82番もmelodieはauftaktで始まるのに、左手は拍頭からのrhythmで、verschobene Taktな感じがします。しかも、指を潜らせながらのoctaveのすばやい移動という難しい課題です。
この3曲が完全にintempoで間違いなく弾ければ、ここまでのBeyerの課題は合格である。
もし弾けなければ、前の指導上の問題点があると言う事だ。
実は、ピアノを学び始めた子供達の90%近い人達が、この3曲に引っかかってしまって、ピアノを挫折してしまう難関の曲なのです。
私は生徒がこの3曲を1月かかっても終了させる事が出来なければ、保留合格にして、先に進みます。そしてBeyer教則本を終了した時点で、保留合格の曲だけをすべてやり直させます。その頃は難しかったBeyerの難曲ももう弾ける様になっているはずですから。
これ以降の曲はBeyerの総まとめの曲で、曲としての表現や、速度と指の粒粒の滑らかさが課題です。
それらがちゃんと弾きこなせていれば、問題なく、次の課題であるブルグミュラーやCzerny30番、Czerny小さな手のための25の練習曲等々に進む事ができます。
88番89番90番91番、93番、98番100番102番104番等にも、それなりの課題が含まれているのだが、あまりにも長文の論文になってしまうし、殆どがBeyer研究とダブってくるので、簡単に説明するだけにしておく。
[Slurについて]
Slurにはphraseを表すためのslurと、articulationを表すための、(所謂bow slurと呼ばれるもの)がある。
Beyer教則本の場合には、88番までは音楽表現の基本であるphraseを表すslurのみが使用されているが、89番以降はPianoの演奏技術の表現を表すための、articulation slurが数多く使用されている。
譜例:
89番歌詞
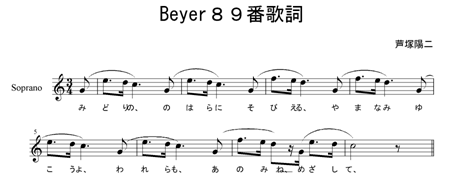
90番の抜きを表すためのslur、正しい同音連打の弾き方、繰り返し記号の後に出てくるホルン五度等、曲は比較的に簡単なのにそれに用いられているテクニックは相当なものである。それらを正しく弾き表すには、それまでの技術を相当しっかりと身につけておかなければならない。
93番のAgogik(緩急法、フレーズ法)を表すslur、98番ではverschobene
Takt(推移節奏)と手首の抜きのstaccato等々、1790年代になってやっとforte-pianoがCembaloに取って代わるようになって、次にforte-pianoから、やっと今日のdoubleactionのPianoが開発されようとしていた当時に、まだまだ革新的であったdoubleactionのPianoの色々な奏法の技術を、これだけ簡単な初心者用の教材によくもまあ色々な盛り込んだものである。
Beyerの、当時は最先端であったPiano技術への知識と、それをPianoを学ぶものに指導しようとする意気込みが、ひしひしと感じられる。
「Beyer教則本と暗譜について」
A:練習番号付け
芦塚メトードでは色々な勉強が複雑に絡み合って構成されている。その顕著なものが練習番号付けのmethodeである。私はよくorchestraの指導の時に、練習番号付けをオケに参加している生徒に宿題に出す事がある。「そんな事が出来るのか?皆、ばらばらに付けてくるので、役に立たないのでは?」
これが違うんだな~!?全員が同じ回答になるんだよ。
Sonate形式を参考に説明すると、全てのsonateはsonate形式である以上、提示部、展開部、再現部の三部に構成されている。(長大な曲では、その後に、Codaの展開部が来るかもしれない。)
いずれにしても、それを練習番号付けすると、A,B、C(=A)、となる。勿論、Coda部を入れるとDがプラスされる。
Aの提示部は第一主題の提示と展開、第二主題の提示と展開、まとめの部分で構成される。それが次の下の階層である。本来はaとすべきなのだが、一々「スモール・エー、スモール・ビー・・・」なんて言えないから、私は[あ]としている。次に第一主題の中を更に、節に分類していく。それは数字1,2であり、更に細かく分類されたものは丸付き数字①、②で表す。
これは構造分析なので、どの生徒が番号をつけても、(最初の階層で使用する文字を定めておくと全員同じ回答になってしまうのだ。)
だから、私がオケ練習で生徒の前で練習番号付けをする必要が無くなり、練習時間や余分な(不要な)エネルギーの節約にもなる。これも芦塚メトードの時短の法則の一環である。
「・・・で、これが暗譜のmethodeと何の関係があるのか?」って??
例えば、Chopinのワルツやスケルツオはその殆どが、A,B,A、Codaの構造をとっている。しかも、Chopinの場合にはAの中も、さらにa,b,aの構造をとっていることが多いのだ。
と言う事で、生徒に8Page以上もある長大な曲を発表会の課題に出して、生徒が「先生、とても一月じゃ間に合わないよ!」と言っても、「だって、このPageとこのPageは同じで、このPageとこのPageも同じなら、正味3Page練習すればよいんだよ。」と説明すると、「何だ!3Pageか!?」と言う事になる。そしてちゃんと弾けるんだよね。これが、・・・・!
B:暗譜のmethode
「100里の道も一歩から」と言う事で、その構造分析や暗譜のmethodeもPianoを学び始めたBeyer教則本の1曲目から始まる。
教室にやってきた先生に「Beyer教則本を構造分析して、構造分析による暗譜を生徒に指導してください。」と実際の譜例をあげて説明してお願いした。