![]()
こういった色々な論文の中で、生徒や父兄の話を実例を入れて、ホームページにアップしたり、冊子として配ったりすると、必ず「この話に書かれている事は、私のことですよね!」と訊ねて来る人がいる。
父兄は自分の家庭が特殊であり、特別であると思い込んでいる。
「私達のような家庭の考え方の例は、先生達はご存知はないと思いますが・・」とか、さも自分達の家庭が特殊な家庭であるかのように話してくる人達がおおいのだよ。
そういった父兄に、昔生徒、父兄達に配った冊子を見せて、「この論文は20年前、30年前に、発表会で配られた論文ですよ!」というと、驚いた表情をする。
その驚きは、私にとっても全く同じ事で、全く同じ話を、10年間、20年間、何度となく繰り返し、話さなければならない・・・ということは、ある意味、私に取っても、苦痛でもある。
親にとっては、子供の教育は初めての経験で、その年齢によって起こる問題は、初めての経験で、未知の悩みかもしれないが、私達、教育者にとっては、10年、20年と、毎年、毎回、繰り返される、同じadviceで、誰も私のadviceを聞こうとしないのも、毎年同じ事で、それは、親と子供に取っての挫折ではなく、私達に取っても、毎回、毎年の指導の挫折と、教育に対する絶望の繰り返しに過ぎないのであるよ。
ヨージーの法則
「教育とは、挫折の代名詞でもある。」
2014/10/04 (土) 17:25
摩訶不思議な日本人の教育
「夢は夢に過ぎない」・・・、「夢は現実とは違う。」
「中学生、高校生になったら、夢は夢なのだから、そろそろ、一生懸命、学業に専念しなければならない。」
それが、普通でしょう??
夢は現実と違って、夢は夢に過ぎないのだから・・・といって、更に夢のまた夢に過ぎない、絶対にどう頑張っても、有名大学に進学出来ない・・という事を、具体的に分っているのに、そのたった1万分の1の可能性を信じて、他の人が、同じ努力をしているから(人がやっているから)・・・というだけの理由で、潜在意識的には、無駄な努力を無駄と分かっているのに、周りがやっているから・・という理由だけで、それは現実的な話だ・・・と信じて、それを分かろうとしない不思議な教育・・・。
100万分の1の確率もないのに、・・・・否、その現実を、知っているのに、敢えて、・・・知ろうとしない、摩訶不思議な日本人の親達
ヨージーの法則
「諦める事を前提としたひたむきな努力」
それこそ、世界のglobalstandardに反する事なのだけどね??
摩訶不思議な日本の教育だよね???
アドバイスについて
アドバイスと言うのは、その人が出来ない事や間違えている事を指摘する事だから、当然、その人が一番言って欲しくない(聞きたくない)事を、あからさまに指摘する形になる。
本当にadviceの上手な人は、相手の人の望む答えを伝達するだけである。それで、相手は納得する。「やっぱり、この答えでよかったのだ!!」と・・・。
ヨージーの法則では、adviceの基本原則は、「自分が望む答えを応えてくれる人に対して、adviceを求めるものだ」ということである。
だから、基本的には、真実しか述べようとしない私に対してadviceを求めてくる人は、極めて希ではある。
と言う事で、作曲家という職業柄、常に演奏家に対して、アドバイスする事が仕事のような私でも、勿論、誰彼かまわずアドバイスをしている分けではない。
一見すると温厚そうな演奏家でも、演奏上の誤りや不備を、指摘されると、烈火の如く怒り出す人の方が多いからだ。
昔、(ヨーロッパから帰国したばかりの頃、2,3年ほどの間、知り合いのピアニストのオケ合わせの練習の手伝いをしていた事がある。
仕事として、お金を取って・・・と言う事ではなく、あくまで私個人の好意からである。
オーケストラの合わせの前に、何度か、私がオケのパートを弾いて、「此処はこう弾かなければならない」とか、「そこはこういう風に弾かないと・・」とか、アドバイスをするのだ。
勿論、相手はproのピアニストなので、Pianoのlessonは二の次、三の次として、あくまでも、オーケストラの合わせ方のpointという事で、作曲家の立場から、how-toをlectureするのだ。
そうして、彼女が日本に帰国して、orchestraとの演奏会を2,3年も続けて来ると、だんだん、彼女の演奏活動も順調に軌道に乗って来て、pianissimoのpassageでも美しい音でオーケストラの中から音が立ち上がってくるように、技術が上達した頃になると、彼女の周りには取り巻きも出来てきて、そろそろ、ちょっと彼女のお鼻が高くなってきた。
と言う分けで、ある演奏会の後、楽屋で演奏の感想を求められたので、いつものように、きつ〜い感想を述べたら彼女、曰く「楽屋に訪ねてきてくれた人は誰も私の演奏をけなしてはいなかったわよ!」との賜わった!
ムカ!っと来たね!
わざわざ楽屋まで演奏をけなしに来る人がいるもんかよ!
人生が分かっていないね。
と言う事で、彼女に対しての、lectureとしての、セカンドピアノの合わせはそれっきりやめてしまった。
勿論、その後も、彼女からの、詫びの言葉は、一言も一切届かなかったしね・・・・私が彼女のPianoのお手伝いをしたのは、完全な親切心からだけだったのでね。
私には、利害はないしね。
という事で、それ以来、彼女とは完全に疎遠になって、30年以上も、会ってはいない。
時折、彼女の演奏会のポスターも見かけるが、行こうとは思わない。
人はもし、自分が他人から「けなされるのが嫌」なら、最初からアドバイスを求めるべきではない。
私はお追従は言わない。
そういう性格だから!
しかし本当に、「アドバイスをしてください。」と言いながら、こちらが、きついアドバイスをすると怒り出す人が多いのには困ったものだ。
先程も書いたように、私の箴言集の、「ヨージーの法則」には 「人は自分の望む答えを言ってくれる相手にしか、アドバイスを求めない。」というのがあるが、それは当たり前である。
きついアドバイスをされるのが嫌なら、最初からアドバイスなど求めなければ良いのに!…というのが、私のアドバイスである。
(1998年6月)
愚痴は愚痴でも、本当に困った愚痴もある。
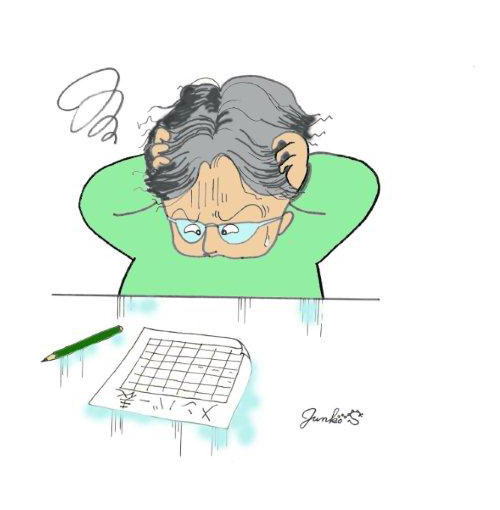
私自身は、・・・・否さ、私は、今迄、演奏活動を30年、40年とやって来ましたが、今回のようにハプニングが続発したコンサートはありませんでした。
基本は、対外出演というか、対外的な演奏活動は、最低でも私の弟子達迄で、未だ音楽への(対社会的な仕事としての意識の育っていない生徒や父兄に対して、)演奏活動に、参加させる事は、希で、相応の意識や価値観を対外出演する教室の生徒や父兄には、要求したからです。
そういった万全の策を講じても、生徒や父兄の意識がついて来なかった・・という事は、私としては痛恨の極みでありました。
当然、昔々の私ならば、怒りまくって、後先の事も考えないで、演奏会自体をキャンセルしたはずなのですが、これがおじいちゃんになったということなのか????・・・主催者の八千代の会場の人達の事や、頑張って練習して来た他の後輩達、生徒達の事を考えると、大人として、(どんなに年を取っても大人にだけはなりたくないのだが・・・・)「ならぬ堪忍、するが堪忍」 と言う事で、鶏冠に来たトサカを鎮めて、memberの組み直しで、お茶を濁そうとしています。
いくらなんでも、オケsoloが、逃げ出す事はないわさね〜〜???
左のイラストは芦塚先生のメンバーチェンジで困ったちゃんの様子をカリカチュアしたものです。
怒りまくっている所、困りまくっている所を、カリカチュアするのは、良いものです。
次の「論文のネタ集」は本来的には、「芦塚陽二の病床記」という私個人で立ち上げているホームページの中の付録のページにこのタイトルと同じタイトルの文章が掲載されています。
だから、当然、本来的には、「芦塚陽二の病床記」がこの文章のホームポジションであるべきなのですが、今回の内容が、余りにも、教育関係だけで、そういった内容が殆どなので、今回はこのページに掲載させてもらいます。
普段の何気ない日常の中で、小耳にはさんだ事や、思い付いた反故を、mailで自宅パソコンに送ります。
それがある程度纏まったら少しづつ、推敲をして、最終稿に近づけて行きます。
そして、それをベースにして、論文の最終稿の作成をします。
論文のネタ集
2012/06/11 (月) 15:32
[記憶力だけを評価する日本独自の教育制度]
日本の学校教育に関しては、小学校から高校のみならず、大学受験までの(実際には大学においても)殆どのカリキュラムが記憶を拠り所とする教育であった。 ・・・というか、「・・・ある。」でいいのだよね。
この理由は、記憶は先人の知識を覚えさせるだけで、一番安直な教育だからである。
大学院を受験する学生を指導したことが何度かあるが、大学院は本来研究機関であるべきである。
それなのに、その目的を持って、何かを研究するという方法論を学んで来た生徒は皆無であった。
という分けで、私が学校教育に対して、子供達が学ぶべき記憶力以外の、カリキュラムとしては、何を指導するべきか?・・・という事で資料となる論文を探していたのだが、運悪く何も探し出す事が出来なかった。
今回は、ネット上の検索が上手く行かなくって、唯一、ネットにupされている、人間の基本的な能力の詳しい分類は、医師を対象にした医学の研究論文だけであった。
という事で、参考文献は諦めて、私の昔の論文を引っ張り出して、カビとホコリは、そのままにして、話を進めて行く事にする。
[記憶力について] 「昔の教育論文からの抜粋」
従来の日本の教育に於いては記憶力偏重な教育がなされている。
しかし、その記憶に関しては、メトードと呼べるものは何もない。
2000年も前からの、儒教型の「繰り返し反復して覚える」という、最も非効率的な方法論を取っているに過ぎない。
教育なんて2000年経っても変わらないのだから、私が今更何を言っても変わるわけはない。
私の30年の努力は無駄な意味の無い努力に過ぎない。
記憶についてのメカニズムは大きくアナログ型の記憶とデジタル型の記憶に分けられる。
アナログ型の記憶法のコツは反復練習であるが、その記憶は、更に、最初の数分間で忘れてしまう短期記憶、一晩寝た次の日にも覚えている中期記憶と、それ以上の日数を記憶出来る長期記憶のパターンに分類される。
また、記憶容量の問題もある。ビットの考え方である。当然、ビットの基本は7ビットであるが、それは、1ビットに含まれる文字数を上げることによって、拡大していくことが出来る。
例を挙げるとすると、「I am a boy」は4ビットであるが、「Iam aboy」と結合して記憶する事で、2ビットにする事が出来るし、更に、「Iamaboy」と一つのsyllableとして記憶すれば、1ビットに集約する事が出来る。
また人間は一日に体験する膨大な情報を無意識にselectして記憶する。
教室で音楽用語を幾ら、何度繰り返して指導しても、音楽用語に興味のない生徒は全く覚えない。
・・・が、しかし、自分が好きなアイドルの名前や詳しい情報を覚えるのは、舌を巻くほどである。
要するに、記憶の基本は興味からである。
つまり、より自分にとって興味がある事柄は、それがどんなに込み入っていて複雑な事であっても、一瞬で覚えてしまう。
若い女の子が、彼氏の事になると、どんな些細な事でも、記憶してしまうのがその証である。
しかし、女の子が女性になって、人生経験が豊かになっていくと、もう、異性の事などは、自分の夫の事であっても、記憶をしようとはしない。
男性も夫も、マンネリ化して、異性としての興味の対象から外れて行くからである。
まあ、それはそれとして、記憶のメカニズムや記憶する媒体に対しての興味を喚起したりしてそういったメカニズムを上手く組み合わせる事によって、アナログ型ではあったとしても、より効率的な記憶法を組み立てる事は出来る。
しかし、如何様に上手に組み立てたとしても、アナログ型の記憶法は、所詮、アナログ型の記憶法に過ぎず、所詮は非効率的である。
アナログ型の思考方法を取るものは、企画指導する側が、思い切った発想の転換や、閃きを忌み嫌うからである。
つまり、そういった新しい改革的な発想は、アナログ型の形態そのものの否定であり、アナログ型のシステムを踏襲しないばかりか、壊してしまうからである。
デジタル型の記憶法や、記憶を引き出す方法論は芦塚メトードによる記憶法のホームページにupしてあるので、ここでは省力する。
人間は幾ら膨大な記憶をしたとしても、その記憶を必要な時に情報として引き出す事が出来なければ、その「記憶をした」という価値すらない。
その記憶が何時、如何なる時に、どのように役立つのかを知らなければ、その記憶の意味はない。
ただのゴミである。
16年掛かって、(否、幼稚園から大学の院までを入れると)、まるまる20年も掛かって、頭の中に巨大なゴミ屋敷を作ったに過ぎない。
引き出す事の出来ない知識とは、単なるゴミにしか過ぎないのだ。
そういったゴミにしか過ぎない知識を、人と比べて、「学歴が自分の方が人よりも優っている」と誤解してしまう。
マンガ音楽家シリーズを監修した時には、その時代時代の細かい生活様式の時代考証をした。
何年に誰某が死んだ、とかいう事ではなく、その時代の様式や生活が理解出来て、その偉人の日常の生活を知ることで、もっと身近なものになっていくのだ。
ヨーロッパで買って来た19世紀や18世紀の文化を当時の絵や銅版画で詳しく説明した本は、マンガの時代考証にとても役に立った。
料理教室でも、ある一つの固有の食べ物のつくり方のhow-toは、どの料理教室に行っても殆ど変わらない。
しかし、同じ料理教室で同じ先生の下で、全く同じように作った料理でも、本当に一人一人味が違う。
京都の市長さんの話であるが、(今は府庁さんかな??)京都にとても美味しい豆腐屋さんがあった。
高齢で後を継ぐ人がいないので、市長さんがその豆腐屋さんに、「お弟子さんを取れば・・?」と言ったら、豆腐屋のおじいさんから、「豆腐を作る作業は誰でも見る事が出来ます。」
「だから、見て盗めばいいのや!」と一蹴されたそうです。
私は「男子厨房に入るべからず」という時代に生きて来ました。
という事で、ご飯の炊き方や料理の仕方を全く親から習った事はありません。
それ以上に、母自体が料理を学べるような、時代には生きていなかったのです。
私の母親は、豪農で庄屋さんの娘として「乳母日傘」で育ってきました。しかし、両親が保証人になった相手が逃げて、家屋敷を失ってしまって、そのショックで両親とも死んでしまいました。
という事で、小学4年生だった母は、小学校をやめて、すぐ下の弟と二人で、幼い弟妹達を育てたのです。
戦前の事ですから、女性に職業はありません。U20の母は、自分に学力が無い事を恥じて、お金を稼ぎながら勉強が出来る看護婦の仕事を選びました。婦長の資格も持っています。
という事で、一般には厳しいです。女性だから・・と言って、優しく、甘くという姿勢は、祖母にしても母にしても、全くありません。
でも、戦前、戦後はそれが当たり前の女性の姿だったのですよ。
私の大学の卒業アルバムや、高校生の時の女の子達の顔を見ると、今の女の子とは全く違います。
もっと、キリリとしていたのですよね。
母が私の中学生の時に、再婚をしたので、私は中学生の時から、県営のアパートで、一人暮らしを已むなくせざるをえませんでした。
一応は、アパートの近くに病院を開業したので、食事は、看護見習いの少女(私よりも年下の)が一日一回運んで来て、火を通してくれました。
後の、食事は、自分で自炊する他はなかったのですよ。
だらか、料理を覚える事は生きるための否応ない必然だったのです。
当時は、勿論、コンビニもないし、インスタントの食品も全くなかったのですよ。
私が高校生になって、やっと、日本初のインスタント・ラーメン(どこがラーメン??)が出来ました。
私の行っていた高校は、受験高であったし、友人達は山岳部でもあったので、それ相応には料理は出来たようです。
今は昔の話ですから、当然、女の子の恋人も友達もいない時代です。
男女交際が出来るような、そういった時代ではなかったからね。
しかも、当時の私達は、生活のために自炊をするのだから、高校生の女の子では、料理の腕は比べ物にならないよ。
他所の私立の高校ならいざ知らず、私達の高校は受験高校だったので、女の子でも、料理裁縫は無理なのだよね。
だから、当時始めて出来たばかりのインスタント・ラーメンは、お世話になっていたのだよ。
3分間待つのだよ!・・・と言いたいのだが、高校生のお小遣いで買える代物ではなかったし、当時の初期型は不味かったよね。
だから、私の料理は誰かに習ったものではなく、目で覚えたものです。
お店で美味しいものを見つけると、その味を家で再現しようと試みました。
だって、お店で料理の仕方を聞いてご覧??
カンカンになって怒られるか、お店を追い出されるかだよ!
今のようにテレビ取材すら、ない時代だから、味は店の秘密で、弟子にも、肝心要の所は教えない。
それが普通なのだよ。
そこの所が今の人達には分からない。
それと昔は料理の本すら、あまりなかったのですよ。
あまり・・というのは、全く・・という意味ではありません。
だから、私は高校生の時には、江上トミさんの料理の本と、村上信夫さんの本で料理の基本を勉強しました。
高校生から大学生ぐらいまでの間ですがね。
それまでの時代までは、味付けの塩梅は感でした。
分量をグラムで表したのは、村上さんがNHKの料理番組で、限られた時間の中で一般の視聴者に説明しなければならなかったからです。
それが何時の間にか、今度は味付けの常識がすっかり逆になってしまって、味付けを教える時には、グラムでしか伝達出来なくなってしまったのです。
料理教室の料理の不味さや、不経済さは、そこから始まったのかもしれません。
私が高校生の時に買った、江上トミさんの料理の本の基本は、大根一本から幾つに切り分けられるか?・・で、その大根の切り分け方で、何種類の大根料理が作れるか?という事が自動的に決まって行くメトードです。
大根料理ではそれぞれの料理で大根の切り方が違います。
から、大根の切り方が分かっていれば、当然、その料理も出来るのです。
日本の家庭料理は、江戸時代からそれぞれの地方で、それも一軒一軒の独自の家庭の味として伝承されてきました。
しかし、その伝承は第二次世界大戦で途切れてしまいます
。
日常の物が全てなくなってしまった戦争の時代には、その家の味を嫁に教えるというような、悠長な事は出来なくなってしまったのです。
だから、日本の社会では、私達の母の世代から日本料理の伝統が切れてしまいます。
それを、江上トミさんが実際に、世代別に実験しているPageがありました。
私達の世代、(私達がまだ20歳になったばかりの時代です。)その次の私達の母の時代、それから、明治時代に生まれたお婆さんの時代に分けてちょうさをしました。
私達の時代の若い女性達は7種類ぐらいの切り分けしか出来ませんでした。
私達の母親の世代では20種類の切り分けが出来ました。
ところが、江戸時代から日本の家庭料理をちゃんと学んできたお婆ちゃん達は70種類の切り分けをしたのですよ。
これは凄い!!驚いた!!
失われた伝統、伝承は、今更、大きかったのですよね。
家庭料理がとても優れている所は、その味を直接知る事が出来るという事に尽きます。。
料理を学ぶ人がまず一番に覚えなければならない事は、「美味しい」という感覚です。
美味しいと感じることが出来れば、その料理を再現出来るようになります。
美味しい味付けが出来るようになるのです。
料理で、まづ一番最初に覚えなければならない事は、味だよ。
「美味しい!」と思ったその味を覚えない限り、料理は始まらない。
幾ら、料理教室で、レシピを覚えても、味を覚えない限り、その料理は張子の虎です。
音楽大学のように、拙い技術だけをアナログ式に勉強していっても、巷の料理教室の料理のような空虚な物真似の音楽が出来上がるだけで、そんな努力を幾ら死に物狂いになって何年も続けたとしても、その先にプロの世界はないし、それで人を感動させる事は出来ません。
勿論、感心させ(ビックリ驚かせ)る事は出来るでしょうけれど、それは魂の感動とは程遠いものなのでね。
人を感動させる事が出来る人だけを、プロと呼ぶ事が出来るのだからね。
勿論、マスコミの世界では、プロの定義は少し違っています。
一発屋的なものでも、世間の関心を引く事が出来れば、人寄せパンダになれば、プロと言って持て囃したりします。
コンクールに入ったから・・・、美人だから・・・、色っぽいから・・・等々の、人々の関心を呼び起こす事が出来る人の事をプロと呼ぶようですし、また、そういう風にプロとして祭り上げたりします。
しかし、そういう人達は、私達の目から見ると単なる一発屋でタレント、アイドルに過ぎません。
私達はそういった人達に対して音楽のプロ、芸術家とは呼ばないのですよ。
それは単なるアイドル的な、プロに過ぎないのです。
その時点で上手く学校に取り入って、先生として収まってしまう人もいます。
音楽大学にとっても、マスコミに人気の演奏家は「人寄せパンダ」として、学生を集めるためのステータスになるからです。
でも、それはマスコミで作られた虚像に過ぎないので、そういった有名なだけの音楽家に学んだ生徒はそれこそ悲惨です。
学ぶべき技術は何もないからです。
マスコミの世界の音楽には、イージー・リスニングというgenreがあります。
イージー・リスニングの音楽を演奏する人はそれこそ美人で色っぽい若い人の方が気持ちいいですからね。
その世界には実力は要らないのです。
運と美貌があれば良いのです。
しかし、音楽に対して、心の支えや魂を満たす事を求める人達にとっては、そういう演奏家の奏でる音楽は飽き足らないし、心の支えにもなりはしませんよね。
幾ら美人でも当世風の空虚な空っぽの音楽では、音楽に真摯な心や感動を求める人達にとっては、無意味な音楽になってしまいます。
私達の教室の生徒達も、対外出演でpurcellのchaconneやPaClbelのchaconneを演奏したのですが、練習の時には、「何よ!この曲は・・・!!」「かったるいし、重たいし、演奏していても疲れる!」と,非難轟々であったのだが、子供達も中学生になって、音楽の表現技術も上がってくると、「purcellやPaClbelのchaconneが弾きたいなぁ〜!」と言い出して、先生達を驚かせています。
「ふ〜ん??変われば、変わるものだ!!」
しかし、音楽大学で、音楽を学んでいる当世の若者達にとっては、歳をとっても、そういった真摯な音楽は、重すぎて、かったるいように感じるようです。
暖かくも寒くもない、何もないそよ風が、自分の頬をなでて、過ぎ去って行く。
それが、きょうびの若者達の理想の音楽でしょう。
それこそ、イージーリスニングの世界です。
それ以上は、もう、心に重たいのですよ。
「心に負担が掛かる事を極端に毛嫌いする」、・・それが当世風の若者の姿なのだよね。。
心に負担をかけないで、技術や知識にだけ走る、それが、今の頭でっかちの人間性のない空虚な当世風の若者であるのだな。
Beethovenが言った言葉、「心に至らん事を!」という心を育てる、という教育はこんにちの学校教育の中にはありません。
知識が教育の全てであり、成績の善し悪しで、その人の人間性までも評価されてしまうのです。
限られた社会空間である学校という生活環境の中では、成績が良いとう事で、先生や親、或いは周りの友人達から認められたとしても、一旦、社会に出てしまうと、そういった成績はもう何の役にも立たなくなってしまいます。
こんにちの学校教育の中では、学校教育の中で学習した知識を、如何に自分の実生活の中に活かしていけば良いのか、という技術は教えません。
折角、苦労して得たその知識を、自分のために活かして、その知識から色々な事を引き出すという、技術や能力がなければ、或いは、その知識を展開して、自分独自の発想の展開を示す事が出来ない限り、幾ら、苦労をして、膨大な人生を費やして得たとしても、その知識は何の役にも立たない、単なるゴミに過ぎないという事を、改めて認識させられてしまう事になるでしょう。
そうして、自分が頑張って勉強して来た過去数十年の人間に取って最も大切な自分の青春時代の人生そのものを、一瞬で社会から否定されてしまう。
それ程、悲惨な事はない。
Aha、miserable!なのでやんすよ!
では、何故、そういった記憶に依る教育がなされて来たのか?
答えは簡単である。
まずは、記憶をさせるという事は、生徒に準備した資料を提供し、覚えさせるだけなので、指導者にとっては、これほど楽な教育はないからです。
音楽でもレコードをまる覚えさせて真似をさせるだけの指導法や、数学の塾でも数字を羅列して、単純に計算させて、訓練で計算力をupさせる事をメトードと呼んでいる、安直なメトードで有名になっている塾もあります。
「聞くだけで英語が喋れるようになる」と宣伝している英会話のsystemすらあるのですからね。
教室を有名にして、日本を、或いは世界を席巻するためには、多くの子飼いの指導者が必要になる。
しかし、苦労をして何十年もかけて、そのsystemを学んでくれるような、愛弟子はどんな職人でも、一生の内に何人かの人材に過ぎないのだよ。
だから、systemを日本に・・或いは世界に広げようとすると、systemが簡単で、安直な事が最も大切な条件になるのだよ。
メトードを広げていくためには、指導者の教育が楽である事が、必須の条件である。
どんなに優れたメトードでも、それを指導者が習得する事が難しければ、その教室は指導者を集め、教育する事が困難だからである。
当然、指導者が集まらなければ、その教室は広がって行く事はない。
分かりきった事だよ。
指導する先生達が安直に習得出来るメトードである事が、教室経営の根Knであり、基本を成すものである。
また、日本の学校教育も同じように、回答力を求めるだけで、何故?どうして?という、疑問に先生が答える事はないのだから、先生が「何故、その答えになったのか?」「どうしてその計算式が必要だったか?」等の質問に答える必要はない。
だから、日本の音楽大学では、生徒が先生に質問をすると、先生は烈火の如く怒り出す!
「黙って、私の言う通りにすればよいのよ!」「ちゃんと出来るようになったら分かるわよ!」と宣ふ!!
生徒からの質問がなければ、・・或いは、その問題の意味を解き明かす必要がなければ、カリキュラムは、大人の書いたスケジュール通りに、授業が進んで行くのだから、それは楽である。
与えられた問題を解くだけなので、子供の教育に何の技術も要しないし、哲学も心理学も必要はない。
(昨日《2013年2月17日》のオケ練習で、小、中学生の子供達に、「授業中や、休み時間に先生に質問をしても怒らない先生は・・?」と聞いたら、約半数の生徒が、「そういう先生がいる。」と答えた。
寧ろ、先生の方が「何か分からない時には何時でも質問してね。」と声かけをしてくれるそうだ。それは、凄い!時代は変わった!10年前に同じ質問をしたら、そういう先生は皆無だったのに・・・やはり、この10年で少しは変わってきたのだね。
それは良いことだ!!)
しかし、逆にその事を言い換えると、「今でもまだ、半分の子供達の先生は、質問をしても、答えてくれない。」 、という事だよね。
子供が分からなければ、体罰を加えれば良い。
そうすれば、分かっていようと、分からないままであろうと、教育した事にはなるし、子供も痛みに耐えて努力した事にはなる。
それが所謂、昔ながらの儒教型の教育である。
芦塚メトードでは、逆に無意味な努力は、時間と労力の無駄使いとして生徒達に戒めているのだがね。
何故、日本の社会では儒教型の教育が行われて来たのか?
次の話も繰り返しホームページに掲載しているし、機会を捉えて、折に触れて、色々な場所で話をしている事ではあるが、歴史的に日本社会に於いて、アナログ型の記憶法を重要視したのは、絶対封建世界に於いては、その社会制度に対する批判や改革は、最も忌むべき事であるので、そういった思考力を身に付けさせる事が、極力ないように、幼い年齢の内から成人するまでの教育の中で、心の中に、所謂、潜在意識の中に埋め込んで、社会に反抗することのない、おとなしい従順な国民を育てるための教育をする事が、国家にとっての最大の優先事項であった。
つまり、子供達が学習する内容は全く問題ではなく、指導者に対して、如何に従順に従うか、ロボットのように、何も考えず、悩まず、敵弾の中に飛び込んで行くか、それが教育の真の目的であったのだよ。こういった、ロボトミー的な教育は、江戸幕府の時代の封建制度を維持する上で、或いは、明治、大正、昭和の軍事国家を支えるためにも、そして、戦後の大手企業の企業戦士を雇用するためにも、この儒教型の思想と教育は、すこぶる都合が良かったからである。
日本社会では、考え、分析し、判断し、理解し、批判する事を極端に忌み嫌う!
中央集権社会では、一人の為政者の判断が末端まで、何の変更も付加もされる事なく、忠実に伝達されるtopdownのsystemが基本である。
徳川家康は徳川家の血筋を守るために、その権力構造を維持させるために、色々な思想の中から、封建制度の確立をさせるために、最も適した思想である孔子の儒教を国家的な指導カリキュラムとして取り入れた。
そのtopdownのsystemは、徳川幕府の封建制度が崩壊した後でも、明治時代の強い軍国主義を維持するために、或いは、敗戦の後の世界に羽ばたく日本企業を育てるために、我々の世代である団塊の世代の日本社会でも、すこぶる都合の良い思想として、大切にされてきた。
日本人の日本人たるDNAとして、その儒教型の意識が、既にバブル経済が崩壊して、社会制度がグローバル化して、年功序列ではなく、実力主義にならなければならなくなった現在の日本社会の中でも、未だに存続し続けて日本人の心の支えとなっているのは摩訶不思議な状態である。
[日本型の父親]
儒教型のtopdownの思想は、寧ろ、儒教の制度とは無関係だと思われがちな一般家庭にとっても、すこぶる都合の良い考え方であった。
普通に考えると、家庭というものは、社会の制度の中から隔絶しているし、封建時代、軍国主義の時代、こんにちの大手企業の社会になっても、そこで働く人間の休息の場なのだから、より安定した変化のない生活がベストとされるのだ。
それこそ、儒教の根本的な思想であり、昔々の江戸時代のtopdownの意識の時代から全く変わらず、そのままの家族構成のままである。
父親が家族の主導をして、妻や子供は父親に従うというのが、日本型の家庭の理想である。
そうすれば、決断を強いられるのは父親だけで、母親や子供達はそれに従えば良いので、従う立場の母親や子供達にとっても、すこぶる楽である。
間違えた選択をしたとしても、間違えた責任は父親にあり、自分達の責任ではないからだ。
しかも、その父親さえ、上司や事と場合によっては、自分の父親等に相談をして、上のadviceを貰って行動をしている。
だから、あながち父親のせいばかりという事になる分けではない。上司も、「自分のadviceは・・・」と、責任を擦り合う無責任のルーチン(ループ)が無限に続く。そして、責任の所在はなくなり、失敗した時にも、その責任の回避が出来る。
儒教は中国の思想であったはずなので、本来的には儒教の国であるはずの中国は共産国なので、儒教的な思想を持っている若者は、何と!殆どいない。
共産主義と儒教思想は根本的に相容れないからである。
という事で、テレビを見ながら、この論文を書いていたら、ちょうど、日本人の若者の意識や自立についてのドキュメントを放映していた。
日本に留学して、そのまま日本社会でリクルートをしようとしている中国人の若い女性が、周りの日本人の友人達からリクルートについて相談を求められた。
彼女はその事を不思議に感じて、その疑問をtweetして見た。
NHKのドキュメントはそこから始まる。
彼女の周りに居る殆どの日本人の友人達が、自分で就職先を調べ、考え、決断するのではなく、就職先のadviceを、親や周りの友人達に求めて、しかも、その意見を自分の決断の参考にするのではなく、そのadviceに従順に従って会社訪問等をしていたので、その自立意識の無さを不思議に思って、SNSにその疑問をぶつけて見たのだが、その反応は、いずれも「子供の時からも、どの学校を受験するか、どの大学に行くか・・を親や先生が決定して、それでこれまでうまく行っていると思うから、リクルートも・・」 とか、「自分には人生経験がないから、既に経験を果たしている年長の人達にadviceを・・」 という答えが返って来たそうだ。
その中国人女性は、呆れ返っていたよ。
「日本人の若者達は、何一つ自分では決断できないのか?!!」って・・・!!
世界の人達から見ると、摩訶不思議な日本人の若者たちという事なのだが、日本に住んで、生活をしていると、「それが摩訶不思議な事である」 、という事が分からない。
そういった社会の中で生まれ育ってしまうとね・・・。

[儒教的な依存の構造のエンドレス]
日本の教育では、子供の内から、子供自身が、自分で自主的に何かを決定することはなく、大人であるはずの母親すらも、決定権を持っていない場合が多い。
しかし、決断を他人に委ねる事は、子供にしても、母親にしても、考える事の煩わしさ、悩む事の辛さを経験しなくても良いのだから、基本的には楽な人生なのだよ。
家庭では、全てを決断している父親ですら、社会人であり男性である立場の父親でも、会社に行くと、自分で仕事を決断し、動く事はない。
そういった裁量権がないのである。
日本型の会社は、トップ・ダウンの経営が基本であり、仕事をする上で、指示や決定は上司がする訳で、上司の行動は社長が裁量する分けなので、お互いに責任を取る必要はない。
言われた通りに、言われた仕事をすれば良いだけなので、すこぶる楽である。
という事で、教育のconceptは、頭がない(考える事のない、ロボットのような)子供を育てる事が優れた日本人を育てる基本である!
先生や親の言う事を忠実に聞いて、その通りに行動する事が、理想の子供ならば、子供が独立し一人で生きて行く事はない。
それが、引き篭もりの、根本の原因である。
育てられる側も、考える事がなければ(自己判断が無ければ)、それは責任もないという事なので、楽である!
ところで、子供の時代から、一度も責任を持たされた事のない人間が、そのまま大人になったとしたら、どういう社会が出来るだろうか?
それは、今現在の日本社会を見れば分かるだろう??
毎日、テレビを賑わせているような、自分本位で、社会や他人に対して全く思いやりのない人間が育つのだよ。
・・・こういった自分の権利ばかりを主張して、権利に伴う責任や義務を果たそうとしない人ばかりの、無味乾燥な社会、所謂、殺伐とした社会が出来るのだよ。
そして、親や先生達の掲げる理想の現実と実社会のギャップに行き詰まってしまった時に、SNBP(負の転換点)が起こる。
よく人が 「あんなに、勉強も出来て、親の言う事もちゃんと聞いて、礼儀立たしい、おとなしい理想的な子供が、何で、そんな大それたことを!!」と、社会やマスコミを賑わしていて、教育の専門家ですら、「理由が分からない」と宣ふ。
しかし、それは心理学上の定形だろうが!!
所謂、SNBP(負の転換点)という、定石なのだろうが!!
それが、「分からない」 というのなら、教育者や親をやめたら??
SNBPは、心理学的には、必然に過ぎないのだよ。
そういったtopdownの権力構造を「良し」とする儒教型の父親の事を、私は「日本型の父親」と呼んで、30年前に大学で「日本型の父親と西洋型の父親」という教育論文を発表した。
しかし、30年経っても、何も変わってはいないのだよ。
同窓会の連中が集まる、カウンターバーがあった。高校の同級生がやっている店だ。
何年経っても代わり映えのしない、汚い店なのだが、長崎の丸山遊郭の中では一番古い店だそうな。
要するに、何も変わらなくって、いつ行っても誰か同窓生がいるから、安心出来るので安定している店なのだそうな。
人間は変化を好まないのだよな??そこに家元制が存続する最大の理由がある。
[仮面日本型父親]
私がこの「日本型父親と西洋型の父親」の論文を書いた1980年代の当時は、まだ、ほとんどの父親が「日本型の父親」のみで、実際には「西洋型の父親」は、全くいなかった。
極々、稀に見受けられる一見すると「西洋型」に見える父親も、実は「仮面西洋型の父親」であって、心の奥底の潜在的な部分では「日本型の父親」なのであった。
つまり、外目には物分りの良い「西洋型の父親」を演じているが、それは、自分の関心がない、或いは利害がない部分のみに於いて・・であり、その父親のテリトリー(所謂、逆鱗)に触れる事になった途端に「日本型の父親」に豹変する。
しかし、30年以上の歳月が流れた、今現在でも「仮面西洋型の父親」が大多数で、子供の一生の決断も、子供達と話あって、子供の意識を一番に考えようとする、本当の意味での「西洋型の日本人」は、私はまだ見た事がない。
「仮面型の父親」の実際の例であるが、母親が小学校の先生で父親が中学校の優秀な先生である父親は、全ての教育を「母親や子供と相談して、家族会議で決めている。」と私に言っていたのだが、よくよく、双方の話を聞いてみると、その父親の前提が「子供や母親は社会を知らない。」という前提の上になっていて、父親が学校で普段生徒達を指導する時によく使う「debate力」で、子供と母親を言いくるめて、それを持って、世間的な大義名分上では「家族で話あって決めた。」と言っていたのだよ。
私の研究論文では、そのdebate力で、導き出された「選択権のない条件の提示」をして、「子供の意見を聞いて、子供と相談して・・」とかいう、親のパワハラ的な手法は子供の挫折感をより増幅する事にしかならない。
親が大人としての経験やdebate力を、相手を説伏する手練手管の技術として、教育に使用してしまうと、結果としては、やっぱり自分では何一つ決められなくて、出る釘や長いものにまかれる就職活動ですら自分で決められない大人子供の日本人達が育ってしまう事になるのだ。
家族間の子供の勉強や進路に対しての話し合いの場でも、その時には、親の口車で言いくるめられて、その場限りでは子供達は納得するかもしれないが、それで子供達や母親が納得をしたとしても、説伏をする事は、力の行使の一つの手段に過ぎなく、それを持って「西洋型の父親」とは言わないのだよ。それはパパハラの一つの種類に過ぎない。
つまり、日本型の教育を西洋型のtemplateでやっているのに過ぎないのだから。そういった誤った教育では、見せ掛けは兎も角としても、決して子供達の自主性が育つ事はないのだから・・・。
これも中国やアメリカの学生達から見ると、不可思議な日本人に見えるのだよ。
勿論、私がヨーロッパに居た時には、私の周りのヨーロッパ人家族の半数以上の父親がヨーロッパ型の父親だったのだがね。
[儒教型の父親が日本に多いもう一つの理由=女性の甘えの構造]
何故、日本には西洋型の父親がいないのか?
それは必ずしも、日本人男性の支配欲のせいだけには出来ないのだな。
日本人の父親がヨーロッパ型の父親になるためには、男性だけがヨーロッパ的なセンスや考え方を持っていてもダメで、女性自身もヨーロッパ型の自立した女性でないと、ヨーロッパ型の家庭は築けないからなのだよ。
寧ろ、日本独特の儒教的な男性支配の安楽な生活を望む日本型の女性に、その原因を見つける事が非常に多いのだから。
日本の女性の自立や社会進出が、世界のあらゆる後進国よりも遅れているその原因は、あながち、旧態然とした老人の政治家達のせいだけではなく、女性自身の意識の中に見出す事が多いのだからね。
日本型の家庭の教育では、女の子の自立を極端に忌み嫌う。
女性は結婚が全てで、女性の幸せとは、金のある有名な一流の会社に働く男性と結婚して、子供を作り育てる事に尽きるという。
それが女性の幸せの全てだそうな。
一流大学を目指しての受験勉強も、音楽への勉強も、親の意識の根底には結婚をするためのステータス作りに過ぎないそうな。
だから、親の娘に対しての仕事に対しての考えも、音楽等のプロ活動も、家庭の生活、子育てや家事に影響しない程度の範囲でなら・・?という、条件下でなら・・という条件が入る。
私達の場合、・・というか、世の中の一般論では、そういった仕事は仕事とは呼ばず、バイトと呼ぶのだよ。
それが日本人には、分からないのかな??
以前、NHKの討論番組で、女性と男性、若者達と中年や初老の世代等々を分けて、「仕事に対しての意識」を討論していたのだが、とある初老の男性が、「時間外にトラブった時に、女性はちゃんと対応してくれない。」とクレームを言っていた事に対して、中年の女性社長が、「私達は、与えられた仕事はちゃんとやっています。」と怒りまくっていたのを記憶している。
初老の男性は何かが起こった時のアフターケヤーの「時間外の対応」の事を話をしているのに、中年の女性社長は与えられた時間の中で「ちゃんと男性よりも丁寧に仕事をしている。」と主張しているのが、水掛け論というか平行線で、傍目にも笑えた。
日本社会では、女性は主婦としての仕事や子育て等を、全て一人でこなさなければならない。
女性が起業をする場合に、一番問題になる点は、家庭と仕事の両立の問題か、それ以前に仕事を優先するために、結婚をするか、しないか?の二者択一である。
現代社会では、女性が仕事をして、ある程度のキャリアを上げ、社会的な地位を得る事は難しい事ではない。
だから、女性にとっても、「子供を産んで、育てる」という事を望まなければ、結婚する事自体に意味がないのだ。
という事で、子供を産めるか、産めないかのギリギリの年齢迄の極端な晩婚が、今まで以上に主流になっていくだろう。
それは女性側だけの問題ではなく、男性側にも、同様な問題が提示されていると言える。
女性がキャリアを持って、生活力や決断力を持つのなら、男性が家庭を持つという事は、日本社会の従来の結婚のような、家事や子育てをしてくれる女性と結婚するという意味合いはなくなるし、そういった昔ながらの女性と結婚する可能性は非常に少なくなる。
もし、男性が家庭生活上で、掃除、洗濯、料理も女性と分担しなければならないのなら、子供を産んで貰うという以外には、女性と結婚する理由はなくなるからである。
それが男性の晩婚化を生み出してしまっている。
政府が少子化の問題を云々しようとするのなら、そこの問題を抜きにして、男女の結婚を考える事は出来ない。
それなのに、政府の少子化の対応は、相変わらず子育て支援に留まっている。
儒教型の家庭生活の崩壊を認めたくないからなのだよ。
昔は、入院施設のある大病院では、婦長は未婚の女性に限られていた。
昔々は、学校の女子教員も、学年主任や校長という責任のある役職に就こうと思ったら、未婚の女性に限られていた。
それは、所謂、時間外の対応や、主婦の場合に於いては、優先度の意識が主婦業(旦那の仕事の都合とかも含めて)、子育てが、仕事の優先度で勝るからである。
妻としての立場と子育てをどちらを優先するかは、人によって違うので、それはどうでも良い事なのだ。
事の根本の原因は、家庭と仕事の両立の問題であるからである。
だから、先程の女性起業家の(女性社長の)例のように、一旦、家に戻ると、もう主婦になって、仕事上の社長ではない、家庭人でいる時には、仕事への対応は出来ない・・というのでは、仕事を発注する立場では、女性社長に対して、安心感が抱けない、という意見は当たり前である。
女性が自立して仕事をしようと思うのなら、リスク管理の少ない、仮に残業があったとしても、時間を選べる業種を選ぶべきだったのである。
男性であろうと、女性であろうと、仕事には責任を伴うのは、当然である。
「時間外の労働は出来ない」というのなら、その女性社長は、時間外の労働のない職業を選ぶべきであったのだよ。
(これはNHKのドキュメントについての感想である。)
ヨーロッパ社会では、男女の子育ては完全に平等である。
しかし、ヨーロッパも、王権の時代、封建時代があったのは、日本と変わりはない分けで、現代のように完全な男女平等が確立したのは、二次大戦後の話である事には変わりはないのだ。
ただ、いち早くグローバル化をしたヨーロッパ社会と、日本型の社会の違いは、女性の自立に対する意識の差に過ぎないのだ。
音楽の社会でも、音楽を学ぶ人の比率では、女性が圧倒的に多いにも関わらず、(日本のデモシカ演奏家は別として、)本当の意味での演奏家には女性の演奏家が極めて少ないのは、恋人が出来たり、家庭が出来たりした後の、女性の意識にその原因があるのであろう。
どんなに、頑張って、演奏活動を始めても、結婚した途端に、現場から居なくなってしまうという現実は変わらない。
それは、女性の幸せの総てが、家庭を中心として考えられていて、女性自身もそれを望んでいるからなのだ。
しかし、女性の理想が結婚生活で、音楽はただのステータス、或いはバイト程度の仕事のために、一途に音楽だけに邁進して、音楽大学受験や留学何という、大変な苦労をして、そして、結婚して音楽を趣味の域にしてしまうというのは、掛かった莫大な金額や、技術を習得するための努力や勉強をするという事は、いくら何でもリスクやハードルが高いよね。
音楽大学に進む女の子の大半は料理も裁縫も全く出来ない人達が殆どなのだよ。
それで、結婚したら困るだろうかな、と思うのだけどね??
学校で一生懸命に勉強をしていても、仕事で必要な充分な「記憶力」を身に付ける事が出来る生徒は殆どいない。
何故ならば、記憶力は学習して身に付くわけではなく、その対象に対しての興味と価値で、記憶が出来るようになるのだからである。
それに、完璧な記憶力を身に付けたとしても、記憶は単なる知識に過ぎず、それ自体では博識をひけらかす以上の意味はない。
記憶による知識を実際に役にたてようとするのなら、その記憶した知識の内容を観察し、判断し、理解し、分析し、そこから求める答えを求めて行かなければならないのだ。
という事で、子供達に、学校で学んだ事について、「どうしてそうなるの?」と質問をすると、それに答えられる生徒は皆無である。
それだけなら、問題はあまり大きくないのだが、寧ろ、子供達がそういう結果論のみを求める教育に順応してしまって、「どうして?」或いは「何故??」という言葉を、軽視するのなら、まだいい方で、嫌がる傾向にあるという事は大問題である。
私が子供達に対して、言葉の意味を説明しようとすると、「芦塚先生は、何を話しているのか、分からない!」と子供達がよく言う。
つまり、子供達が私から、聞きたいのは答えであって、「どうしてそうなるのか?」という過程ではないからである。
という事で、私がそれの成り立ちや意味等を説明しようとすると、子供達は自分達が求めている話と違う話を、私が始めてしまうので、面食らってしまうのだよ。
学校教育や塾教育で、やっているように、問題に対する反応として、解答を記憶させる指導をしていたら、その問題を、理解しているわけではないので、一旦その解答方法を覚えたとしても、直ぐに忘れてしまう。学校の勉強が「校門を出ない」のはそのためである。
[正しい学習指導とは]
子供達が物事をちゃんと記憶し、それを将来に活かせるようにするには、先ず「その必要性を理解し、その問題の意味をちゃんと理解すると、忘れないようになるのだよ!」と、子供達にも、しょっちゅう説明するのだが、それが(理解する事や、考える事、必要性を意識する事等々が)、子供達にとっては、かったるくて時間の無駄に思えるのだよ。
学校や塾の教育で求めているのは解答であって、問題を理解する事や、何故、そういった解き方が導き出されたのか、という解き方の方法論ではないからだ。
とは言っても、それを学校や塾の先生に「指導しろ」、と言っても、それは無理かもしれないね。
それこそ、大学教授並みの知識と見識が必要となるからだ。
物事はsimpleになればなる程、その説明は難しくなるのだよ。
だから、ノーベル賞の学者の先生達の、初歩の授業をテレビで見ていると、初歩の初歩の話であったとしても、極めつけに面白い!
簡単に見えた事の話が、何処までも奥が深くて、話が尽きないのだよ。
それは凄いよ!!
やはり、ノーベル賞を取るlevelの人達は違う。
それが、そこまで説明出来て、初めて「その事が分かっている」 と言えるのだよね。
正しく勉強をする時に必要な能力は、先ず先人達の残した文章を読んで、先人の知恵と経験を理解する事である。
その理解に必要な能力は、その文章を客観的に理解し、分析し、判断する力である。
そこまでを、認知力と言う。
先人の知恵が、正しいか、誤っているかは、物を見比べて、比較し分析する能力が必要となる。物を見る力の事を観察力と言う。
先程と同じ事の繰り返しになってしまうのだが、観察力というのは、主情を交えず、物事を客観的に見つめ理解し判断する、所謂、正しく物を見る力であり、そこから更に発展させて、分析し判断し正しく理解する事を持って認知力という。
文章の内容を理解する読解力は、理解力や判断力と同じ意味だろうし、認知力というのは、よく分からないのだが、自分の経験値に照らし合わせて、判断する力という事なのか。
洞察力というのは、文章そのものに、既に書かれている内容ではなく、その文章の持つ裏の意味や、書かれていない所まで、類推し、分析し、洞察(推論を伴った判断力)をするので、洞察力となる。
ここまでが記憶とその理解に関する領域である。
それからは、それを伝達するという作業になる。
思考力というのは、必ずしも与えられた情報に対してのみ、行われる作業ではない。
自分の考えの場合もあるし、その場合には発想力になるのだが、発想力も、必ずしも自分の考えだけに限定するものではない。
思考力とは、基本的には知識上の情報を使用して思考する場合が多いが、発想力となると閃きや想像力、創造力、或いは独創力のような自由な思考による場合が多くなる。
私が、「このメトードは私が始めて創り出したメトードだ。」という事を自慢していたら、高校の数学の先生をやっていた女性に、「人間は自分が創造したと思っていても、必ず昔の人か、誰かがやっているのよ!そんなに、簡単に創造なんて出来るものじゃないのよ!」と、愚蔑的な顔をして言われてしまった。
しかし、それはその先生が、学校教育的な視点でしか勉強をして来なかったからで、無から有を作り出す別の方法論を知らないだけで、本当は無から有を創り出す方法(methode)はあるし、それを学ぶ事は難しい事ではないのだよ。
私達がやっている音楽の歴史は、ルネッサンスから数えても、音楽の歴史はタッタの五百年に過ぎないのだよ。
音楽の基本的な性質が違うのだから、別にピタゴラスの時代から、計算し勉強する必要はないのだよ。
それに、調や弦楽器の確立は、1600年のbaroque時代以降からに過ぎない。
そうすると、100年は減るのだな。
ピアノの音楽の研究になると、forte-pianoが出来て来てからだから、1780年前後からなのだが、音楽史的には、Haydnが完全にforte-pianoに鍵盤楽器を移行してしまう1790年以降、 と調べなければならない資料の数は激減してしまう。
自分が研究したい分野、場所、人等々を絞り込めば絞り込む程、本当に必要な資料というのが少なくなってしまいます。
極端な場合には、資料そのものが全くなくなってしまうのですよ。
逆に、世界中の資料をネットや文献で求めても、100の資料が集まらなくて困る事も往々にしてある。
人は原則として人のやっている事を研究するという性質がある。
つまり、研究というのは色々な人が色々な事をやっているように見えて、実は殆どの人達が同じ研究をやっているのだよ。
つまり、メージャーなBachとか、HandelとかMozartとかchopinとか、ヴァイオリンだったら、Wieniawskiとかの超有名な作曲家達の研究は、色々な人達が色々な角度から、専門的に研究しているのでその中で人のやっていない研究をしようと思っても、なかなか難しいのだよ。それでも、その作曲家が好きな人はいるだろう。
その場合には、独自性は諦めて、スペシャリストになる手もある。
それでも、社会的には充分だと思うよ。
独自性に拘る理由はないのだから。
しかし、自分が大した実力もないのに、一角(ひとかど)の研究をしたければ、色々な分野の中から、誰もやっていない穴場を探せばよい。
そうすれば、誰も研究していない所を研究できるのだよ。
人のやっていない研究を探す事は、いとも簡単な事だ。
あのbaroqueの音楽で超有名なPaClbelだとしても、近年までcanonしか知られていなかったし、それこそ楽譜だって、canonの1曲だけしか出版されていなかったのだよ。
この数年になって、かなり多くのbaroque時代の曲が新しく発見されて、出版されて来ている。
biberやpurcellに至っても、全てこの数年に再発見されている作曲家で、日本ではそのほとんどの曲が本邦初演の曲となるのだよ。
何故、今になって、そういった無名の優れた作曲家達の作品が日の目を見るようになったか??って?
それは、パソコンの発達に起因するのだよ。
昔だったら、多くの教会や図書館に埋もれていて、数百年の間、一度も日の目を見る事がなかった古文書が、パソコン上で公開される事によって、世界中の人が見る事が出来るようになったという事なのだよ。
それと、古文書の中から、楽譜を起こすという作業は、こんにちまで、職人の手技で楽譜起こしされていて、大変な手間とお金が掛かったのだよ。
しかし、パソコンの発達で、手軽に楽譜起こしが出来るようになったのだな。
finale等のノーテーション・ソフトの開発と発達によって、非常に安価に珍しい曲が出版されるようになったし、出版社を介しなくても、個人や図書館がoriginalで楽譜を出版出来るようになった事が、今まで膨大な古文書の中に埋もれていた、優れた作品を、もう一度、世の中にappealする事が出来るようになったからである。
こんにちの私達はそういったこれまでの歴史上にない恵まれた環境に生きている。勿論、この10年、20年に限った話である。
先程のfinaleというノーテーションのソフトでも、始めて発売された時には、30万ぐらい、というか、以上したのだよ。それが、発売から10年以上経った今では、5万とか9万とかまで安くなっている。それも、一般の人達や研究者が手軽に自分の研究を発表出来るようになった一つの理由なのだよ。
そういった恵まれた環境の中で、更に、自分の独自性を追求したければ、その研究の仕方の方法論を学ぶべきである。
誰も研究していないのだから、「自分の主張が正しい。」と主張したいのなら、何故に正しいのかという論理性をトコトン追求する事だよ。
幾ら自分が情緒的に正しいと思っても、それが単なる自己満足的な感情論であり、情緒論ならば、それは論文としての態はなさない。
多くの人達を説得するには、その主張を裏付ける普遍的な論理性が必要なのだよ。
齢 60歳も後半を超す頃になると、周りの人たちから「芦塚先生、 60を過ぎると記憶力が減退しますよね! 」と、雑談の中で、同意を求めて、話しかけられることがよくあります。
その時に、私が必ず答える事にしている定石の回答は 「歳をとって減退したのは好奇心であり、記憶力では無いのです。 」 というと、ほとんどの人が驚いた表情をするのだが、しかし納得はする。
しかし、これはあながち歳をとった人だけに言えることではなく、寧ろ年齢には関係がない。
平和ボケと過保護社会の日本独自の無関心なのだよ。
だから当然、一般よりもかなり優秀な子供達であるはずの、教室の子供達も、世間一般の子供達と同様に、自分の身の回りの事であったとしても、身の回りの事に極端に興味が薄く、それが大好きな音楽の勉強(オーケストラの練習) 等の勉強であったとしても、なかなか興味を持って、覚えようとしないのが、普通なのだ。
という事で、私のレッスンの殆どのconceptは、子供たちが興味を持つ事を喚起するためのレッスンである。