私が、病気で入退院を繰り返し始めて以降は、現実的に私に弟子が一人もいなくなってしまったので、今現在は、その領域の区別がうやむやで曖昧になっていますが、今は私の指導している生徒、全員がそのものずばり生徒なのですよ。
ちなみに、父兄の間では、生徒と弟子の違いは、生徒の中の一番優秀な技術を持った生徒が弟子だ・・・という勘違いがあります。
或いは、音楽大学に進学する音楽専科の生徒が、芦塚先生の弟子だ、と思い込んでいる人達もいます。
しかし、それは根本的に、間違いです。
生徒と弟子の違いは年齢や技術力の違いではないのです。
では、何が違うのか??
それは意識なのですよ。
私が常日頃から、生徒達に言っていて、100年経っても理解して貰えない言葉、proになる秘訣は「1%の努力と99%の意識」なのですよ。
当たり前の事なのですが、弟子は、弟子入りをした人達の事を言います。
弟子入りをするという事は、先生と日常生活を共にするという意味なので、どんなに優秀な生徒であっても、弟子入りをしない限り生徒なのですよ。
「江古田詣」のPageに詳しく書いてありますが、教室から留学した生徒や、音楽大学に進学した生徒、それにコンクール組の生徒達も、生徒であって、芦塚先生の弟子ではありません。
それは、その生徒達の将来の目的が教室の目的とは違うからです。
「何故??」って???
音楽は技術ではなく、考え方、つまり意識なのです。
proになる秘訣はproの考え方と日常の生活態度(日常の姿勢)を学ぶ事なのだからです。
寝て、起きる迄の、いや、起きて、寝る迄の師匠の態度に、学ぶべきものが隠されているのです。
こんな時にも、あんな時にも、やはり、人の上に立つ人は、少し考え方が違います。
その違いを学べれば、100%、proになる事が出来るのですよ。
京都の有名なお豆腐屋さんが歳を取っても、一人も弟子がいないので、京都の市長さんが、「あなたの味を残すために弟子を取りなさい。」とアドバイスしたら、そのお爺さんから、「豆腐を作っている所を秘密にした覚えはおまへん。盗めばいいんどす。」と言われてしまった」、とその市長さんのessayの本に書かれていました。
巷には、料理教室というのがあります。
でも、その教室に来ている生徒達が、皆、同じ材料を、同じ分量入れて、同じように、火加減をするのですが、皆、味が違うのですよね。
先生と同じ味にはならないのですよ。
以前、江古田詣をしていた生徒達がいます。
お泊りで江古田に来て、教室の雑用を手伝って帰るのですが、江古田詣を始めると皆驚く程、楽器が上手になります。
だから、「教室の雑用を手伝っている間に、先生から暇を見つけて楽器を指導して貰っているのだ。」・・という噂が父兄達の間に立った事があります。
しかし、先生達は、lessonの無い時には、教室の事務や雑用で忙しいので、お手伝いをする内容の説明だけで終わってしまいます。
その生徒に楽器のlectureをする時間は、絶対的にありません。
それでも、江古田詣の生徒達は皆上手くなるのですよ。
不思議です。
というか、それが私の言っている「1%の努力と99%の意識」と言う事なのですがね。
先生達がproとして、生徒達のために仕事をしている所を見て、学ぶ事で、音楽に対する密度が出るのですよ。
学校のように、その時間に、その場所に行って教えて貰うものに、職業の技術はないのですよ。
ヨーロッパの音楽大学でもそうですが、音大に入学するのは簡単です。
1年間は誰でも入れるでしょう。
でも、1年後には、その大学で勉強が続けられるかのテストがあり、殆どの生徒がそれで落ちてしまいます。
私達の業界では、留学生とは3年、4年間、その先生の元で勉強した生徒だけを言うのです。
1年で帰国した人達には、遊学生としか言わないのです。
聴講生も同じです。
何年聴講したとしても、留学生とは根本的に違うのですよ。
そこにも、意識のランクがあるのですよ。
という事で、今回は、You Tubeで良いkadenzを見つけて、aircheckで書き取って・・・・と考えていて、唯一、時代錯誤でないkadenzをchoiceしました。
結構、短めのkadenzなので、梨紗ちゃんの聴音の勉強を兼ねて、aircheckで書き取らせて、私がそれをfinaleで清書して、間違えたpassageや変な進行の場所を訂正をして、orchestraの練習用に、使おう・・・と、思っって、finaleに入力して、少々、良くない所や、間違いのpassageを修正して、print outして、牧野先生に持って行ったののですが、牧野先生からは、「本番で演奏するkadenzとは別のkadenz両方オケ練習で弾かせるのは、・・・・????」とclaim(難色)が入っったので、本番に、彼女が弾く私のoriginalのkadenzのshortcutversionを作るように言われたので、急遽また、別のkadenzを作る事になってしまいました。
まあ、・・・だとしても、今日中には、作ってしまう予定です。

kadenzのshortcutversionの必要性について
前回の発表会でも、練習の時からsoliste達が、kadenzが終わって、演奏をorchestraに渡す時のtimingが、皆さん、何とも下手なのですが、kadenzを繋げて、弾けるように、自分で作るように、宿題を出したのですが、結局誰一人、その宿題をやって来る生徒はいませんでした。(これは、ひかりちゃんや緋依ちゃん達のお話ではなく、上級生のお話です。)
逆に、小さい生徒の場合には、kadenzをorchestraから貰う練習と、kadenzが終わって、orchestraに渡すための練習をしなければならないからです。
kadenzの最後のtrillで、orchestraに渡すのですが、その場合には、kadenzの最後のtrillは、orchestraと同じtempoになっていないと、上級生が、元のtempoに戻れないのですよ。
kadenzのorchestraへの受け渡しの勉強には、orchestraが必要なのですが、kadenzのinと、outの練習が必要なだけで、kadenzの真ん中の部分は、lessonで先生に見て貰えば良いので、オケ練習の時には必要はありません。
という事で、上記の宿題の話になるのですが、皆さんkadenzに入ったら、ブチっと音楽を切って、次のオケに渡すpassageだけを弾いてしまうので、kadenzの練習にはなりません。
本当は、kadenzをちゃんと毎回演奏して、入りとoutを練習すると良いのですが、それは時間の無駄です。
という事で、kadenzの縮小版を作るように宿題を毎回出しているのですが、その宿題を・・・と、da capoで続きます・・・。
kadenzのorchestraとの合わせは、上級生にとっては時間の無駄になるので、完全版は、soloのlessonの時にでも、Piano・Begleitung (伴奏)と一緒に、ちゃんと練習しておくと良いのですが、そのlesson時間が全く取れないので、今は、本番だけの当てずっぽうの場当たりの演奏になってしまっています。
困ったものです。
という事で、kadenzの受け渡しの話が続きますが、普段のオケ練習の時では、orchestraは、常に与えられた一定のtempoの中で、練習しているのですが、soloを勉強している生徒は、kadenzの練習の出来具合が、毎回違うので、orchestraに渡すtempoの設定が微妙に違うのです。
大声で「イチ!ニ!サン!ヨン!」と怒鳴りながら指揮棒を振っても、それは生徒の練習の出来の問題なので、tempoが微妙に毎回違うのですよ。
だから、切れ目なく、kadenzから、orchestraへの受け渡しが出来るようなkadenzが必要なのです。
その時に大切な事は、orchestraに渡すpassageだけは、本番のkadenzの演奏と同じpassageで、しかも同じtempoとtimingでなければなりません。
という事で、kadenzの短い簡易versionの譜面を急遽、作成して、練習する事にしました。
ひかりちゃん達のように、小学生の場合には、私がそれを作っても良いのですが、本当は、上級生なら、kadenzの簡易versionは自分で作れなければなりません。
proの人達との合わせの時には、その場の雰囲気で、proの人がその場で、即興で演奏してくれるのですがね。
kadenzに入る時には、kadenzの入りが終わって、kadenzの渡しのpassageに入る時に、音楽をブチっと、切ってはいけません。
あくまで、本来のkadenzの縮小版でなければなりません。
参考までに: 私のkadenzの縮小版です。
間の9小節を省略して、kadenzのinからoutまでの8小節ですが、切らないで(途中で音楽を止めないで・・)そのままorchestraのtuttiに入れます。
本来の、kadenzも1分未満の短いものですが、練習の時には、その1分ももったいないのですが、だからといって、orchestraの渡し部だけでは、前回のような不安定さが残ります。だから、入部から、少し真ん中のpassageをsuggestしながら、渡し部に入ります。
これで、kadenzのminiature版が出来ました。
間の9小節というのは、その間の9小節が省略されたという意味で、空白の小節という意味ではないので、そのまま、繋げて演奏します。
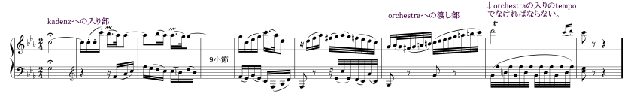
さて、kadenzのお話から、Ⅱ楽章のお話に戻って・・・
比較的に淡々と演奏されるⅡ楽章なのですが、Bでは、themaが展開されて、始まります。
5小節目auftaktから、甘えるような感じでstrettoに演奏します。
7小節目はその返しでおさめるように演奏します。

勿論、古典的な範囲内のrubatoである事は、とても大切で、必要以上に大きくtempoを動かしてはいけません。
Metronom的には、メモリの1.2の範囲でしょう。
次のpassageは、slurがarticulationslurで、書かれているので、演奏をする人が、指使い等をミスしやすいので、参考までにphraseslurを書いておきます。
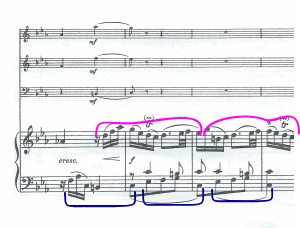
特にこの左手のphraseの拍頭迄のphraseの区切りは、非常に大切であり、しかも、右手のmelodieのslurとは、合わないので、特に意識して注意する事が大切である。
また、右手のaccenttrillは、phraseの区切り(所謂、ピヨピヨ奏法)のphraseを強調するためのtrillなので、拍節奏法の強拍を意味する分けではない。
拍節法の強拍は、当然、2.3小節目の付点8分音符になります。

このJ・C・Bachは、kadenzを中心としてお話を進めて来ましが、なんと、なんと、Ⅲ楽章にはkadenzがありません。
楽譜でチョッと、checkしてみたのですが、kadenzはおろか、eingang(episode)すら入るスペースはありません。
構造式というか、Ⅲ楽章の形式は、本来的にはrondo形式になるはずなのですが、もっと、simpleな歌謡形式で作曲されていて、最初のthemaであるmelodie Aが、Variationして行くだけの極めて単純な形式です。