
������A��������l���u�^�C�}�[�������Ă���H�v�ƁA��������A�u�^�C�}�[��T���Ă���ԂɃp�\�R���̍�Ǝ��̂��I��邩��I�v�Ɖ����ė����B
�������ɂ��̎��̍�Ǝ��̂́A�����̃^�C�}�[��T���Ď����ė���ԂɁA�o���オ���Ă��܂���������Ȃ�����ǂ��A���̎��⎟�̎��̍�Ƃ��S��������Ƃ𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ȃ�A�^�C�}�[�Ŏ��Ԃ��v�鎖�́A���Z�ɂȂ�E�E�Ƃ�������Y��Ă���̂ł���B
���Z�Ƃ́A����������5�~�A10�~�̒P�ʂ�ςݏd�˂đ傫�Ȏ��Ԃɂ���̂��Ƃ����������Y��Ȃ̂���ȁB
���\��ł͎q���B�̏o����̎��Ԃ̒��ӂŁA�u��l15�b�i�s���x�ꂽ�Ƃ���ƁA�Ō�̐l�̏o�Ԃł�30���̒x��ɂȂ�̂���I�v�ƁA���ӂ��Ă���̂ɂˁH�H
�E�E�E�E�Ƃ������A�����������A��̎��́A�l���悤�Ƃ͂��Ȃ��̂��ȁH�H
����́A���ɂ����߂��Ȃ��̂ŁA�{���͈ꎞ�������Ȃ̂���B
���[���Ŏd���𗊂ނƁA�u����������A���o���Ȃ��̂Ō�ŁA���܂��B�v�ƕԎ����Ԃ��Ă���B
���̗��R�͂��̓s�x�F�X�ŁA�肩�ł͂Ȃ����A�������A���ǂ̏��A���̐l���A��Ŏd�����������͂Ȃ����A���̎d�����I����������Ȃ��B
������A��낤�Ƃ��Ȃ��l�i���C�̂Ȃ��l�j�̂���܂�̌�����ł��B

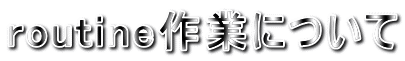
�@���Z�̒�`��ƁA���邢�̓��[�e�B����Ƃɂ́A�~�X�����Ȃ�����Ƃ����Ӗ�������B
�Ⴆ�A���f������n�鎞�ɂ́A�u�E�����āA�������āv�Ƃ����̂�����B
�ł��A�������ꂪ�h�C�c��������A�u�������āA�E������v�̂����A����́A�����ʍs�ƉE���ʍs�̈Ⴂ�ŁA���ꂼ�ꎩ���ɋ߂������Ɍ��Ȃ��Ɗ댯������E�E�Ƃ������R�œ�����O�̘b�ł���B
�ł��A���{�l�̓h�C�c�ł��E�����č������悤�Ƃ���E�E�E��������[�`���̈Ӗ����������Ă��鎖�Ɍ���������̂���B
��������ɓ��ěƂ߂�ƁA���̎���ŁA���^�̃e���r�����̂����A�X�s�[�J�[����ʂɑ��āA�����߂��āA��ʑS�̂ɋ����āA�r�r���������\���邳���o��悤�ɂȂ��āA�����Ȃ̂ŁA�O�t���Ń{�[�Y�̃X�s�[�J�[�����B
�ʔ̂łQ�@�킠�����̂ŁA�S�O�Ȃ������������̂����A�V�����@��̓e���r�̃I���I�t�ƃX�s�[�J�[�̃I���I�t���A�����Ă����̂����A�����������������S���Ȃ���Ă��Ȃ������̂ŁA���������āA���s���Ă��܂����B
�l�i���啪������̂����A����Ȃ����̎��Ȃ̂�����A�����ŃI���E�I�t�̏o���鍂�����̋@�킪�ǂ������̂����A�ԕi�͏o���Ȃ��̂ŁA���߂č������̂܂g�p���Ă���B
�Ƃ������ŁA�e���r�����鎞�ɂ͗ǂ��̂����A�e���r���������ɁA�u�e���r���ɏ����āA�X�s�[�J�[�������v�̂��A�u�X�s�[�J�[�������āA�e���r���������v�̑I����������̂����A���ꂪ���ۂɂ́A�ƂĂ��d�v�ȑ�Ȏ��ɂȂ�̂���B
��ʓI�ɂ́A����ȁA���ׂȎ��͂ǂ���ł��ǂ��悤�Ɏv��ꂪ�������A�d���ƂȂ�ƁA�����͍s���Ȃ��B
�܂�A�e���r���ɏ����ƁA���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�X�s�[�J�[���������̂��A�ۂ��́A������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B������A�X�s�[�J�[���ɏ��������A�����Ȃ̂���B
�X�s�[�J�[���ɏ����ƁA�e���r�̉����������Ă��܂��̂ŁA�X�s�[�J�[�̓d������������m�F�o����B
���̏�ŁA�e���r�������~�X�͐�ɋN����Ȃ��̂���B
���ꂪ�A��`��Ɓiroutine��Ɓj�������ł́A��ȈӖ��i��|�j�ł�����B
���{�ł́A�q���������Ɍ��āA�����o���Ȃ���A�E��������A�ԂƂԂ����Ă��܂���������Ȃ��̂���B
�E���Ɍ��āA������ݏo�������ɁA��������Ԃ�����ė����Ƃ��Ă��A���̎Ԃ̑����Ă��铹�H�ɂ͖�������������̂�����A�ً}���͖��Ȃ��o����̂���B
���ꂪ�A�u�E�����āE�E�E�v�̈Ӗ��ł���B
�Ԃ̑O�����āA�E�����m�F���Ă���A�Ԃ��o���E�E�Ƃ����̂��A�����������m�F��ƂȂ̂��B�����ӂ�ƂԂ����Ă��܂��B
�q���ɂƂ��Ă��A�����́A�Ђ���Ƃ�����A��l�ɂ��Ă��A�����������������ẮA����̐����ɉ����āA�ƂĂ���Ȃ̂���B
�Ԃ̉^�]�ł��A�悸�͑O���m�F�ŁA����m�F�ł���B
���ꂩ��Ԃ����B
�O���m�F�����Ȃ��܂܂ɁA�Ԃi������ƁA�厖�̂������N�����Ă��܂����낤��B
�S�����l�̃~�X�ŁA�ǂ��Ƃ��~�X������B
����̓p�\�R����file���g����Ƃł���B
template�Ƃ��āAfile���g�p�����肷�鎞�ɁA�d����������x�o���Ă���ۑ�����ƁA����file������ď����Ă��܂���������B
�����́A��Ƃ̉ߒ��ŁA�~�X��Ƃ��Ă��܂��A�ŏ��ɖ߂낤�Ƃ������ɁA�ŏ���file�������āA�ǂ����悤���Ȃ��Ȃ鎖���ǂ�����̂��B
���[�e�B����Ƃ̌�����Ƃ��ĂȂ�Atemplate�ɂȂ�file���ŏ����u�ʖ��ŕۑ��v�����āA����file�ō�Ƃ�����Ɨǂ��̂��B
�Ⴕ�A����ĊԈႦ���Ƃ��Ă�template�͎c���Ă���̂�����A�ŏ��ɖ߂�Ηǂ������Ȃ̂�����E�E�B
��������A���k�����l�̊ԈႢ�������B
������������\���̏�ɐV�����Ȃ̕\��������Ă��܂��āA���ǁA�������͂��Ȃ̂ɁA���̓��̈�������Ă��܂����A�Ƃ��������B
�܊p��������������܂��A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����A����͖c��Ȏ��Ԃ̖��ʂł���̂́A�����̗��Ȃ̂����A��������������Ƃ��l�́A�S�Ăɓn���āA���l�̃~�X������B
�ł��A���̐��k������Aroutine��Ƃɂ��Ē��ӂ������ɂ��ւ�炸�A�������܂��A�����~�X�����Ă����B
�u�搶��template������������Ȃ̂ŁA���R�A�搶���ʖ��ŕۑ��������E�E�E�ƁA�v������ł����v�E�E�Ƃ����ꂵ���ȕى������Ă����B
�������A����͕ى��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�搶��template��������̂�����A����template�̕ۑ��͍ς�ł���B
����template���g���č�Ƃ����镪���Ȃ̂ŁAtemplate�͓��R�u�ʖ��ŕۑ��v���Ă����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����āA�m�F�͎����ł���̂��m�F�ł���A�l��������Ǝv�����ނ̂́Apro�Ƃ��Ă̍�Ƃł͂Ȃ�����ł���B
�l�ɐӔC���������Ԃ��Ă��ẮApro�ǂ��납�A�Љ�l�Ƃ��Ă̎d���͏o���Ȃ��̂���B
���[�e�B����Ƃ̒�`�́A�����������n�������~�X��h�����ɂ���̂����A�����������~�X���悭����l�B�́A���̃��[�e�B����Ƃ�^�ʖڂɂ��鎖��ӂ�̂���B
�~�X����ɔƂ��l�B�́A�����̃~�X�Ȃ��鎖�͂������Ƃ��Ă��A���P�����悤�Ƃ͌����Ă��Ȃ��̂���B
������܂��A�~�X��Ƃ��B
mail�������ė����A�Ƃ������ė��Ȃ������E�E�Ƃ��́A�n�������~�X���A�����������ė������[����ǂݕԂ��K�����Ȃ�����A�i�X�A�c��Ȗ��ǃ��[���̒��ɖ�����čs���B
�u�����́����������𗊂̂����E�E�E�v�Ƃ����ƁA�Q�ĂĖc��ȃ��[���̒�����A���ɂ��Ǝ��ԂŌ��������āA����Ƃ̎��A�T���o���āA�u�����A�Y��Ă����v�Ƃ����B
�Y��ċ������̂́A���������A�ގ��Ƃ̂��f�[�g�E�E�E���ł����āA��ʎЉ�̉�Ђ̎d���ŁA���܂ꂽ�d����Y�ꂽ��A���A��Ȃ̂���I�E�E�E��I�I
�@�ގ��Ƃ̃f�[�g�́A��l�Œ��ǂ��P���J������ςގ�������ǁA�d���ł́A�u�o�������ۂ��H�H�v�u��������A���Ȃ����H�H�v�ł����āA���̎d���ɁA�u�Y��܂����I�v�Ƃ����ى��͂Ȃ�����ˁB
�@outlook�ł́A�����������~�X��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�^�O�̒��Ɂu�t���O�̐ݒ�v�Ƃ������ڂ�����B
�����ŁA����mail�ɁA�u����A�܂Łv��t���鎖���o����B
����������A���T���◈�T���Ƃ������悤�ɁA�܂ł̐ݒ�����鎖���o���邵�A�܂��́Aoutlook�ɂ�ToDo������̂ŁAToDo���g���̂��A��̎�ł���B
�g�т̏ꍇ�ɂ́A�����������@�\���Ȃ��̂ŁA�����ی���t���鎖�ɂ��Ă���B
�����d���Ƃ��Ĉȗ�����mail��A���肩��d�����˗����ꂽ�ꍇ�A�����́A�����̔��������������u�ی�v�ɂ��鎖�ɂ��Ă���B
�ܘ_�Amemo�����g���̂����Amemo���ɂ́A���������X�g�Ƃ��Ă̎g�p�̕��������̂ŁA�d�����h�������ꍇ�ɂ́Amail�����̂܂܂̕����A�������ǂ�����ł���B
�������A��������Ă����Ƃ̑����́Aendless��Ƃł���ꍇ�������B
�_�����ȓ��͊�{�I�ɂ�endless�̍�ƂȂ̂ł��B
�u��Ȃ����������I�v�Ǝv���Ă�����A���炭���K���Ă���ƁA�܂��F�X�Ǝ蒼������ӏ����o�Ă��܂��B
������A���̓s�x�A�y���̎蒼�������Ă�����A�搶�B�ɓ{���Ă��܂��܂����B
�u�����y���͐��k�ɓn�����̂�����A���X�ς��Ȃ��ł�I�v�Ƃ��A�u�{���ɂ���Ŋ����e�ł����H�v�Ƃ��ł��B
�ł��A��Ȃ�endless��ƂȂ̂���B
�d���͊������鎖�͂Ȃ��̂ł���B
�ǂ�ȑ�Ƃ̍�i�ł��A��������Ƃ������͗L�蓾�Ȃ��̂��ȁB
�_�E�r���`��Q�[�e�ɂ��Ă��A���ʂ܂Ŏ����̍�i���蒼���������Ă���̂ł���B
�ܘ_�A����͍�ȓ��̍�i�����̘b�ł͂Ȃ��AP���������ₖ�����������̗��K�ɂ��Ă������Ȃ̂���I�I
�����q���B�ɁA�{���ɋ��������̂́A�����̏��Ȃ̂����ˁH�H
���\��̂��߂̊��Ƃ��č�Ȃ��ꂽ�Ȃ́A���\��I���ƁA������́A���Ȃ͏I������͂��ł���B
�������A���̏ꍇ�ɂ́A���\��I����Ă��̋Ȃ̖������I�������ł��A���̋Ȃ𐄝Ȃ�������ꍇ�������̂���B
���̋Ȃ̉��t���I�������ł��A�Ȃ̐��Ȃ��d�˂镪���Ȃ̂ŁA���R�A���t��̓����ł������Ƃ��Ă��A�i�����̑ΊO�o���ł������Ƃ��Ă��A�o���҂��q���B�ł������Ƃ��Ă��A�܂�A�@���Ȃ�������ł������Ƃ��Ă��j�C�ɐH��Ȃ���Γ����ł����C�ŕύX���܂��B
���ꂪ����policy�Ȃ̂�����ˁB
�q���B���w��ł���Ȃɂ��Ă��A���\��I����������E�E�ƌ����āA���ꂪ���i���������ł͂Ȃ��̂ł��B
�����A���̎q�������y�ɐi�ނ����Ȃ̂Ȃ�A�E�E�E�ہA�y����w�Ԃ̂Ȃ�A���ł����t�o����悤�ɂ���̂��ړI�̂͂��ł��B
����pro�Ƃ��ĉ��y�̓��ɐi�ނƂ�����A���i������E�E�Ƃ������͗L�蓾�܂���B
���̃����N�ł͍��i�͂��邩������܂��A���̃����N�ō��i�����̂Ȃ�A���̃����N�킵�Ȃ���Ȃ�܂���B
���̋Ȃ̉��t����������Ƃ������͐�ɗL�蓾�Ȃ��̂ł���B�A�n�b�I
�w�Z����ł́A�P�����I���Ƃ��̉ے��͏I������B
�������A�d����endless�ŏI��鎖�͂Ȃ��̂���B
���ɁA���y�̏ꍇ�ɂ͂ˁH�H
���\��́A��̋��ɉ߂��Ȃ��̂���B
�����Ȃł��A���̉��t���repertory�ɏ��A�܂��A���K���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ہA���̗\�肪���������Ƃ��Ă��A���K��endless�ɑ����̂���B
���H�̂悤�ɁE�E�E�ˁH�H�H
�u���H�͑����`��I�ǁ`���܂ł��`�`�v���Ȃ�H�H�H
����́A���Ă̌|�p�A�E�l�̋Z�ɉ����āA�����́Aathlete�B�ɂƂ��Ă��������ƂȂ̂ł��B
�@�܂ÁA��Ђɓ������V�lOL�B���܂��A��ЂŎw�������̂��u�������݁A�d�b�̎�t�A�R�s�[��Ɓv�̎O�ł��B
���ꂪ���Ȃ�A��ɐE�i�������Ɍ����̂Ȃ玑�i�Ƃ��������ȁH�j�������ďA�E���邩�A�i�v�A�E����悢�̂ł��B
������������悤�ɁA�F�X�Ȏd����project�́A�K���A����̒�^��Ƃɐi��ōs���܂��B
�����ł́A���������������g���Ċy���𐧍삷���Ƃł�������A�z�[���y�[�W�̍�Ƃ�����܂����A��ԕ�����Ղ���ƂƂ��ẮA��ʓI�ɂ́u�R�s�[�̍�Ɓv�ł��傤���ˁB
�������A�R�s�[�̍�Ƃƌ����Ă��A�ƒ�̃R�s�[��ƂƂ͈���āA��Ђł̃R�s�[�͕��G�ł��B
�܂Ƃ��͖ܘ_�A���ʂ̃R�s�[��Qup�A���{��Ƃ�ƁA���ꂱ���G���h���X�Ŋo���镨������܂��B
���̋Ɩ��p�̃R�s�[�@�́Ascanner��Page��ǂݍ��ނƁA���������v�Z���Ȃ��Ă������ŁA���ʂ̂Qup�̐��{�R�s�[���o���܂��B
���{�����鎞�ɂ́A�K���E�����Page�ɂȂ�܂��B
���ʂ̃y�[�W�͂P���̃R�s�[�̂Qup��������A�\�ʂ͂QPage�ڂƂRPage�ڂ�Page�������킹��ƁA�T�ɂȂ�܂��B
���ʂ͓��R�A�PPage�ڂƂSPage�ڂ�����A�����TPage�ɂȂ�̂ł���B
�R�s�[�������Q���̏ꍇ�ɂ́A�WPage�ɂȂ镪���Ȃ̂ŁA���v�͂X�̐����ɂȂ�܂��B
�֑��ł����A�R�s�[�������R���̕��͂ɂȂ�ƁA�Ō�̃y�[�W���i�����Ă��Ȃ����Ă��j�P�QPage�ڂł�����A���̍��v�͂P�R�ɂȂ�܂��B
������A�QPage�ڂ̗��̃y�[�W�́A�H�H
���ꂪ���{�̌����ł��B
����͉�Ђł͏펯�͈̔͂ł��B
�l�̏ꍇ�ƈ���āA��Ђ̃R�s�[��Ƃ̏ꍇ�ɂ́A�P���ȃR�s�[��Ƃł��A�����������m�����K�v�ɂȂ�̂ł���B
�@�R�s�[��Ƃƌ����ƁA�uA4�ŕ\�ʂ�����print out����悢�B�v�Ɗ��Ⴂ���Ă���l�B�����܂����A��ЊW�ł̍�ƂƂ��Ȃ�ƁA�R�s�[��Ƃƌ����ǂ��A����ȊȒP�ŒP���ȍ�Ƃł͂Ȃ��̂ł���B
�P�ɁAA4�̔������R�s�[����Ƃ��Ă��A�P�ɂP�C�Q�����R�s�[����ꍇ�ƁA���S�����R�s�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����j���O�R�X�g�̖�肪�N�����Ă��܂��B
�Ɩ��p�̃R�s�[�@�̏ꍇ�ɂ́AA4�A�P���̃����j���O�R�X�g��A3�̃����j���O�R�X�g�������ꍇ�������̂ł��B
�����̃R�s�[�@���A�Ɩ��p�̃R�s�[�@�Ȃ̂ŁAA4��A3�̃R�s�[��͓����ɂȂ�܂��B
�����畔���������ꍇ�ɂ́AA3��A4�Q�����R�s�[���āA������גf���܂��B
��������ƁA�R�s�[�㎆�オ���Ȃ��čςނ���ł��B
�����̃R�s�[�ł��A���������Ƃ����R�s�[�オ������܂��B
�ܘ_�A�R�s�[�@�̃��[�X��́A�����̉ƒ����������Ȃ��炢�ł��B
�ł�����A�R�s�[��̌o��Ƃ����ǂ���ЂƂ��Ă͔n���ɂȂ�Ȃ��̂ł���B
�Ƃ������ŁA��Ђ�OL�ł��A�����ƃR�s�[��Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂łɂ́A��N�߂��͊|����̂ł���B
�d�b�̉��́A�R�s�[��Ƃ����A�����Ƃ����Ɨy���ɓ���B
�P���Ȍh��@�̖������A��ЂƂ��Č����ėǂ����Ɛ�Ɍ����Ă͂����Ȃ��������邩��ł��B
���̎��������Ђ̑����i�����j�ɂ�����鎖�����Ă���̂ł��B
�d�����~�X���Ȃ��悤�ɂ�����@�_�ŁA�L���Ȃ̂̓n�C�����b�q�̖@���ł��낤�B
�ނ́A����H��Ŕ��������J���ЊQ5000���]�v�w�I�ɒ��ׁA�v�Z���A�ȉ��̂悤�Ȗ@�������B�u�ЊQ�v�ɂ��Č��ꂽ���l�́u1:29:300�v�ł������B���̓���Ƃ��āA�u�d���v�ȏ�̍ЊQ��1����������A���̔w��ɂ́A29���́u�y���v���ЊQ���N����A300�����́u�q�����Ƃ����E�n�b�Ƃ����v�����i�낤����S���ɂȂ�j���Q�̂Ȃ��ЊQ���N���Ă������ƂɂȂ�B
�n�C�����b�q�̖@���́A�悭�m���Ă���@���Ȃ̂����A�����Ɋw�Ԑl�͏��Ȃ��B
�d�����o���悤�Ƃ���l���A�R�s�[���~�X�����Ƃ���B
�������A���̃~�X�ɂ́A���̐l�̐��i�ł���A���̐l�̎d���̎d���̖��_�����̃~�X��U�����Ă���ꍇ��������������̂��B
���̂��N�����l�́A�������ߐM���Ă���B
�u��Ɏ����͎��̂͋N�����Ȃ��v�ƐM���Ă���B
����ŁA�q�����Ƃ���~�X��A�n�b�Ƃ���~�X�ɂ́A���Ȃ����鎖�͂Ȃ��B
�������A��������𒍈ӂ���ƁA���̐l���u�R�s�[��Ȃ�āA1��2�~3�~�̐��E�Ȃ̂ɁA����匾���I�P�`���I�I�v�Ƃ����A�v���Ȃ��B
����1�~�̃~�X���������i���A29�̑傫�ȃ~�X�ƁA1�x�̋����ꂴ��~�X�Ɍq����E�E�Ƃ́A�v��Ȃ��̂���B
���́A�Ԃ̖Ƌ������������̐��k�B�ɂ́A�u�q�����Ƃ���^�]�͐�ɂ��Ȃ��悤�ɂ��鎖�v�u�^�]���ɁA�q�����Ƃ�����A���̓��A����͓����q���������Ȃ��悤�ɒ��ӂ����Ȃ����B�v�Ƃ������𒍈ӂ�����B
�l�Ԃ́A���̓����̓��ŁA�R���f�V�������ς��B
������A���̓��Ƀq�����Ƃ���Ƃ�����A���ꂪ���̓��̒��ӓ_�ɂȂ�̂���B
�����悤�ȃ~�X���K���A���̓��̓��ɂ���B
���̓��ɂ́A�܂��ʂ̃q����������B
�q�������Ȃ��Ȃ�ƁA����͕s���ӂł���B
������Ȃ̂���I�I

![]()
���\�A�搶�B�̍s�������Ă���ƁA�S�����Z�ɂȂ�Ȃ��s�������Ă���ꍇ�������̂ł��B
�������グ��Ɛ肪�Ȃ��̂����m��܂��A�������A����͂��̐l�̎d���ɑ���p���̖��Ȃ̂ł���B
���̎p�����ς��Ƒ��Ă̍s����ς��鎖���o���܂��B
��̎p���ŗǂ��Ƃ���A�悸�A��Ԑg�߂ȏ�����n�߂�Ηǂ��̂ł��B
���̈�̗��������Ƃ���A����́A�u�����̎d�����I���܂ŁA���̐l��҂�����v�ƌ������ɐs����ł��傤�ˁB
�m���ɁA���̐l�ɂƂ��ẮA�����̂��ׂ��d�����D��x�͍��������m��܂��A�������A���̎��ԁA���̐l�́A�����������Ȃ��ő҂��Ă���E�E�E�Ƃ��������Ȃ̂ł��B
����͋��ɂ̎��Ԃ̖��ʎg���ɉ߂��܂���B
�����̏���������Ȃ��ƁA�l���g�����͏o���܂���B
�����I�Ɏd�������Ȃ��čs������ł͂Ȃ��E�E�Ƃ������Ȃ̂ł��B
����͂��̂܂܁A�����A�l���g���闧��Alevel�ł͂Ȃ��E�E�Ƃ������ɂȂ�܂��B
���̒m�荇���ŁA�d���̏o����Ƃ����Ӗ��ŁA�ƂĂ����h�o����o�ŎЂ̕ҏW�������܂����B
�������A�ނ͗]��ɂ��d�����o���߂���̂ŁA������{�����鎖���o���܂���ł����B�����ɗ��ނ̂����A�����ł����������������ł��B
�ނ��A�h�]�ŁA�ҏW�����J�������ɁA10�l�̕ҏW�̐l�B��2�N�ԑ��Ă̎d����stop���āA�ނ̂���Ă����d���̌�n�������������ł��B
�������A�ނ��ǂ�ȂɎd�����o�����Ƃ��Ă��A10�l�̕�����{�����āA�d��������̂Ȃ�A�����Ƃ����Ƒ傫�Ȏd�����o�����͂��ł��B
����́Atop�ƕ����̈Ⴂ�ł���B
�z���̃`���b�ƁA�����Ɏd���̓`�B�A���������āA���ꂩ�玩���̎d���ɓ���ƁA�d���S�̂Ƃ��ẮA�u���Z�v�ɂȂ�̂ɁE�E�E�Ƃ����v���̂ł����A�����͌����Ȃ��悤�ł��B�悸�A���ꂾ����Еt���Ă���A��������ˁH�H���ăl�H�H����A���̎��Ԃ��ܑ̖����̂���B���ꂪ�������ƃl�B
�l�̏�ɂ͗��Ă�̂�I�I

�֑��ł����U
�@�h�C�c�̊w�Z�̂������������͓��{�̋��炓�����������Ƃ͂��Ȃ�قȂ�܂��B
���w�Z4�N���̎��ɁA��w�ɐi�w���邩�A�E�Ƃɏ]�����邩�����߂āA��w�i�w�����߂��q���̓M���i�W�E���i���A����т̊w�Z�j�ɐi�w���܂��B
�@�E�Ƃɏ]������q���B�̓n���f���V���[���A�����A�E�Ɓi���A���j�ɐi�w���܂��B
�����ŁA�}�C�X�^�[�̎��i�����܂��B
�@�h�C�c�̑�w���͕s�ɁA�U������ʂɒ���܂��B
�u����ׂ�v�Ƃ����̂́A���̍��̌��t�Ŗ��������Ƃ��������̂��Ƃł��B
�@�u���́A����ȂɐF�X�ȍ��̌��t������ׂ��悤�ɂȂ�̂��H�v�Ƃ��������A�h�C�c�l�̗F�l�Ɏ��₵�܂����B
�ޏ��͋����Ă���܂����B�@
�u�h�C�c�ł́A���w���̎�����A���e����ƃM���V�����O��I�ɂȂ炢�܂��B���e����Ȃ�āA���͉����ł��b����鎖�͂Ȃ��̂����ǁA���[���b�p�̌��t�̃��[�c�͂��̓�̌��ꂩ��Ȃ�̂���B���e����̓t�����X���C�^���A��A�X�y�C����ɂȂ��āA�M���V���ꂩ��́A�p��A�h�C�c��ɔh�����Ă����܂��B������A�I�����_�ꓙ�́A�p��ƃh�C�c��̒��ԂŁA�p��ƃh�C�c���b����ƁA���ƂȂ��A����悤�ɂȂ�܂��B�v
�@�Ƃ������ŁA�z�[�t�u���C�n�E�X�ŁA�r�[�������݂Ȃ���A�u���{��͂ǂ��Ȃ��Ă���́H�v�Ɛq�˂�ꂽ�̂ŁA�u�J���������~��܂��B�v�Ƃ������t��������Ȃ���A�ܒi���p�Ƃ��A���@�����������A���̏�ň�u�ŁA�F�X�Ɗ��p�������čs���܂����B
�����āA�u�ǂ����ďo����́H�v�ƕ�������A�ޏ����u���e����͎��i���p�Ȃ̂ŁA���{��̕ω��͊ȒP��I�v�ƁA�������Ă���܂����B
�@�p���S�@V�@O�@C���������ł����A���@�Ƃ����̂́A�{���́A��w���w�ԁi�b���j�����ȒP�ɂȂ�悤�ɂ��邽�߂̂������������ł������͂��Ȃ̂ł����ˁI
���̍����炩�A���@�����@�̂��߂̊w��ɐ��艺�����Ă��܂����̂ł���B
���B�́A��̑O�̋���ŁA�p��̕��@���Ɋw��ŁA��b�͈�x���K��Ȃ��܂܂ɁA��w�܂ł��܂����B
�@������A�h�C�c�ݏZ�̓��{�l�ł��A�V���͓ǂ߂邯��ǁA�h�C�c�l�ƃE�C�b�g�ɂƂ�b�͑S���o���Ȃ��Ƃ����l�B�𑽂����܂����B
���{�l�̓h�C�c�ɗ��w���Ă��A�����ɃR���j�[������Ă��܂��āA���{�l���m�Ƃ����t������Ȃ�����ł���B
���ł́A�悸��b���K���āA���ꂩ��A���X�ɕ��@�ł����A����͑S���������Ǝv���܂���B
�\���͉�b�ɂ͂��邯��ǁA���@�ɂ͂Ȃ�����ˁB
���t�Ǝ��Z�͉��̊W������́H���āH�H�H
���t�ɂ�����A�u���@�v�͖{���I�ɂ́A��^�̊��ʂ�����̍�ƂȂ̂ł���B
���w�̌v�Z���������Ȃ̂ł���B
������A���͒��w���̎��ɁA�搶�ɉ������A�u����͌����̐��E�ł͉����Ӗ�����̂��H�v�Ɖ��������₵�Ă��܂����B
�@���Z���̎��ɁA�u�����̓���Љ�̒��̌v�Z�����Ă���̂ɁA���ŋ������o�Ă���̂��H�v�Ɓ@�A���Z�̐搶�Ɏ��₵�܂����B
�ܘ_�A���������搶�͈�l�����Ȃ������̂ł����ˁB
��ɓ���ɍs�������������u�搶�ɕ���������ǁA�����Ă���Ȃ�������B�v�ƌ�������A�ނ��u�����̉Ƃ̒��ɐ��������Ȃ�����A���𗧂ĂāA���̒��Ő��������̂���I�v�Ɩ��m�ɓ����Ă���܂����B
���Z���ł��A���̗ǂ���͈Ⴄ�ˁI�I
�l�p�l�ʂ̓�������Ȃ���B

[feedback�ɂ���]
Facebook�ł͂���܂����Ifeedback�ł���I�I
�����A�l�ɂ��̂𗊂ގ��ɁA���̐l�̎d�������č���ł��āA�Z�������ɂ͂悭�A�u��ŁA���Ԃ��o���������Ă����܂��B�v�ƕԎ�������鎞������܂��B
�ʏ�́A�����u���Ԃ��o���������Ă����܂��B�v�Ƃ����̂́A�U�ȓI�f��̌��t�ł��B
�������A��ɁA�{���ɁA�u��ŁE�E�E�v�ƌ����Ă���ꍇ������܂��B
�������A�Z�����ɂ��܂��āA�E�E�E�ŁA���̂܂ܖY�ꋎ���āA���̎d���̃I�[�_�[�͓�x�ƁA�Ȃ���Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�v�́A���[�W�[�̎d���̖@���ɂ�����悤���u��ł̎d���͂Ȃ��v�̂ł���B
�u�ł��A�{���Ɏd�����Z�����ďo���Ȃ���������v�ƁA�ى�����鎖������܂��B�ܘ_�A�d�����Z�����āA���̃I�[�_�[�̎d�����d���̃��X�g�ɉ����邱�Ƃ���o���Ȃ������̂ł��傤����ǁAselect���ꂽ���Ƃ��ẮA������Ɠ��ɗ��܂��B
��ЂƂ��Ďd����A�g����̂Ȃ�A�����Ŏ����d�����I�[�_�[���āA���̊ԕʂ̎d����i�߂邱�Ƃ��o����̂Ȃ�A��БS�̂Ƃ��Ă̎d���͒��鎖�ɂȂ�܂��B���ꂪ�A�g�̎d���̎d���ł��B
������ƁA�Ӗ������͈Ⴂ�܂����A�����A�g����d���łȂ��A��l�̎d�������Ă��āA�d�������č���ł��܂��āA���Z�����Ȃ��āA���ɊԂɍ��������ɂȂ��Ȃ������ɁA�悭���͐l�������s���ɏo�鎖���悭����܂��B
����́A�r���Ŏd���𓊂��o���āA�����̐�����|���A���A�d���ł�������ɂȂ��Ă��܂��Ă������̎d��������Ƃ������ł��B
�d���Ńo�^�����Ă��鎄���A�ˑR�������������n�߂Ă��܂��������A���߂Č����l���A�u�搶�͂��ɁA�d���𓊂��o���āA���߂ɓ������I�v�Ƃ��u���ɐ搶�����������B�v�Ƃ��A�т����肵�Ă��܂����B
���͒ʏ�ł́A�d���ɒx��鎖(���ɒx��鎖)���A�d�����Ȃ��鎖����ɂ��Ȃ����A����������Ȃ�����ł��B
�d�����ώG�ɂȂ��āA�ǂ��l�߂�ꂽ���ɂ́A�l�̓��̒��͖��ӎ��ɍ�����ԂɂȂ�܂��B
��x�A�ǂ��l�߂��č�����ԂɂȂ������ɂ́A�l�͖��ӎ��ɓ�����Ƃ����Ă݂���A�ԈႦ�����@�Ŏd����������ƁA���̃X�p�C�����Ɋׂ��Ă��܂��܂��B
�����Ȃ�ƁA��鎖�Ȃ����A�ꐶ���������قǁA�d�����t�ɑ����āA��i���O�i���s���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�������������ɁA��ԑ�Ȏ��́A��x���̍�Ƃ��O����q�ϓI�Ɍ��ߒ����Ă݂�E�E�E�ƌ������Ƃł��B
�ǂ�������A�O���猩��邩�H�H�ƌ����ƁA���̈ӎ�����x�����Č���Ɨǂ��̂ł��B
�d���ōs���l�܂�����A�����̑|��������Ƃ��E�E�ł��B
���ꂾ���ŁA�����̈ӎ����痣��鎖���o���܂��B
�����ƁA�q�ϓI�Ɍ����Ă���ƁA�d���̍�ƍs���Ńo�C�p�X�������鎖���o������A�d���̈ꕔ��l�ɗ���ŁA���Z��������A�����́A���̌��߂�ꂽ���ł͂Ȃ��A��ɂ��Ă��悢�d���������������肵�āA�菇�������������o����悤�ɂȂ�܂��B
���ꓙ����肭������x�g�ݒ������ɂ���āA��ɊԂɍ���Ȃ��d���ł��Ԃɍ��킹�鎖���o����̂ł��B
�{���ɒǂ��l�߂�ꂽ���ɂ́A�������������X�N�ɑΉ��o����\�͂��K�v�ɂȂ�܂��B
�l����Y�ސl���ǂ��l�߂��Ă����̂́A�����Ŏ�����ǂ��l�߂邩��A�����ꂪ�Ȃ��Ȃ�̂ł��B
�T���f�B�^�`�I�����A�l�Ԃ̂����������Ƃ��玩�������������āA�q�ϓI�Ɏ������������鏊����n�܂�̂ł��B
�S���w�̓��ϖ@�������Ȃ̂ł���B
�ł��A���ς�T�͂��ꎩ�̂�����B
�|��������ڂȂ�N�ł��o���邩��ˁB
�������A�l�͎������ǂ��l�߂�ꂽ���ɂ́A���̑������瓦��悤�Ƃ��鎖�́A�Ȃ��Ȃ��o���܂���B
�ǂ��l�߂��āA���Ƃ����ꂩ�瓦��悤�Ƃ���ƁA�܂��܂����ʂ�����邠�܂�ɁA�ǂ��l�߂��āi�Ƃ������A���Ɍ��킹��Ǝ����Ŏ�����ǂ��l�߂Ă���̂ɉ߂��Ȃ��̂ł����ˁj�A���ׂƂ������̓D���̒����甲���o�����͓���̂ł��B
�������ʓI�ɂ͕��̃X�p�C�����Ƃ����܂��B
���������A������Ղ������ƁA�d�����Z�����Ȃ��āA���̎d�������Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă���ƁA�p�j�b�N�ɂȂ��Ă��܂��āA�d���ɂ�������̖��ʂ⎸�s���o�Ă��܂��̂ŁA�܂��܂��d�����x���Ȃ�Ƃ����X�p�C�����Ɋׂ�̂ł��B
�������������ɁA�����玄�������������������Ă��A�N�����������������Ă͂���܂���B
�����āA���ʂ��C�^�Y���ɏd�˂čs���̂ł��B
�����������A�ǂ����܂ꂽ���ɂ����A���̂����������������̎�@���K�v�ƂȂ�̂ł��B
�����ŁA�����Ƃ����������������i�q�ώ��j�����鎖���o����A�v��ʏ�肢�����@�����������邱�Ƃ�����̂ł��B
�������A�ӔC�����������قǁA���������ӂ��Ɏ��ԂɁi�m���}�Ɂj�ǂ����Ă�ꂽ���ɂ́A�����������������i���ȕ��́j������͓̂���悤�ł��ˁB
�������Ђ̏ꍇ�́A��̍�ƍH�����A���̐l�B�ƕ��S���Ă��Ȃ����Ƃ��悭����܂��B
�Ƃ������A���ꂪ�w�ǂȂ̂ł��傤���E�E�E�B
���̏ꍇ�ł��A�d���̏d�v�ȕ����̑唼�́A�x�e�����̐l���قƂ�ǂ̎d��������̂ŁA�C����Ă���l�ɂȂ�Ȃ���A���Ԃɒǂ��Ă��܂��āA���̐l�ւ̎d���̔������A�����A��ɂȂ��Ă��܂������悭����܂��B
����͎��Z�̃��g�[�h�i�̒��ł́A�l�Ƃ̋�����Ɓj�ł͐�ɂ���Ă͂����Ȃ����i����Ȃ����j�Ȃ̂ł��B
�܂�A���Ԃ̃��O���l���Ă݂�ƁA�l�ɔ��������d���͂��̎d�����o���オ���Ă���܂łɁA���Ԃ�������܂��B
������A��Ɏd�������Ă���A�����̎d���ɂ�����A���������d������ɏo���オ��̂ŁA�����̎d�����I����Ă���A���̎d���̑��������鎖���o���邩��ł��B
�����Ɏ��Ԃ��o���Ă���A�d��������ƁA�����̎d���͈�i�����āA���̎d���Ɏ��|�����͂��Ȃ̂ɁA���̎��Ɏd�������镪���Ȃ̂ŁA���̎d�������������鎖�͏o���܂���B�Ƃ������ŁA�K�R�I�ɁA�����ɁA���̎��̎d�����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̔��������d��������������̂͌�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ������ɁA�d���͍ی��Ȃ��x��čs���Ă��܂��܂��B
���Z�́A�������������̂悤�ɁA3���A5���Ƃ������Ԃ��҂��ŁA�����1���ԁA2���ԂƂ������Ԃ�����čs���̂ł��B
�ł��A���Z�̂����ƌ����͑S�������ŁA�d���ɑ��Ă̗v�̂̈����l�́A�ꐶ�����ɓw�͂���Γw�͂�����A�����̈������ʂȎ��Ԃ𑝂₵�čs���̂ł��B
���y�̗��K�ɉ����鈰�˃��g�[�h�́A���ʂȖ��Ӗ��ȗ��K���Ȃ��āA�����̗ǂ��K�v�Œ���̗��K������E�E�E�Ƃ������ł��B
�K�v�A�Œ���Ƃ����Ӗ��́A�l�Ԃ��{���ɏW���o���鎞�Ԃ͑R���Ȃ�����Ȃ̂ł��B
�ł�����A�����łQ���ԁA�R���Ԃ������K�o���Ȃ����k���A�^�L�����t�Ƃɒ�q�����������A5���ԁA�U���ԗ��K�o����悤�ɂȂ����ƁA�{�l���e�����ł��܂����B�u����ς�A�L���ȉ��t�ƂɏK���ƈႤ��ˁ`�I�v�ƁE�E�B
�������A����܂ł́A���J�Ɉꗱ�ꗱ�̉�������āA���K���Ă����̂ɁA�w�ɔC���ăp���p���Ƒ������K���āA�������莩���̉����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���ꂮ�炢�_�o���g��Ȃ��̂�������A�����Ԃł����K�o�����ˁB
�ł��A���̋����◱���J�ɕ��������ė��K����̂Ȃ�A�w���Ȃ�A�S���Ԃ����x���Ǝv����B�v���ł��A�T���ԗ��K�o����l�͏��Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA5���ԂƂ����̂͊y��Ɍ������ė��K����Ƃ����Ӗ��ŁA�v���͊y��Ɍ������ė��K��������A�y���Ɍ������Č������Ă��鎞�Ԃ̕��������̂���B
������Ƃ��b�������Ɉ��Ă��܂�������ǁA�v�͖��ʂȎ��Ԃ��Ȃ������A�d���̔\�����A�������̊�{�Ȃ̂��Ƃ������Ȃ̂ł��B
�O���́A���̐l���d�������Ȃ��邩�痊�ނ̂�����A���R���̕��̎��Z�ɂȂ�܂��B
������A�������d�����I����āA���̍�ƂɎ��|���肽����A��炻�̎��Ɏ����̎d�����Z�����Ă��A�O���̎d�����ɂ��Ă����Ȃ���A�����̎d������i���������ɁA���̎d���ɂ͎��|����܂���B
������A�ǂ�ȂɖZ�����Ă��A�O���̎d�����ɃI�[�_�[���鎖����{�ł��B
��������Z��technic�̈�ł��B
�����̍�ȉƒB�́A��Ȃ̃A�C�f�B�A���Ђ˂�o���̂ɁA�悭�U�������Ă��܂����B
�x�[�g�[���F���ɂ́A�A�C�f�B�A�ɖv�����邠�܂�ɁA�R�̒��ɖ�������A�ׂ̒��ɂ܂ŕ����Ă����Ă��܂��A���Q�҂ɊԈ���ĘS���ɕ����߂��āA�����m�����������Q�Ăċ킯���āA�x�[�g�[���F���ɎӍ߂������Ƃ����܂��Ƃ��₩�Ȉ�b�܂ł���܂��B
�������q�����g �V���g���E�X���U�����Ɏg�p�����Ƃ����A�ƂĂ��������M�Ղ̍�Ȃ̃X�P�b�`�u�b�N�������Ă��܂��B�i����̂Ȃ��悤�Ɍ����Ă����܂����A�u�����Ă��܂��B�v�ƌ����Ă��A�ܘ_�A��ȉƖ{�l�̒��M���ł͂���܂���B�t�@�N�V�~���łł��B�j
�N���V�b�N�̑����̍�ȉƒB�́i�����܂߂āj�s�A�m�̑O�ō�Ȃ��邱�Ƃ͖w�ǂ���܂���B
�V���[�x���g�̂悤�ɁA���݉��Ńr�[���̃R�[�X�^�[�ɁA��Ȃ�����l����������������܂��A���̍�ȉƒB�����Ă��鐞�̒����t���b�N�R�[�g�̃|�P�b�g�͌ܐ���������̂ɂƂĂ��֗����ƌ����Ă����ȉƂ����܂����B
�c���́A�t���b�N�R�[�g�͎c�O�Ȃ��璅�����Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ܐ��������������Ƃ������́A���܂��������͂���܂��c�B
�h�C�c���w���́A�����A��Ȃ̈Ă��Ђ˂�o�����߂ɁA�����̐������ڂ�|�������ł͂Ȃ��A�悭�U�������Ă��܂����B
�h�C�c�̏����Ȓ��i�o�������������j�����͂ސX�͂ƂĂ��f���炵���A���X�⎭�Ȃǂ̏�������A���̒��ł��n���l�Y�~�Ȃǂ��悭�������܂����B