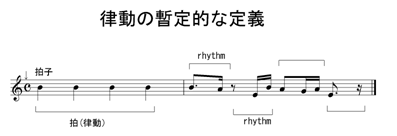
メトロノームの使い方を解説する前に、言葉を定義しておかなければならないのだが、困ったことに拍子と拍、rhythmと律動の定義はしっかりと決まっているわけではない。その使い分けは音楽仲間達の間の一般的な通説にしか過ぎないのである。「拍打ち」と言う言葉に見られるように、本来的には拍子と拍とrhythmの定義の上で明確な差はない。それではすこぶる困るので、私達は拍節に該当する、定期的なブロックのrhythmの繰り返しを拍子とし、律動を拍とし、不定形の音型をrhythmとすることにした。つまり、拍節は拍子であり、拍節の中の律動を拍と定義するわけである。
この定義は私個人の定義ではなく、広く音楽界すべての共通した定義である。
[初心者へのメトロノームの導入]
メトロノームを使用していないレスナーの方に、「何故、メトロノームを使用しないのか?」とその理由を訊ねると、最初からメトロノームを使おうとしたことがなかった論外の先生達の他に、一度はメトロノームをレッスンで使ってみようと試みたのだが、失敗してしまったレスナー達が多くいました。その人達の話にはメトロノームの使用に対しての共通のmistake(失敗)を見い出す事が出来ます。
その内の最も数多く見受けられる失敗は、レスナーの多くの先生達が、生徒が曲をちゃんと弾けるようになる前から、テンポの揺れやrhythmの矯正にメトロノームを使用したということです。
あたかも、パラドックスのような話ですが、私が「ピアノの初心者にメトロノームを使ってはいけません。」 と言うと、「えっ?!rhythmが取れないから、(揺れるから)(不安だから)メトロノームを使うのではないの?」「初心者に使用しては駄目なの?それじゃ?何のためにメトロノームを使うの?」 と、驚いて、質問を返してくる先生が多いのです。「じゃぁ、何のために??」と不思議がっている、先生達の素朴な驚きと、疑問が聞こえて来る気がします。
勿論、当然、メトロノームはrhythmを矯正するために使用するのですよ。
しかし、自転車と同じで、その前に、子供にメトロノーム使い方やメトロノーム自体に子供達を慣らしてから、使用しないと、逆効果になってしまうのですよ。
自転車だって、子供が怖がっている内に、外に連れ出してしまうと、一生自転車に乗れなくなってしまいます。
自転車に乗れない多くの大人の人が、まず最初に言う言葉は、「子供の時に怖い思いをしたから・・」ですよ。
だから、まず、自転車に乗れるように、自転車に乗るための基本の練習をすること、それを先に勉強しなければなりません。
その順序だての事をsystemと言うのです。
私が子供の頃の時代には、水泳なども、泳げない人をボートに乗せて沖へ漕ぎ出してから、ボートをひっくり返しておぼれさせて、泳ぎを教えるといったような、乱暴な指導法がまかり通っていました。
今では、考えられない指導法なのでしょうが、systemも何も無い、根性論的な往き当たりばったりの指導法ですよね。
メトロノームもいきなり、合わせさせるという事ならば、そういった乱暴な指導法と変わりません。そこのstep(順序だて)がないから、子供がメトロノーム恐怖症になってしまうのです。
では、その導入の仕方を説明しましょう。
[メトロノームの早期教育]
自転車乗りと同じで、メトロノームもピアノの学習し始めの早い時期に、慣れることが、正しいrhythm感を育てる意味でとても有利です。
メトロノームを小さな子供達や初心者に指導するには、体感訓練が必要です。
メトロノームの音を聞き取れるようにするには、まずは体にrhythmを感じさせる事なのです。
その為にはまず、メトロノームに慣れることから始めなければなりません。
では、本題に入りましょう。
[指導のための段階(step)の設定]
まず、生徒にメトロノームの使用法を指導するときには、(特に年齢が低い場合には)、レッスンの最初から、いきなりメトロノームを使用してはいけません。
Point:生徒がメトロノームに合わせるのではなく、メトロノームを生徒の演奏出来るテンポに合わせるようにしなければなりません。
そのstepは第一段階では、生徒が、ある程度曲を間違えないで弾けるようになってから、先生がその生徒の弾いている曲のテンポを計ります。
それから、そのtempoを生徒に確認して、メトロノームと一緒に弾かせます。
その時に、「そのテンポは生徒が自分で弾いたテンポである」ということを生徒に確認します。つまり、「メトロノームなしでは、ちゃんと弾けたのだ。」という事を本人に確認させるのです。
それはいたずらに生徒がメトロノームに不安感を持つことを避けるためなのです。
いきなり、目標のテンポで弾かせるのではなく、その生徒が今弾けているテンポをメトロノームで計り、それに合わせさせるようにします。
このときのテンポの設定には細心の注意を払わなければなりません。
メトロノームtempoが身についていない生徒は、演奏しているtempoが揺れているケースが多いからです。最初の小節を子供の演奏しているテンポに正確に測って、メトロノームのテンポを取ったとしても、子供の場合には2、3小節弾くとすぐにずれてしまう。
テンポ設定が遅すぎると子供はテンポを待てないし、速ければ指がついていかず、メトロノームにおいていかれるし、無理やりについていこうとすると、指がばらばらになる(雑な演奏をするような)原因を作ってしまいます。
殆どの先生達がそこのメトロノームのtempoの設定を、間違えてしまうのです。
曲の途中で技術的に演奏が遅くなるのなら、その前からMetronomのテンポを変えて、遅いテンポに変えればよいのです。何も、最初から、一定のテンポで練習する必要は無いのです。子供がどれぐらい遅くなってしまったのか、を自覚できればよいのです。発表会迄の長いスタンスで、一定のテンポで弾けるようになればよいのです。
子供達がメトロノームを普通に使えるようになるためには、とても気長な指導が必要なのです。いきなり、子供達を目標のメトロノームに合わせて練習させると、子供達はメトロノームが嫌いになってしまいます。
私達の教室では、先生達が生徒に対して、現在の練習tempoと、発表会等で演奏するときの目標tempoを生徒に指示します。生徒は今現在弾ける練習のtempoを少しずつ、目標のtempoに近づけていきます。そのテンポの細かい指示は初級は勿論ですが、中級ぐらいになっても、先生が細かく設定します。勿論、中級になると生徒が自分自身でも練習のtempoを設定して練習してきます。無理がないように先生は生徒の演奏をcheckし、練習テンポの設定を細かく配慮します。
[メトロノームのテンポが見つけられない潜在意識的な理由]
生徒がメトロノームに合わせられるようにならない原因の多くは、先生達が、「生徒が演奏出来るテンポの設定」よりも、ほんの少し速めに設定するからです。
では、何故、先生達はメトロノームのテンポを生徒の弾けるtempoよりも速めに設定してしまうのでしょうか?
私が先生達を観察している限り、その設定の間違いの根本的な原因は、先生達の生徒への願望であるように思います。
つまり、無意識にですが、生徒に「このテンポで弾いてほしい。」とか、「もう、このテンポで演奏出来ている(はずだ!)。」という、思い込みなどです。
願望となると、そこの部分は先生の指導力の問題なので、私がとやかく言う事は出来ないのですが、私が先生達をlectureする時に、先生が生徒に指示したメトロノームテンポを実際に生徒が演奏可能なメトロノームテンポに訂正して、生徒に演奏させると、殆どの先生達が驚きの声を上げます。
共通のその声は「もっと弾けている、と思っていました。」 という声です。
「だから、それはあなたの願望なのだよ!」
先生が生徒に対して、願望を持つ事はとても大切な事ですが、生徒を観察する時にはちゃんと客観的に見れなければなりませんよ。
譜例:メトロノームテンポの見つけ方
先ほどもお話したように、ワン・フレーズの抜き出し箇所であっても、詳しくcheckして見ると、下記のように子供の演奏には、微妙なテンポのばらつきがあります。
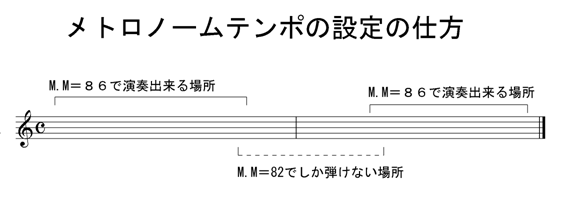
初心者の子供の演奏の場合には一つのphraseやmelodieラインであったとしても、その中で、上記のようにメトロノームtempoが微妙に揺れているのに、生徒自身はおろか、先生でさえもそれについて気が付いていないケースが非常に多いのです。
ですから、上記のケースの場合でも、子供が家庭学習で「メトロノーム・テンポを86で練習してきた。」といったとしても、その言葉を鵜呑みにしてはいけません。
ちゃんと遅くなった場所を先生が正しく、正確にメトロノームで測りなおさなければなりません。
という事で、この譜例のケースでは、最初のテンポは86ではなくって、82のtempoで練習を開始しなければなりません。(或いは、まず、「抜き出し練習の抜き出し」 で、「82の部分」だけを「82」で自信を持って弾けるように練習させて、それから、少しずつ、一マスづつ(目盛づつ)上げていけばよいのです。)
82で自信を持って弾けるようになったら、83で練習して、弾けなければ82に戻って、自信がついたら又83に挑戦するというように、弾けるようになるまでその反復練習をするとよいのです。そして少しずつテンポを上げて行って、M.M=82でしか弾けない箇所が、86で弾けるようになったら、最初の86の場所まで戻って、抜き出しの全体練習をすると良いのです。
こういう風にお話をすると、とてもめんどくさい練習のように見えてしまうのですが、実際にそういったレッスンをすると、生徒は演奏出来なかった場所が、着実に2,3日もすると、自信を持って演奏出来るようになります。それをめんどくさがると、結果として、何日も何ヶ月かかっても演奏出来ない事になってしまいます。日本の「急がば回れ」の諺のように、最初に丁寧に練習をすると、確実に仕上げていくことが出来るので、結果として非常に早く曲を仕上げることが出来るようになります。だから、こう言ったしっかりとした目的を持った練習をする事は、ただ、だらだらと練習するのとは違って、結果的にはとても早く上達するので、練習の時短になる、効果的な練習法であると言えます。
私達のレッスンでは、生徒がレッスンの時間内に弾けるようになるように、先生が生徒と一緒に練習をして行きます。生徒が一人でも弾けるようになったら、初めて宿題にします。
弾けるようになったら、そこで初めて、「宿題にする」のですよ!「合格にする」のではないのですよ!!
蛇足:
[指導者が生徒を(自分のレッスンを)客観的に見れるようにするための訓練法]
お気に入りの生徒や、コンクール等を目指す生徒に対しては、どうしても、先生が客観的に生徒を観察出来ない場合が多いようです。
そのアドバイスとしては、自分が客観的に見る自信がない場合には、lessonをビデオに撮って、2,3日後で、他の仕事をしながら、(食事の用意をしながら、或いは食事をしながら)自分のlessonを見直してみると良いのです。「~しながら・・」という事には、ちゃんとした理由があります。
テレビの前で、楽譜を準備して、筆記用具等を準備したりすると、どうしても身構えて見てしまいます。そうすると、折角の「客観的に見る」 という事が出来なくなるからです。
一度、観客として漠然と見ておいて、その時点で気がついた所を、改めてcheckする時に楽譜を準備して、パソコンに入力しながら、(楽譜に書き込みながら)見ればよいのです。
日にちをおけば置くほど、かなり客観的に見れるようになりますよ!
ビデオで後日checkすると言う事は、とても大変な事のように思われますよね。しかし、あなたが指導している総ての生徒をcheckする必要はないのです。その週の中で、自分が一番自信のない生徒を一人だけピックアップして、checkすればよいのです。一人の生徒が客観的に観察出来る様になったら、他の生徒も客観的に観察出来る様になるからです。
一人でよいのですよ。(それが、不安なら2,3、人で良いのです。)
[初歩の段階では拍子の音を入れてはいけない]
写真:ぜんまい式のメトロノームの拍子の設定のつまみ

生徒が練習してきた曲の演奏テンポを計測したとしても、初心者の間は、拍子を(正確にはbeatといいます。)設定したとしても、まだ何拍子かという、拍を設定する必要はありません。
拍に合わせるという事は、次のstepになるからです。
ですから、初心者の間の拍子の設定(拍の設定)は必ず0拍子でなければなりません。
拍頭が戻ってくるタイミングを待つ必要はないので、レッスン時間や練習時間の短縮になります。
拍子を設定しなければ、練習のpointをbeatだけに集中出来るからです。
[メトロノームのbeatの設定は拍子を設定するものではない]
初心者の場合には、まず曲の(拍子ではなく)基本となるbeat(ビート・律動)を設定します。
とは言っても、仮に指導している曲の拍子が4/4拍子であったとしも、だからと言って、ストレートに4分音符のbeatを設定してはいけません。勿論、曲のbeatの単位が4分音符であれば4分音符のbeatででも良いのですが、殆どの曲は、それよりも、もっと小さな音符の単位で書かれています。ですから、beatの最小の単位は何であるかを、楽譜でcheckしなければなりません。(勿論、曲の中に出てきた最小のrhythmの単位がbeatの単位である、という意味ではありませんよ。)
つまり曲の拍子が4/4拍子であったとしも、曲の基本のビート(律動)が八分音符であるとすれば、メトロノームの単位は、最初は八分音符の速さをメトロノームの単位に設定にします。
練習が進んで、だんだん上手に弾けるようになったら、メトロノームの拍取りを大きく取るようにします。最初、8beatで8分音符を単位にrhythmを取っていたら、上手に弾けるようになったら、次にはテンポを上げる前に、必ず拍の単位を上げて練習します。最初、8分音符で練習していた場合には、今度は4分音符の単位にして練習します。
これから先は上級生の練習法になりますが、早い曲の場合には、例え4/4拍子であったとしても、2分音符の単位でメトロノームの拍子を設定します。
つまり、メトロノームの単位が4分音符が80と仮定した場合には、次には全く同じテンポであったとしても、メトロノームの拍の取り方を2分音符の40に設定して、練習すると良いのです。
結論的に言うと、例えば、M.M=80の曲があるとします。
練習段階のstep1では、(例が4拍子の曲だとして、)拍子の設定のtempoよりも更に小さな8beat=160で練習します。そのテンポで演奏出来るようになると、次には楽譜通りの4beat=80で練習します。初心者の場合には此処まででよいと思います。
以下のお話は中級の生徒から上級の生徒に対してのメトロノームの設定のお話ですが、曲が早い曲の場合には、早くても落ち着いた感じで(焦った感じにならないように)演奏するために、拍を大きく2beat=40にして演奏します。
メトロノームのテンポは拍を大きく取れば取る程、難しくなって行きます。
反対に曲のimageは8beat、4beat、2beatの順に、大きく取れば取る程、落ち着いた感じで演奏しているようになっていきます。
プロの演奏家の演奏のテンポがとても早いのに、実際のテンポよりも遅く聞こえるのはそのテンポの感じ方が拍子の指定よりも大きく採っている性なのです。
[音の粒を出すためのメトロノーム練習(ビッコの矯正のメトロノーム)]
初心者の弾くBeyerの教則本でも、74番の左手のtoriolen(3連音)の練習や101番の右手の16分音符の速い動きでは指がビッコをひいてしまいます。正確な粒粒を出して練習するためには、同じ粒の単位でメトロノームを鳴らすと良いのですが、それはぜんまい式のアナログ型のメトロノームでは出来ません。
ちなみに、74番のtoriolenの課題は右手がmelodieなので、そのmelodieをmelodieとして聞けるテンポ(melodieに聞こえるテンポ)はどんなに遅くても、M.M=76ぐらいになります。そのtoriolenの粒をメトロノームのメモリで表すと、228となります。ぜんまい式のメトロノームの一番速いテンポは208なので、当然beatを(粒粒を)合わせる事は出来ません。
電子式のメトロノームも一般の安いタイプでは208までしかメモリがありません。しかし、私の愛用している、上記のメトロノームは30から1目盛りずつ250まであります。
しかし、高性能の電子式メトロノームには付属の機能として、rhythmの機能がついていますので、76に設定して、rhythmを3連音をセレクトすると、beatの練習が手軽にできます。
というのは、Beyerの101番は指の回しの練習課題曲ですから、例え初心者であったとしても、最低M.M=100以上では弾かなければなりません。そうすると、粒粒を合わせるのには100×4でbeatは400となってしまいます。幾ら高性能のメトロノームであっても、rhythm機能が付いていない限り、それは出来ません。
この場合も拍子を100に合わせてrhythmを16 beatに設定すればよいので、簡単に練習が出来ます。
rhythmTrainer

本当はそういったrhythmのトレーニング(訓練)が出来るように、メトロノームをもっと高度にしたrhythmの練習用の器具があります。
リズムトレーナーとか、メーカーによって色々な呼び方をします。下の写真は私の愛用の携帯用のrhythmTrainerで、メーカーの製品名もそのままrhythmTrainerです。
残念ながら、左の写真の製品は今現在は生産終了なので、教室や生徒達は別のメーカーの製品を使っています。
勿論、以上のお話は合格テンポのお話ですから、練習の組み立て方としては、まず生徒が演奏出来るテンポから練習し始めなければなりません。
①まず、びっこをひかずに、きちんと弾けるテンポを探します。
例えばそのテンポが♪=80だったら、拍子を80にセットして、次にrhythmを合わせます。74番の練習曲ならばrhythmの設定をtoriolenにします。101番ならば、16分音符に設定します。
初級の場合にはそれで、メトロノームにちゃんと合わせる事が出来るようになったら合格です。
もう少し、高度なlevelまで指導したければ次のstepに入ります。
[拍の読み替えの練習]
②♪=80のテンポできちんとメトロノームに合わせることが出来たら、次にメトロノームを♩=40にして合わせてみます。実際には♪=80と同じテンポですが、拍の取り方が大きく変わるので、rhythmの正確さが必要になります。そのために格段に難しくなります。
③♩=40ができたら今度は少しテンポをアップして♪=96にしてみます。
それが出来るようになったら、♩=48でもやってみましょう。
④少しずつテンポの設定を上げながら、同じようにして練習していきます。
[弾けてはいるのだが完成度のバランスが悪い]
指定された範囲をメトロノームでなんとかちゃんと弾けるようになったのですが、その出来具合が今一つです。どうcheckしたら良いでしょうか?
私が生徒にレッスンをしていたときのお話の一例です。
「メトロノーム練習をしているときに、同じ拍なのに、そのテンポが遅く感じられたり、速く感じられる所があるんじゃあない?」
「ひょっとして、このメトロノームは速くなったり遅くなったりする!」 などと思ったりして??
テンポが、遅く感じる所は、あなたがよく弾けているのか、それとも、或いは気分が急いでしまっているので遅く感じてしまっているのではないのかな?
つまり、メトロノーム・テンポが、速く感じられる所は、メトロノームテンポ通り弾けていたとしても、まだTechnik的に(技術的に)充分じゃあない所、つまりまだ充分には出来ていない所なのだよ。
丹念に抜き出し練習や分解練習などをして、自信を持って弾けるようにしようね。
逆に遅く感じられる所は、あせって弾いているところだから、気持ちを落ちつかせて、よく丁寧にメトロノームの音を聞いて、正確に合わせられるように練習しよう。
曲がだいたいin tempoで弾けるようになったら、ザッと通してメトロノームに合わせ弾いてみて、そういう風に、自分の技術のばらつきがないように、メトロノームのテンポで不安な所、技術の足りない所を捜し出して見る事はとても大切な勉強です。