[初心者に良く見受けられる、弾く事に一生懸命で、メトロノームの音が聞こえない場合の指導法]
初心者や小さな子供の場合には、最初の間は弾くことだけで精一杯なのですから、子供自身が「弾きながらメトロノームの音を聞き取る」と言う事は、不可能に近い事です。
その場合には先生が、生徒にテンポを体感させる為、生徒の肩などを軽くリズムをとって叩いてあげるとよいでしょう。
しかし、よく一般の先生達に見受けられるのは、思いっきり平手で子供の背中をバンバン叩いている先生が多いようです。そういった光景は音楽大学等でもよく見かけますが、大人の生徒であっても、恐怖と痛みで顔が引きつっているように見えますね。
ましてや小さな子供達を扱う音楽教室で、幾ら子供にrhythmを体感させるためだと言っても、背中や型などを、強く叩いてリズムを指示してはいけません。
子供は恐怖心から、ますます逆に正しいリズムが取れなくなり、メトロノーム嫌いになる原因となります。
子供への正しいrhythmの与え方(体感のさせ方)は、優しく子供の肩に手を乗せて(というよりも、触れてと言った方が良いのかな??)、人差し指の先だけで、軽くリズムを取るようにします。子供が体感としてbeatを感じるにはこれだけで充分なのですから。
[メトロノーム練習は極端に遅くして練習をしても必ずしも易しくなるわけではない。]
「弾けなければ、少し遅く弾かせれば良いのでは?」と考える先生も多いと思いますが、それがそれほど単純ではないのです。
第一には、生徒は練習してきたテンポでしか弾けないので、早くしても、遅くしても、どちらも弾けなくなります。
その場合には弾けなくなったpassage(部分)の場所を抜き出して、生徒が弾いているテンポを測り直します。そして、遅くなった部分の所だけのtempoを測り、その部分だけを抜き出しして練習させるのです。
メトロノームのテンポの見つけ方の詳しい説明と、譜例は、前述の「メトロノーム・テンポの見つけ方」を参考にしてください。
[弾けないからと言って、闇雲に遅く練習しても意味はない]
前の節と同じ文章のように、見えてしまいますが、ちょっと内容的なアプローチの意味が違います。
よく、弾けないからと言って、非常にゆっくり練習すると良い、と思い込んで、生徒に非常にゆっくりと練習させる先生がいます。勿論、音を確認して正確に覚えるための練習としては、とても良い練習なのですが、指や筋肉のトレーニングにはならないのです。
つまり速い動きの時に使用する筋肉と遅い時に使用する筋肉では場所や力の加減が全く違うからなのです。
速いpassageを練習するには、まず音をしっかり覚えてから、ある程度の、仮に遅いテンポであったとしても、その筋肉が使用される最低限のテンポで練習しなければならないのです。
芦塚メトードでも、勿論、「slow motion練習」 という非常に遅く弾いて練習する練習法があります。
しかし、それは野球選手の「シャドウ練習」 と同じ練習法で、イメージト・レーニングのための練習なので、体全体を使用して演奏をする上級生の動きをcheckするための練習法になります。所謂、初級の生徒が「早くは弾けないから、ゆっくり練習する」という練習とは全く意味が違います。
[メトロノームは抜き出し練習の場所だけを練習する事]
メトロノーム練習は、決して曲全体をメトロノーム練習してはいけません。
それこそ、最初の前書きに音大の先生のメトロノームの批判のように、非音楽的になってしまいます。一生懸命練習したとしても、音楽的に何のメリットもありません。
大切な事は、曲の演奏上の難しいpassageの2~3小節だけを、抜き出してゆっくりと正確に練習することです。速く、指先だけでいい加減に練習する事は、下手になる練習なのです。だから、ゆっくりと確実に確認しながら練習する事が出来るようになれば、最初のメトロノームの導入としては100点満点です。
応用編
テンポの設定
「『ハイ!メトロノームにあわせてみよう!』 じゃ、誰も出来ないよ!」
メトロノームを使えるようになるにはstepがある。
[その曲がその曲であるためのテンポ]
―遅くても、速くても、駄目なものは駄目―
レスナーの中には、「この曲を早い時期に弾かせたい。」という先生の願望、或いは生徒や親の願望から、生徒の技術levelを無視した無理難題の曲を発表会等で弾かせてしまう先生がいます。
そのために、その曲の本来のtempoよりも、どうしようもなく遅いテンポで生徒が曲を弾いたりすることを、良く見受けます。
反対に、コンクール等を聞きに行くと、早く弾く事で、細かい表現を誤魔化して弾いている生徒を良く見ます。
昔々は、確かに中央のコンクールもそうでしたが、さすがに全国大会を持っているコンクールでは、今はそういった「早く弾ければよい。」という評価は少ないようです。
地方予選などではまだそういった評価をされるケースもままあるようですが、本選まで行くとそれはなくなります。
しかし今でも、地方のコンクールなどのlevelの低いコンクールでは、そんな弾き方でも合格する事があるようです。
でも、まったく間違わないで丁寧に演奏出来た生徒が不合格になって、間違いだらけの演奏をした生徒が合格するような、そういったコンクールはごく普通にありますから、コンクールなどの評価は最初から気にしないことです。
曲にはその曲がその曲のimageを表現できるキャパシティのテンポがあります。
その曲のimageで例えば80がベストのテンポであったとしても、76まではその曲のimageがキープ出来るとか、速くとも88までは何とか・・・とかです。
その限界を超えたものは、もう別の曲であって、その曲とは言えないのですよ。
[一つの曲の中での複数のメトロノーテンポの設定]
Sonatineやsonate等の大規模な曲になってくると、複数のテンポ設定があります。
ソナタを例に取ると、第一主題のテンポ、第二主題のテンポ、展開部の色々と変化するテンポ等複雑に絡み合います。
(ちなみにTempoⅠ テンポ・プリモは日本語では第一テンポで!という意味になります。)
当然、TempoⅡ テンポ・セコンダ 所謂、第二テンポで!という事もあるということですよ。
という事で私達の教室のオケ練習では第一テンポ、第二テンポ、第三テンポ、等と細かく設定します。オーケストラや室内楽は、生徒達が家で各自練習をしてくるので、全員が合ったときにちゃんと同じテンポで弾けないと練習になりませんからね。
先程のsonate等の蛇足ですが、プロの演奏の場合、repriseで第一テンポが再現される時には、演奏会等では、全く同じテンポに再現される事はありません。そうではなく、ほんの少し、1メモリ、2メモリぐらいは早めに設定するのです。
そうしないと、お客さんは再現部が遅くなったような気がしてくるのです。
勿論、教室で子供達に指導する時も、そのように一マス、二マス、テンポを上げて演奏させるのです。
蛇足ですが、先程のメトロノームの例では、最初の主題がM.M=80だとすると、一マス上げるとメトロノーム・テンポは84になり、二マス上げると88という事になります。 一マスか二マスか、そのテンポの違いはとても大きいですよ。
いずれにしても、音楽を表現する上で、最初から最後まで同じテンポで弾くという事は、むしろまれな事になります。だからどんな曲でも、その1曲の中でもmelodieやpassageに合ったテンポをいくつか設定することになります。
[臨界テンポのお話]
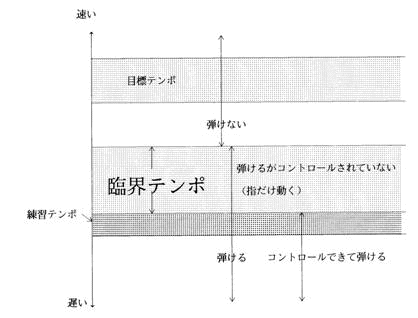
メトロノームのテンポを設定するに当たり、長年の経験上で、間違えないで安定して弾けるテンポと間違える不安定なテンポの間に、「ある特別なテンポ」が存在しているという事が分かってきました。そのテンポを芦塚メトードでは「臨界テンポ」と呼んでいます。
「臨界テンポ」とは、「コントロールされ、しっかりと弾けているテンポ」と、「全く弾けなくなるテンポ」の間に挟まれた、「弾けてはいるがコントロールされていないテンポ」の事です。
いくら指が動いていても、或いは、misstouchをしなかったとしても、演奏する人の意識でコントロールされてなければ、その演奏は本当に弾けたとは言えないのです。
コンクールなどでも、その臨界テンポギリギリで弾いている人が結構多いのです。
コントロールされていない演奏は、それは単なる指の体操であって、音楽とは呼べません。
確かに昔の日本のコンクールは、そういったオリンピックの競技みたいなところがありました。しかし、今現在は大分、そういった評価は直ってきたようですが、まだそこの所をかんちがいしたまま、コンクールに出ている生徒達や、そういった風に指導してコンクールに出している先生達もいて、なかなか皆さんに分かってもらえていないようです。
学習者はこの「臨界テンポ」の一歩手前のテンポで練習しなければなりません。これがメトロノームの「練習テンポ」の設定です。
「練習テンポ」は遅すぎれば無駄な練習(無意味)になり、速すぎれば(コントロールの取れない)雑な練習になってしまい、練習すればするほど、むしろ下手になってしまいます。
練習をする人が、曲のあるパッセージを練習している時に、その人の「練習テンポ」は、間違えて、たった1目盛り速く弾いたとしても、突然弾けなくなってしまう程、はっきりと存在しています。
[練習テンポの見つけ方]
その曲をキチンと仕上げるためには、曲の練習テンポは1つのテンポだけで行ってはいけません。色々なテンポで練習して、その曲の柔軟性を身につけなければなりません。
又、先程も述べたように、例えばM.M=120の曲だからといって、最初から120で練習するというのは効率の良い練習とは言えません。
自分の技術の上達に合わせてメトロノームのテンポを徐々に上げて目標となるテンポに近づけて行く方法がもっとも良い練習です。
曲を仕上げた時の目標テンポが120の曲を例にとって説明しましょう。
まだ120で弾けない場合には、思い切りメトロノームのテンポを下げてみましょう。
この時には、前に私が話した、曲想がキープ出来る範囲のテンポ以内でテンポを落とすのではなく、曲のimage(曲想)を無視して、あくまで技術の練習として、極端にテンポを下げてみるのです。
これを私は「スローモーション練習」と言っています。
「slow motion練習」 は可能な限り、暗譜でするようにします。「slow motionの練習」 は技術練習、所謂、technical練習というよりも、頭の中の記憶の精度を上げるための練習であると理解してください。
ですから、ちゃんと音が頭で把握できるようになると、この練習の特徴は、一メモリ、一メモリ上げて行く必要はありません。一気に10メモリぐらいづつ、テンポを上げて行っても良いのです。
一気にテンポを上げていくと、ある程度テンポが上がった時点で又、躓きます。しかし、こんどの問題は前回の音楽の理解と記憶の問題ではありません。今度はtechnicalな問題でぶつかったわけなのです。
そこで、此処で臨界テンポの話が出てきます。
ある程度、早くすると指がもつれたり、ついていかなかったりします。そこで、自分が不安を感じたり指をコントロールできなくなるテンポが、いったいメトロノーム幾つなのかを探し確認します。
「80なら10回弾いても、10回とも確実に間違えないで弾けるが、メトロノーム84だと4回、5回に1回は間違う」というように、安定して弾けるテンポと「このテンポからくずれはじめる」という境界線のテンポを確実に探していきます。それが練習テンポと臨界テンポの境目の正しい練習テンポなのです。
くずれはじめる一歩手前の練習テンポを100%確実にすることが、次の練習テンポに繋げていく重要なpointになります。
子供達はどうしても繰り返しの練習(反復練習)をすると、練習の仕方が雑になってきます。そのために、幾ら練習をしても上手にならない。練習すればするほど雑になる、といったどうしようもない状態に陥っている事がよく見受けられます。
それを矯正するために私は(集中力を持続するための)ゲームを作りました。
子供達が大好きなオセロゲームです。
このゲームの根本にある理論は、パソコンで一度間違えた情報を入力すると、正しい情報を入力するためには間違えた情報を消去しなければならない。という理論です。
練習も同様に、子供達の練習でよく見受けられる、練習の仕方は10階練習しなければならないとすれば、間違えても正しくても10回練習すればよいと思い込んでいる生徒が意外と多いのです。もっと問題なのは、一回でも正しく弾けると、練習が終わったと思い込んでいる生徒です。
私はその子達にいつも説明をします。
「間違いも頭に同じようにインプットされるのだから、1回、正しく弾けたのと、1回、間違えて弾いたのでは何回練習したことになるのかな?2回?1回?0回?」
「う~ん??あっ!0回だ!!」
「そうだよね!じゃぁ、5回練習しなさいと先生に言われて、5回練習したのだけど、4回間違えて最後の1回正しく弾けたとすると、その日の練習の成果はどうなるのかな?」
「え~?間違いえが4回で、正しく弾けたのが1回だから、う~ん・・・」
「つまり、その日は3回練習していない事になるよね。だから、次の日、3回正しく練習したとしても、0回練習したことになるんだよね。」
「あっ!そうか?」
という事で、レッスン・キットの中から、おもむろにオセロのチップを出します。
写真:オセロのチップ

「じゃぁ、今から5回この小節を練習してみよう!
正しく弾けたら白、間違えたら黒だよ!」
1回目は正しく弾けたね~ぇ!はい白チップ1枚
あれ?2回目は間違えたよね。黒チップではなくって、プラス・マイナスだから、白のチップがなくなるんだよ!
「あっ!そうか?」
あれ?又間違えちゃったね。なら今度は黒チップ1枚だよ!
「あ~ん!!」
次の課程では、正しく弾けたか、間違えたかは生徒が自分で判断します。
最初の間は、白のチップを5枚ためるのには、結構大変なので、3枚ぐらいから始めます。
だんだん集中力が身に付いて来るに従って、間違いが少なくなってきます。
最終的には5枚の白チップを5回で獲得できるようになります。
練習の時間や量ではなく、練習の質を上げる事、確実性を身に付ける事が上達への早道なのです。
最初の練習テンポが確実に弾けるようになったら1目盛り上げます。
これを単純に繰り返していけば、着実に目標のテンポに近づけていくことができるのです。
そして実際に弾きたいテンポより10メモリぐらい速めのテンポでも安心して弾けるようになったら出来上がりです。
「練習テンポ」を見つけ出すことはとても難しいので、基本的には生徒は無理です。
上級生になって、自分で見つけられるようになるまでは「練習テンポ」を指定するのはレスナーの役目だと思ってください。
生徒に宿題を出すときには、「ここの部分はメトロノーム」=84~92の問で練習すること」のように、具体的な数字を指定すると良いでしょう。
[1小節を1拍として捉える曲]
ある超有名な音楽大学の先生が生徒に「音符の単位が短く書かれる曲は速いのよ!」と、まことしやかに生徒達に話ていたそうです。
4分音符に対して16分音符は速くなければならないという勘違いの意味です。
それを聞いた私の生徒が、腹を立てて、「ご注進!」と、私の所にその先生の話を告げ口しに来ました。「私は子供の頃から、芦塚先生からは逆に習っていたから!」 という事なのです。
多分、その先生は、「音符の分割と時間の分割」を速度(テンポの問題)と勘違いしてしまったのでしょうね。
実際には、作曲家は曲の速度が速くなればなるほど、音符の単位を大きく書きます。
譜例:Mozart Symphonie41 Cジュピター Ⅳ楽章
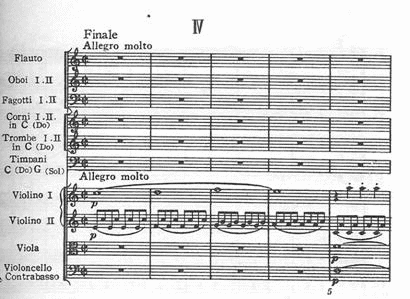
このMozartのジュピターSymphonieのⅣ楽章のように、非常に早い楽章の場合には、1小節を1拍でとって、4小節間で4拍の4拍子に振る事が多いのです。
指揮をするときにはそのように、拍を大きく取って指揮をします。
それは拍子通りに指揮をすると、指揮棒の動く速度が速すぎて演奏者からは指揮棒が見えなくなってしまうので、事実上、演奏のタイミングを合わせる事は不可能になってしまうからなのです。
(そういった、不可能な指揮を往年の名指揮者であるフルトベェングラーの指揮で見ることが出来ます。フルトベェングラーの指揮の光景は、資料映像として数多く映画にとられて残っています。今日でも、音楽図書館などで簡単に見ることが出来ます。問題の箇所はBeethovenの第九の終楽章の最後のpassageです。)
確かに、フルトベェングラーの理論では、指揮者はオーケストラよりも半分先行して指揮をするという理論があって、いつも、そのように指揮をしています。まるで音声と映像がずれているような、(昔の映画撮りでは、音声と映像は基本的には別に録画録音したので、そういったずれのある映画はざらでした。というか、殆どの映画がずれている。) しかし、それとは明らかに違う一種異様な指揮で、そういったずらしたままで演奏出来るオーケストラは世界広しと言えど、ベルリンフィルしかありませんでした。
超一流のオーケストラのTechnikがあって、初めて出来る業(演奏)でした。
しかし、今お話しているフルトベェングラーの「不可能な指揮」 というお話は、オーケストラが指揮者のタクトをずらして演奏しているという極めて高度な技のお話ではなく、単に第9の終楽章のfinaleの速度が速すぎてフルトベェングラーの指揮棒の速度がBeethovenの第九の終楽章のテンポに付いていかなかっただけの話なのです。
フルトベェングラーは律儀にも、小節の中の拍子をまじめに振ろうとしたのです。でも、残念ながら、老人であるフルトベェングラーが幾ら素早く指揮棒を振っても、第九の終楽章のfinaleのテンポには着いて行けませんでした。それを世界一級のorchestra奏者であるベルリンフィルの人達は、フルトベェングラーの指揮を見るのではなく、彼の演奏したいテンポを感じ取って、指揮とは全く関係のないテンポで演奏しただけのことです。オケの団員のフルトベェングラーに対する尊敬と団員自身の高度な技術に裏打ちされた非常にマイスター的な演奏ですね。
当然、殆どの指揮者は1小節を1拍として、4小節で4拍として、拍子を取ります。
またそれとは逆の場合で、作曲家は一般的に、曲の速度が遅くなればなるほど、逆に音符の単位を小さく書きます。そして、拍(拍子)を大きく取るようにします。
譜例:Bach 無伴奏ソナタ g moll 前奏曲(直筆楽譜facsimile版)