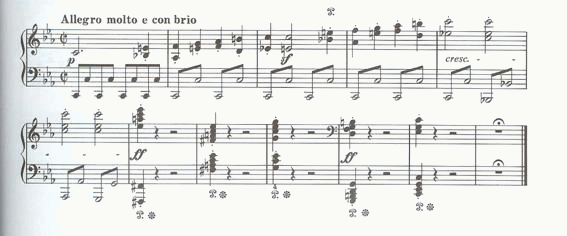
この譜例はBeethovenのPathetiqueとして知られるPianosonate c mollのⅠ楽章の最後の12小節です。不思議な事は最後の小節に音符がまったく書かれていない全休符に、しかもご丁寧にfermataまでくっついた小節が追加されている事です。
私がまだ、高校生の頃この曲を勉強していた時に、先生にこの素朴な疑問を質問したのですが、先生は「これは余韻を表しているんだよ!」とまことしやかに答えてくれました。純朴な高校生の私でも、納得の行く答えではありませんでした。
同じ質問を音楽大学時代にも教授の先生達を捉まえてしてみたのですが、全く同じような答えしか返って来ませんでした。
その後、私は私なりに、色々な文献を調べて見たのですが、その疑問に対する明確な答えはどの本にも載っていませんでした。
実は、このBeethovenのPathetique(パセティツク)のⅠ楽章に限らず、バロック時代から近現代に至るまでこのように最後の終止の書かれた和音の次の小節に、1小節まるまる休止符が書かれただけの小節が付け足されている曲はたくさんあります。極端な場合には、さほど例は多くありませんが、3小節で3拍子を表す曲の場合には、最後の小節の後に、2小節も休符の小節が付け足される事があります。
何故、そのように書かれているのでしょうか?その意味は作曲家が「1小節を1拍取りしなさい」という指示をしているのです。
例えばベートーベンの場合でも、1小節を1拍にとって、2小節目を2拍目としてとり、2拍が1つのセットとして感じるようにします。だから、1小節が終わったからそこで終わるのではなく、2拍目としての2小節目がわざわざ書かれているのです。休止の弱拍の小節(2拍目)までしっかりと感じとらなければいけません。これもメトロノームを使って1小節を1拍として練習していくと良いでしょう。
いろいろな曲を勉強するようになると、このように曲の最後の小節に完全なお休みの小節が付け足された曲を沢山見る事が出来ます。
[拍子の弾き分け]
拍子の問題で言えば、日本人は次の弾き分けが苦手です。
8分の6拍子と8分の3拍子の弾き分け、C(4分の4拍子)と¢(2分の2拍子)の弾き分けなどです。8分の3拍子の曲は3拍子の曲ですし、8分の6拍子は3連音の2拍子といえるので、基本的に2拍子の曲です。しかし、その弾き分けの違いをちゃんと指導出来るレスナーは、日本では非常に少ないのです。
譜例:1. Beyerでlectureされなければならない3拍子と6拍子の違い。
この曲はBeyerの48番の冒頭の4小節です。
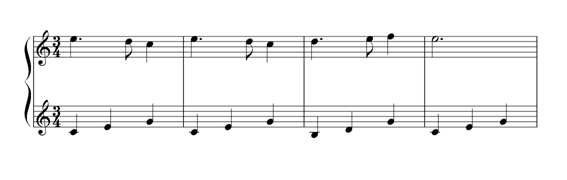
譜例:2. この曲はBeyerの52番の冒頭の4小節です。最初の2小節は同じmelodieですね。同じテンポの同じmelodieを3拍子と6拍子に弾き分ける事がこの曲の課題なのです。
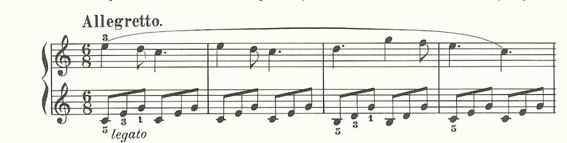
同様に次の譜例はソナチネ・アルバムの1巻に載っているHaydnのC DurのsonateのⅠ楽章です。
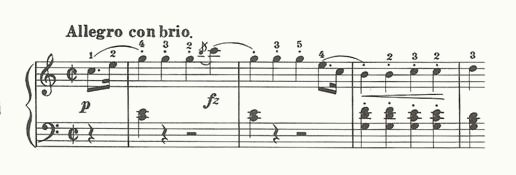
この曲をアラブレーベ(所謂、2分の2拍子)で弾かせるように指導しているレスナーを見たことがありません。皆さん4分の4拍子で指導しています。
明らかに違うのにね。
次の曲はChopinのÉtude Op.25 Nr.2 です。この曲の右手は3連音なのですが、音楽大学などでは、正しく演奏されたことを聞いた事はありません。