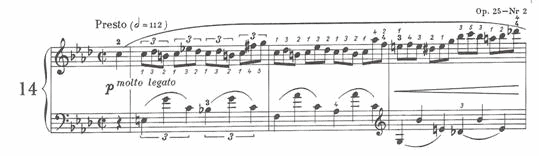
音楽大学などで学生が演奏しているのを聞くと(先生も含めて)、上記のような複雑なrhythmではなく(それじゃぁ、ChopinのÉtudeではないだろう!!)間違えた、簡単なrhythmで演奏しています。
譜例:間違えたrhythmによる演奏
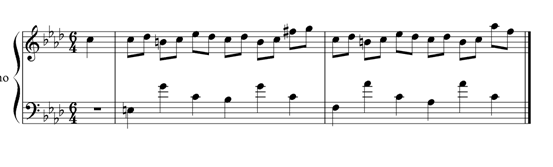
それで、私が正しいrhythmでゆっくりと演奏してあげると、皆、「えっ?!そんなに難しい曲だったの?」と驚いてしまいます。
実はロマン派の時代は両手の独立と音符の粒粒を生かすためにこういった風な複雑なrhythmを組み合わせて演奏することが多かったのです。
次の曲はみんなによく知られている仔犬のワルツです。
この曲を弾いている生徒達は、この曲の本来的な難しさを意識しないで弾いているとは思います。
しかし、譜面に注意して、曲をよく分析して見てみると実に複雑なrhythmで作曲されていることが良く分かります。
ロマン派の曲ではChopinの曲に限らず、同時に二つの拍子が平行して流れて行く曲をよく見かけます。
そういった拍子の事を、ポリリズム(複リズム)複拍子といいます。
譜例:複拍子の例 Chopinの仔犬のワルツ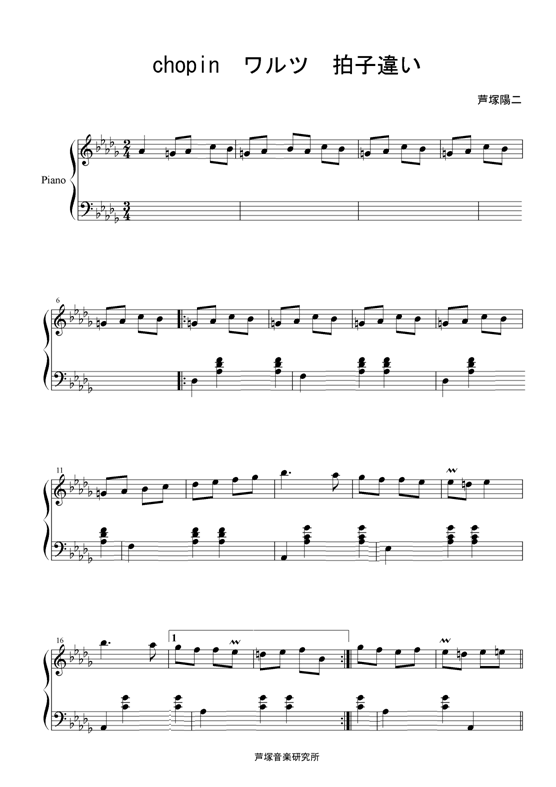
[メトロノームを使用した練習法の例]
中級クラスからは色々な練習法を覚えていきます。
その練習法は基本的に
①Rhythmのvariation
②Articulation練習
③分解練習
④variation練習
等の練習法があります。
学習者は各グレード毎に多様な練習法を学びますが、此処でその全部の練習法をお話するのはページ的に不可能なので、メトロノームに関係する(というか、rhythmに関係する)練習法の中で、①のrhythmのvariationを例にあげて説明します。
①のrhythmの練習法の中で、まず初心者の子供達が最初に習う基本的な練習法はskip練習です。skip練習には8分音符を基本の単位にしたもの、16分音符を基本の単位にしたもの、さらに、3連符系のskip練習一覧等があります。
勿論、それをノートに書き表すと大変な量になりますが、それを曲の難しいpassageの性格に合わせて、セレクトして練習をさせます。
一例として16分音符を単位としたskip練習一覧を載せておきます。
譜例:16分音符の基本的なskip練習一覧(Beyer101番のskip練習法)