クルト・レーデルがミュンヒェナー・プロアルテと一緒に演奏しているPachelbelのオーケストラversionは、多分このMüller-Harptmannの編曲版を底本にして、Kurt Redelが、自由な発展、発想をさせていると思われるが、それでも、Mueller-Hartmannとは違って、調性は原調のf mollに戻されている。
それは当然の事だと考える。
f mollならば、第三音はAsになるから、violinも三度の音を自由に調整出来るからである。
ちなみに、クルト・レーデル(Kurt Redel)は、Pachelbelのcanonの世界初演をやった事で、有名なのだが、そのarrangeは、classic音楽とはかけ離れていて、寧ろイージー・リスニングの世界に近いかも知れない。
私達の教室のcanonは、Pachelbelのoriginalversionで、Cembaloのornamentも古式豊かで、traditionalなままの演奏である。
このchaconneのもう一つの大きな問題点は、originalのorgelの曲とは、Variationの順番が入れ変わっているという事である。
Kurt Redelは、arrange自体は、かなり自由で近現代風な技法をふんだんに取り入れて、イージー・リスニングの世界に片足をドップリと突っ込んでいるのだが、Variationの順番は、Mueller-Hartmannの版に従っているので、不思議ではある。
Kurt RedelがMueller-Hartmann版を底本にした事自体は、間違いないと思われるのだが、かなりpizzicatoを多用して、現代風のイージー・リスニングのarrangeになっている。
それに対して、Mueller-Hartmannは、Pachelbelのchaconneの原曲は、余り弄ってはいなくて、originalのorgelの譜面を、比較的にそのまま、素直に弦合奏に置き換えただけなので、これをarrangeと言うかどうかは、また一つの疑問ともなる。
まあ、それでも、arrangeである事には変わりはないのだが・・・。
と言う事で、私の場合も、Pachelbelのorgelのpartはそのまま生かしながら、それに付加するような形で、arrangeをしていったので、曲の配列の他には、Mueller-Hartmannの版に従ったのか否かと言われれば、Mueller-Hartmann版もKurt
Redel版も、ただ参考にしたに過ぎない。
Kurt Redel版と書いてしまったので、老婆心ながら、ついでに確認しておくが、CacciniやTelemannの時同様に、Kurt Redelは自分のorchestraのためにarrangeをしたのだから、一般に楽譜が出版されている(市販されている)分けではないし、と言う事で、楽譜を取り寄せる事も出来ないのだよ。
Kurt Redelの批判や参考は、You Tube上の音楽の話であるので、教室としては、楽譜はないし、楽譜起こしをする気もないので、Kurt
Redelに付いての楽譜の問い合わせに返答する事は出来ないので悪しからず・・・。
これもどうでも良い事なのだが、上記の譜面のように、Mueller-Hartmann版では、2ndviolinとviolaが中声部のpartで重ねられている。melodieを担当する1stviolinが1声なのに、中声部だけ分厚くなるのは、何ともいただけない。この小節をviolaだけに担当させれば、先程の純正の3度の問題も解消するのだが、その場合には、themaが2ndviolinを欠いた3声部でarrangeしなければならないか、新しく2ndviolinにpartを作曲するかの選択肢になる。
それは、結構難しい技術なのだよ。
という事で、私の改訂のversionでは2ndviolinのpartに新たにmelodieを付け加えている。
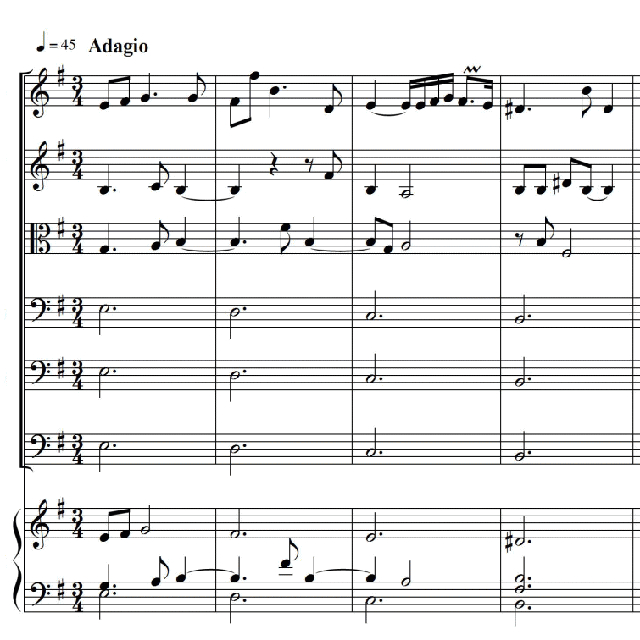
一年前の11月の、上記のMueller-Hartmannのversionによるorchestraの練習風景は、You Tubeから削除しました。
私の新しいversionが完成したので、次回以降は、Mueller-Hartmann版は使用しないからです。
という事で、今回の、13年12月15日の、今年、最後の定形のオケ練習の風景です。
来週はクリスマス会なので、練習はありませんし、そのまま合宿で冬休みで今年も終わりです。
え~っ?! ぎょぇ~!! (@_@;)
もう来年かいな??!!!
ヨージーの法則:
「時間は歳と共に、加速する。」※注)
新しい芦塚陽二versionによるPachelbelのchaconneの13年12月15日の千葉教室のor chestra練習風景ですが、斉藤先生が四日市教室に出向のために、指導者不在の全員子供達だけの練習になりました。
という事で、「あれれ??・・・1stのmemberが・・・一人だけ??」、「あれ??2ndは・・・??」 というmember不足のためにmemberを入れ替えたりしての練習です。
「それじゃあ、練習にはならないのじゃあないの??」って??
そんな事は、オーディションでmemberを決めた分けではないし、memberがいないのは、何時もの事だし、練習のconceptを出せれば良いのだから、どうでもいいのですよ、アハッ!(^^♪
※注)「時間が歳と共に、どんどん早く感じられる」のは、「若い頃、あまり勤勉でなかった私だけの『ツケ』のようなものか?」と思っていたら、何とギリシャ時代からの格言だそうです。「知らなかった!!」「若い頃、遊んで歳を取って後悔しているのは私だけじゃあ、なかったんだ!!」「アッ、ハッ、ハッ、ハッ、ハ!!」
参考までに:Wikipediaより抜粋:
ジャネーの法則は、19世紀のフランスの哲学者・ポール・ジャネが発案し、甥の心理学者・ピエール・ジャネが著作で紹介した法則。主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象を心理学的に解明した。
簡単に言えば生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する(年齢に反比例する)。
要約すれば、計算上は、人生の折り返し地点は、70歳、80歳生きたとして、35歳、40歳ではなく、15歳から17歳18歳ぐらいになるということだよ。そのズレは生まれた年数から計算するか、物心付いた年齢、多分3歳ぐらいを始めとして計算するかの違いなのだよ。
日本では作家の渡辺淳一さんが、時間の流れの速さを「川の流れ」に喩えてこう言いっている。
「20代はちょろちょろ流れる小川、30代で川になり、40代で急に早くなった流れは、50代では激流、60代では滝のごとし」と喩えているそうです。
へ~え??真面目で勤勉な人達も、私と同じように感じるんだ!!ふ~ん?? (°д°)
Variation形式について
これから、Pachelbelのchaconne e のオケ練習に入る前に、Variation形式について、説明しておく。
一般には(楽典の教本や、通論の理論書的には) Variationには、形式というのは存在しないという事になっている。
だから、私が「Variation形式で、・・・」 というと、音楽に造詣(ぞうけい)が深い人の方が、逆に、「えっ?!Variationに形式なんかあったの??」と驚ろいて、しまうのかもしれませんね。
Variationについての、通論的、楽典的な基礎知識としては、Variationの種類は二つあります。
その一つは、厳格にthemaのmelodieが、そのままに、装飾、変奏されていく=装飾Variationと呼ばれるVariationと、Variationのthemaを、曲の(Motiv)として、自由に展開発展させていく、「性格(的)Variation」と呼ばれる種類のVariationと、大きく分けてその2種類のVariationがあります。
しかし、楽典や通論に書いてあるのは、そこまでであって、それ以上のVariationの形式について、述べられた書物はありません。
殆ど多くのVariationは、装飾Variationであり、性格Variationと違って、音楽が静的で変化に乏しい、この種のVariationを演奏するのは、困難でを伴います。
私の若い頃には、corelliのviolinのためのviolinsonate、「la folia」とか、Beethovenの32のVariation等や、ドイツ留学中に手に入れた楽譜であるVivaldiのtriosonateの「la folia」等々の長大な曲を、どう演奏すれば、audienceを飽きさせないで、最後まで、引き込ませて演奏して行く事が出来るのか?・・という事が、私の若い頃からの懸案事項で、長年の課題でした。
音楽教室を作って以降の話になるのだが、試みに1986年に一度、Vivaldiのtriosonateの「la folia」を、子供達に演奏させて見たのだが、結果はやはり、曲が冗長である、というブーイングを受けてしまったように思います。
その後、10年以上も、このVivaldiのtriosonateであるla foliaを、中心として、baroque楽器を使用したbaroque奏法の研究と一緒に、このVariation形式で作曲された楽曲の演奏法の研究を推し進めて行きました。
Variationの演奏の方法は、Beethovenの手紙を読んでいた時に、ある時に突然、閃いたのです。
勿論、その手紙は、既に高校生の頃から、何度も目を通してはいたのだが、それがVariation形式を演奏する上でのヒントになるなんて、とても、思いつかなかったのですよ。
そのヒントにたどり着いてから、改めて、Variationを、再構成し、tempoの設定や、装飾等の色々な工夫を試みて、10年後に、再度挑戦したVivaldiの「la folia」のtriosonate versionは、結構、好評でした。
その後の、2006年9月23日 東京練馬区大泉ゆめりあホールでのコンサートはYou Tubeで視聴する事が出来ます。
と言う事で、Variation形式という一つの形式は、今では逆に、私の最も得意とする演奏形式のstyleになっている。
1990年代に入ると、そういったVariation形式による長大な曲の演奏というのも、音楽界でも一般的になって来て、baroque音楽の奏者にとっては、常識的な演奏styleになってきました。
Corelli=Geminianiのla foliaや、Vivaldiのla foliaは、私が演奏する場合には、Variationの順番を原曲のままの順で演奏しているが、多くの人達は自分の解釈で、Variationの配列を変えて、自分の演奏上の都合で、大きな曲の流れを作ることが一般的になってきています。
私も、biberやcorelli等の曲では、曲の配列を変更して演奏しています。
そういった曲(配列の変更をした方がよい)曲は結構多いのですが、それはbaroque時代に、慣習的に極一般的な事でした。。
また、長大なVariationは、ケースバイケースで、逆に、そのVariationを幾つか、割愛して演奏することも多い。のです
Tartiniのcorelliの主題による50のVariationどころではない、70のVariationまであったりするので、演奏会等では、全曲を通しで演奏するのは不可能です。violinのsolo(独奏)なのに、演奏時間は半日ぐらいは掛かります。
(完全な練習曲、Etudeとして、書かれているのですよ。)
教室では、勿論、順番を変えたり、同じ技術のEtude的な曲を省いたりして、演奏させています。
これはプロversionのbaroqueensembleでも、同様で、寧ろ、baroqueの場合には、曲を変更しないで演奏する事の方が珍しいかもしれませんよね。
PachelbelのVariation形式
PachelbelのVariationの形式は、通常の他のVariation形式と同様に、themaから、徐々にtempo upして行って、一つの盛り上がりの頂点を作ります。
それから、ゆっくりしたVariationに戻って、またtempo upを少しして、ゆっくりとした曲に再び収まります。
その型を、2回程繰り返す(都合、3回になる)のだが、1回目と最後の回は結構長めにsetするのだが、中間部は少し短めにする。
これが・・と言うか、これに近い形を私はVariation形式と名付ける事にしました。
勿論、音楽通論(楽典)の書物には、そういった形式の記載がある分けではないのだが、それでも大作曲家達のVariationはその形式を踏襲するのですよ。。
でも、そういった形式は結構あります。
その典型的な例はbogen formである。これも、Bachの時代から多くの作曲家の手によって使用されていた形式なのですが、音楽の楽典的な本には掲載されていないのです。
ジプシーのラプソディの形式(ドゥムカ)とか、landlerの形式同様に、ちょうど日本の雅楽(?)の形式のように序破急では、大雑把過ぎて、学問的には形式とは呼べないのかもしれませんね??寧ろ、様式と呼んだ方が良かったりして・・・??
それはさておき、Pachelbelのchaconneも、他の作曲家と全く同じ、Variation形式で作曲されています。
先ず、themaの提示(若しくは掲示という人もいる)部で通常のchaconne同様に、bassの定旋律が2回繰り返されて、chaconneのthemaの8小節を構成します。
この8小節をthemaとします。
それから前半部は、Variation1から、11まで、一つのククリとして演奏される。前半部はthemaを含めて12の部分からなる。
次のVariationは12Variationから16Variationまで、5つのVariationで、次も、17Variationから、21Variationまでの5つのVariationしかない。この二つの部分を合わせても、10のVariationしかない。後はthemaが繰り返されて、終わる。
A部「thema+11Variation」+(B部「5Variation」+C部「5Variation」+thema)というbalanceで成り立っている。
3部構成とすると、unbalanceなのだが、A+(B+C)という、大きな2部構成の構造式という事で演奏するとバランスは取れているのです。

よく、la foliaやchaconne等のthemaをmelodieと勘違いしている人がいるのだが、baroqueの変奏曲は、低音のbassが定旋律となって、繰り返されて、そのbassmelodieの和音上に色々なfiguration(これは日本語に訳すのは難しい)が展開されて行く形式を取ります。
Pachelbelのthemaも4小節のbassの定旋律が二回繰り返されて、その低音上に、8小節目のthemaのmelodieが演奏されます。
下記の譜面は、basso continuoで書かれたTommaso Vitaliのoriginalの譜面であるが、bassの定旋律上にmelodieが展開されている状況が良く分かる。