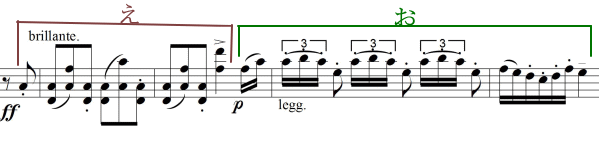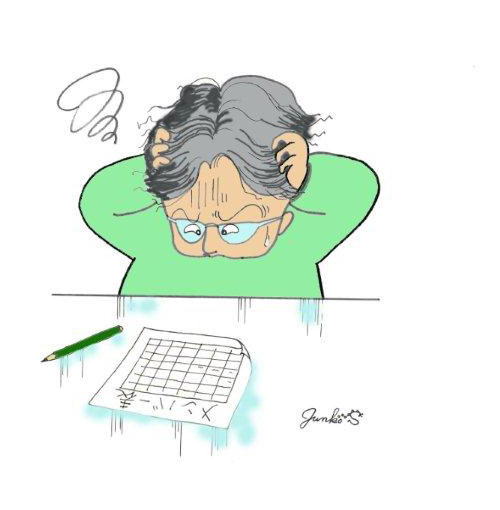前ページ

このphraseでは、1回目は思わせぶりにオーバーに、rondoのthemaのAが回帰する度に、2回目のA、3回目のAとなるに従って、引っ張りを少なくしていきます。
これも、Landlerだけではなく、rondo的な舞曲の定石の演奏法です。
しかし、そのテンポの設定こそが、典型的なLandlerの特徴でもあります。
Aの部分は、a+b+aの3部形式で作曲されています。
aの部分は、8小節で出来ていますが、それぞれ2小節単位のphraseで出来ています。
bの部分はゆっくりとしたやさしい感じのmelodie「あ」で始まりますが、3小節目に入ったら、「い」の部分になりますが、突然、速く端折るような感じで演奏されます。
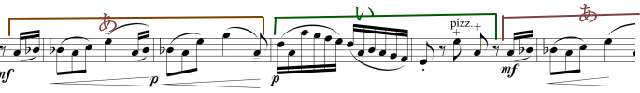 ⇒「う」へ
⇒「う」へ
「い」が終わると、また、「あ」に戻り、次には「う」に進みます。
つまり、緩、急、緩、急とめまぐるしくtempoが変化するのです。舞曲ならではのtempoの設定で、通常のconcertoには無いtempoの感覚です。
それが2回繰り返されて(「あ」+「い」の4小節と、「あ」+「う」の4小節のように…)、また、Aの部分(8小節)に戻ります。
ここまでがrondoのA(=24小節)です。
次はrondoのBの部分ですが、何と、8小節しかありません。
Bの部分は、僅か8小節しかないのですが、印象的なpassageで作曲されています。
このrhythmは、ハンガリーの民謡等にもよく見受けられる、私がBarentanz(熊さんのdance)と呼んでいる特徴的なdanceです。
Bartokの使用したHungaryの民謡の歌詞が熊さんのdanceという可愛らしい歌詞だったから、その特徴的なrhythmを、私も熊さんdanceと呼んでいるのです。熊さんが大きな体をいっぱいにして、脅かしている状態と、驚いて一目散に逃げ回っているリスのような情景です。つまり「え」の部分が熊さんで、「お」の部分が逃げているリスさんです。
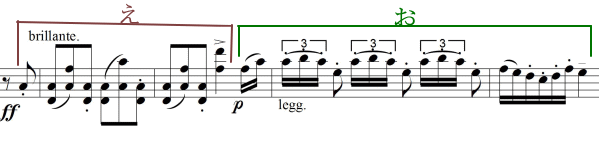
⇒「え」「か」へ
このpassageもbと同じように、緩、急、緩、急と繰り返されるのですが、bよりももっとオーバーな表現になります。
まさに舞曲の面目躍如とした、非常に印象的なpassageです。
この曲のrhythm構造は、伴奏が2拍子の和音で伴奏されるのに対して、「え」は、そのままの2拍子であるが、「お」のlegg.のpassageは、まるであたかも2拍子のような、飛び跳ねるようなrhythmで演奏されます。(+1auftakt/2+2+2+3+2/+1auftakt・・・)
結果的にorchestraの伴奏の8/6拍子に対して、soloviolinの8/2拍子系のpolyrhythm(ポリリズム=複拍子)となっています。
baroque音楽の非常に古い舞曲の音楽には、hemiola(ヘミオラ)と呼ばれる3拍子の曲の2小節を2拍子に演奏する習慣があります。
biberやcorelli等のbaroqueの作曲家のkammersonate等によく見受けられるが、kammersonateは、舞曲を集めた形式(組曲)であり、実際にその曲で踊られる事もあったので、当然と言えば当然なのです。
hemiolaは3拍子の2小節を2小節に括り直す分けなので、このSeitzの曲の場合には、hemiolaとは言えないのだが、当然、民族音楽は古い伝承的なステップを踏襲しているので、Landlerには、hemiolaを伴う曲が多いのは当たり前であり、このSeitzの作品のBの部分もhemiolaモドキと言っても良いのは当然です。
(舞曲のdanceのstepが先にあって、「Hemiolaがどうのこうの!!」という理屈は、後世に、学者の手によって、作られたからなのですよ。)
Wien産まれの生粋のWienっ子であるKreislerのAlte Tanzweisenという3っつのviolinのための小品(愛の喜び、愛の悲しみ、美しきロスマリン)は、ワルツではなく、Landlerとして作曲されているので、基本的な昔ながらのhemiolaを使用しています。
Seitzの場合には、学術的な整合よりも、舞曲のステップとして、このhemiolaモドキを使用しています。
寧ろ、そちらの方が、現実的で、リアリティがあって良いようです。
次にrondoの定番であるならば、A+B+Aと進まなければなりませんが、回帰したAは、はなはだ不完全なものです。
aは全く省略されて、いきなりbの2小節から、始まるのですが、急の「い」の部分は、全く新しく「き」と、「く」のpassageになります。「く」は「あ」に対して速いpassageですが、オケ練習していると、子供達の演奏では「く’」で突然遅くなる傾向にあります。本当は、「あ」は少しゆっくり目で「く」で突然早くして、次は今回は「く’」の一回目から、徐々に遅くなって行きます。と言う事で、「く’」の1回目は「く」と同じtempoでなければなりません。
「く」の後半部は、反復されて、Aに戻るためのつなぎのpassageとして使用されています。

基本の構造式ではA+B+Aから中間部のDになります。
小rondoの場合には、A+B+A+C+Aに簡単なCodaが付くのが一般的なので、それぞれの部分は、ほぼ同じ長さです。
しかし、それに対して、通常の大rondoの場合には、Dの長さは、A+B+Aとほぼ同じ長さになります。
という事で、大rondoの構造式の場合には、A+B+Aをまとめて、αとして、Dをβとして、表す場合もあります。
このSeitzの場合にも、イントロを含めたABAの小節数は61小節もあります。それに対して、このDの中間部は次のEの部分まで53小節もあります。通常のrondoに付け加えられたEの部分は33小節もありますが、中間部Dはイントロの13小節と、本文の32小節、つなぎの8小節でEの部分のmelodie部分とDの部分のmelodieの32小節が整合しているのです。
最後のthemaへの回帰は、8小節のAの部分だけしかありません。
突然の、G・P(Generalpause)の後、お定まりの「追い出し」の猛ダッシュが始まります。ちなみに、「追い出しの部分」も、32小節で構造式のバランスをとっています。
スキのない素晴らしい、クレバーな構造式ですね。
基本的なLandlerの構造式は、ABAと、同じ長さのCで、次はADAEAが、それぞれのAが省略された形で、元のABAとほぼ同じ長さになります。
では、Seitzの構造式を、表にまとめてみましょう。
title小節数 Motivのククリ
イントロ
10 2+2+1+1+4 A 8a 8b 8a 2+2+2+21+1+2,1+1+2 B8
A8b 4+4 A部のつなぎ3 C部イントロ13 C 32 8+8+8+8 C部のつなぎ8 D 9 8
17 a b A10 GPを含む Coda部 (finaleの追い出し部) 8a 8a 8b 8c
しかし、Landlerの揺らしを正確に揺らすのは、Mazurkaなみに難しい。
激しいtempoの緩急が、自然に聞こえるようになるには、相当の練習が必要でしょうね。
揺らしの話へリンクします。
また、violinの表現技術、所謂、bowtechnicも、上記の構造式から導き出されたtechnicでなければならないのは、明らかです。
構造式の中に、表現すべき全てが、書かれているからでなのです。
先ずは、音楽の構造式から、音楽表現が引き出されるのだよ。
その音楽表現に対して、その表現を最も効率よく引き出すbowtechnicが選ばれていくのだよ。
という事で、「まえがき」に書いたように、このSeitzのconcertoが、「内容もなく、手軽に簡単に演奏出来る」という勘違いは、「ただ弾く」という事と、ちゃんと「弾く」という事の区別が分からない人達の話であって、全く別の次元の話なのだよな!!
それが、一般のviolinの学習者は、未だ音楽の理解と解釈が未熟な分けだから兎も角として、violinのプロの奏者や指導者にとっても、理解出来ないという事は、許せない事だ。
同じ愚痴の繰り返しになってしまうのだが、Beyerにしても、Diabelliにしても、或いは、violinのSeitzにしても、100年も歴史に残って行くものに対しての、尊敬の念がない教育者は、私は子供の指導に携わるべきではないと思う。
同様に、baroqueや古典派の音楽の様式のtheoryを無視して、自分の感性だけで、演奏をする演奏家、指揮者も、基本的に音楽に携わる資格はないと思うのだがね。
自信がなければ、自分の得意とするgenreで演奏活動をすべきだろう。
教育者は、子供の教育教材を小馬鹿にしていて、子供の指導が出来る分けはなかろう。
「子供だから、この程度で良い・・」という発想なら、教育者としては、あるまじき考え方だ。
同様に、作曲者に対しての尊厳もなく、自分を表現する材料としてしか作品を捉えない音楽家達は、不遜で不誠実で腹が立つよね!
どんなに見かけは簡単で、安易なものに見えたとしても、歴史の淘汰に残って行く作品は、それなりの普遍性があるのだよ。
それが、kinderlei(子供じみて)に見えるのなら、それは音楽家としての自分の勉強不足を恥じるべきであろう。
Munchenの国際コンクールでも、予選でChopinやLisztやRakhmaninovのテクニカルな小品ではなく、HaydnやMozartのPianosonate等が課題に出る事がよくあります。
その時には、日本人のコンクール出場者達が、事前の予想に反して予選で総崩れするんだな!!
そんな簡単な曲をどう弾き分けて良いのか、他の出場者と差別化して良いのか、それが分からなくなるのだな??
しかし、古典派のsonateやconcertoを演奏する事は、そんなに簡単な事ではないのだよ。
古典派の様式や、当時の奏法をちゃんしたtheoryとして正しく認識した上で、典雅で上品で抑制のとれた古典派の技術を駆使して演奏しなければならないのだよ。
まえがきのパールマンの話以外でも、****(注)のHaydnのcelloconcertoの演奏の話でも、古典派を専門に研究している演奏家や指揮者達にとっては、耐えられない演奏なのだよ。
演奏としては、それなりなのだろうが、それをHaydnとか古典派の音楽とは呼ばない。古典派には古典派としての時代考証があってこその、interpretationなのだよ。古典派の演奏は典雅で優美なものなのだよ。横っ面をひっぱたくような近現代的な奏法は、baroqueや古典派の時代の奏法にはないのだよな。そこの所を勘違いして、自分の解釈を押し付けても、そりゃ聞こえませぬ、伝兵衛様だよな??(注)指揮者の実名、演奏団体の実名は削除しました。
幾ら世界的な演奏家だとしても、音楽のgenreが違えば、interpretationの違いは明白であり、その音楽のNiveauが根本的に違う。
そこは餅は餅屋なのだよ。
幾ら、世界的に有名な演奏家だとしても、本当の本物の演奏はまた一味違うのだな??!!
時代時代に、その奏法の違いがあるのだよ。
音楽は難しい!!
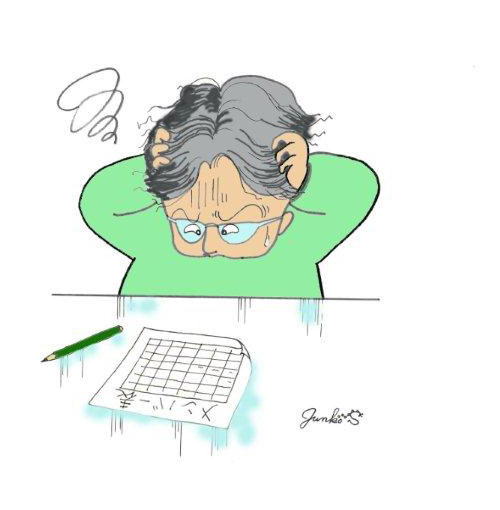


フリードリヒ・ザイツ (Friedrich Seitz)Thuringen州 Gunthersleben ⇒Dessau+
( 1848年6月12日 - 1918年5月22日)は、ドイツ・ロマン派の作曲家、ヴァイオリニスト。
初心者用のヴァイオリン協奏曲の作者としてヴァイオリン学習者には有名。
学生のためのヴァイオリン協奏曲5作品などが知られている。

Hohmannや、他の教育音楽の作曲家同様に、Seitzも、殆どその資料は出てきません。
(それでも、Hohmannやその他の教育音楽の作曲家に比べたら、まだ資料はある方なのです。
で、どんな顔をした人なのかな??とネットで調べてみたのだが、こりゃぁ、無理だわサ!!
何とか、かんとか、嘘か本当かは知りませんが、左の絵は、ネット上で唯一ヒットしたFriedrich Seitzの肖像画です。
それ以外の、後のSeitzの肖像画や、それと覚しき絵や写真は、衣装や環境がSeitzの生きた時代に対して、時代考証的に合わなくて、とても、Seitzの絵とは思えませんでした。
その中で、唯一の「・・・かな?」という肖像画です。
残念ながら、真偽の程の責任は持てません。
Seitzの生まれた年は、所謂、3月革命の年なのですが、それよりも、ビーダーマイヤーの時代が終わった年とされる年でもあります。
それと同時に、産業革命の時代とほぼ同じ時代に生きた人という事が言えます。
最も、死んだ年の1918年はチョッと問題ありですがね。西暦で言うとピンと来ないのですが、大正7年というと、何かしら身近な気がしますね。1914年から、Seitzが死んだ1918年までが第一次世界大戦です。つまり、第一次世界大戦の終わった年に死んでいます。
私達にとっては、おじいさん、おばあさんの世代です。今の人達は曾お祖父さんぐらいかな??いずれにしても、そんな遠い話ではありません。という事で、生徒さんのMarlene
Dietrichさんの写真をピックアップしてみました。
ドイツ語ではLebenslaufと言いますが、訳すると履歴書じゃ、おかしいし、経歴でもないし、自分だったら、自伝とか半生記とかなるのでしょうが、所謂、Seitzの略歴です。資料は、フリー百科事典『ウイキペディア(Wikipedea)を丸写ししました。
私もあまりよく知らないので・・・。
フリードリヒ・ザイツはテューリンゲン州ギュンタースレベン(Gunthersleben)で農家の子として生まれた。
ザイツはゾンダースハウゼンで、かつてマクデブルクでコンサートマスターを務めていたカール・ヴィルヘルム・ウールリッヒに師事してヴァイオリンを学ぶ。
1874年には、ドレスデンのコンサートマスターであるヨハン・クリストフ・ラウターバッハに師事している。
1869年、ザイツはゾンダースハウゼンの楽団にヴァイオリニストとして参加し、1873年にはカペルマイスターに選ばれた。
1876年、ザイツはマクデブルクに移り、市の交響楽団のコンサートマスターとなった。
ザイツは、マクデブルク初の音楽学校の創立者であると考えられている。
彼は1884年にはデッサウのヘルツォクリヒェン宮廷楽団の指揮者となり、1888年にはバイロイト音楽祭のコンサートマスターを務めた。
フリードリヒ・ザイツは、当時としては最も著名なヴァイオリニストとして、ヨーロッパ中に演奏旅行を行った。
彼はコーブルクのオペラ座などの多くのドイツ国内の都市ばかりでなく、ロンドンやホラントまでも出向いた。
ザイツは1908年に引退する。
彼はシュヴァルツブルク=ゾンダースハウゼン公とアンハルト公の両名から、その充実した音楽活動と教育活動を讃えられて芸術・科学メダルを贈られた。
1918年、デッサウで死去。
次ページ

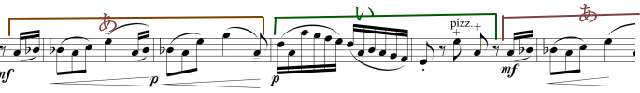 ⇒「う」へ
⇒「う」へ