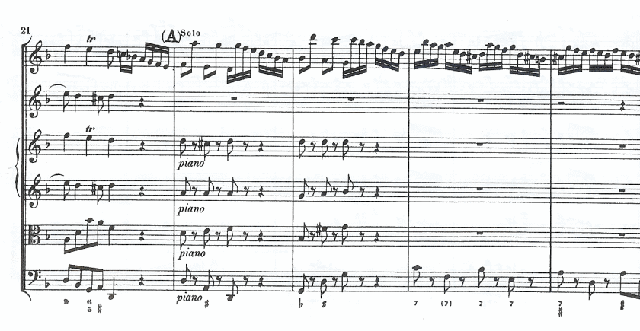
21彫愡栚丄偙偺嵍懁偺彫愡偼tutti偱偡丅3攺栚偐傜1倱倧倢倧偑巒傑傝傑偡丅
妝晥偺婰晥忋偱偼丄偦偺傑傑偺tutti偱墘憈偡傞傛偆偵巜帵偝傟偰偄傞偺偱偡偑丄偦傟偱偼倱倧倢倧偺violin偵懳偟偰丄柍棟偑偁傞偺偱丄嫮庛傪P偲巜掕偟偰偁傝傑偡丅
偟偐偟丄偦傟偱傕丄晄帺慠偵挳偙偊偰偟傑偄傑偡丅
偦偺棟桼偼丄捠忢baroque偺倱倧倢倧丂violin偺敽憈偼丄basso continuo偵側偭偰丄倱倧倢倧丂cello丄乮栜榑丄偝傕側偔偽丄viola da gamba乯偲Cembalo偑丄儚僉傪墘憈偡傞乮敽憈偡傞乯偺偑晛捠偩偭偨偐傜偱偡丅
偲偄偆帠偼丄婔傜pianissimo偱抏偄偨偲偟偰傕丄violin傗viola偑orchestra偺恖悢偺傑傑偱墘憈偟偰偟傑偭偰偼丄壒偑嫮偔弌夁偓偰丄晄帺慠偵側偭偰偟傑偆偺偱偡丅
偮傑傝丄basso continuo偺婎杮尨懃偼丄solo偺妝婍偵懳偟偰偼丄solo偺敽憈偱側偗傟偽側傜側偄偺偱偡丅
偩偐傜丄嫵幒偺僆働偱偼丄楙廗偱偼丄慡堳偑楙廗偟傑偡偑丄杮斣偼乮A乯偺俹偺晹暘偐傜偼丄僾儖僩丒儕乕僟乕偩偗偑soli乮solo偺暋悢宍乯偺墘憈傪偡傞帠偵側傝傑偡丅
摨條偵丄Vivaldi偺偙偺O倫.3N倰.6丂偺倎 倣倧倢倢嬋傕丄solo偺晹暘偺敽憈偵丄soli偲偄偆巜掕偼丄尨晥偵偼側偄偺偱偡偑丄嫵幒偱偼丄13彫愡栚偐傜偺violin偲viola偼僾儖僩丒儅僗僞乕偩偗偺soli偱墘憈偝偣傞帠偵偟偰偄傑偡丅
偦傟偱傕丄violin偲viola偺壒偑unison側偺偱丄摨偠壒偑俀杮偯偮偱敽憈偝傟傞偺偱丄壒偼寢峔嫮傔偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
栜榑丄偙偺score偱偼忋偐傜係抜栚偺cello丄solopart側偺偱偡偑丄侾俀彫愡偺3攺栚偐傜偼丄basso continuo偺solo偵側傝傑偡丅慡堳偑solo偵側傞偺偱丄偲偰傕僶儔儞僗偑傛偔丄嬁偒傑偡丅
嫵幒偱嶌惉偟偨score偱偼丄basso continuo偺solo丂cello偲丄orchestra偺cello丄Kontrabass偼暿偺抜偵彂偐傟偰偄傑偡丅
偦傟偼Vivaldi偺帪戙偵偼丄tutti偐傜solo傊偺堏傝曄傢傝偺orchestra丂part偺嵟屻偺壒偼丄solo偺壒偲偟偰彂偐傟偰偄傞偺偱丄嵟屻偺壒偺挿偝偑彂偐傟偰偄傑偣傫丅偦傟偱丄姩堘偄傪偟偰墘憈偡傞orchestra偑懡偄偐傜偱偡丅
偙偺暥復傪僋儕僢僋偡傞偲丄嘨妝復偺orchestra偐傜solo偵堏傝曄傢傞彫愡偺original偺晥柺偺椺傪嶲徠偡傞帠偑弌棃傑偡丅
Cembalopart嶌嬋埌捤梲擇乮拞媺version乯