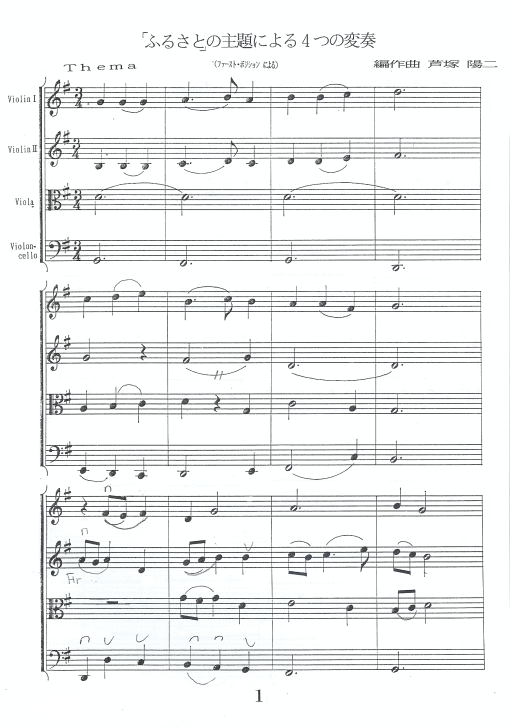
次の楽譜は教室内外でも、よく演奏されている、(今回《2013年6月30日》、八千代でも演奏する事になっている)私の編作曲「ふるさとの主題による変奏曲」の楽譜なのですが、斉藤先生が未だ中学生の時に、浄書の勉強の一貫として、私の指導の下に書いた楽譜です。
(勿論、bowing等の書き込みは後日の演奏の時のものです。)
教室の生徒達は、同じ音楽を専門にする生徒でも、教室の先生になるための勉強をしている生徒と、音楽大学の進学を目的とする生徒とは、全く別のcurriculumで、勉強しています。
また、音楽大学を目標にする以前に、当面の(その年の目標をコンクールにして勉強する生徒達もいますが)当面の目標をコンクールにして、勉強する生徒も、音楽大学進学を目標とする生徒と、殆ど同じconceptで指導します。
音楽大学の受験は、楽典やsolfege等の教科をかなりのウエイトで勉強しなければなりません。
でも、その教科の中には、音符の書き方のような基本的な勉強は入っていません。あくまで学校教材としての楽典なのですから。
主科の楽器の指導に関しても、基本は減点法なので、何処が悪いかの粗探しがレッスンの基本になります。
どうしても重箱の隅を突くような、レッスンになります。
音楽大学の先生達は音楽表現で表情を作ったり、揺らしの表現を極端に嫌がります。
作曲家が何故そう書いたのか?・・・ではなく、もっと、ストレートに、「楽譜に書いてある事をそのまま、忠実に率直に表現する事」が、音楽大学特有の曲の作り方です。
一般の大学の受験生と同じように、受験の為のcurriculumがあって、それを忠実に勉強しなければなりません。
つまり、音楽大学を目指したり、コンクールを目指す生徒達は、昔々の生徒であったとしても、楽譜の浄書の仕方等を学ぶ為の時間は、とてもないという話なのです。
それに、音楽大学の卒業生は、楽器でその曲が演奏出来れば、子供達の指導が出来ると思い込んでいますが、実際にはそんな簡単なものではありません。一般の人達は、「音楽の初期の勉強は、誰でも、何処でも良い。」と考えがちなのですが、実際は、ぎゃくなのです。
音楽を学ぶ上で、初期の指導はとても大切です。音楽の導入の時期に楽譜を読めるようになっておかないと、それ以降大変な苦労を強いられる事になるのです。
最初から教室で勉強を始めた生徒達は、譜読みの苦労を全く知りませんが、教室の外で音楽の勉強を始めて、教室にやって来た生徒達は、譜読みの仕方を学ぶ事で、中々苦労するようです。(譜読みではなく、譜読みの仕方のお話ですよ。)
昔々、ピアノを学んで来た親御さんが、子供を連れて見えられて、「私はBeyerは嫌いです。出来れば、Beyer以外の教則本で指導して欲しいのですが・・。」と言われる事がよくあります。(本当によくあるのですよ。)
それに対して、「教室は色々な教則本の研究をしていますので、どんな教則本でも対応出来ますが、その前に教室のBeyerの教則本の指導を見てみませんか?」と言って、Beyerがすっかり嫌いになった、その親御さんの子供に(親御さんではなく、その子供ですよ・・・!!)先生が、その生徒が今その教室で勉強しているBeyerを指導してみせると、「私も、こういう風に習えれば良かったのに・・・!」という応えが返ってきます。
つまり、原因はBeyerでなくても、どの教則本でも、指導者が無知だと、良いレッスンは受けられないし、その結果、音楽が(楽器が)嫌いになってしまうのですよ。
子供が音楽を(楽器を)好きになるか否かは、先生次第という事なのですよ。
でも、子供達が音楽を、或いは自分が演奏している楽器を好きになるように教育するのは、大変な勉強が必要になります。
それだけ、浄書の勉強にも、finaleの勉強にも、その一つ一つのインストラクターに必要な勉強の基本は、その一つ一つの技術を習得する事が、大変な時間と手間が掛かって、音楽大学受験の勉強のような「レッスン時間に、教室に行って、レッスンを受ける」・・・という限られた時間の中だけで学べる程、簡単なものではないという事なのです。
巷の音楽教室には、大きく二種類の教室があります。
音楽大学を卒業していれば、或いは楽器を勉強した経験があれば・・・・、教室の先生に採用される音楽教室。
その資格があれば、誰でも自分の自由に指導出来ます。
それに対して、ヤマハやカワイのように、或いはスズキヴァイオリン教室のように、その企業の指導者になるための資格試験やgrade試験を受けて、それから、採用試験を受ける場合です。この場合には、どの音楽大学を卒業したのかは、一切配慮はされません。あくまで、その企業の資格を取る事が条件です。
また、教室に独自のcurriculumがあって、そのcurriculumを勉強する事が、採用条件の教室もあります。
私達の教室では、教室の指導者を希望する先生達に対して、curriculumの習得を採用条件にはしていません。それは、教室の指導者になりたい先生がcurriculumの習得を目指しても、中々簡単には技術の習得が**では出来ないからです。
その話に関しては「巷の音楽教室である芦塚音楽研究所」に詳しく書いてありますので、そちらを参照してください。
私達の教室の指導方針とそのcurriculumは、作曲家が「何故、どうしてそう書いたのか??」という事を大切にします。
また、その作曲家の生活していた時代の慣習から、その曲の当時の演奏法を学びます。
音楽史も単なる学校教育上の音楽史ではなく、現実の歴史的な音楽の認識や音楽上の基礎を徹底的に勉強します。
唯、問題を解くのではなく、その問題の本質を解明するのです。
つまり、一人ひとりの作曲家の曲を勉強するのではなく、古典派の様式として、曲を解釈して、分析し、それを練習に活かして行くのです。
そうすれば、一人の作曲家を徹底的に勉強する事で、他の作曲家の音楽も同様に演奏出来るようになるからです。
芦塚メトードの時短の法則は、急がば回れの方法論でもあるのです。
根本を理解出来れば、その法則を忘れる事も、それに近い問題も簡単に解く事が出来るからです。
音符の書き方の基本もその常識の中に入ってきます。
留学やプロの演奏家を目指す生徒の場合も、教室の先生を目指す生徒と同じcurriculumになります。
今、生徒達にfinaleの導入を指導しているのですが、私の方針として、教室の仕事で派生したfinaleの課題を生徒にやらせることで、時短をはかっています。それが、父兄には、生徒が教室のお手伝いをしているように見えてしまうようなのですが、残念ながら、その程度の技術力では、足を引っ張る事はあっても、先生達のお手伝いには程遠いのです。
やはり先生達の仕事のお手伝いとして、finaleを使いこなせるように、なるまでには、仕事として、或いは職人としての勉強のstyleでないと、とても無理なのです。
あくまでも、勉強としてのfinaleの使い方のlectureなのですからね。
「先生達へのお手伝い」と、「仕事としての勉強のためのlecture」の違いについては「江古田詣」に詳しく説明してありますので、そちらを参照してください。
[インスタント・レタリング]
浄書の水準は、努力だけではなく、ある程度、絵心の能力や書く人の性格の問題もあります。
という事で、その楽譜のクオリティ(水準)を安定させるために、ヨーロッパでは、インスタント・レタリングによる楽譜の浄書もありました。
私の場合には、作曲に必要な技術や知識としてではなく、自分の作品を出版するための、知識として、とか、音楽の以外の詩や小説を出版したり、教育関係の本に寄稿したりといった、現実的なニーズに迫られて、インスタント・レタリングの知識を、音楽とは関係なく習得していました。
という事で、インスタント・レタリングは、私にとっては、そんな難しい技術ではなかったのですが、しかし、漫画家のスクリーントーン同様に、1枚、1枚の紙がとても高価だし、音符の場合には、スクリーントーンが、国産ではなく、イギリス製だったので、非常に1枚のコストが高いのと、音符を制作する上で、出来ない(スクリーントーンに売っていない事例も)事も多かったので、弟子達には、結局の所、楽譜の表題や作曲者の氏名をスクリーントーンを使用する事を指導するぐらいで、基本的なスクリーントーンの技法を教えるのみで、音符をスクリーントーンで書くといった事までは、指導しませんでした。
そういう事で、次の楽譜の例は、私がインスタント・レタリングの手法によって作った実際の譜例であります。
この楽譜の譜例は、私の著書である「Cembalo教則本」なのですが、何故、私がインスタントレタリングという超七面倒臭い手法で楽譜を制作したのかというと、この楽譜が作成された当時は、未だfinaleというソフトが、まだ30万、40万という値段の頃で、パソコンも超ヘボく、プリンターすら、ロクな機械が無かったPC95、98や、マックも今日のパソコンからは、考えられない、C原語から移行中の時代で、finaleとても、仕事として、「普段使い」に普通に使える時代では、なかったからで、はっきり言うと、finaleが超高価過ぎて買えなかったからですよ。
パソコンも、1台何十万もした時代でしたからね。
つまり、その当時は、楽譜は「手書き」が当たり前の時代だったのですよ。
という事で、この「Cembalo教則本」の論文の楽譜の部分の浄書も、大変な努力と手間暇を掛けて、イン・レタを使用して、アナログ的に、大変な時間を掛けて、1ページ、1ページ、楽譜を作っています。
勿論、このレタリング作業も私自身が、一人でコツコツとしたものです。
印刷が薄いのは、イン・レタの性ではなく、当時の性能の悪いコピー機からとったコピーをコピーしたものだからです。
ちなみに、文字は和文タイプです。勿論、私が活字拾いで入力しています。